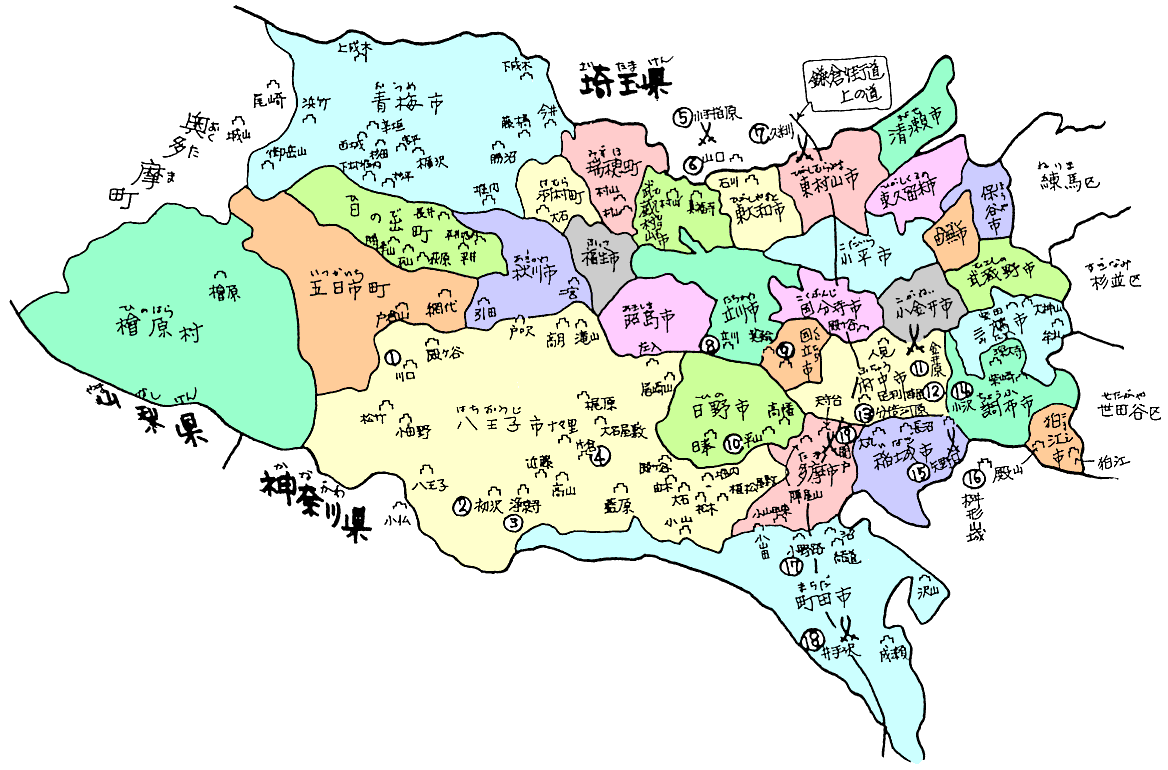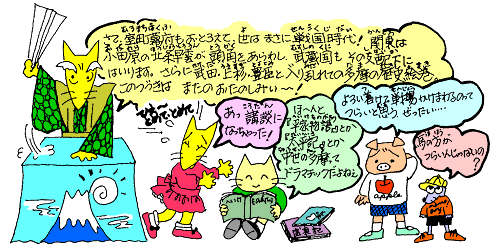武蔵武士のたんじょう!

むかし、むかし、そのむかし、平安時代とよばれた頃、武蔵国は京の都から見れば、遠い遠い東国のさいはての地だった。ここには、都の貴族や寺社の荘園、朝廷の牧場などが置かれていた。そして朝廷からは国司(地方長官)という役人が派けんされていた。
今の府中は、武蔵国府といって、当時の役所があったところだ。
国司の任期は、もとは4年または6年と限られていたが年数がきても都に帰らずいついてしまう者が多かった。国司でいた間に開こんした土地を手ばなしていくのは惜しかったし、第一、地方では都からの貴人・役人としてあがめられる国司たちも、都に帰れば下級貴族にすぎなかった。
ところで当時の東国はそうとう治安が悪かった。
盗賊たちが歩きまわるは、東北地方には朝廷に従わない蝦夷とよばれる豪族たちはいるは……。
 延喜9(919)年には、前の国府の役人、源任が武蔵国府を襲うし、承平5(935)年には平将門の乱もおきている。
延喜9(919)年には、前の国府の役人、源任が武蔵国府を襲うし、承平5(935)年には平将門の乱もおきている。
やむをえず、朝廷では、地方に居ついた国司や郡司らに警察力を与えることになった。
こうして、土地を持ち、戦う力を強めていった者が、武士とよばれるようになり、武蔵国のあちこちをねじろにした武蔵武士があらわれる。
この武士たちが鎌倉幕府をつくりあげ、武士中心の時代がやって来る。
天正18(1590)年、豊臣秀吉に、小田原北条とともに滅ぼされるまで、関東平野は戦乱に明け暮れ、武蔵武士たちがかけめぐっていたのだ!
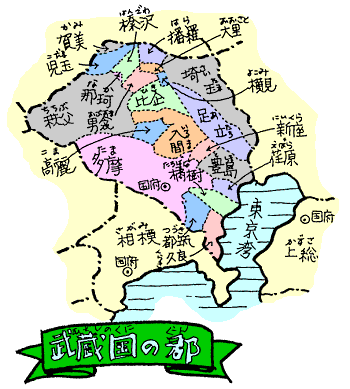
武蔵国は、いまの東京都・埼玉県のほとんどと神奈川県川崎市・横浜市のほとんどをふくむ地域でその中は21の郡にわかれていた。今の多摩地区はもちろん多摩郡にふくまれている。
年表
年表
| 世紀 |
時代 |
年 |
ことがら |
| 7世紀 |
飛鳥 |
大化元年(645)ごろ |
- 武蔵国が成立。国府が多摩郡に置かれる。
|
| 奈良 |
| 9世紀 |
平安 |
貞観3(861)年 |
- 11月 群盗(つまり、ぬすっとの群れ)のため、武蔵国は郡ごとに検非違使を置く。
|
| 10世紀 |
延喜9(919)年 |
- 武蔵国の前権介源任が盗賊の頭となって、武蔵国府をおそう。
|
| 承平5(935)年 |
- 2月 平将門の乱 おこる。
武蔵も一時将門の支配下にはいった。
|
| 天慶3(940)年 |
- 2月 平将門、藤原秀郷・平貞盛らに敗れる。
- このころより勅旨田や勅旨牧(天皇の命令で開こんされた私有地や牧場)が武蔵国の各地に置かれはじめる。
|
| 11世紀 |
長元元年(1028)年 |
- 6月 平忠常の乱 おこる。
乱は3年間におよび関東諸国はあれはてる。
|
| 永承6(1051)年 |
- この年、前九年の役 おこる。
|
| 永保3(1083)年 |
- この年、後三年の役 おこる。
- この世紀中、さかんな土地の開発から、秩父氏、江戸氏などの平家諸流や武蔵七党など多くの武士団がたん生する。
|
| 12世紀 |
保元元年(1156)年 |
|
| 平治元年(1159)年 |
|
| 永暦元年(1160)年 |
- 1月 源義朝 殺され、
- 3月 源頼朝 伊豆に流される。
|
| 治承4(1180)年 |
- 8月 源頼朝 伊豆で挙兵。
源平合戦では武蔵武士が活やくする。
|
| 文治元年(1185)年 |
|
| 鎌倉 |
建久3(1192)年 |
- 7月 源頼朝 征夷大将軍となる。
≪鎌倉幕府 成立≫ |
| 14世紀 |
元弘元年(1331)年 |
- 9月 楠正成ら挙兵。
|
元弘2
正慶元年(1332)年 |
- 3月 幕府、後醍醐天皇を隠岐に流す。
|
元弘3
正慶2(1333)年 |
- 5月 新田義貞の鎌倉攻め。
≪鎌倉幕府 滅亡≫
ここでも武蔵武士が活やくする。 |
| 南北朝 |
建武2(1335)年 |
- 7月 中先代の乱
- 8月 足利尊氏、征東将軍となる。
|
| 延元元年(1336)年 |
- 11月 室町幕府 成立。
|
| 延元3(1338)年 |
- 8月 足利尊氏、征夷大将軍となる。
 |
武蔵七党
武蔵国の武士団は血縁(血のつながり)で結ばれた集まりだ。
中でも武蔵七党というのが有名だ。7つの党の数え方はきちんと決っていないけれど、主なものはつぎのとおりだ。
野与党
平忠常の次男胤宗の子、基宗がおこす。
基宗は野与の荘官だった。
南北埼玉郡に勢力をもつ。
西党
日奉連宗頼が武蔵守となって、その一族は武蔵国府から西を中心に発展。そのため西党とよばれるようになる。
小川・由比の牧を支配していたともいわれ、一族には平山氏、小川氏、立川氏、由井氏、二宮氏、川口氏などがある。
私市党
私市家盛が武蔵守になってやって来てはじまったといわれる。
「私市」は皇后領地(天皇のおきさきの領地)を治める仕事をする人で、皇后の牧の管理もしていた。北埼玉郡から大里郡中心。
一族には久下氏、成木氏などがある。
児玉党
藤原氏の一門。藤原道隆の孫の子、維能が武蔵介となって児玉郡を開たくしたのがはじまり。
一族には児玉氏、越生氏など。
横山党
小野篁の7代目の子孫といわれる小野孝泰が武蔵守となってやって来て、多摩の横山(今の八王子)を中心に開たく。
武蔵七党中最大の規模を誇る。一族に横山氏、椚田氏、由木氏、藍原氏などがある。ちなみに、小野篁は平安初期の有名な学者で、参議だ。
【参議とは】奈良時代にできた役職。朝廷での会議に参加できる人だ。
丹党
宣化天皇より出た多治比古王の子、広足が丹治の姓をもらい、武蔵守となってやって来たのがはじまり。秩父・児玉の両郡が中心で秩父郡の石田の牧を管理していたらしい。
村山党
平忠常の子孫で、野与基永の弟、村山貫主頼任がそのはじまり。
狭山丘陵中心に活やく。一族には、金子氏、狭山氏、山口氏、久米氏、難波田氏などがある。
猪俣党
横山党の一族。小野孝泰の子孫時範が児玉郡猪俣に館をつくり、猪俣氏となった。那珂郡が中心。一族には、猪俣氏、荏原氏、人見氏、男衾氏、甘糟氏、岡部氏など。
『平家物語』の中で薩摩守平忠度を討ちとったといわれる岡部六弥太忠澄もこの一族だ。
牧と武士

「
牧」とはつまり、
牧場だよ。
武蔵国には
石川牧(
横浜市)、
小川牧(
秋川市)、
由比牧(
八王子市)、
立野牧(
横浜市)、
秩父牧(
秩父市)、
小野牧(
秩父郡)などがあった。
(牧の位置は『荘園分布図』竹内理三編をもとにしました。)
牧では
馬を
育てていたんだ。
牧を
土台に
発展した
武士団は
多い。
何しろこのころの
戦いは
騎馬戦が
中心だから。
馬を
育てる
牧と
武士団の
関わりは
深いんだよ。
平氏と源氏
桓武平氏
桓武天皇(784年即位)のひまご(孫の子)の子にあたる高望王が平の姓をもらって上総介となって東国に来た。
その
子孫はそれぞれ
関東の
国々の
上級の
役人となり、
土着し、
力をたくわえていった。
伊豆の
北条、
相模の
土肥、
三浦、
上総の
上総、
下総の
千葉、
武蔵の
秩父氏らは「
坂東八
平氏」といわれ、
保元・
平治の
乱から
鎌倉幕府ができるころにかけて
大いに
活やくした。
秩父氏の一族
秩父氏は平良文(高望王の五男)の孫将常からはじまる名門だ。一族には畠山氏、河越氏、江戸氏などがある。
南多摩郡を本拠にしていた小山田氏も、そのはじまりは畠山重能(鎌倉幕府初めごろの重臣畠山重忠の父)の弟、有重だ。
また、有重の子、稲毛三郎重成は橘樹郡に勢力をもった。
清和源氏
清和天皇(858年即位)の孫が源の姓をもらい、天慶年間(938~941?年)武蔵介となって武蔵国に来た。
源氏の名をあげたのは源頼信(この人は平忠常の乱をしずめている)の子、頼義とその子義家だ。
2人は奥州の安倍頼時父子の乱をおさめ、また、義家は後三年の役でも活やく。
関東の武士たちは、義家をうやまい、慕った。
鎌倉幕府をひらいた源頼朝はこの義家のひまごだ。
鎌倉街道
 幕府のある鎌倉へむかういく筋かの道を鎌倉街道とか、鎌倉往還とよぶ。関東の武士たちと幕府を結びつける道であったし、戦さがおこって「いざ鎌倉!」という時は、軍事用の路線にもなった。そのうち、主な道は
幕府のある鎌倉へむかういく筋かの道を鎌倉街道とか、鎌倉往還とよぶ。関東の武士たちと幕府を結びつける道であったし、戦さがおこって「いざ鎌倉!」という時は、軍事用の路線にもなった。そのうち、主な道は
上の道
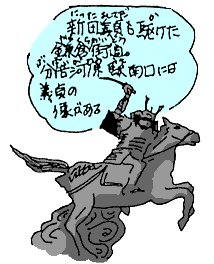 鎌倉小山田
鎌倉小山田(
町田市)
関戸(
多摩市)
分倍河原(
府中市)
恋ヶ窪(
国分寺市)
久米川(
東村山市)をとおる。
小平を
通っているのは、このルートなのだ!
下の道
鎌倉鶴見(横浜市)下総・上総(千葉県)へむかう。
中の道
上の道と下の道のまん中あたりを通り、府中で上の道と合流する。
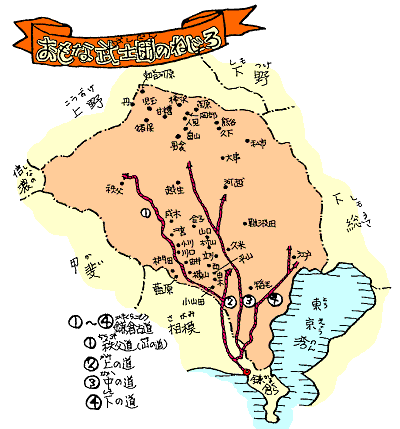
中世のこんな出来事、あんな人

武蔵国府と国司・郡司
9世紀以降、朝廷は全国を66の国と2つの島にわけた。そして、そのそれぞれに守・介・掾・目の階級の役人らを中央から派けんして政治を行わせたり、警察や裁判所の役目させたりした。これを国司という。
国司が仕事する役所を国衙といい、その所在地を国府といった。武蔵の国府は今の府中だ。
国司の下には郡内の政務を行う役人、郡司がいた。国司が4年または6年の任期があるのに対し、郡司は任期なし。しかも代々子孫に伝えられるかたちで地方豪族が任命されることが多かった。
検非違使
もともとは京都の安全を守る仕事をする役人だった。のちに地方の国々にも置かれるようになる。
野盗が集まって乱暴を働くので、武蔵国も郡ごとに検非違使が置かれた。
が、武士が成長してくると、形だけのものになってしまう。
平将門の乱(935年)
将門は桓武平氏の出。相続問題で一族が争うなか、叔父の国香を討ち、さらに関東8か国を支配して、自分を「新皇」(新しい天皇)と称した。
940年、将門は藤原秀郷、平貞盛らに討ちとられた。
平忠常の乱(1028年)
平将門の乱の後、東国では桓武平氏が勢力を伸ばした。中でも平忠常は、上総・下総(今の千葉県)あたりを足がかりにして力をつけ、朝廷に納める物を押えてしまった。
朝廷はなかなかこの反乱をしずめることができなかった。乱より3年後、甲斐守源頼信が討手に命じられると忠常は降伏。
この乱の後、東国では清和源氏が勢力を持つようになる。
武蔵の戦さ上手
まず将門を討った藤原秀郷。鎌倉時代には熊谷次郎直実・斎藤別当実盛・畠山重忠・金子十郎・平山武者所季重ら『平家物語』などに登場する有名人がいる。室町時代には新田義貞・足利尊氏・長尾景春・太田道真とその子道灌が活やくした。
前九年の役(1051年)・後三年の役(1083年)
陸奥(今の東北の東部のちいき)の安倍氏は朝廷にそむいて半ば独立した国家をその地に築いてしまった。
これが前九年の役のはじまりで、源頼義(平忠常の乱を治めた源頼信の子)が陸奥守となり、これを平定。戦いは12年間にもおよんだ。
一方、後三年の役は、奥羽(東北地方)の豪族清原氏のおこした一族の間の紛争。こちらは源頼義の長男で八幡太郎といわれた源義家が平定した。
保元の乱(1156年)
皇室の皇位継承問題(誰が天皇になるか)と藤原氏一族の間の権力争いが結びついておきた乱。
崇徳上皇と藤原頼長が挙兵したのに対し、後白河天皇(崇徳上皇の弟)と関白藤原忠通が源義朝・平清盛らを味方にむかえ討った。
戦いは一日でおわり、敗れた崇徳上皇は讃岐国へ流されてしまった。
平治の乱(1159年)
保元の乱で活やくした平清盛と源義朝に対する朝廷の扱いやほうびにはかなり差があった。清盛の方がまさって、義朝を圧倒するようになった。
義朝は清盛の留守をねらって挙兵したが、急ぎ帰った清盛軍に敗れ、殺されてしまう。
義朝の子、13歳の頼朝は伊豆に流された。
成人した頼朝は1180年、伊豆で挙兵。平氏を滅ぼし、1192年征夷大将軍となって、鎌倉に日本初の武家政権をつくりあげた。
御家人とは…
家人というのはもともとは貴族や武士の家来のことだ。
鎌倉時代には源頼朝に見参の礼をした(直接お目にかかって、その家来となった)武士のことを、頼朝に敬意をあらわして御家人とよんだ。「御」というのは敬う気持ちをあらわす言葉だからね。
鎌倉幕府の滅亡まで
源頼朝のひらいた鎌倉幕府も、源氏の血は三代将軍実朝で絶えた。それより後は、頼朝の妻、政子の一族である北条氏が執権として政治を行うようになった。
しかし、鎌倉時代も末になると貴族や武士の間から、幕府に対する不満が高まってきた。
新田義貞と鎌倉攻め(1333年)
新田義貞は上野国の生まれ。源氏の名門だったが北条氏から長い間冷たい扱いをうけてきた。
はじめは幕府の命令で、楠正成のこもる千早城の攻撃に加わっていたが、のち、後醍醐天皇に味方して挙兵した。1333年5月8日のことだ。
5月11日には 小手指原(今の所沢)で
5月12日には 久米川(東村山市と埼玉県の境)で幕府軍と戦い、連勝。
5月15日には 分倍河原(今の府中)で執権北条高時の弟、泰家軍と戦い、
よく5月16日の決戦で義貞軍が勝ち、幕府軍は鎌倉に退いた。
5月18日からは鎌倉総攻撃にはいり
5月22日 北条高時が自殺。鎌倉幕府は滅亡した。
中先代の乱(1335年)
北条高時の子、時行が鎌倉幕府の復活をはかっておこした反乱。
1335年7月、武蔵で足利直義(尊氏の弟)らを破り、鎌倉をおとした。が、8月には東に下ってきた尊氏に敗れ、時行は逃げた。
この乱の後、尊氏は関東にとどまり、後醍醐天皇の建武政権に対抗するようになった。
時行はその後、南朝軍に加わり、1352年には鎌倉に攻め入ったが、捕えられ、殺された。
後醍醐天皇と楠正成
後醍醐天皇は1321年に即位。幕府を倒す計画をしたが、失敗して、1332年、隠岐に流された。それにもめげず、1333年隠岐を脱出。諸国に幕府を倒すための挙兵を呼びかけた。
楠正成は河内国(今の大阪)の豪族だが、出身は明らかではない。後醍醐天皇の計画に加わり、1331年河内赤坂城に挙兵。よく年には千早城に移り、幕府軍と戦い、諸国に幕府を倒す軍をおこすよううながした。
足利尊氏
新田氏とならぶ源氏の名門。はじめは「高氏」だったが、幕府を倒した時のほうびに、後醍醐天皇の名尊治の一字を賜わり、「尊氏」となる。
1335年、北条時行の乱をしずめるため鎌倉へ下り、次いで建武政権にそむき、京の都に攻めのぼった。
よく年、戦いに破れ、九州におちのびたが、再び挙兵。楠正成らを破り、京の都にはいって、1336年、光明天皇をたて、室町幕府をひらいた。1338年には征夷大将軍となり、ここに再び源氏の血統による武家政権ができあがった。
後醍醐天皇は吉野にのがれて南朝をひらき、北朝をたてた足利氏の幕府に対抗した。
朝廷が再び統一されたのは1392年のことだ。
武蔵野合戦
足利尊氏と新田義貞の対立は、1335年、中先代の乱がおさまった後に早くも表面化。関東の武士たちもふた手に分かれた。この新田・足利の争いは、南北朝の対立するきっかけの一つともなった。
新田義貞は1338年、藤島(今の福井県)で戦死。その後は足利尊氏方と新田義興(義貞の子)・義宗(義興の弟)の争いとなり、1352年うるう2月に決戦をむかえた。
小手指原(埼玉県)・人見原(府中市)・金井原(小金井市)などを舞台に合戦をくりひろげ、この時期を境に新田軍は勢いがおとろえていく。義興は足利基氏(尊氏の四男坊だ)・畠山国清にはかられ、武蔵矢野口の渡(稲城市)で殺された。
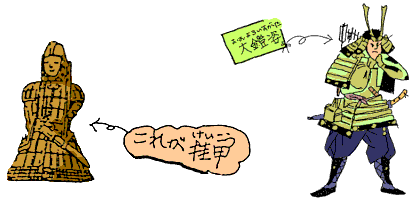 5世紀ごろ、朝鮮を経て日本に伝わった中国の挂甲(「かけよろい」といわれる古代のよろい)が鎧の起源だ。
5世紀ごろ、朝鮮を経て日本に伝わった中国の挂甲(「かけよろい」といわれる古代のよろい)が鎧の起源だ。
平安時代になると、武士の騎馬の射戦(馬にのって弓矢で戦うこと)にむくスタイルにかわっていった。
こんなにあるぞ!多摩のお城と古戦場マップ
分布図は「多摩の古城址」参照
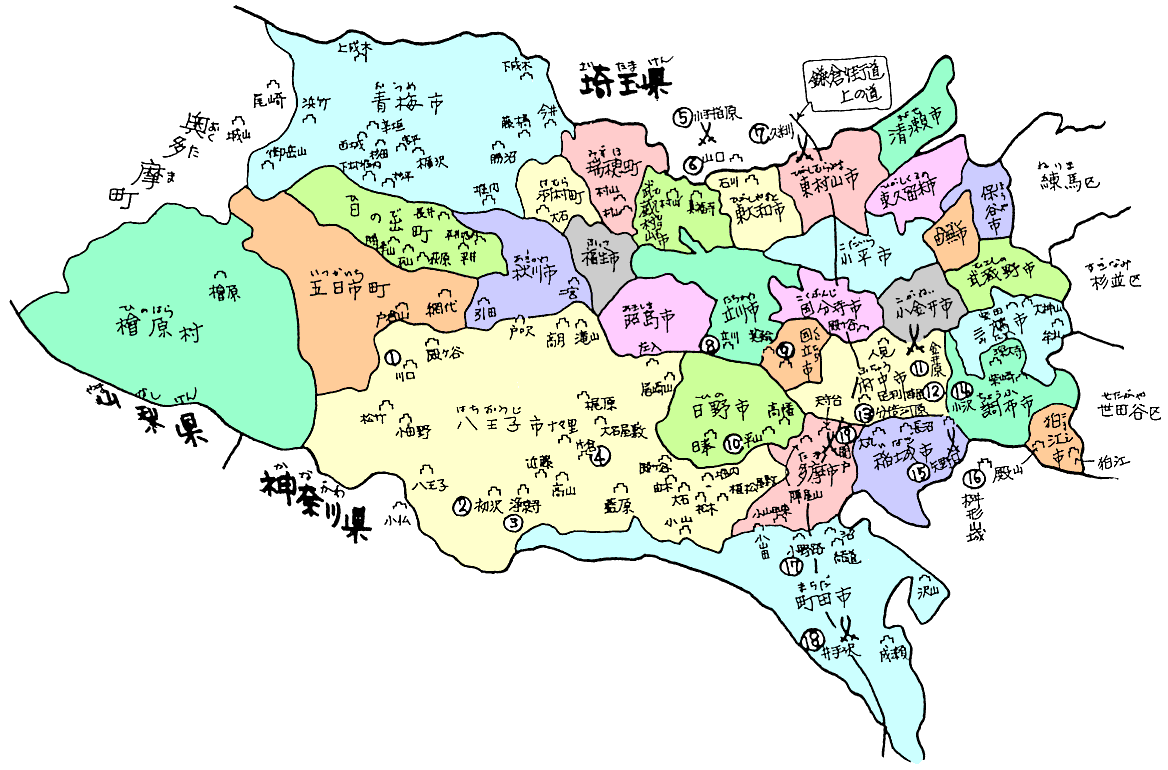
1.川口兵庫介館跡(八王子市川口)
川口氏は武蔵七党の西党の一族。鎌倉時代から室町時代まで、この館をねじろに川口郷を支配した。応永年間(1394~1428年)の兵庫介幸季のころに最も繁栄したといわれる。
2.初沢城跡(八王子市初沢町)
またの名を椚田城。高乗寺城。武蔵七党の横山党に属す椚田城の住居だともいうし、鎌倉幕府の重臣大江広元の子孫、長井氏の城だったともいう。
3.浄泉寺城跡(八王子市館町)
平安時代の武将で、源頼義の家臣であった鎌倉権五郎景政の館のあとといわれる。が、北条氏照の重臣、近藤出羽守の館だったという説もある。権五郎景政は義家に従って出陣した後三年の役で右目を射ぬかれたという。その姿のまま敵を討ち、陣地へ帰ると、味方の者が景政の顔に足をかけ、矢をひきぬこうとした。景政は、「武士が弓矢にあたって死ぬのは世の常だ。が、生きているうちに顔を足でふみつけられるのはかんべんならん!」と怒ったとか。
4.片倉城跡(八王子市片倉町)
室町時代前期、鎌倉幕府の重臣だった大江広元の子孫、長井道広が築いたともいうし、その父、大江備中守師親がつくったという説も。
このあたり、もともとは横山氏の土地だったが、鎌倉時代に大江氏に与えられた。その後100年ほどこの地は大江氏が支配。応永9(1402)年、長井道広が奥州で伊達氏との戦いに破れ、死ぬとこの城も使われなくなった。
戦国時代には、小田原北条氏の支城の一つだったが、天正18(1590)年、豊臣軍の小田原攻めとともに滅んだ。
5.古手指ヶ原古戦場(狭山丘陵北・所沢市西部)
- 元弘3(1333)年、鎌倉攻めの新田義貞軍と幕府の北条軍がはじめてここで出会い、戦う。
- 建武2(1335)年、中先代の乱の時もここで合戦があった。
- 正平7(1352)年、武蔵野合戦。足利尊氏対新田義興・義宗軍がここで戦う。
6.山口城跡(所沢市山口)
村山貫主頼任の孫、小七郎家継が山口氏を名のり、この地に館をかまえたのがはじまり。山口氏は鎌倉時代前からこのあたり一帯に勢力を持っていた。
南北朝時代には新田義貞に味方して戦ったが足利に攻められて城は滅んでしまった。
7.久米川古戦場
ここは鎌倉街道の宿として栄えた地。交通の上で重要な場所は合戦の場ともなった。
- 元弘3(1333)年、新田義貞軍対幕府の北条軍ここで戦う。
- 建武2(1335)年、中先代の乱の時もここで合戦。
8.立川城跡(立川市柴崎)
立川氏は武蔵七党の西党日奉氏の一族。源頼朝の挙兵にはせさんじ、平家討ばつに活やくした。
鎌倉時代から戦国時代にかけ、このあたりを支配した。城があったのは普済寺のあたり。天正18(1590)年、豊臣軍の小田原攻めとともに滅んだ。
9.三田氏館跡(国立市谷保)
津戸三郎為守が城主だったといわれる。一方、現在もこの地に住んでいる三田氏の先祖が代々城主だったという説もあってこうよばれる。為守は鎌倉幕府の御家人。熊谷直実と同じころの人らしい。
10.平山城跡(日野市平山)
武蔵七党の西党日奉氏の一族、平山武者所季重の館。平山季重は『平家物語』『源平盛衰記』に登場する武蔵武士団の実力者。一の谷の戦いで熊谷次郎直実と先陣あらそいをした。
11.金井原古戦場
正平7(1352)年、武蔵野合戦。足利尊氏対新田義興・義宗の合戦場。
- この戦いでは秋川すじの南一揆とよばれる武士団が、足利軍の先陣となって活やくした。
金井原(今の小金井市)とそれにつづく人見原(今の府中市)を舞台に戦いがくりひろげられた。
12.足利陣屋(府中市片町)
平安時代中ごろ、平将門を討った藤原秀郷が館をたてていたところで、そのあと「市川山見性寺」という寺になったといわれる。
南北朝時代の14世紀中ごろ、足利尊氏がこの寺を再興。自分のもとの名の「高氏」から一字とって「高安寺」と名付けたとか。
ちょうど分倍河原をみおろす絶好の場所で、南北朝時代から室町時代、しばしば足利氏の陣屋(兵士のとどまるところ)となった。ここは足利氏の府中防衛基地だったのだ。
13.分倍河原古戦場(京王線府中駅南)
ここは鎌倉と府中をむすび、川越にぬける鎌倉街道の重要な地点。幕府にとって、ここで敗れることは鎌倉がおちることにつながった。
そういう場所だから、必死の激戦がくりひろげられた。
- 元弘3(1333)年、鎌倉攻めの新田義貞軍対北条軍の決戦場。
- 建武2(1335)年、中先代の乱。
- 正平7(1352)年、武蔵野合戦。
14.小沢城跡(稲城市矢野口)
はじめはこの地方の豪族のすまいだったが、のち、稲毛三郎重成の城となった。南武蔵の重要な地点で鎌倉時代より数えきれぬほどの戦いの的となる。関東地方を代表する山城で、八王子の滝山城と肩をならべる。
15.矢野口(稲城市矢野口)
延文3(1358)年、鎌倉に向け出陣した新田義興はここの渡で謀られ、死んだ。
16.桝形山城跡(川崎市)
小沢城主、稲毛三郎重成の出城。
重成は小山田有重の子。妻は北条政子(源頼朝の妻)の妹だ。とても勢力があったのだけれど、元久2(1205)年、北条氏の陰謀のため、鎌倉で殺された。
17.小野路城跡(町田市小野路町台)
小山田有重の二男、二郎重義の住んだ城といわれる。
18.井出の沢古戦場(町田市本町田)
ここも鎌倉街道の要地。中先代の乱の合戦場。
19.関戸原古戦場
新田義貞の鎌倉攻めで分倍河原の戦いのあと、幕府軍北条泰家は、あやうくここで討ち死にするところ、丹党の武士らにたすけられ鎌倉へ戻った。
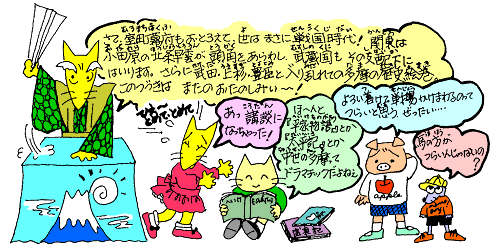
参考にした本
郷土資料室から
「東京都の歴史散歩・下」
「角川地名大辞典」
「多摩の古城址」
「多摩の歴史散歩」
「多摩丘陵の古城址」
「武蔵武士」
「多摩のあゆみ」第17号
「多摩歴史散歩1~3」
「史跡をたずねて 各駅停車シリーズ」
…その他いろいろ
児童コーナーから
「ほるぷ 日本の歴史2」
「鎌倉と南北朝」
その他
「戦国史事典」
「年表 日本の歴史1~4」
「戦国武家事典」
「平凡社大百科事典」
小平市に関すること
多摩に関すること
江戸・東京に関すること
玉川上水・小金井桜に関すること
その他


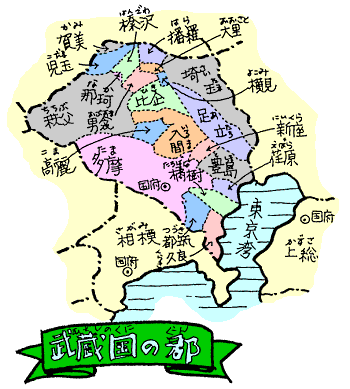

 「
「
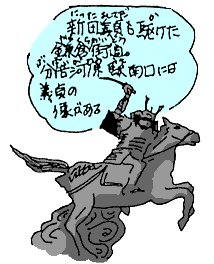
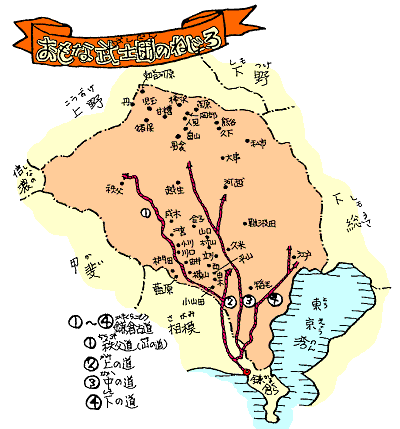

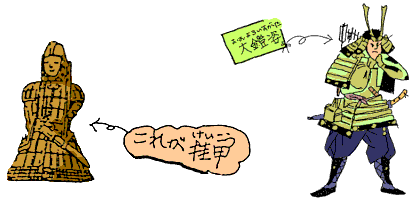 5
5