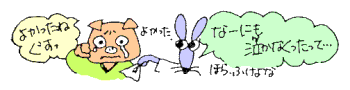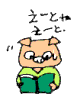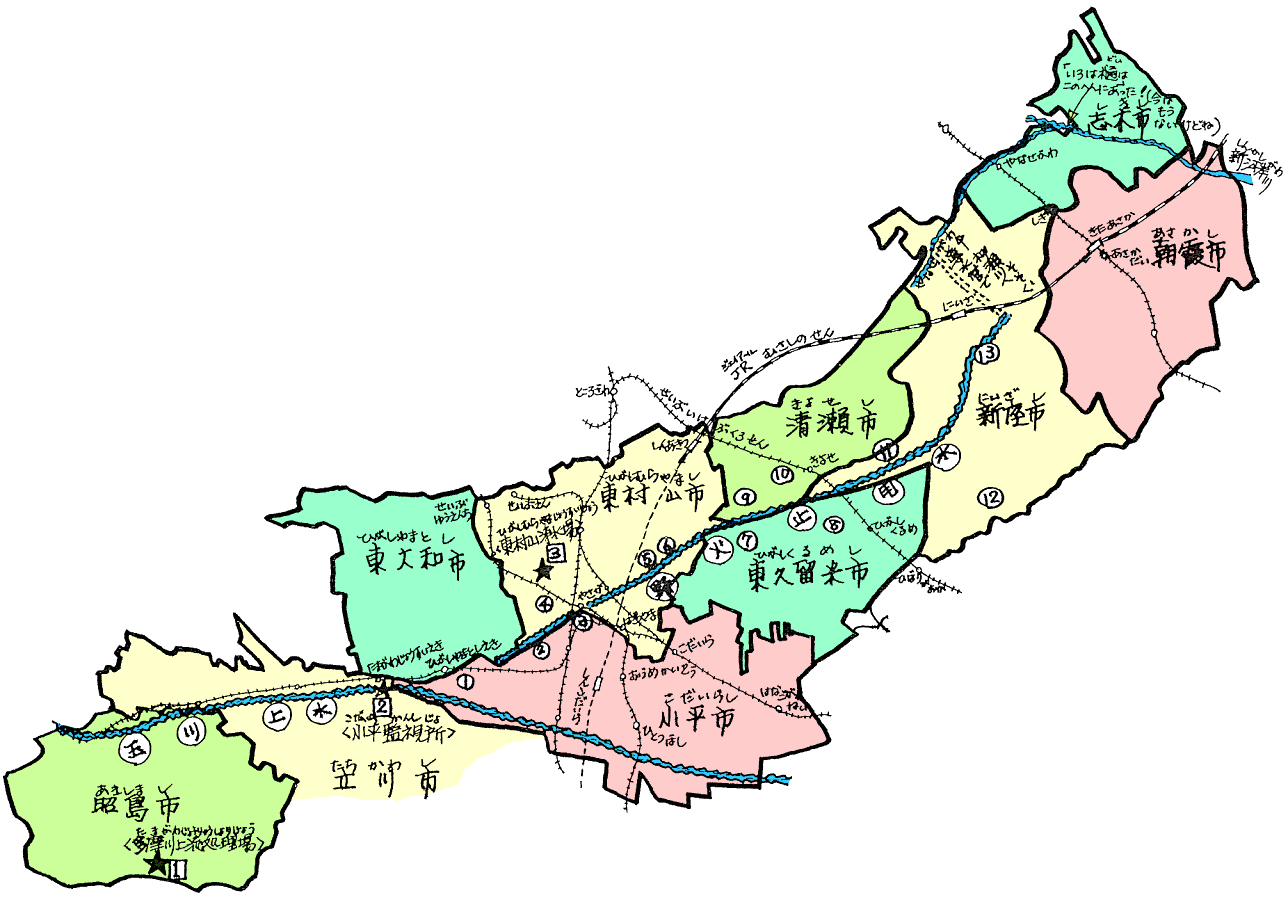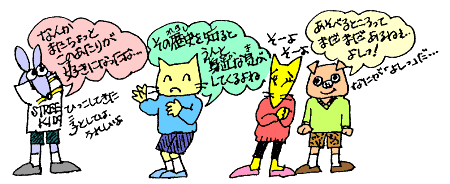野火止用水とは
野火止用水って、知ってる?
承応4年(1655)に作られた玉川上水の分水なんだ。
取入口は多摩郡小川村(今の小平市中島町)だった。
水路は小平市、東大和市、東村山市、清瀬市、東久留米市の間をぬって埼玉県にはいる。
むかしは新座市から志木市の新河岸川に流れこむコースだったけれど、今は、平林寺のちょいと先から地下にもぐり、導水管で柳瀬川にそそいでいる。(「野火止用水おさんぽマップ」を参考にしてね。)
完成当時、その距離24キロメートル(25キロメートルとも)。水の深さは深いところでおよそ90センチメートル。浅いところで60センチメートル。幅は狭いところで1.8メートル。玉川上水からの分水量は30パーセント。
玉川上水の分水の中では、野火止用水は最大規模だ。
もっとも古く、もっとも距離が長く、もっとも分水量が多い。
野火止用水は、どうやって誕生したんだろう? どんな歴史があるんだろう? ちょっとのぞいてみたいよね。
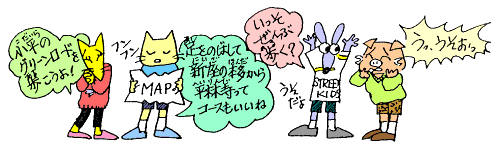
野火止用水 年表
野火止用水 年表
| 年 |
できごと |
| 承応元年(1652) |
老中松平伊豆守信綱、総奉行となって、庄右衛門・清右衛門兄弟に、玉川上水の工事を命じる。 |
| 承応2年(1653) |
玉川上水の工事始まる。2回の失敗の後、安松金右衛門が兄弟の手助けをしたといわれている。
信綱、野火止の新田開発を始め、農家55戸(54戸という説も)を移住させる。 |
| 承応3年(1654) |
玉川上水完成。そのてがらとして、信綱、自分の領土である野火止への分水を幕府から許される。 |
| 承応4年(1655) |
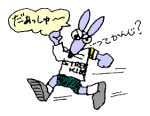 2月10日より、野火止用水の工事始まり、3月20日に完成する。24~5キロメートルの水路をわずか40日間で掘り通したわけだ。 2月10日より、野火止用水の工事始まり、3月20日に完成する。24~5キロメートルの水路をわずか40日間で掘り通したわけだ。 |
| 寛文2年(1662) |
信綱、亡くなる。 |
| 寛文3年(1663) |
信綱の子輝綱、岩槻の平林寺を野火止に移す。 |
| 明治36年(1903) |
野火止用水の使用組合できる。この組合による用水の管理は、今も、新座市、朝霞市、志木市によって引きつがれている。 |
| 昭和19年(1944) |
埼玉県が野火止用水を県史跡に指定。 |
| 昭和24年(1949) |
野火止地区に簡易水道ができはじめ、飲み水としての利用が減り始める。 |
| 昭和30年代後半 |
流域で、急な宅地化がすすむ。 |
| 昭和48年(1973) |
東京都の水事情の悪化などの理由から、玉川上水からの分水、止められる。
6月、「平林禅寺の自然を守る会」より、東京都へ野火止用水の「歴史環境保全地域」指定と、用水を守ってほしいという要望書が出される。
9月、東京都と埼玉県の連絡会議で、埼玉県が野火止用水の流れを復活させることを要望する。 |
| 昭和49年(1974) |
4月、立川市・東大和市・東村山市・清瀬市・東久留米市、そして小平市とで「野火止用水保全対策協議会」をつくる。
12月、東京都、条例に基づいて、野火止用水を「歴史環境保全地域」に指定。 |
| 昭和54年(1979) |
東京都と埼玉県、連絡会議で、野火止用水の流れを早くもとにもどそうと決める。通す水には多摩川上流処理場の下水処理水を利用することにする。 |
| 昭和56年(1981) |
野火止用水への導水管の工事、始まる。 |
| 昭和59年(1984) |
 工事完成。この年、ついに野火止用水の流れは復活した。 工事完成。この年、ついに野火止用水の流れは復活した。 |
野火止用水の歴史 その1
のぶつな ねんぴょう
| 年 |
できごと |
| 慶長元年(1596) |
10月30日 大河内金兵衛久綱の長男として生まれる。 |
| 6年(1601) |
叔父、松平正綱の養子となる。 |
| 8年(1603) |
徳川秀忠(2代将軍)、ついで家康(初代将軍)に初おめみえする。 |
| 9年(1604) |
7月17日 徳川家光(3代将軍)誕生。
7月25日 信綱、家光のお付きとなる。 |
| 16年(1611) |
11月15日 信綱元服。(つまり成人式) |
| 元和9年(1623) |
7月 伊豆守に任ぜられる。 |
| 寛永10年(1633) |
5月5日 老中職につく。
3万石武蔵国忍城、城主となる。 |
| 15年(1638) |
2月28日 島原の乱をおさめる。 |
| 16年(1639) |
正月5日 島原の乱のてがらにより、6万石、川越城、城主となる。 |
| 慶安4年(1651) |
4月20日 家光亡くなる。
信綱、家綱(4代将軍)につかえるようになる。 |
| 承応元年(1652) |
玉川上水工事の総奉行となる。 |
| 2年(1653) |
野火止の新田開発にのりだす。 |
| 3年(1654) |
玉川上水完成。 |
| 4年(1655) |
野火止上水完成。 |
| 寛文2年(1662) |
3月16日 信綱、亡くなる。67才。金重村平林寺に埋葬。 |
| 寛文3年(1663) |
信綱の生前の計画どおり、平林寺を野火止に移す。 |
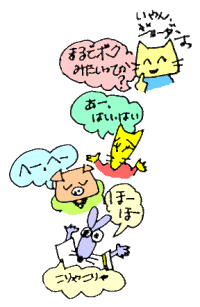 寛永10年(1634)、忍城(今の埼玉県行田市)3万石の城主となった松平伊豆守信綱。禄高こそ多くはないが、将軍家光自慢の家臣だった。
寛永10年(1634)、忍城(今の埼玉県行田市)3万石の城主となった松平伊豆守信綱。禄高こそ多くはないが、将軍家光自慢の家臣だった。
なにしろ、この人、「知恵伊豆」(“知恵が出ず”にかけてる)と呼ばれるほどに頭がいい。
「伊豆のような家来がもうひとりいたら、(自分は)天下の世話などやかなくてすむ」とか「将軍になる人は多いだろうけど、自分くらい幸せ者はいない。右手に讃岐(老中の1人、酒井忠勝のこと。この人も、まじめ、努力家、有能)、左手に伊豆がいる」とかね。家光にほめられまくってるんだ。
幕府の中にあっては老中として基礎づくりに力を尽くし、川越の藩主としては、野火止用水を引いて、新田開発をし、藩の政治を確かなものにするため、働いた。
2.まずは、玉川上水
ふえる一方の江戸の住民の飲み水を手に入れるため、玉川上水は計画された。多摩川の水を羽村から引いて、四谷の大木戸まで43キロメートルの水路を作ろうというわけなんだ。
工事を担当したのは庄右衛門、清右衛門の玉川兄弟。一方、松平伊豆守信綱は、この計画の総奉行を命じられた。(司令官のようなものだね。)
工事はたてつづけに2度失敗。幕府は計画を中止しようとした。けれど信綱はあきらめなかった。
3度目は、信綱の家臣安松金右衛門が、得意の測量の技術をいかして、玉川兄弟の仕事を助けたともいわれ(でも、ちゃんとした記録が残っていないんだよね)、承応3年(1654)、玉川上水は完成する。
3.野火止の平林寺
信綱の
一族と
平林寺とのつながりは、
祖父の
大河内金兵衛秀綱がこの
寺に
葬られたことに
始まる。
もともとは
武蔵国金重村(
今の
埼玉県岩槻市)にあった。それを
野火止に
移そうとした
信綱のねらいは
新田開発にかかわりがあるという。
平林寺を
新田開発の
中心にすえて、
開拓農民たちの
心の
支えにしたかったのだ。
また、こういう
説もある。
川越は
江戸城を
守る
大事な
拠点だ。
万一江戸城が
攻められた
時には、たくさんの
武士を
集められる
場所が
必要になる。
平林寺を
移したのはそのためだ。
戦さ
用の
食糧は
野火止新田から
調達できるしね。
玉川上水の
水を30
%も
分水できるようになっているのも、こうした
非常事態を
考えてのことかもしれない。

4.技術者 安松金右衛門
安松金右衛門吉実。先祖は播州(兵庫県)の出だという。正保元年(1644)より信綱につかえるようになった。信綱の命を受け、野火止用水を作ったのはこの人だ。
玉川上水の時も、その設計技術をいかして、庄右衛門、清右衛門兄弟の工事に手助けをしたのではないかと言われる。
寛文2年(1662)3月に信綱が亡くなると、その子輝綱につかえた。「独礼」といっておおやけの儀式の時、1人で藩主に会い、あいさつすることのできる名誉な格式を与えられていた。それはやっぱり、金右衛門がやりとげてきた仕事が認められていたからなんだろうね。
貞享3年(1686)10月、川越で亡くなった。なきがらは新宿の大宗寺に葬られたけれど、昭和10年(1935)11月、平林寺に移された。今は、彼の能力をいかしてくれた主君、信綱のそばに眠っている。
4.野火止へ水を!
川越城主になった信綱は、新田開発を考えていた。その舞台は野火止。玉川上水の計画が動き始めた承応2年(1653)には信綱はそう決めていた。
野火止も水にめぐまれない武蔵野の台地だ。玉川上水完成のあかつきには、ここにも水を引くぞ、と信綱は考えていたのだろう。
そして、同じ年の8月には、早くも川越の領内から55戸(54戸という説も)の農家が野火止に移って来た。やがて、新座、志木、富士見、清瀬、東久留米のあたりからも開発のための出かせぎがはいってくる。それだけでなく、藩の家臣たちも加わった。(自分のところで使っている者たちに耕作をさせたりしたんだ。)
藩をあげての新田開発は、承応4年(1655)に完成した野火止用水の水にうるおされ、めざましく生産量をあげていった。
野火止の新田開発はその後の武蔵野新田の開発の始まりでもあった。明暦2年(1656)には小川村(もちろん小平市!)が名のりをあげ、よく年、玉川上水2本目の分水、小川分水が作られた。
番外 まわるよ、水車
日本での水車についての記録は、『日本書記』の610年のところに出てくるのが最初なんだ。“水車の力でひく石臼をつくった”と書かれているよ。
江戸時代にはいって、新田開発が盛んになると、農業は発達した。今までより農産物がたくさんとれるようになると、今度はそれを商品化するようになる。商品をたくさん作るには人間の力だけでは間にあわない。そこで水車の動力が注目された。
武蔵野の場合は、江戸に近いし、麦やソバの畑作地帯だったから、水車の力でそれらを製粉しては、商品として、江戸に運んだ。
でも、水車は誰にも彼にも作れたわけじゃない。作る費用も高かったし、水車で商売をするには、「冥加金」(税金です)が必要だった。
そういうお金を負担しても、充分見あう働きをする。それが水車だったから、江戸時代半ばから、明治の頃まで水車かせぎは盛んだった。
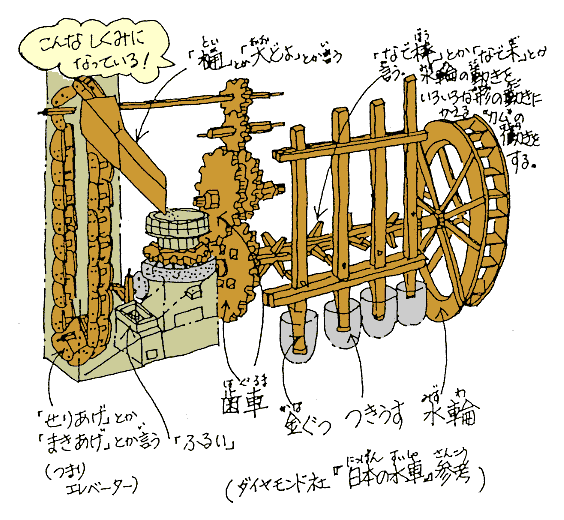
野火止用水の歴史 その2
5.生活とむすびついた水
野火止用水の
水は、
飲み
水、
風呂、すいじ、
洗たく、と
生活のあらゆることに
使われて、これが
終戦後まで
続いた。
水遊びや、
火事の
時の
消火のためにも
使われたし、
水の
流れを
利用して
水車がまわされた。
宝暦12
年(1762)に
最初の
水車が
作られてから、
大正時代頃まで、
新座市内だけでも
野火止用水でまわる
水車は34
個以上。
精米や
製粉をして
働いていた。
大切な
用水の
水は、
江戸時代から
野火止村など9か
村で
作った
組合が
管理をしてきた。
水がれの
時は、
江戸の
飲み
水である
玉川上水が
優先で、
野火止用水にまわされる
水は「2
歩止め」「3
歩止め」と
制限される。そんな
時は
組合が、
幕府の
役所などに、
水をまわしてもらう
願いを
出しに
行ったりした。
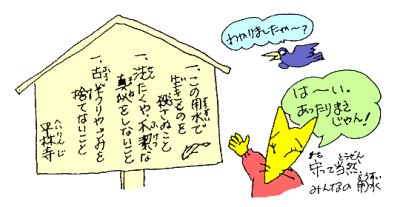 組合
組合ばかりではなく、
平林寺も、
野火止用水を
守るため、
高札(
掲示板みたいなもの)で、まわりの
人々に
呼びかけた。
用水の
水はみんなの
大切な
命の
水だったからね。
明治36
年(1903)5
月には、
北足立郡大和田町など2
町2
村で、
用水管理のための
組合が
作られた。これは
現在、
新座市、
朝霞市、
志木市の3
市で
作る「
野火止用水使用組合」に
続くものだ。
6.止められた野火止用水
戦後の東京はたびたび異常渇水におそわれた。(つまり、水不足。こどもきょうどしりょうNo.24『東京の水道』を参考にしてね。)
そのつど、野火止用水は玉川上水とともに流れる水の量が減り、流域の人たちは困ってしまった。
さらに昭和26年(1951)、用水の水から赤痢が発生。このことが昭和24年(1949)に誕生していた簡易水道の普及をうながすことになった。
昭和30年代後半になると、上流の小平市や東村山市で宅地化が急に進んだ。家庭で使った汚れた水が流れこむようになり、野火止用水は汚染していった。
流域の新座町では、野火止用水に頼らない、本格的な上水道を作ろうと動きだした。
用水の汚染と上水道の普及の中、昭和48年(1973)、ついに東京都は、野火止用水への分水を止めたのだった。
番外野火止用水の「いろは樋」
野火止用水は
初め
新河岸川に
流れこんでいた。けれど
対岸、
宗岡村(
今の
埼玉県志木市)の
地頭、
岡部忠直の
願いによって、
川を
懸樋でまたいで、
用水の
水を
川向こうの
水田かんがいに
利用することになった。
設計と
工事を
担当したのは
忠直の
家臣の
白井武左衛門(
安松金右衛門が
作ったという
説も。)
武左衛門は、
柳瀬川と
新河岸川が
合流する
地点の
下流に48
個のます
型の
樋をつなぎ
合わせて、
水を
通そうと
考えた。
寛文2
年(1662)、
野火止用水ができて7
年後、
懸樋は
作られた。
長さ358m。
幅60cm。ます
型の
樋の
数から、いろは48
文字になぞらえて、「いろは
樋」と
呼ばれた。
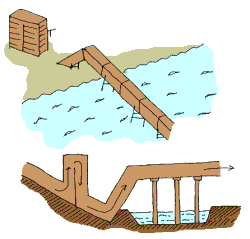
(『
玉川上水と
分水』
参考)
坂の
上に
作った
木の
箱(
小ます)に
水をため、そこから
地面の
下の
木の
樋をつたって、
大ますまで
勢いよく、
水を
通す。
大ますいっぱいになった
水は、そのまま、いろは
樋によって、
新河岸川を
渡る。
水をいったん
高い
所にあげてから
低い
所に
移す、「サイフォン
式」だ。
「野火止」の地名
飛鳥・奈良時代、朝鮮半島から日本へ渡って来た人たちがいた。彼らは武蔵野の地にも住みついて、麻や紫根(ムラサキの根、染料だよ)を栽培して、この原野で焼畑農業をおこなった。
畑を焼く野火の煙は、遠くからながめると紫色に見える。「紫にかすむ野」が武蔵野の名のはじまりともいうし、紫根がとれるので「紫野」と呼ばれたのがはじまりだともいう。野火止の地名は、焼畑農業にかかわりがある。「野火止」というのは、野焼きの火が家に飛び火しないように築かれる塚や堤のこと。はじめ「野火留」と書くことが多かったけれど、元禄10年(1697)頃から、「野火止」とも書かれるようになっていた。
野火止用水、またの名は…
ずばり、「伊豆殿堀」。野火止用水の恩恵を受けた人びとは、伊豆守であった信綱への感謝をこめて、こう呼んだ。地元では「いずてんぼり」とも言うらしい。
7.復活
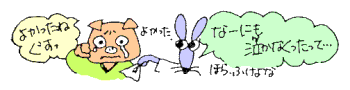 野火止用水
野火止用水の
流れを
取り
戻そうという
声はすぐにあがった。
昭和48
年(1973)6
月、「
平林禅寺の
自然と
文化を
守る
会」が
水質調査をして、
東京都知事に、
野火止用水の
都内流域全てを「
歴史環境保全地域」に
指定するように
要望した。(
埼玉県では
昭和19
年3
月31
日に
史跡指定している。)
3ヶ
月後の9
月には、
東京都と
埼玉県の
連絡会議で、
野火止用水の
整備の
問題がとりあげられた。
12
月には
埼玉県が、また
昭和49
年(1974)6
月には
埼玉県と
野火止用水使用組合が
協力して、
用水流域の
文化財や、
環境、
水質などの
調査をおこなった。
それから
半年後の12
月、
東京都は
小平市から、
野火止用水が
小金井街道にぶつかる
埼玉県境までの9.6キロメートルを「
歴史環境保全地域」に
指定した。
昭和54
年(1979)11
月の
東京都と
埼玉県の
連絡会議で、
多摩川上流処理場(
昭島市)の
処理水を
送り、
野火止用水の
流れを
復活させようという
提案がされる。
そのためには
昭島市の
処理場から、
小平市栄町の
放流口まで、
処理水を
送る
導水管を
通さなければならない。
工事には
昭和56
年度~59
年度まで、4
年間を
費やした。
昭和59
年(1984)8
月、ついに
野火止用水に
流れが
帰ってきた。300
年もの
間、
地域の
人のくらしにむすびついて、
生きてきた
用水は11
年ぶりに
息を
吹き
返したのだった。
歴史環境保全地域って?
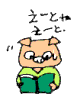 歴史的
歴史的な
遺産とひとつになった
自然があり、その
両方を
保護する
必要のある
地域のこと。
野火止用水おさんぽマップ
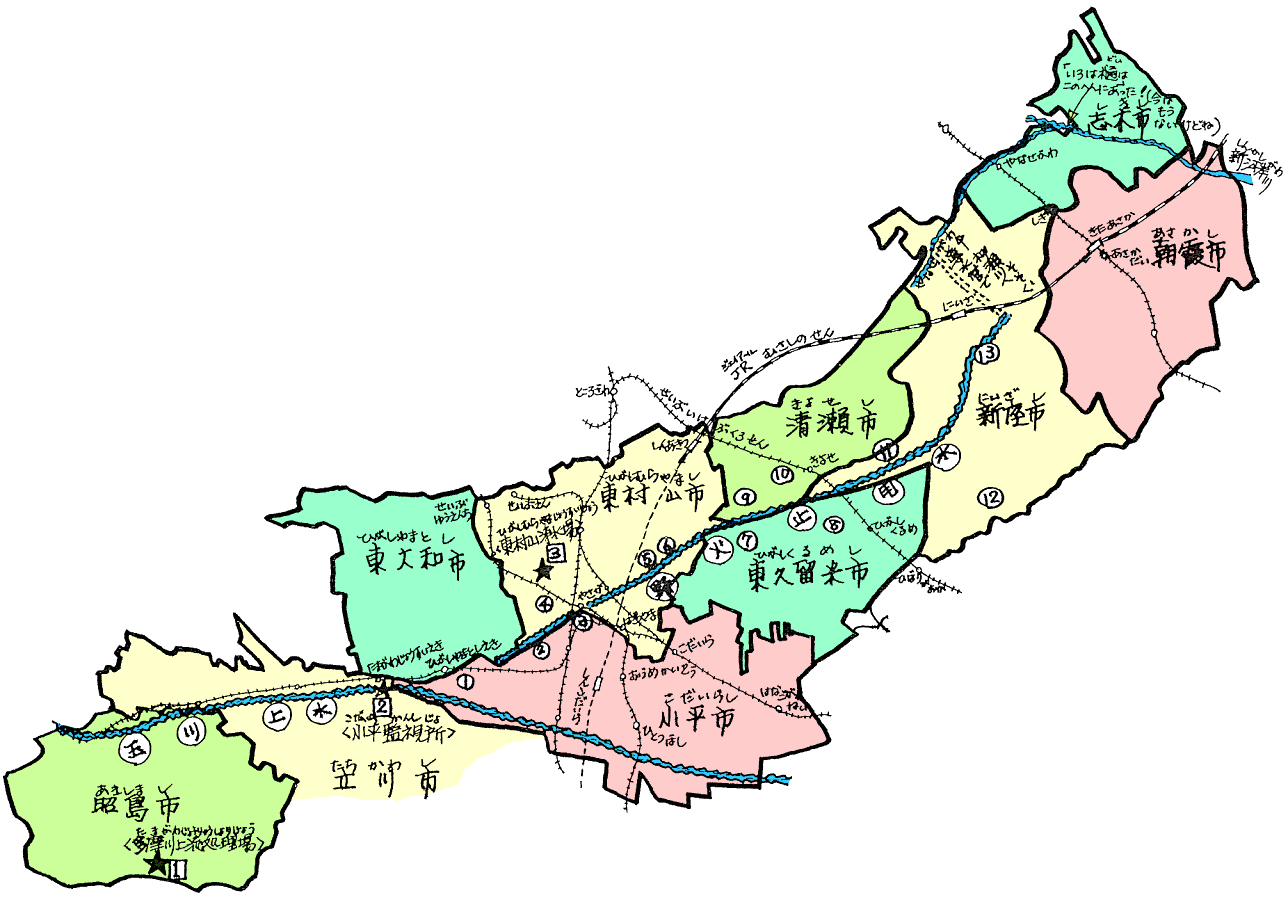
1.東京都薬用植物園
小平市中島町21-1 東大和市駅下車、徒歩2分
薬草を理解してもらうために、昭和20年9月にできた植物園。およそ32,500平方メートルの園内には世界中の薬草が1,600種類も植えられ、季節ごとに花が咲くよ。
2.野火止緑地
小平市栄町の市境地域 東大和市駅下車、徒歩15分
野火止橋から、ふれあい橋、どんぐり橋と野火止用水を下ってゆけば、雑木林にかこまれたグリーン・ロード。すてきな散歩道だ。
3.九道の辻公園
小平市小川東町2-3-4 八坂駅下車、徒歩3分
玉川上水と同じく歴史的遺産、野火止用水の持つ「水」「武蔵野」をイメージした彫刻がならぶ。
平成元年にできた池、滝、築山、あずまやがそろった和風の公園。
4.都立東村山中央公園
東村山市富士見町5-4-67 八坂駅下車、徒歩5分
121,099平方メートルの広い園内には林あり、バード・サンクチュアリーあり。狭山・境緑道のすぐそばだから、サイクリングの時、寄るのもいいよね。
5.恩多野火止水車苑
東村山市恩多町3-32-3 八坂駅下車
天明2年(1782)から昭和26年(1951)の間、ここには「当麻水車」とよばれる水車があった。
野火止用水の流れを利用して、製粉・精米・自家発電をおこない、貴重な動力だった。この水車を再現した水車苑は野火止用水を歩く人たちのいこいの場として平成3年につくられた。
6.万年橋の大ケヤキ
東村山市恩多町1-11
承応3年(1654)、野火止用水を掘る時に、すでに大木だったので、その下を通して水路をつくった。木が橋のように用水をまたいでいるので「万年橋」とよばれるようになった。樹令は600年くらいだ、という説といやいや、野火止用水ができたあとだ。樹令300年くらいだ、という説があり。いずれにしても大ケヤキ! 昭和44年3月、市の天然記念物に指定。
7.下里本邑遺跡公園
東久留米市野火止3-3-4 東久留米駅より西武バス「都大橋」下車、徒歩5分
この地域の人間の歴史は古い!
約25,000年前の先土器時代から、縄文、弥生、奈良、平安時代に及ぶ遺跡がある。
黒目川の水源地だった東久留米市内には他にも130以上もの遺跡が見つかっている。やっぱり水って生活にはかかせないもんね。
8.小山台遺跡公園
東久留米市1-10 東久留米駅下車、徒歩10分
中学生を中心に、市民の手で調査した縄文時代の遺跡。竪穴式住居が復原してあるし、ここの高台からは市内がひと目で見わたせる。
9.竹丘自然公園
清瀬市竹丘3-691-6 清瀬駅下車、徒歩30分
それほど広くはないけれど、武蔵野ではめずらしくなった野草が保護されていて、野草公園として人気あり。
10.松山緑地公園
清瀬市中里4-650 清瀬駅下車徒歩15分
池を中心に、滝にふん水に広い芝生。広さは43,300平方メートル。武蔵野のふんいきをあじわえる。
11.西堀・新堀コミュニティーセンター
新座市新堀1-5-9
野火止用水の史跡資料の展示室があって、江戸時代の用水の古絵図のパネルや写真の資料などがある。展示室は利用されている日もあるから、見学できるかは、行く前に確かめようね。
042-492-4655
12.新座市立歴史民俗資料館 月よう、祝日、お休み!
新座市片山1-21-25
野火止用水にはかつてたくさんの水車がかかっていた。ここではその水車の資料をあつめ、展示している。
13.平林寺
新座市野火止3-1-1 新座市駅下車
調布の深大寺とならぶ武蔵野の歴史あるお寺。もともとは永和元年(1375)に太田道灌のおとうさんが武蔵国金重村(今の岩槻市)に建てたのがはじまり。松平伊豆守信綱も、安松金右衛門もここに眠る。
1. 多摩川上流処理場
昭和53年5月に動き出した下水処理場。昭島・福生・青梅・立川・武蔵村山・羽村・瑞穂の下水を処理している。この処理水が野火止用水の流れにいかされている。
2. 小平監視所
江戸時代で言えば水番所。上水のゴミをとりのぞいたり、水位を監視したり。ここから先は導水管で上水を東村山浄水場へ送る。
3. 東村山浄水場
多摩川系と利根川系の両方から水をとり入れ、浄化して、あちこちに水を送っている。小平市内を通っているサイクリング道路の下にはその水道管が通っているよ。
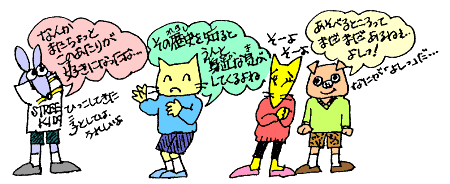
参考にした本
「野火止用水」
「新座市史」
「清流の復活」
「東久留米市の文化財」
「東村山の文化財・史跡」
「九道の辻公園あんない」
「玉川上水・親と子の歴史散歩」
「西武新宿線歴史散歩」
「最新多摩あるくマップ」
「史跡探訪関東100選」
「わたしの街の散歩道」
小平市、東村山市、清瀬市、東久留米市、新座市、
志木市、その他の地域の地図…などいろいろ。
小平市に関すること
多摩に関すること
江戸・東京に関すること
玉川上水・小金井桜に関すること
その他
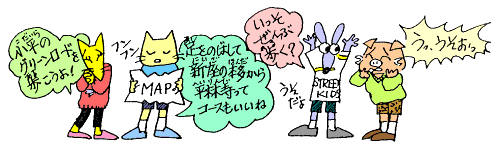
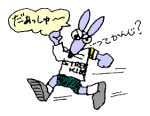 2
2
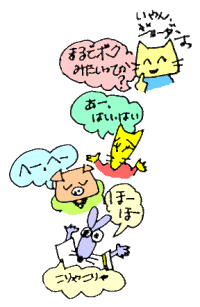

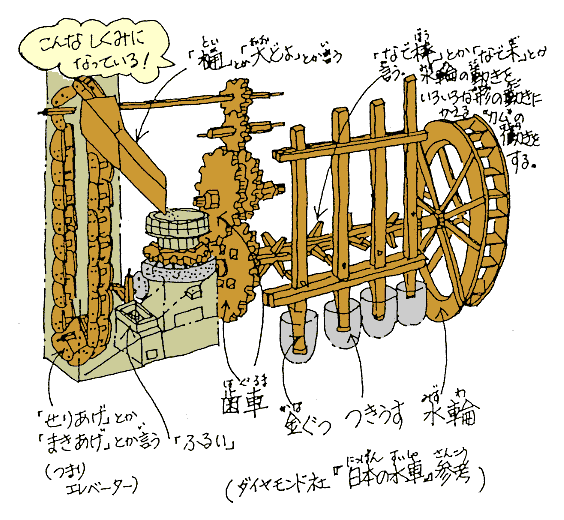
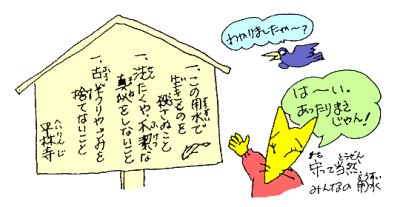
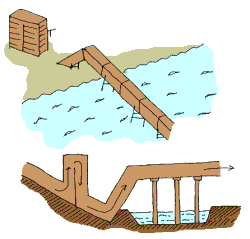 (『
(『