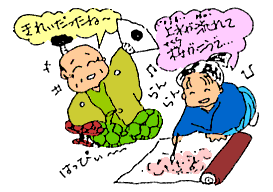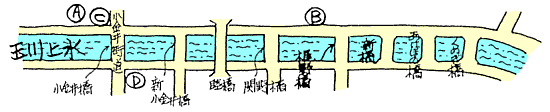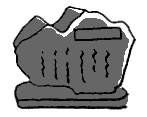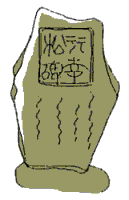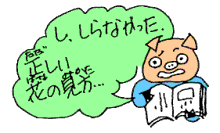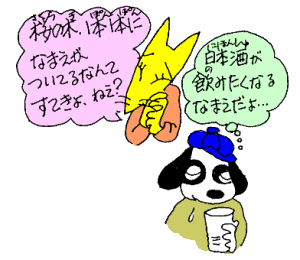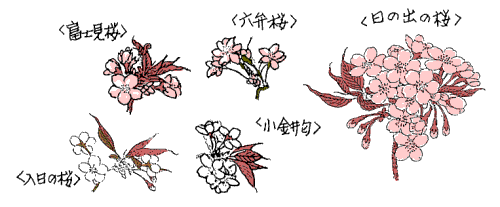名勝小金井桜縁起
江戸時代は元文2年(と言われているが…)。将軍吉宗の命を受け、武蔵野新田の発展に力を尽くす川崎平右衛門は、玉川上水の両岸に桜を植えた。小金井橋を中心に、東西およそ1里(4キロメートルぐらい)の間に、吉野や桜川からとりよせた桜並木ができたのだ。
植えた理由は、桜の花が上水に落ちると解毒のききめがあるから(大切な飲み水だもんね)とか、花見客で堤が踏み固められて、崩れを防ぐから、とか、ここが名所となればまわりの新田の発展になるからとか、いろいろあげられている。江戸から6里あまり(25キロメートルくらいか)も離れていて、不便だったから、初めのころこそ、人に知られていなかったが、享和(1801~)ごろから、江戸の文化人をはじめ、花見客が増え、小金井桜を紹介する本もたくさん出た。
天保15(1844)年には、第13代将軍になる前の家定も花見をしている。なにしろ徳川家のあととり息子だから、その日の前後はもう大さわぎだ。
火を出すな。犬・牛・馬はしっかりつないでおけ。家の中でじっと静かにしていろ…などなどまわりの村々におふれがまわった。明治になると天皇も花見に行幸されたよ。
明治のころの庶民の花見は、歩きのほかに、甲武鉄道(今のJR中央線)や川越線(今の西武国分寺線)を利用した。八木節や追分などを歌う芸人や茶店もでた。お酒や、だんごや、里いものゆでたのを売った。まわりの農家も、花見の時期はみせをだしたらしい。おみやげ屋も出て、造花の桜のかんざしや、お菓子を売った。
酔っぱらいの中には、行儀の悪い人もいて、上水に落っこちたり、ケンカをしたり、酒の空びんを上水に投げこんだり…(本当に悪いやつだよ)。地元の子どもや若者はびんを網ですくって売り、こづかいをかせいだそうだ。
桜をまもる
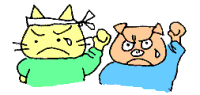 桜
桜も
年を
取ってくると、
花の
勢いがなくなってくる。
並木を
整えるには
植えついでいかなければならない。けれど、
桜は
玉川上水とちがって
誰が
責任を
持つのかはっきりしなかった。
代官大熊善太郎は
家定の
花見をきっかけに
小金井桜の
名を
残すのに
努めた。
嘉永2
年、
上水沿いの
百姓たちに「
由緒ある
上水桜を
村々の
協力で
守れ」とおふれを
出している。そして、この
年、
数百本の
桜の
植え
替えと
手入れがおこなわれた。
安政3(1856)
年にも、
大規模な
植え
替えがおこなわれている。
苗木の
数は、
境村13
本、
梶野新田40
本、
小金井新田121
本、
鈴木新田137
本と
分担して、
計311
本だった。
明治半ばには、
東京大学理学博士、
三好学が
小金井桜の
調査を
始め、
保護を
呼びかけた。この
人は「サクラ
博士」と
言われたよ。
東京市も
力を
入れはじめ、
大正13
年には
国の
名勝に
指定。その
後、
太平洋戦争や
公害を
経て、
今、
小金井の
桜は…。
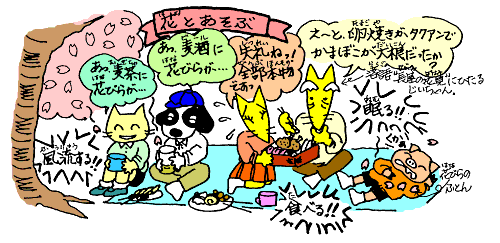
「小金井桜」年表
「小金井桜」年表
| 年 |
できごと |
| 1737(元文2) |
この年、玉川上水の両岸に桜を植える。 |
| 1801(寛政13) |
この年、国学者屋代弘賢が小金井に花見をした時の様子を『不忍叢書』に書く。 |
| 1804(文化1) |
3月12日、俳人(俳句をよむ人)露庵有佐(露々庵とも)、小金井に花見をし、『玉花勝覧』を書く。
これより、小金井は江戸近郊指折りの桜の名所となる。 |
| 1806(文化3) |
2月26日、国学者屋代弘賢、再び小金井を訪れ、『小金井乃記』を書く。
2月、儒学者の佐藤一斎、先生の林述斎と一緒に小金井に花見。『小金井橋観桜記』を書く。 |
| 1809(文化6) |
2月30日、太田蜀山人(南畝)、小金井に桜見物。『調布日記』にこのことを記す。 |
| 1810(文化7) |
3月21日、「小金井桜樹碑」、小金井橋のそばに建つ。 |
| 1812(文化9) |
この年、長州出身の村尾正靖という人が小金井に花見をし、『嘉陵紀行』を書く。 |
| 1813(文化10) |
2月23日、江戸郭然寺の住職、釈敬順が小金井に花見。『遊暦雑記』を書く。 |
| 1833(天保4) |
この年、『江戸名所図会』に小金井桜が紹介される。 |
| 1838(天保9) |
この年、代官大熊善太郎、玉川上水堤に桜の苗木406本を植えたす。 |
| 1849(嘉永2) |
1月、代官大熊善太郎、玉川上水沿いの村の百姓たちに、上水桜の面倒を見させる。 |
| 1851(嘉永4) |
この年、下田半兵衛、玉川上水のほとりに桜の手入れの模様を記した碑(「桜樹接種碑」)を建てる。 |
| 1855(安政2) |
8月、境村・梶野新田・小金井新田・鈴木新田の4か村に、小金井桜の苗木や肥料などの費用を配るため、代官小林藤之助の部下、秋山茂八郎、出張する。 |
| 1856(安政3) |
この年、小金井桜の植え足し、大規模に行う。 |
| 1883(明治16) |
4月23日、明治天皇、小金井に遠乗り。花見をする。 |
| 1884(明治17) |
4月26日、皇太后と皇后、小金井に花見。 |
| 1901(明治34) |
この年、大町桂月、『小金井の桜』を書く。 |
| 1902(明治35) |
4月、「明治天皇行幸松碑」を建てる。 |
| 1903(明治36) |
5月、皇太子、小金井に花見。 |
| 1907(明治40) |
この年、東京大学理学博士、三好学が小金井桜の調査を行う。 |
| 1912(明治45) |
4月、史蹟名勝天然記念物協会と三好学、東京市に小金井桜の保護を願い出る。 |
| 1913(大正2) |
小金井・小平・保谷・武蔵野4か村の有志で「小金井保桜会」(小金井桜を守る会)がつくられる。 |
| 1923(大正12) |
この年の調査では、小金井桜は、南の岸761本、北の岸710本の計1、471本あった。 |
| 1924(大正13) |
12月9日、小金井桜、国の名勝に指定される。 |
| 1927(昭和2) |
この年、三好学、『小金井桜花図説1・2』を出版する。 |
| |
太平洋戦争中と、戦後の混乱した時代には桜の手入れどころではなく、燃料にするため、枝を切られたりして、小金井桜はかなり痛めつけられた。
昭和29年には五日市街道が拡張。
昭和43~53年、小金井市で360本ほど植え足したりしたが…。
排気ガス、その他の原因でこのごろは、老木は枯れ、若木は育たなくなってしまった。 |

小平周辺桜マップ
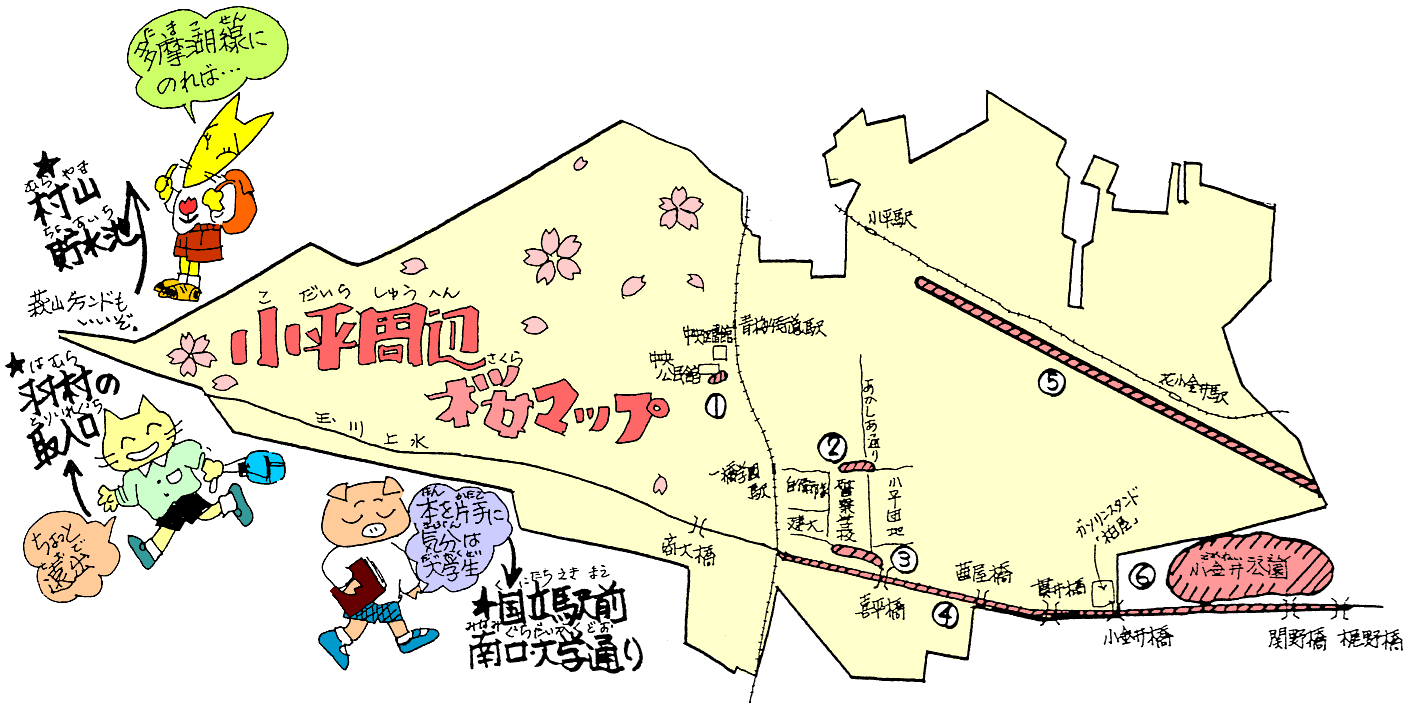
1.中央公民館南側
たかの街道沿い、中央公民館よこの道は、ちょっとした桜並木。
ベンチもあるし、帰りにとなりの中央図書館によるのもGood!だ。
2.警察学校北門前
ここからあかしあ通りに出るまでの歩道50メートルは桜の並木道。
3.警察学校正門前
桜の木40本あまりがつくるピンクのトンネル。ここはゴージャスだぞ。
ただし、花に見とれて車道に飛び出してはいけない。
4.玉川上水堤
やせても、枯れても小金井桜だ。
排気ガスにやられても、毎年健気に花を咲かせている。
5.狭山・境緑道
都立狭山公園から、武蔵野市境浄水場まで10.5キロメートルの遊歩道。ここの花小金井駅東から小金井駅近くの3キロメートルの間は、地元の人たちが植えたソメイヨシノ240本!の桜並木。
6.小金井公園
面積70万平方メートル。武蔵野の面影を残すこの公園。
今では、衰えた玉川上水堤の桜にかわって花見の名所となっている。
山桜、ソメイヨシノを中心にその数2,000本。
江戸時代の小金井桜花見のためのイラスト・マップ
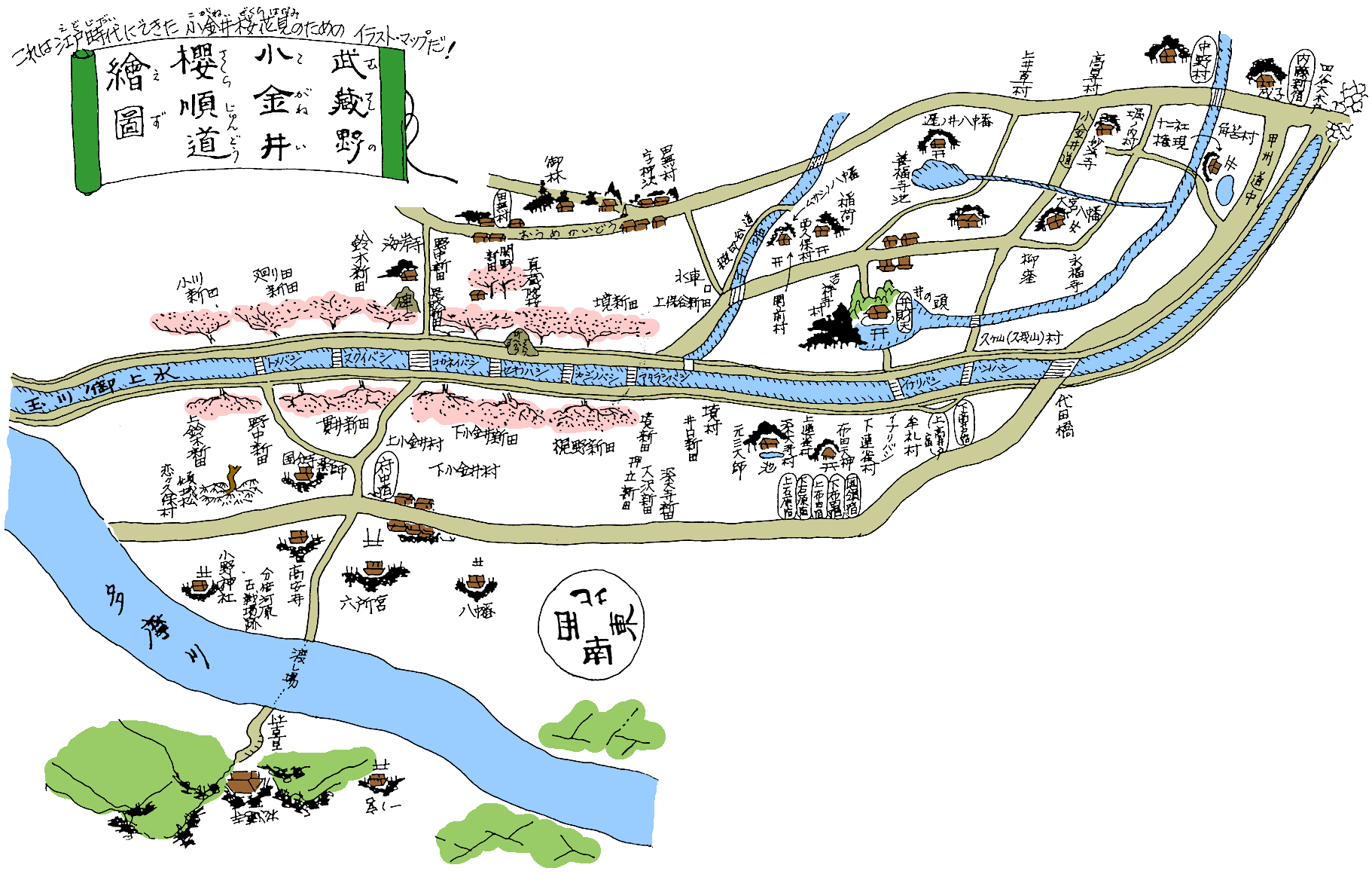
「柏屋」のこと…
「柏屋」は、江戸のころから小金井橋のたもとにあった花見茶屋。今はガソリンスタンドとなって、その名を残している。御幸町の東南端、小金井市との境目のところだ。七代目までは代々勘兵衛を名のり、このあたり一番の料亭だった。
毎年、花見の時分には、酒・しょうゆ・寿司・鮎などの川魚・卵・野菜をうんと仕入れ、料理人やら、給仕女やら、2~30人もの人を雇い入れていた。
明治天皇が行幸の時も、柏屋の前の堤に休憩所が設けられた。明治の頃には、柏屋の他にも、花見時の料理屋や休憩所が、上水の両岸やまわりの空き地にずらり並んだ。紅白の幕を張り、赤いもうせん(フェルトみたいな敷物)を敷き、ちょうちんもつるした。
お寿司・お菓子・だんご・里いものゆでたの・早堀りのタケノコ・鮎などを用意した。他に名の残るみせでは茜屋橋そばの茜屋、角屋などがあった。
「小金井のサクラ」はどこからどこまで?
国が名勝として指定しているのは、小平市学園西町1丁目商大橋の上流から、武蔵野市関前5丁目境橋まで。
その後の小金井桜
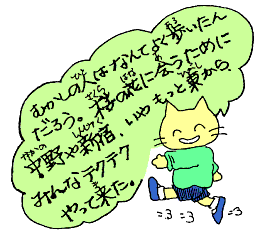 小金井桜
小金井桜が
花見客でにぎわったのは、
昭和の
初めごろまでという。
茶屋は
土手にえんえんと
続き、
流しは
歌を
歌い、
人びとは
仮装したりして
花見を
楽しんだ。
大正から
昭和2
年にかけてつくられた
村山貯水池は
小金井桜の
花見客をめちゃくちゃに
減らした。それと
昭和元年、
小金井駅ができたことも、さびれた
理由の
一つだという。
駅が
武蔵境と
国分寺しかなかった
頃は、
花見の
客はふたつの
駅の
間の
上水べりを
往き
来して、
堤もにぎわった。が、
小金井駅ができると
駅から
小金井橋にまっすぐ
行って、そのまんまとんぼ
返りする
客が
増え、
堤をそぞろ
歩く
人は
少なくなった。
お江戸の本に書かれた小金井桜
1.「四神地名録」 寛政6(1794)年・古河古松軒
小金井桜をはじめてとりあげた本。古河古松軒は岡山出身の幕府の役人。あちこちの土地で、人々のくらしぶりをよく観察した。「四神」とは、4つの方角という意味。これは、江戸の東西南北の近郊について書いた本なんだ。
「満開の様子は何とも言えぬ絶景。江戸に近ければ、もっと人が集まるだろうに…。ほめる人もないのに、毎年毎年、咲いては散るのは可憐なことだ。」と言っている。
この本に書かれてから、江戸の人々もだんだん小金井桜の美しさを知るようになった。
2.「享和雑記」
「四神地名録」より6~7年後に書かれたらしい。享和年間の町の様子を書く。小金井を行楽地として紹介した最初の本。
寛政の改革も一段落して、レクリエーションを求める江戸の人々に、小金井桜の花見が流行しはじめる。
「小金井桜の見事なのは、炭を運んだり、下肥を汲んでいく、村から来る連中のうわさで聞くとおり。江戸から7里よりは近い。帰りには井の頭弁天、大宮八幡にも寄れる。」と書いている。
ここから先、小金井桜の花見の紀行文がぞくぞく出る。
3.「小金橋にあそふことは」 享和年間(1801年ごろか?)・屋代弘賢
屋代弘賢は、幕府の御家人の子で、国学者。享和元年3月、44才の時、小金井桜の花見をした。
「桜を植えた川崎(平右衛門)の志を生かすため、また、これから花を訪ねて行こうとする人のため、この文を書いた。」という。
4.辻知篤の紀行文
この人は、幕府の御徒士(下級武士)。享和3年2月24日、友人たちと小金井桜の花見をする。朝6時ごろ、牛込(今の新宿区)の家を出て、夜10時に家に帰りつくまでが書かれている。自分の連れて来た犬を、他の犬から守ったり、道をまちがえて、さんざんな目にあったり。飾らない、珍道中の花見なのだ。
5.「玉花勝覧」 文化元年(1804)・露庵有佐
有佐は俳人(俳句をつくる人)。文化元年3月12日、師匠や友人を誘って、小金井桜の花見。この紀行文は、小金井を江戸近郊でも指折りの名所にのし上げた。
題名の「玉花勝覧」は玉川上水堤の花見、という意味。村やみせの略図入りの道案内絵図が6ページものっていて、ガイドブックとして最適だった。
ところで、読み方なんだけど、どうして「ぎょくかしょうらん」ではないのかなあ。「王」じゃなくて「玉」なのに。
6.「小金井乃記」 文化3(1806)年・屋代弘賢
この年、2月26日。(3)の「小金橋にあそふことは」の屋代弘賢が再び小金井を訪れて書いたもの。
「上水堤には、すみれ、たんぽぽ、かふろ草などが咲き、南北には、桜や竹のむこうに、桃の花が眺められ、たいへん楽しい。」と言っている。
7.「小金井橋観桜記」 文化3(1806)年・佐藤一斎
この年2月、儒学者の一斎は、師の述斎と小金井桜の花見。ここの桜と、隅田川の桜とではどちらがすぐれているか、話題になった。
「玉川上水は、川はばが狭いから、隅田川の雄大な眺めには負ける」と述斎が思った時、折りからの風で、2人は桜吹雪に包まれた。その見事さに、述斎は「こりゃ、すごい! わたしがまちがっていた。」と叫ぶほかなかった。
隅田川のように混雑しておらず、しみじみとした趣きのある小金井桜の眺めの勝ちだ、と述斎はぬくい橋にたたずんで言いきったとか。
8.「調布日記」 文化6(1809)年・太田蜀山人
太田蜀山人(南畝)は、幕府の役人でもあり、狂歌・戯作を書いた江戸文学のヒーローでもある。
この年、2月23日、小金井桜を見る。時に蜀山人、61才。
「ひごろ、桜が好きで、江戸中くまなく見歩いたけれど、これほど果てなく桜を見たことなんてなかった。61才にしてこんな桜は初めて見た。今日から遠桜山人と名のる」と感激しているのだ。
9.「嘉陵紀行」 文化9(1812)年ころ・村尾正靖
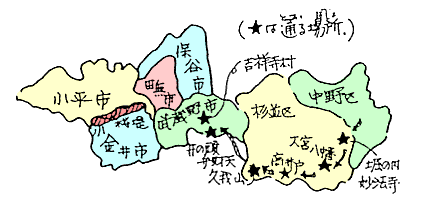
「
中野から
堀の
内妙法寺(
杉並区)をすぎ、
大宮八幡宮へ
詣で、
高井戸を
通って、
久我山へ
行き、
井の
頭弁財天をおまいりして、
吉祥寺村に
出、
大通りを
行って
保谷村。さらに
西南へ
行けば
玉川上水に
出て、
川に
沿って
西へ
行けば
小金井だよ」と
言う。こんなコースかな?
10.「遊歴雑記」 文化10(1813)年・釈敬順(号は十方庵)
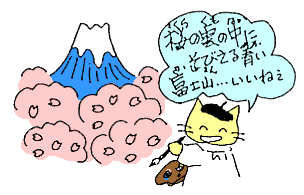
この
年2
月23
日、
江戸小日向水道町の
郭然寺住職、
釈敬順が、
小金井桜の
花見。
「
花の
時期は、
立春の70
日後くらい。
絶景は、
小金井橋からの
眺めで
西には
富士箱根が
見え、
両岸の
桜は
前も
後ろも
尽きることがない。」と
言う。
11.「観花図巻」 文政9(1826)年・有馬誉純
この
年3
月、
越前丸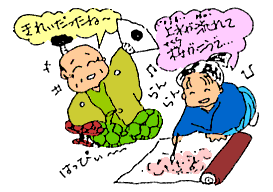 岡藩有馬誉純
岡藩有馬誉純が
息子と
家臣をともなって
小金井へ。
大名の
花見だ。
江戸から
馬で
遠乗りし、
家に
帰ると
花見の
紀行と、
絵と、
詩歌を
集め、1
冊の
本にした。
このお
殿さまは、
文学にくわしく、
絵もじょうずだったということだ。
12.「新編武蔵風土記稿」
文化から文政にかけて、徳川幕府が編さんした武蔵の地理の本。「小金井橋、上下両岸二里ほどの間に、桜の木は数百株。花の盛りには、花見の人が道に続く。小金井の桜として名が高く、人に知られている。」と書いている。
13.「江戸名所図会」 天保4(1833)年・斎藤月岺
江戸とその近郊の見どころガイドブックの決定版! 全部で7巻20冊!
斎藤月岺は神田雉子町の名主さん。この中に「金井橋」がでてくる。この本には、「(小金井桜は)立春から54~5日から咲きはじめ、60日目満開、70日目で落ちる。」とある。
4ページにもおよぶ長谷川雪旦のさし絵は人目をひきつけた。
14.「東都歳時記」 天保7(1836)年・斎藤月岺
「江戸名所図会」と同じく、斎藤月岺が作った。
「江戸名所図会」より、こちらの方が「金井橋」の説明がくわしい。
15.「江戸名所花暦」 天保8(1837)年・岡山鳥
天保ごろの小金井桜の様子がよく記されている。関野新田・保谷新田のあたりに、そば、酒を売るみせあり、とか。関野の真蔵院門前に茶みせがある、とか。関野橋と小金井橋の間には橋が2つあるが、丸木橋かなにかで、農夫が通うためのものだ、とか…。
このころ、小金井橋そばにあった茶みせ柏屋は「この家に宿をとらなくちゃ、花を全て見られない」として1泊する花見客が増えたことも書かれている。
小金井桜 由来の碑
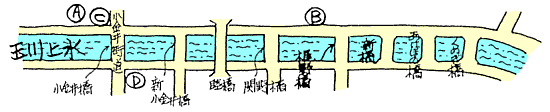
A.小金井桜樹碑 御幸町・海岸寺境内
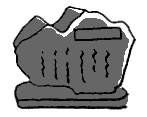 清水村
清水村(
今の
東大和市)の
人、
大久保五郎兵衛忠休(
号は
狭南)は、この
碑を
建てたいと
願いつつ、
完成しないまま
亡くなった。それを
惜しんだ
娘むこの石永貞(石子亨)や、
狭南の
門下生らが
文化7(1810)
年に
完成させた。
碑には、
小金井桜の
由来を
刻むとともに、「『
武野八景』という
本に、
小金井桜の
素晴らしさを
書いたので、
江戸からの
見物客が
増えた。
文章を
書く
人の
中に、いい
加減なものもでてきた。
そこでまちがいを
防ぐため、
石に
刻んだ。」とこの
碑を
建てた
理由がのべられている。
B.桜樹接種碑 小金井市関野町1丁目
 街道
街道に
面した
側には「さくら
折るべからず」とあり、
裏には、
田無の
大名主、
下田半兵衛が
建て、
無量老人という
人の
書だと
刻まれている。
嘉永2
年の
桜の
手入れの
模様を
記録して、
嘉永4
年に
建てられたもの。
碑の
内容は、「
小金井の
桜も100
年たって、
枯れるものも
多いので、
嘉永2
年春、
代官の
大熊(
善太郎)が
田無の
名主半兵衛に、まわりの
村々と
力を
合わせ、
老木には
肥料をやり、
枯れたものは
植えかえるように、と
言い、みな
喜んで
数百本の
桜を
植え
足した。」というもの。
C.行幸松碑 御幸町
明治16
年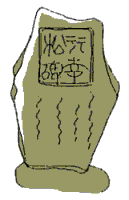
4月23日の明治天皇の花見を記念して、鈴木新田で松を植えた。
明治35(1902)年、さらに海岸寺住職、玄恪が、地元の人々と相談し、松を植えた由来を記した碑を建てた。
碑の裏面には、これに関わった鈴木新田の人々の名が刻まれている。
D.名勝小金井桜碑 御幸町
 大正
大正14(1925)
年、
東京市が
小金井橋のたもとに
建てた。ここが、
日本でも
指折りの
桜の
名所であること、
大正13
年に
国の
名勝に
指定されたこと、
小金井桜の
由来などが
記される。
ちなみに、
小金井桜は
最盛期には
数千本といわれているが、
大正14
年の
東京市の
調査では1168
本、
昭和58
年の
調査では700
本となっている。
ダイジェスト「小金井の桜」
『小金井の桜』。この本は小金井桜の案内のため、大正15年4月に発行された。
“サクラ博士”三好学が指導、東京市公園課が編集した。
小金井桜の位置
小金井の桜は、東京府北多摩郡小平、小金井、武蔵野の3か村を流れる、東京市玉川上水路沿いの岸、1里(約3.9キロメートル)あまりに植えられたもの。
国の名勝に指定されているのは、
南側の岸は、小平村鈴木新田字上580番地から、武蔵野村大字境字上水南1107番地まで
北側の岸は、小平村小川新田字上水内1175番地から武蔵野村関前字樋1280番地まで
つまり、上流は、東京市水道局小川水衛所から
下流は、同じく水道局の境水衛所までの桜並木だ。
花見の道順
 中央線
中央線なら
東京駅から24
分ごとに
発車して、
武蔵境駅まで
約1
時間
武蔵小金井駅・
国分寺駅までだって1
時間20
分以内だ。
花見の
時期は
臨時電車も
出る。
乗車賃は…
東京駅から
武蔵境駅まで
片道35
銭
武蔵小金井駅まで 40
銭
国分寺駅まで 44
銭
一
番ながめが
良いのは、
小金井桜のどまん
中、
小金井橋。
上流を
見ても、
下流を
見ても最高!
境水衛所~(約25町・2700メートル)~小金井橋~(約30町・3300メートル)~小川水衛所
これが“桜の見方”だ!
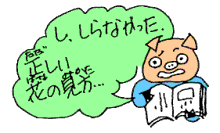 桜
桜を
見るなら、
朝がいい。
それも
太陽を
背にして
見よう。
花が
明るく、あざやかに
見える。
晴れた
青空に
照らして
見るとほんとに
美しい。
小金井桜を
見るには、
朝、
境駅で
降りて、
境水衛所から、
桜並木を
上流に
進んで
行こう。
太陽を
背に、
小川水衛所まで
桜が
楽しめる。
花の時期
年にもよるが、だいたい、4月中旬が盛り。(今なら上旬だよねえ。)
早咲きは4月10日ごろから、
遅咲きは4月20日ごろ咲く。
全体としては2週間くらい咲きつづけるけど、真っ盛りは、わずか3~4日の間だ。
桜の種類
日本の山桜は白山桜と紅山桜に大きく分けられる。小金井桜は全部白山桜だ。
おもに、吉野と桜川からとりよせた。吉野種は花が白く、桜川種は赤い。
白山桜の特徴は、若葉の色がさまざまで、美しいこと。紅色のもの、黄色を帯びたもの、緑のもの…といろいろの色だ。
それに、花の形、枝の様子、匂いの強さもいろいろ。小金井の桜は1本1本が違って美しい。また武蔵野の土の性質にもよく合っている。
山桜は、染井吉野や里桜にくらべると寿命が長い。ただ、都会では環境のせいで、寿命が短いようだ。
桜のなまえ
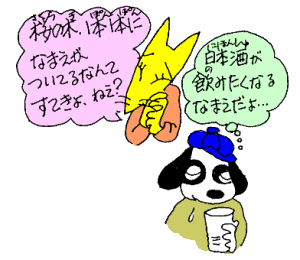 小金井桜
小金井桜の
中でも、
花が
見事だったり、
木が
大きくて
立派なものには、ちゃんと
名前がついている。
日の出の桜 関野橋近く。上水の北側にある大木。美しい赤芽。
入日の桜日の出の桜の先にある大木。黄芽。
六弁桜 茶芽。淡い紅色の花。花びらが6まいになっているものがある。
口紅桜 赤芽。白い花のまん中に紅色のたて筋が通り、花びらの先がうす紅色。
高嶺桜 日の出の桜に似ている。花はうす紅色。
曙桜 小金井の匂桜のひとつ。茶芽で、花は白。香りが強い。
三吉野桜 日の出の桜の近くで上水の南側。樺芽で枝が横に広がり、傘の形をしている。
富士見桜 かつては、小金井の桜並木で一番の大木だった。赤芽。花の数は少ないが、大輪で淡い紅色が美しい。
東天匂 赤芽で、花は白。大輪の匂桜。花の直径が一寸二分(3.6センチぐらい)もある。
小金井匂 赤芽。花は白。これも匂桜。花は東天匂のよりも小さい。
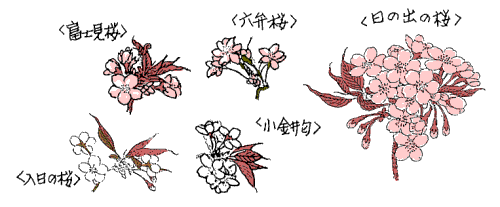
参考にした本
「小金井市誌 第2、第3」
「市報こだいら縮刷版」
「小金井今昔ばなし」
「西武新宿線歴史散歩」
アサヒタウンズ編「玉川上水」
「小金井の桜」
比留間博著「玉川上水」
「明治東京名所図会」
「江戸名所図会 下」
「小平郷土研究会 会報第2号」
「郷土夜話 その1」
「武蔵名勝図会」
「東京の名所・旧跡」
「武蔵野」第66号ほか
「多摩のあゆみ」第4号
などなど…
小平市に関すること
多摩に関すること
江戸・東京に関すること
玉川上水・小金井桜に関すること
その他
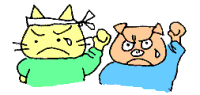
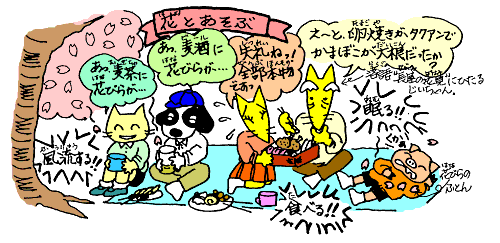

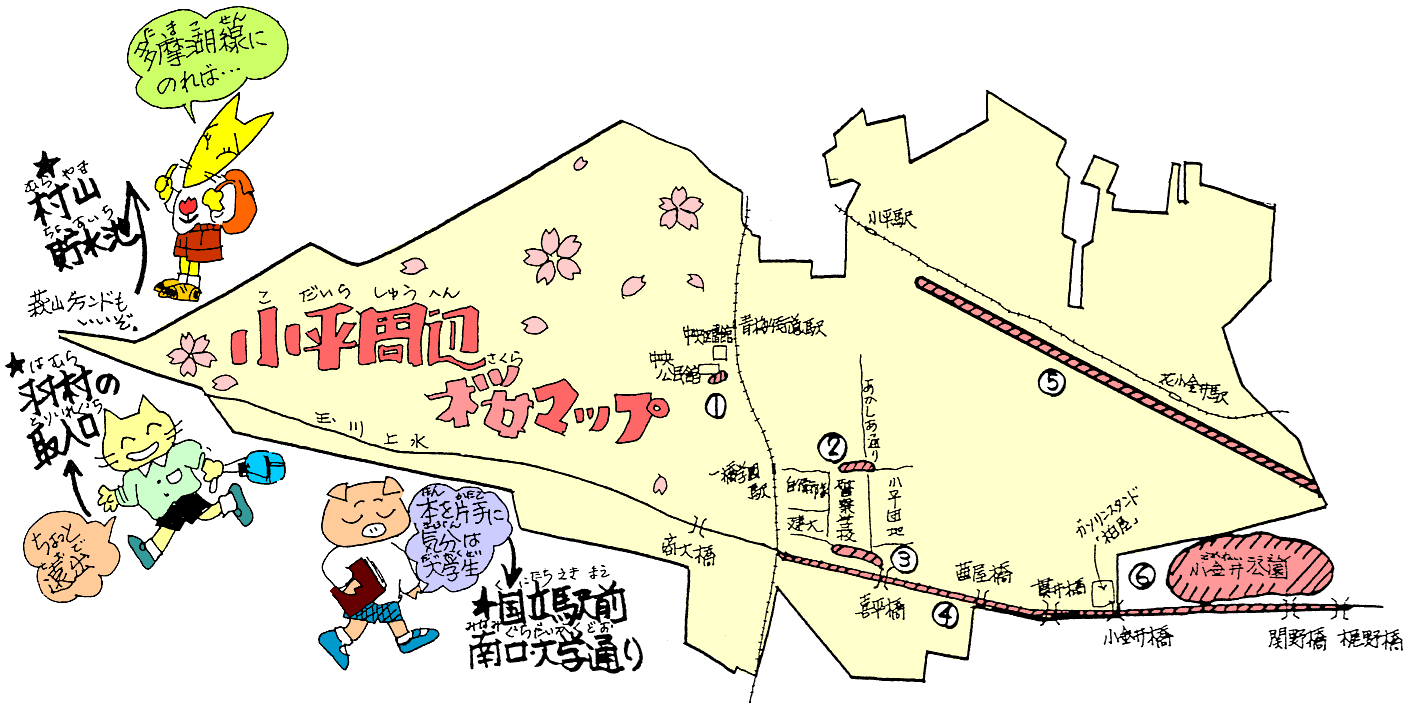
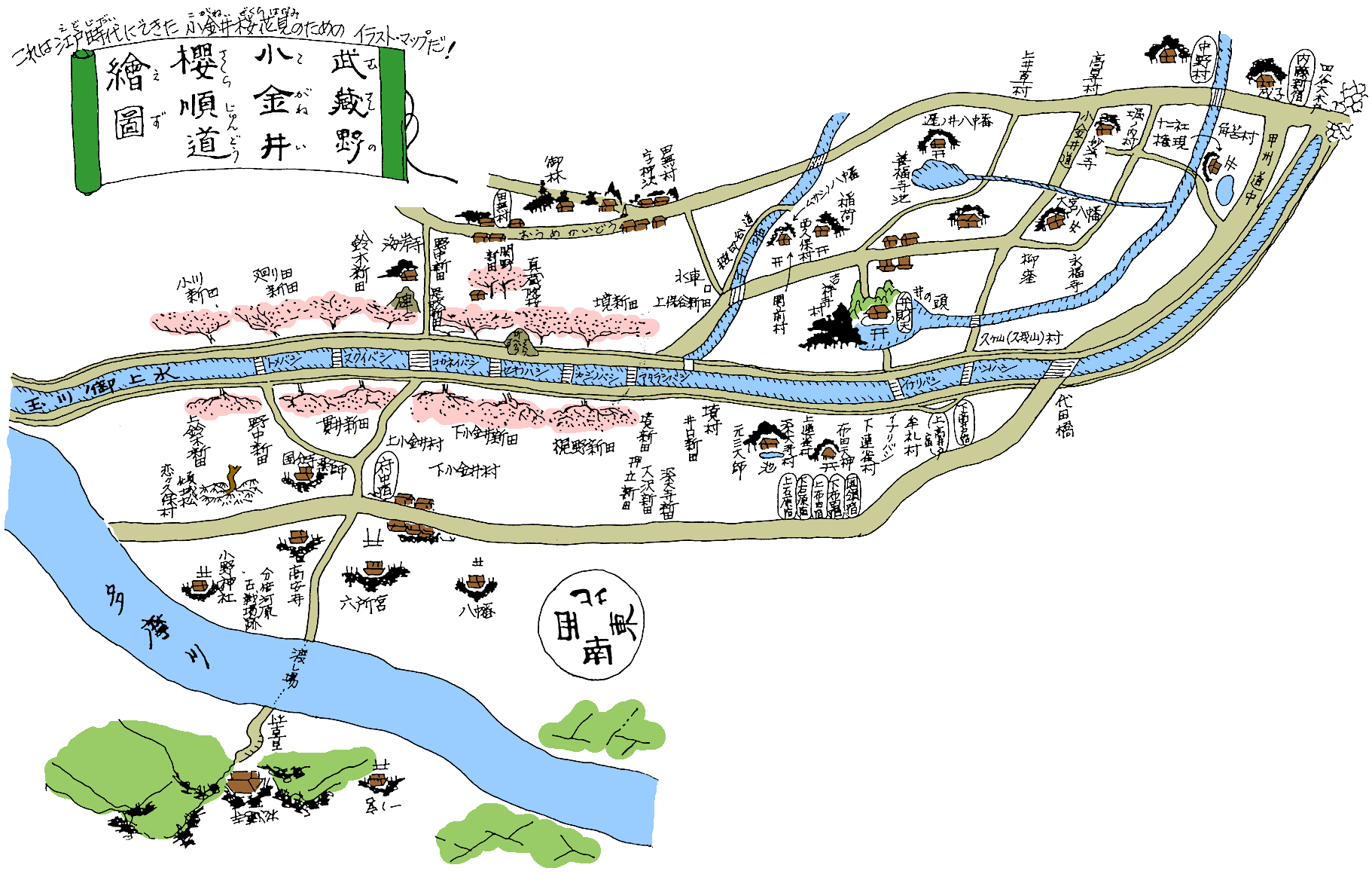
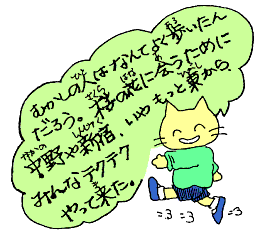
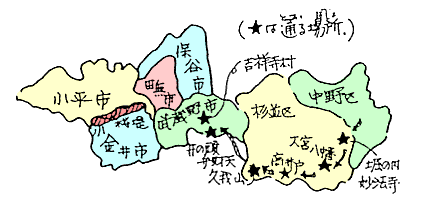 「
「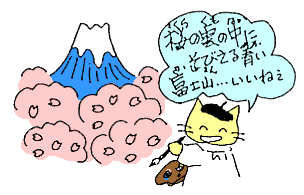 この
この