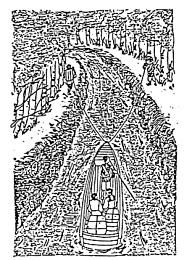玉川上水って知ってる?
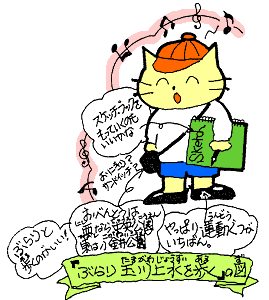 みんな、玉川上水って知ってる?
みんな、玉川上水って知ってる?
授業で習った人もいるだろうし、学校の行き帰りに毎日通る人もいるだろうし、日よう日にお父さんやお母さんと散歩する人だっているだろうし…。
小平では玉川上水は五日市街道と平行して走っている。このまちに住んでいるわたしたちにとって玉川上水ってとても身近だよね。春はサクラがきれいだし、夏は緑が茂る。秋はドングリをひろえるし、冬の景色だっていい。
玉川上水がつくられたのは、1654年(承応3年)。徳川家康が江戸幕府をひらいてから50年ほど後のこと。
江戸にはすでに神田上水があったけれど人口がふえて水不足になっていた。
そこで玉川庄右衛門、清右衛門の兄弟が新しい用水をつくるよう幕府から命じられた。
玉川兄弟は武蔵国羽村(今の西多摩郡羽村町)に取り入れ口をつくって多摩川の水を引き、江戸は四谷の大木戸まで、そのきょり43キロメートルの用水堀を完成させた。
ところがこの大仕事、なんと8ヵ月というスピードでやってしまったんだって。
玉川上水の本を読むと、今みたいに便利な機械なんか持たなかった頃の人たちの知恵とか、努力とか、願いとかが1ページ、1ページから伝わってくるようだよ。
玉川兄弟って?
玉川兄弟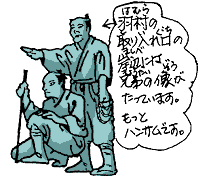
はもともと
江戸の
町人だったと
言われています。
多摩川ぞいの
村の
農民だった、
羽村の
出身だという
話もあります。
玉川兄弟の
子孫が
書いた
記録では、
幕府から
与えられた
資金 6,000
両はこの
大変な
工事の
途中で
使いきってしまったということです。そこでふたりは、
自分たちの
家屋敷を
売ってお
金をつくり、
工事をやりとげたのだとか。
また、
他の
記録には、
工事に
大きな
失敗が2
度もあったと
書かれています。
初めは、
今の
国立市の
青柳から
堀りだしましたが、
途中で
土地の
高い
所に
堀りすすみ、
水が
流れなくなりました。
2
度目は
今の
福生市から
堀りましたが、
JR 拝島駅の
近くまできたとき、
水が
地面にすいこまれ、
流れなくなりました。
3
度目の
正直で
工事は
成功したのだとか…。
玉川上水の本
ここでしょうかいした本は中央としょかんの「きょうどしりょうしつ(2かい)」にある!
じどうコーナーにおいてある本もある!
としょかんのひとにきいてみようね!
玉川上水のれきしがわかる! しくみがわかる!
江戸に水がやってきた-玉川兄弟ものがたり-
小沢 長治・さく 田中 良・え
岩崎書店
 どんどん 大きくなってゆく江戸の町では水が足りなくなってきました。
どんどん 大きくなってゆく江戸の町では水が足りなくなってきました。
庄右衛門と清右衛門は多摩川の水を江戸に引きたいと思いました。
「あのきれいな水をみんなにはらいっぱいのませてやりたい。」
絵本で読む玉川兄弟ものがたり。
中央図書館郷土資料室と各館絵本 コーナーにあります。
玉川上水-その歴史と役割-
羽村町郷土博物館・へんしゅう
羽村町教育委員会・発行
 あとがきに、
あとがきに、
「もちろん、高校生、大学生にも、大人のみなさんにも読んでいただけると思います。」と書いてあるけれど、ほんと、誰が読んでも良い本は、良い。
小学校の高学年向きですが、とてもわかりやすく、くわしいのです。
中央図書館郷土資料室と、各館児童コーナーぶんるい「20」にある!
玉川上水と分水
 小坂 克信
小坂 克信・
著
新人物往来社この本も読みやすい。わかりやすい。
それから、新田開発の話ものっているよ。
中央図書館郷土資料室にあります。
玉川上水-水と緑と人間の賛歌-
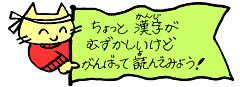
アサヒタウンズ・へん
けやき
出版“アサヒタウンズ”という、多摩の話題をいろいろのせている新聞にれんさいされていた玉川上水の記事を1さつの本にまとめたもの。とってもおもしろい。
玉川上水が大すきで、大切にしている人たちの話などたくさんのエピソードが。もちろん小平のこともでてくる。
中央図書館郷土資料室と各館郷土資料コーナーにある!
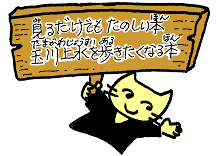
玉川上水の野草 第一集・第二集
織田 雅雄・さつえい へんしゅう
小平市玉川上水を守る会・発行
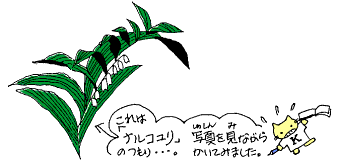 リンドウ、アケビ、ワレモコウ…玉川上水の四季に生きる植物たちと会える本。
リンドウ、アケビ、ワレモコウ…玉川上水の四季に生きる植物たちと会える本。
カラー写真がとてもきれい。
さあ、きみの知ってる草花はあるかな?
中央図書館郷土資料室にあります。
玉川上水散策絵図
 村松 昭
村松 昭・え
聖岳社これは本ではないです。
まきものみたいにびよよよ~んとひろがるイラスト・マップ。
羽村の取り入れ口から杉並の暗きょまで、玉川上水、ひとながめ。
流れにそって公園や名所もよくわかる。カラーの絵は何度見てもたのしい!
中央図書館郷土資料室にあります。
玉川上水を船が通った?
明治3年4月15日、玉川上水に船を通して品物を東京に運びたいという村々の願いが政府から許可されました。
そのころ、多摩地方の品物を東京まで運ぶには、人や馬が背負ったり、いかだにのせて多摩川をくだったりという方法がとられましたが、いちばん近くて便利なのは玉川上水を利用することだったのです。
羽村と四谷大木戸の間の通船が始まり、またたくまにさかんになりました。
ところが、明治5年4月15日、とつぜん政府から通船禁止の命令がありました。船の数がふえるにつれて上水がだんだんよごれてきて、飲み水としてつごうが悪い、というのが理由でした。
人々は何度も再開の願いを出しましたがもう許可にはなりませんでした。
このようにたった2年間でしたが、船は玉川上水を通ったのです。
玉川上水の通船
どうやって船は通ったの?
東京への行きは流れにのってくだるから、らくちん、らくちん。
でも、かえりは流れにさからうので、船に綱をつけ、両岸でひっぱりながらのぼっていったんだって。この絵みたいに。
どんなものを船で東京に運んだの?
野菜、炭、まき、酒、たばこ、ぶどう、茶、生糸、もめん、紙など多摩の生産物が多かった。
けれど、甲州(今の山梨県)や信州(今の長野県)のように遠くからの荷もあった。
参考にした本
「玉川上水-その歴史と役割」
「玉川上水と分水」
くわしいことは「玉川上水の本」を見てね
小平市に関すること
多摩に関すること
江戸・東京に関すること
玉川上水・小金井桜に関すること
その他
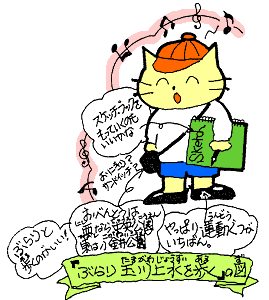 みんな、
みんな、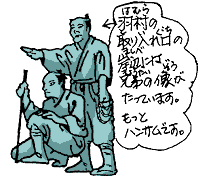
 どんどん
どんどん  あとがきに、
あとがきに、
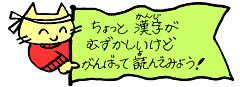 アサヒタウンズ・へん
アサヒタウンズ・へん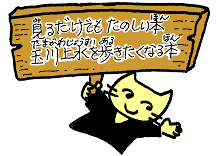
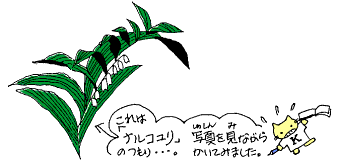 リンドウ、アケビ、ワレモコウ…
リンドウ、アケビ、ワレモコウ…