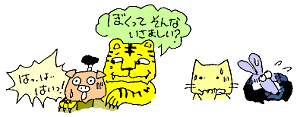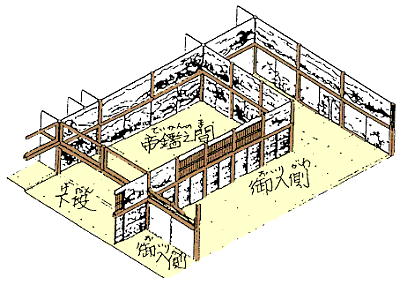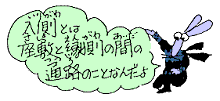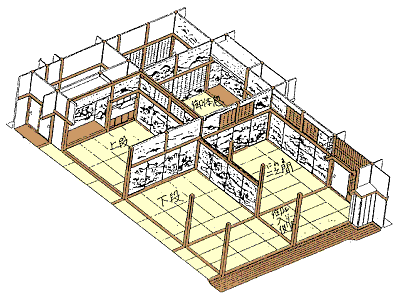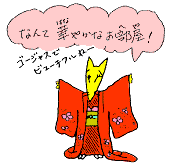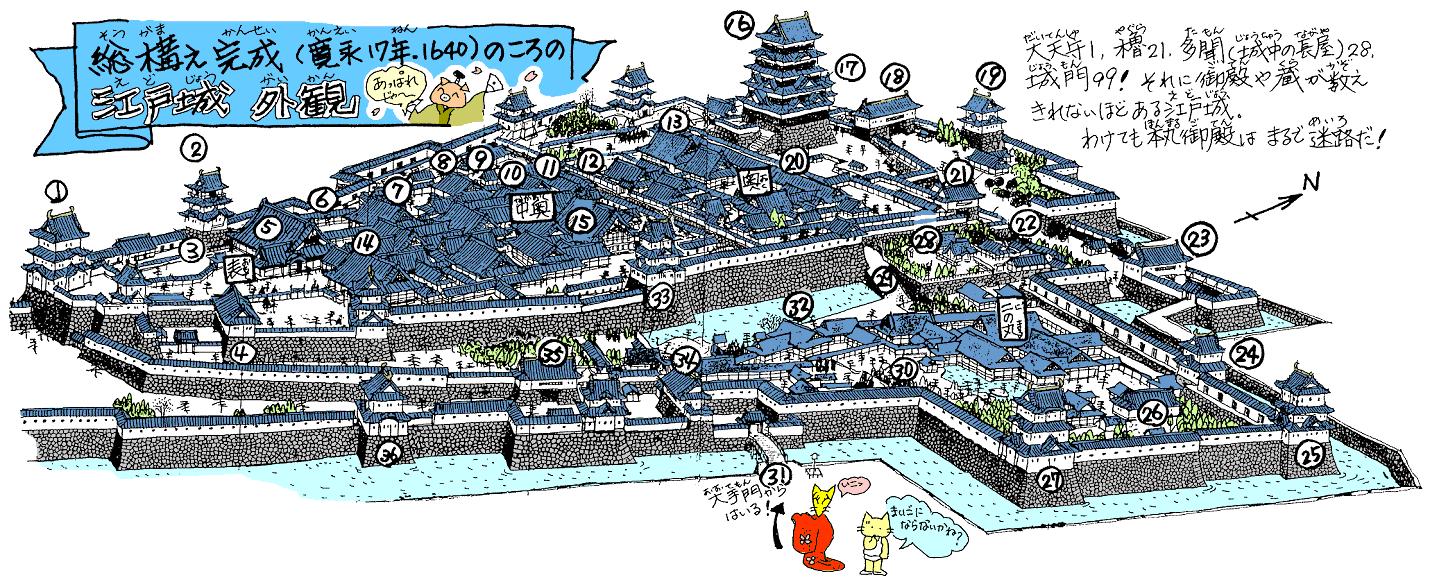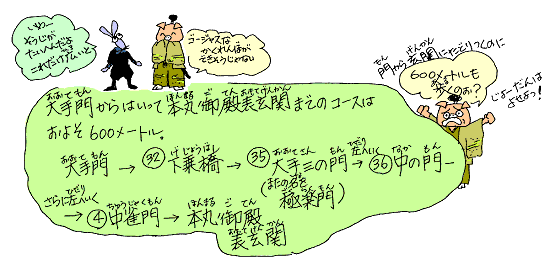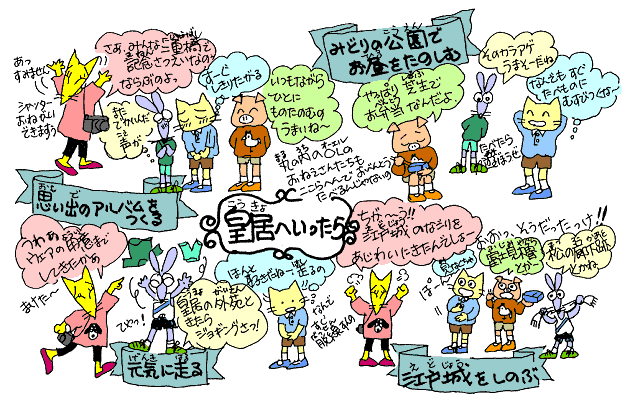江戸城内を探検だ!
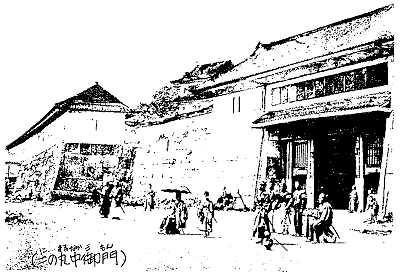
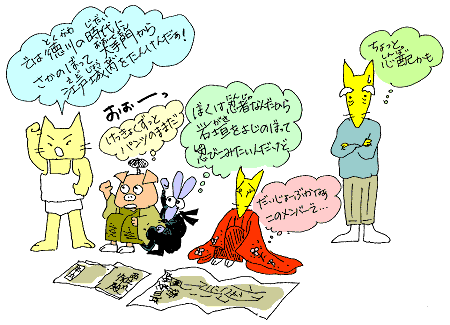
と、言うわけで、今回はいよいよ、江戸城内にせまりまする。
数えきれない城門、櫓、多聞に御殿が迷路のように立ち並び、こいつはすごいワンダー・ランドだ。
この中をいったいどれくらいたくさんの歴史上の有名人が通っていったんだろう?
みんなもちょっと江戸城の住人の気分になって、あちらこちらをのぞいてみよう。
 タイムマシンがなくっても…
タイムマシンがなくっても…
江戸城は火事などで失われた部分もあったけど、明治維新の時にもだいぶとりこわしがおこなわれた。それに関東大震災なんかもあったしね。それでも皇居のまわりには、当時の江戸城のおもかげがあちらこちらに残ってるよ。
地図で見る江戸の移り変わり
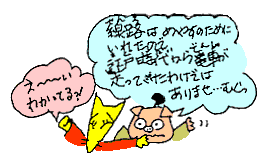
- 江戸の第1次建設 慶長7年(1602)ごろ(「慶長7年江戸図」より)
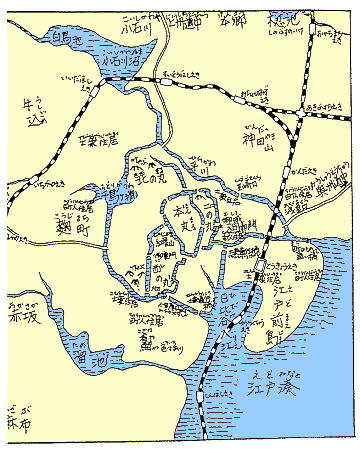
- 江戸の第2次建設 慶長13年(1608)ごろ(「慶長13年江戸図」より)
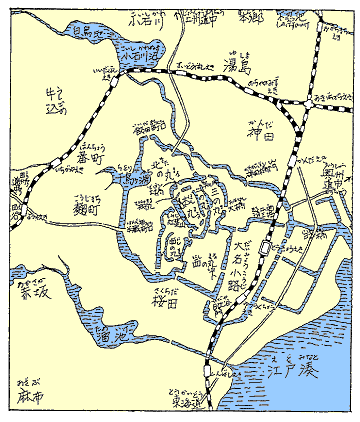
- 江戸の第3次建設 寛永9年(1632)ごろ(「武州豊嶋郡江戸庄図」より)
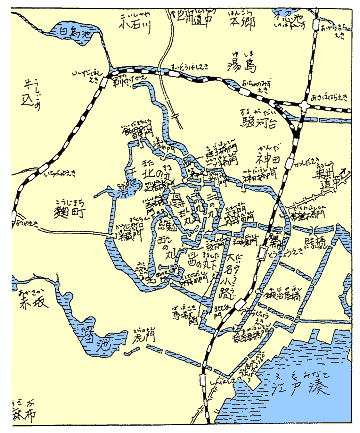
- 江戸の第4次建設 正保元年(1644)ごろ(「正保年間江戸図」より)
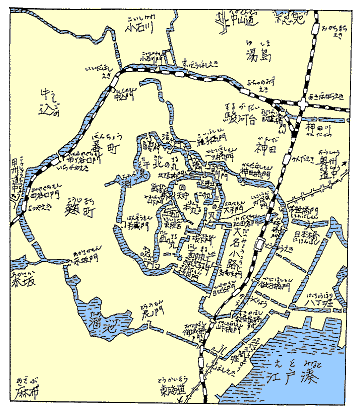
江戸城のつくり その1
1.城の構造
 城
城と、その
城下町は「
郭」という、
塁(とりで)と
堀とでかこまれた
部分から
成り
立っている。その
中の
仕組みはこうだ!
外郭(そとのくるわ) 城下町全体まで含める範囲のこと。古くは「総構え」とも言った。
内郭(うちのくるわ) お城のあるところを言う。本丸、二の丸、三の丸などからなる。
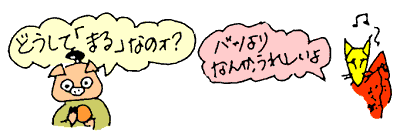
「丸」とは「郭」(「曲輪」とも書く)と同じ意味。とりでや城のまわりにめぐらす、土手や石垣を言い、またその内側の場所をさす。
山城があったりまえだった鎌倉時代、山のてっぺんをまっ平らにして郭を築いたのでその敷地は丸かった。そこから「丸」と呼ばれるようになったんだって。
本丸 もっとも重要なところ。城主が住んで政治をおこなう役所。
二の丸 城主の子どもなど、近い血筋の者たちの屋敷が建てられる。
三の丸 重臣たちが住んだり、米や武器などの蔵が置かれる。
大きい城になると、この他にこんな丸もつくる。
山里丸 城主の別荘。
西の丸 本丸の西につくる。城主が隠居した時の屋敷を建てる。
そして、本丸、二の丸、三の丸の組み合わせの基本パターンはこうだ!
(1)梯郭式
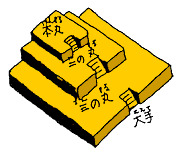 三
三の
丸の
大手(
正面)から、
二の
丸、
本丸と
順に
梯(
階段)をのぼるように
高くなる
構え。
山城、
平山城に
多い。
(2)環郭式
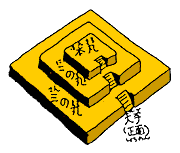 本丸
本丸を
中心にその
外へ
環(
輪)のように
二の
丸、
三の
丸をめぐらす
構え。
平山城や
平城に
多い。
(3)連郭式
大手から、
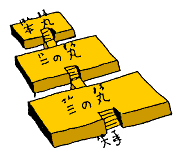 三
三の
丸、
二の
丸、
本丸を
一列に
連らねる
構え。
平城に
多い。
(4)渦郭式
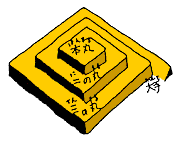 三
三の
丸から
渦まきのように、
二の
丸、
本丸へといたる
構え。
平山城に
多い。
江戸城は(4)の渦郭式の構えをとっている。
本丸の高台のまわりを、二の丸、三の丸、西の丸、北の丸が渦まき状に取り囲む。城の構えとしてはもっとも複雑で攻められにくい。
2.江戸城の内郭
本丸、二の丸、三の丸、西の丸、北の丸とそろったその面積は全国の城の中で、最大規模。
まず本丸
将軍の
住居であり、
政治をおこなう
役所でもある。この
建物の
北西部には
五層の
大天守、
南はしには
富士見の
三層櫓がそびえ
立ち、
天下を
見おろしていた。
 本丸御殿
本丸御殿の
中はつぎの3つの
区域に
分かれる。
表 幕府の
役所。
大広間や
遠侍、
白書院や
重臣の
控え
室などがある。「
忠臣蔵」で
有名な
松ノ廊下(
御成廊下)もここにある。
中奥 将軍の
住居。「
表」が
公用なのに
対して、ここからは
将軍の「
私」のエリア。
御休息の
間、御座の間、
井呂裏之間、
湯殿などからなる。ここから
御鈴廊下を
通って、
大奥へいたる。
奥 その
広さから「
大奥」とも
呼ばれるようになる。
将軍の
奥さんや、
奥女中たちの
住居。
ちょっとひとこと
江戸城の大天守は明暦の大火(1657)で焼けおちたあと、再建されることはなかった。
その後は富士見櫓が大天守の役割をはたしていた。
二の丸
将軍の別荘として使われたり、世嗣(次の将軍になる予定の息子)の住居になることもあった。
二の丸のいちばん初めの工事(寛永7年・1630)と、つぎの工事(寛永13年・1636)は小堀遠州が設計。桂離宮とくらべられるような、すばらしい庭園が造られた。明暦の大火(1657)や、延享(1747)、文久(1863)の火事で焼ける度、再建されたけれど、本丸同様、豪華さはひかえるようになった。
三の丸
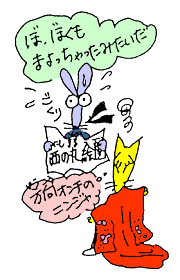
だいたい
二の
丸と
同じような
役割りで
使われた。
西の丸
大御所(
引退した
先代将軍)の
隠居所。
北の
丘には
紅葉山の
霊廟(
先祖の
霊をまつってあるところ)があり、まん
中に
館が
立つ。
その
西南は
山里丸の
庭が
広がる。
宝永7
年(1710)には「
吹上の
御庭」も
設けられて、
梅園、
馬場、
田んぼ、
花壇などがあった。さらにそのあちこちに、
滝見茶屋、
花壇茶屋、
紅葉茶屋などの
茶室がちらばっていた。
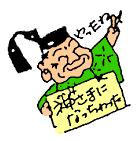 慶長
慶長20
年(1615)5
月、
大坂夏の
陣で
豊臣家の
滅亡を
見とどけると、よく
年元和2
年(1616)4
月、
家康は
亡くなった。そのなきがらは
静岡の
久能山にまつられ、
後に
日光にうつされた。
東照宮というのは
家康をまつる
神社なのだけれど、
江戸城内、
西の
丸の
紅葉山にも
東照宮は
建てられた。
北の丸
もともとは重臣の屋敷のための土地だった。けれど明暦の大火(1657)以降は花畑とか将軍の血筋の者の屋敷地になったりした。
火事による焼失と再建をくりかえし、徳川の時代が終わりを告げる時、西の丸だけが江戸城にのこされた最後の御殿になっていた。明治維新後はここが皇居となり、明治6年(1873)に焼けてしまうまで使われた。西の丸が皇居となった理由だ。
3.江戸城の石垣積み
慶長10年(1605)4月、家康は隠居し、二代将軍秀忠が本格的な天下普請を受け継いだ。城のまわりの石垣を築く仕事も大名たちに割り当てられた。
日比谷入江の埋め立て地に積むと、重い石垣は沈んでしまう。そこで「筏地形」といって、埋め立ての泥の中に筏を組んで止めてから、石垣を積む方法がとられた。それでも石垣はくずれ、工事中の事故でたくさんの死傷者が出た。
そんななかで、加藤清正 (注釈)は、 武蔵野に茂る茅を刈りとらせ、泥地に敷きつめると、10~15歳の子どもを集め、その上で遊ばせた。こうしてじゅうぶん踏みかためてから、石垣を築いた。おかげで、時間はかかったけれど、地震にもびくともしない頑丈な石垣ができあがったということだ。
 (注釈)加藤清正(1562-1611)
(注釈)加藤清正(1562-1611)
通称、虎之助。幼ない頃から豊臣秀吉に仕え、多くの手がらをたてた。関ヶ原の戦いでは徳川方についたが、秀吉の恩を思って、豊臣家も大事にした。家康からは肥後国を与えられ、熊本城主。築城・治水工事の名人といわれたうえ、文学や芸術にも理解が深く、論語をよく読み、信仰心のあつい人だった。
石垣積みは、織田信長の安土城以来、城を築くさいに大名たちが一番力を入れるところ。石垣に使う石は、安山岩や花崗岩、片麻岩などだ。
そして、石の積み方にはいくつかの方法がある。
(1)野面積み
自然の
石をそのまま
積む、というもっとも
古いやり
方。
古代・
中世の
城の
石垣はこの
方法。
(2)打ち込みハギ
自然の石を積み上げてから、石垣の外側の部分だけを平らに仕上げる。それから、石と石の間のつなぎに小石をはさんで打ち込む。
信長の
安土城以来、
広まった
方法でこの
当時の
城はこのやり
方を
用いた。
(3)切り込みハギ
たて・横・長さの比をおよそ1対1対2の割合の直方体(キャラメルの箱の形)にして切り出した石を積んでゆく。
石と
石の
間にほとんどすき
間がない。
江戸の
初めに
盛んになった
方法。
もちろん
江戸城の
石垣は、これ。
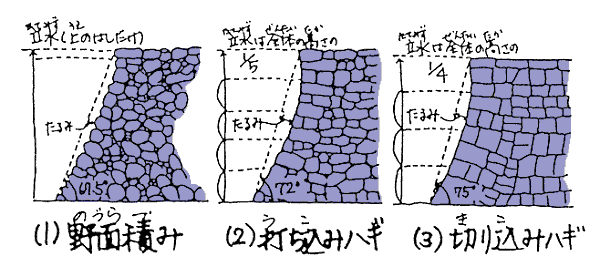 石垣
石垣の
勾配は、
野面積みで67.5
度、
打ち
込みハギで75
度、
切り
込みハギで75
度というのが
基本。
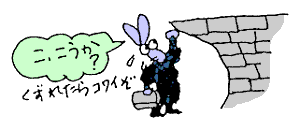
そして
大事なのは、
石垣の
下から
中央まで、たるみがありながら、
上はしは
垂直になっているってことなんだ。これを「
立水」(
水平にしたものを
垂直にたてるという
意味)という。さらに
石積みの
技術が
発達すると、
石垣の
上端が
外側にソリ
出てくる。これを「
忍び
返し」という。
4.そびえる天守
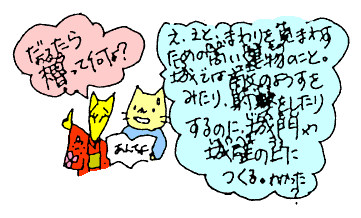 天守
天守というのは
本丸にある
最大の
櫓をいう。
戦争のさいには
展望台、
司令塔、そして
最後のとりでともなる
重要な
拠点だ。
天守は
家康時代の
慶長12
年(1607)の
工事では「
環立式」という
形をとった。これは
戦国の
実戦用のつくりだった。
本丸の
中心にそびえ
立つ、
大天守の
東、
北、
西に
順番に
小天守を
建てて、
輪のようにつなぐ。こうすると
本丸の
中にさらに
四つの
天守で
囲んだ「
天守丸」という
郭ができて、
本丸が
敵に
攻めこまれても、この
天守丸だけで
籠城できる。
それが
二代将軍秀忠の
時代になると、
元和9
年(1623)の
工事で「
単立式」という
形に
建てかえられた。
天守は
城のシンボルにすぎなくなった。
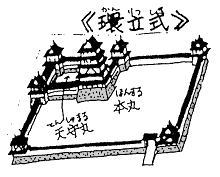
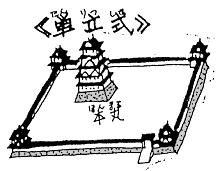
さらに
三代将軍家光の
時代、
寛永15
年(1638)に
工事があって、この
時完成した
天守はどの
方向から
見ても
正面に
見えるデザインだったので、「
八方正面」と
呼ばれた。
江戸城の
天守は
地震や
台風に
強く、
木造でも
土壁が
厚く、
屋根は
銅瓦ぶきの
耐火建築だった。
このころは
土瓦がふつうで、
金属瓦を
使ったのは
江戸城が
日本最初、だった。けれども
開いた
窓から
火がはいってしまったおかげで、
明暦の
大火(1657)により
焼けてしまい、その
後建て
直されることはなかった。
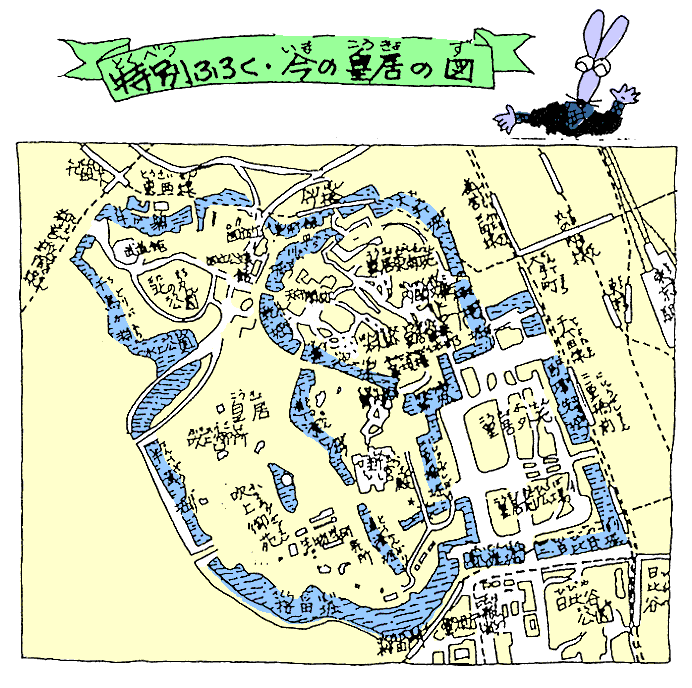
かつての江戸城を忍ぶばかりが能じゃないぞ!
皇居のまわりは科学技術館あり、国立近代美術館あり、春のお花見、千鳥ヶ淵のボート乗りと遊べる、遊べる。
江戸城のつくり その2
5.城門、たくさん
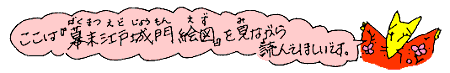 城門
城門は「
見付」とも
呼ばれ、
堀の
節になっていた。「
見付」は「
見付ける」-つまり、
見張りのための
場所。そして、
郭の
出入口になっているような
重要な
門はほとんどが
枡形門といわれるもの。
枡形門というのは、
出入口に
四角形の
一画を
設けて、
城の
外側に「一の
門」、
城の
内側に「
二の
門」とふたつの
関門を
設けるもの。これは
敵に
攻めこまれにくいように、という
工夫のひとつだ。
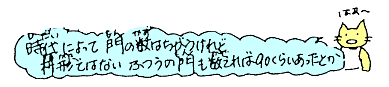
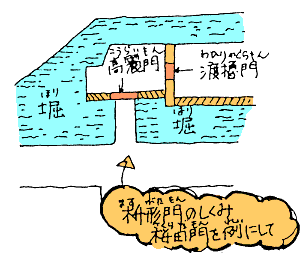 寛永
寛永3
年(1626)には
警備の
規則もできあがり、
大手門、
中の
門、
中雀門など、
中心に
近い
門の
警備は、
旗本・
御家人が
担当した。
本丸、
西の
丸の
門と
内郭の
門は
大名が
担当した。
江戸城の
門は
俗に「三十六
見付」とよばれ、それだけたくさんあったんだってことなんだ。
今はもうなくなってしまった
門も
多いけれど、そのいくつかを
紹介してみるね。
(カッコ)
内は「
城門絵図」の
中の
位置番号。
牛込門
江戸城外郭の北。寛永13年(1636)に建てたといわれる。そのころ、このあたりはカエデの林だったので、「紅葉門」とも呼ばれた。(44)
数寄屋橋門
日比谷門から数寄屋町への出口にあたっていたので、この名がついた。数寄屋町というのは江戸の初めにこのあたりに住んだ織田有楽斎(注釈)の数寄屋造りの茶室が有名だったのでうまれた町名だとか。(他にも説はあるらしいけれど。)(36)
(注釈)織田有楽斎(1547~1621)
織田信長の弟。千利休から作法を伝授された茶人でもある。数寄屋橋門外の屋敷跡は「有楽町」という名が今ものこる。
西の丸大手門
 今
今の
皇居の
正門で
二重橋のところだ。
家康の
隠居所として
建てられた
西の
丸の
正門だった。
堀を
渡る
橋が
内と
外に
二重にかけられて、「
一の
橋」を
渡って「
一の
門」にはいり、さらに「
二の
橋」を
渡らなければ
城内にはいれない、というつくりで、
警備のかたい
門構え。(
今の
二重橋とはつくりがちがっていた。)(1)
半蔵門
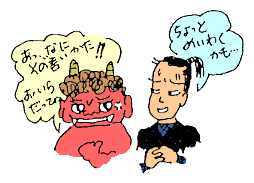 家康
家康の
時代、
伊賀者たちの
組頭で、「
鬼半蔵」と
呼ばれた
服部石見守正成(1542~1596)の
組屋敷があったので、この
名がついた、と『
御府内備考』に
書かれている。
江戸城から
甲州街道へ
通じる
重要な
門だ。(26)
坂下門
江戸時代には「西の丸坂下門」といった。西の丸から下った坂の下にあったからだろう。今は宮内庁の出入口になっている。(2)
田安門
このあたり、むかしは田安村といい、月見の名所だったそうな。家康の入国後は、関八州の役人たちの屋敷が設けられ、代官町となった。八代将軍吉宗は、次男の屋敷をこの門の内に建てて、徳川三卿のひとつ、田安家をつくった。(27)
日比谷門
 寛永
寛永4
年(1627)に
建てられた。
広島の
浅野家が
石壁をつくり、あの、
伊達正宗が
枡形を
築いた。(24)
四谷門
寛永13年(1636)の建築といわれる。半蔵門を通って、この門に出て、そこからが甲州街道のスタートだ。そして、武蔵野台地が扇形に広がる、要の部分にあたる重要な門。だから、ここには徳川ご三家のうちの、紀州・尾張両大名の屋敷が置かれた。(42)
桜田門
警視庁の建物と向かい合っている。文禄年間(1592~1596)に西の丸が建てられた時、内桜田門に対して、ここを外桜田門とした。万延元年(1860)3月には、ここで大老井伊直弼が暗殺されている。(25)
常磐橋門
慶長年間の古い絵図では「浅草口」、寛永年間の図では「追手口」と記されている。門の名まえも時代でかわるんだね。ここは江戸城外郭の正門であります。(33)
徳川家 三家・家門・三卿・庶流
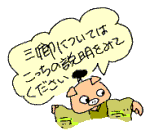 家康
家康が
慶長8
年(1603)に
幕府を
開いてから265
年間、
徳川家は
代々将軍職を
受け
継いで
来た。そして、
将軍家の
分家は、「
三家」、「
家門」、「
三卿」、「
庶流」に
分けられていった。
御三家 本家を
継ぐ
権利を
持つ、つぎの
家系。
家康の 9
子、
義直を
初代とする
尾張家。
10
子、
頼宣を
初代とする
紀州家。
11
子、
頼房を
初代とする
水戸家。
三卿 のちに
御三家同様、
本家を
継ぐ
権利をもつ
家系に
加わる。
八代将軍吉宗の
子、
宗武を
初代とする
田安家。
同じく
吉宗の
子、
宗尹を
初代とする
一橋家。
九代将軍家重の
子、
重好を
初代とする
清水家。
以上の
六家は「
徳川」
姓を
名のった。
家門 家康の
次男、
結城秀康を
初代とする
越前松平家。
二代将軍秀忠の
子保科正之(のち
松平をなのる)の
会津松平家。
庶流 以上の
家の
子どもたちのうち、
大名になった
者たちをいう。「
松平」
姓を
名のった。
6.大名小路
一年を自分の領地で、つぎの一年を江戸で暮らすという大名の参勤交代制度は、江戸にたくさんの大名屋敷をつくりだすことになった。
大名屋敷はその役割で、みっつに区別される。
上屋敷 大名小路など、江戸城内郭におかれ(明暦の大火以前はね)、大名本人が住み、江戸城へ出仕(出勤)するのに便利。
中屋敷 外堀の内側にあって、大名の奥さんや子どもたちが住む屋敷。上屋敷を補佐する役目もある。
下屋敷 外堀の外に建てられた。大きな庭園などがあって別荘として使われた。
江戸城の東部分、「大名小路」とよばれる地域は大名屋敷がずらりとならんだ。もっとも、明暦の大火(1657)以降は、御三家の引っ越しにともなって、これらの大名たちも屋敷替えをしなければならなかったけれど。それまでは、だいたいこんな配置だった。
譜代大名の屋敷(関ヶ原の戦い前からの徳川の家臣)
江戸城正門(大手門)一帯。中でも、老中・若年寄といった幕府の重要な役職者の屋敷は、本丸大手門、西の丸大手門に近い「西の丸下」に置かれた。このあたりはもう「松平」姓の屋敷のオンパレードなんだ。
外様大名の屋敷(関ヶ原の戦い後に徳川の家臣となった大名)
大名小路の右うずまきを延ばした先の日比谷門に区切られたむこうに屋敷が置かれた。日比谷、桜田、霞ヶ関の一帯で、赤坂ため池まで続いた。
おまけ 大名じゃないんだけど
旗本屋敷
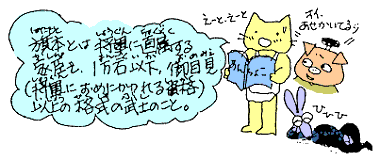 赤坂門
赤坂門から
喰違門、
四谷門、
市ヶ谷門、
牛込門、
筋違橋門の
一帯にあった。このあたりは
麹町台地があって
川が
少なく、
自然の
地形だけでは
防衛が
十分でなかった。だから、
将軍直属の
家臣である
旗本をたくさん
置いて、
江戸城の
守りをかためた。そこから「
番町」という
町の
名もおこった。
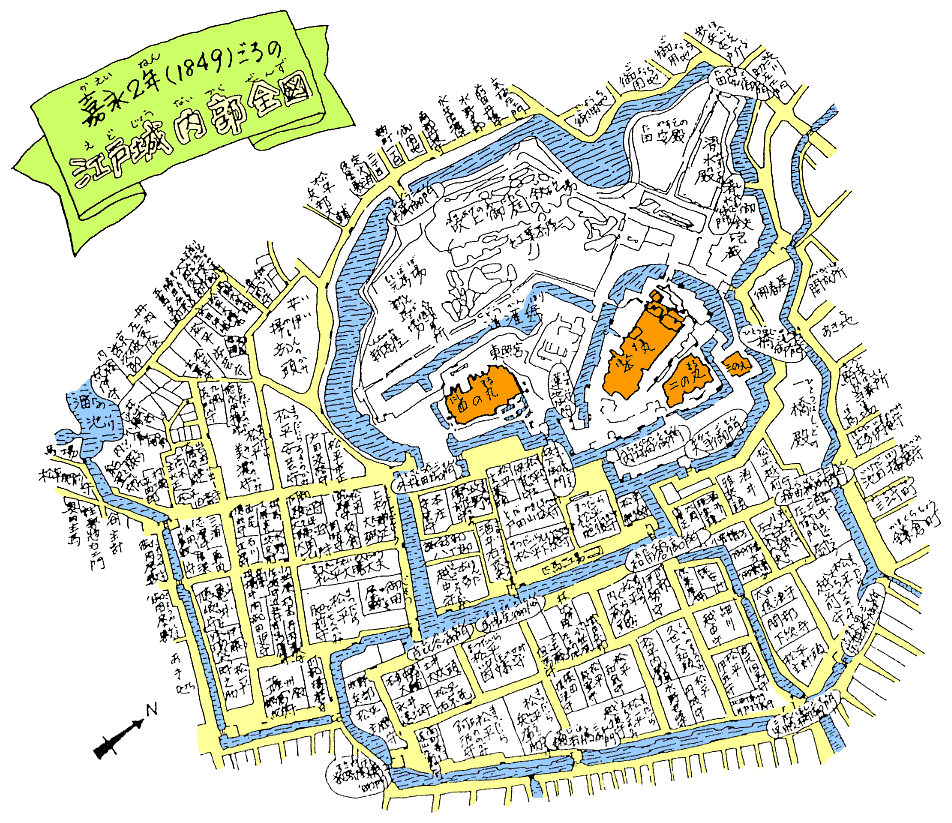
幕末江戸城門絵図
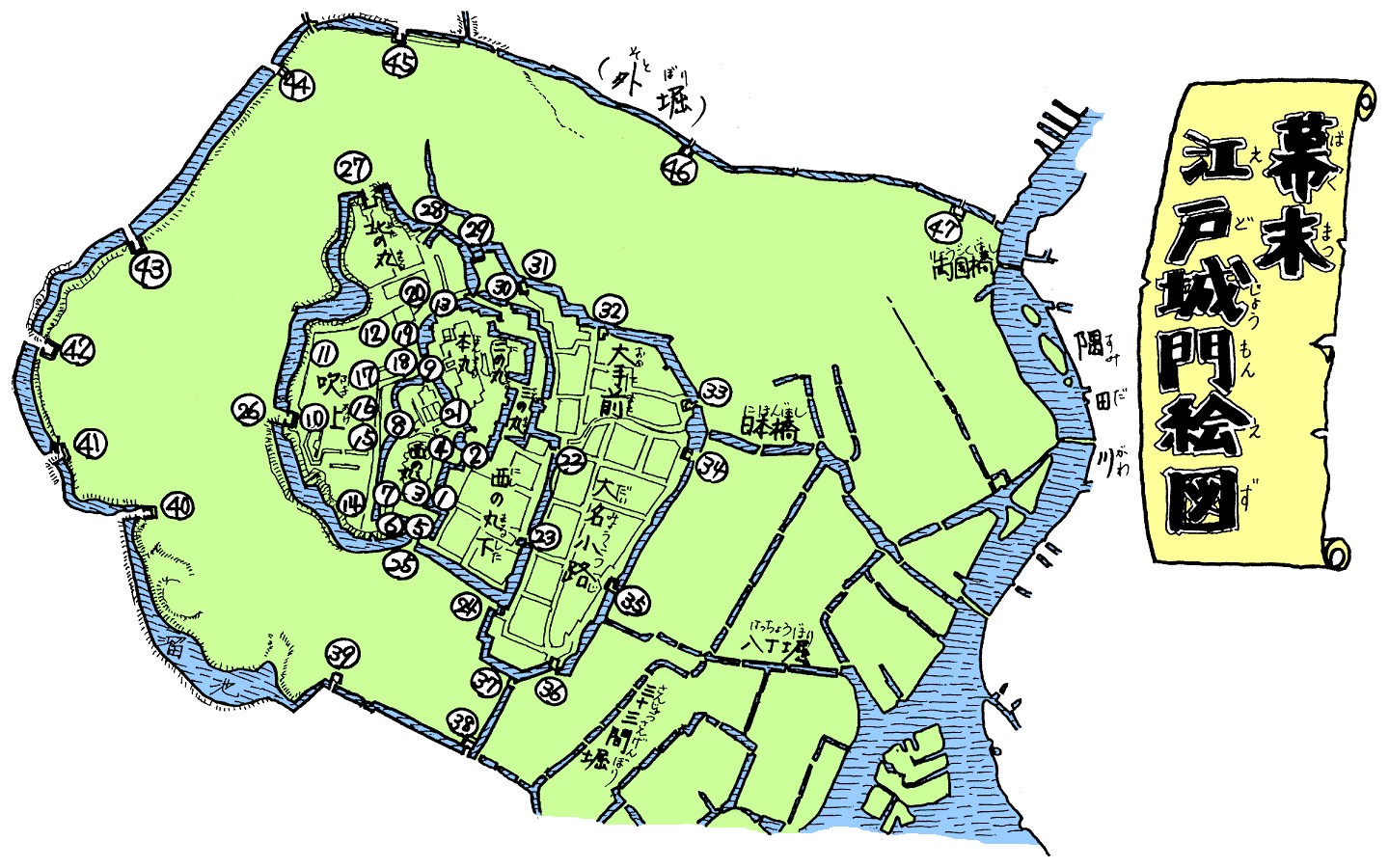
- 西の丸大手門
- 坂下門
- 西の丸書院前門
- 西の丸裏門
- 仲仕切門
- 吹上門
- 山里門
- 大田門
- 紅葉山下門
- 半蔵御庭入口門
- 西門
- 植木門
- 矢来門
- 新門
- 一之門
- ニ之門
- 入隅門
- 御成門
- 十三間門
- 鷹門
- 御橋門
- 和田倉門
- 馬場先門
- 日比谷門
- 外桜田門
- 半蔵門
- 田安門
- 清水門
- 雉子橋門
- 竹橋門
- 一ツ橋門
- 神田橋門
- 常磐橋門
- 呉服橋門
- 鍛冶橋門
- 数寄屋橋門
- 山下橋門
- 幸橋門
- 虎ノ門
- 赤坂門
- 喰違門
- 四谷門
- 市ヶ谷門
- 牛込門
- 小石川門
- 筋違橋門
- 浅草橋門
これが江戸城本丸御殿内部だ!
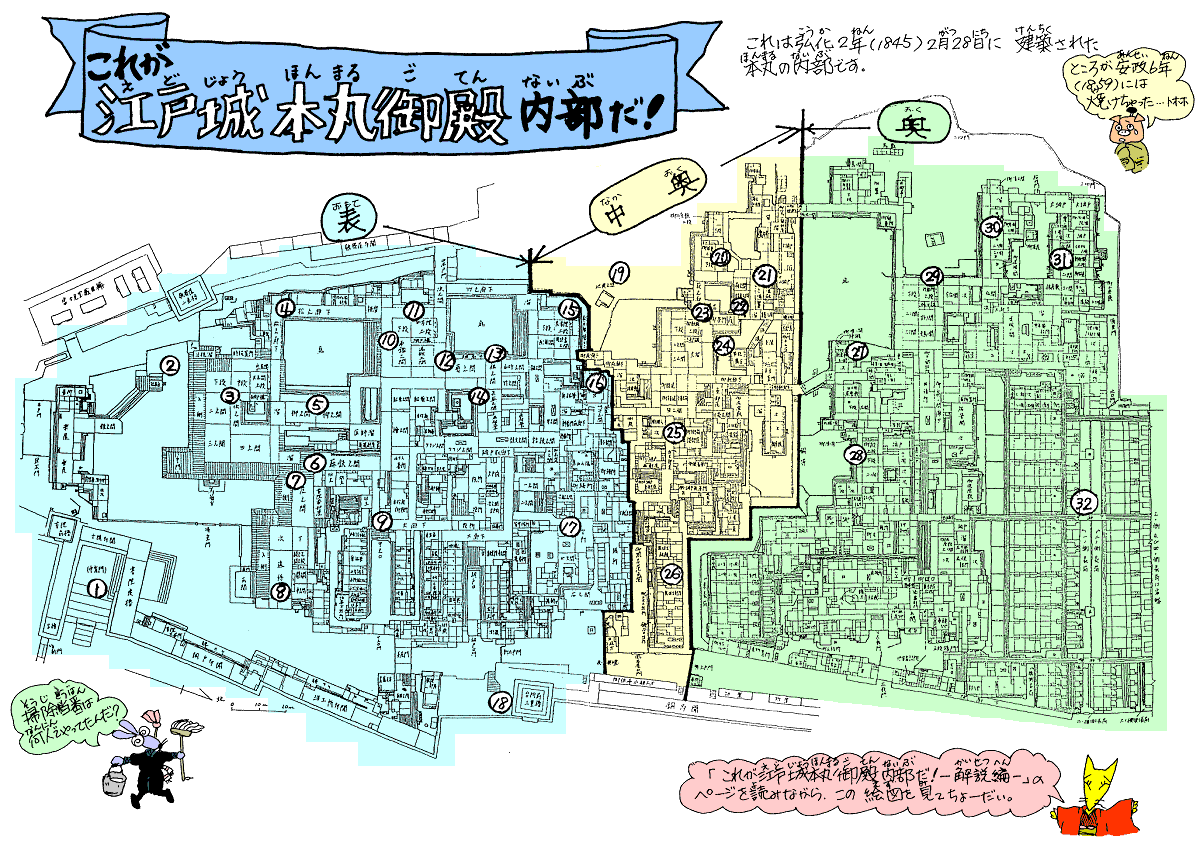
これが江戸城本丸御殿内部だ! 解説編
表(おもて)
将軍への謁見(お目通り)その他の儀式のための広間とか、ふだん役人たちが仕事をする座敷などがある。
江戸城の「役所」のエリアだ。
- 中雀門
- 能舞台 公の儀式の日などに、ここで能がおこなわれる。
- 大広間 畳の数で400畳をこす、文字通りの大広間。儀式・公式行事用の部屋。
- 松之廊下
- 柳之間 大名が登城した時の詰所。(つまり控えの間)
- 蘇鉄の間 大名の供侍の詰所。
- 虎之間 書院番の詰所。書院番というのは江戸城の警備や、将軍の江戸市中への巡回に従うことなどが主な仕事。
- 遠侍 御徒の詰所。お目通り以下の下級武士で、将軍の警備にあたるのが御徒だ。
- 目付衆御用所 「目付」とは監督する役の人。江戸時代、大名を監督する役人を「大目付」、旗本・御家人の監督を「目付」といった。
- 帝鑑之間 ここも大名登城のさいの詰所。
- 白書院 公式行事用の部屋だけれど「大広間」にくらべると、ちょっと内輪の儀式用。
- 菊之間 番頭の詰所。警備、護衛の仕事をする人を番方(または番衆)といったが、番頭はその頭の人のこと。
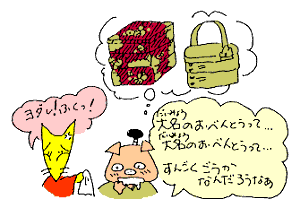 雁之間 ここも大名登城のさいの詰所。
雁之間 ここも大名登城のさいの詰所。- 芙蓉之間 勘定奉行、寺社奉行、町奉行など江戸時代にはいろいろな「お奉行さま」がいたが、その詰所。
- 黒書院 11白書院と役割り同じ。
- 御用部屋 老中・若年寄が詰める。かなり奥まった位置にあるし、部屋の中に、密談の時、火ばしで字を書くための「いろり」があるところなど、なかなかのもんだ。
- 台所 将軍の食事を用意するところ。大名たちは、登城の時はそれぞれの屋敷からお弁当が届いたらしい。
- 台所前三重櫓
中奥(なかおく)
将軍の官邸。住居であるとともに、将軍が書類に目を通す仕事の場でもあった。「表」とひとつづきだ。
- 地震之間 耐震建築。さすがに地震国日本。こういう施設もあったんだねえ。
- 御休息 将軍の寝室。
- 湯殿 もちろん、おフロだ。
- 井呂裏之間 将軍がおそばの者と楽しくおしゃべりするための部屋。
- 御座之間 将軍のふだんの部屋であるとともに仕事部屋でもある。
- 奥能舞台 こちらの能舞台は「表」の舞台とちがって、将軍自身の楽しみのためのもの。
- 側用人の部屋 このあたりは将軍の身のまわりの世話をする側用人の控えの部屋などがある。
- 奥坊主部屋 将軍にお茶をいれたり、大名の接待をする役の坊主を奥坊主といった。
奥(おく、またの名を「大奥」)
将軍の私邸。御台所(奥さん)を中心に、将軍の子どもや奥女中たちが生活する。「中奥」とは塀で仕切られていて、「御鈴廊下」と呼ぶ、長い廊下だけでつながっている。中は大きく3つのエリアに分かれる。
 (1)大奥御殿向 将軍の御台所(奥さん)の住居のエリア。
(1)大奥御殿向 将軍の御台所(奥さん)の住居のエリア。
(2)御広敷 大奥の事務をとり扱う役所のエリア。
(3)長局向 奥女中たちの生活するエリア。
- 新座敷 将軍のお母さんの住居。
- 御殿
- 対面所 外からのお客さまを接待するための部屋。
- 御座之間 このあたりが将軍と御台所(奥さん)が対面するための部屋。
- 御休息之間、御化粧之間 このあたりが御台所(奥さん)のふだんの部屋。
- 長局 奥女中たちの部屋。
7.虎之間
将軍と
対面の
儀式などをするの
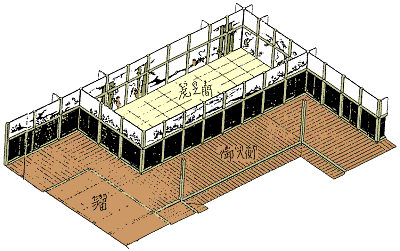
に
大名たちは
玄関からはいり、
遠侍を
通って
大広間へ
向かう。
虎之間は
遠侍と
大広間をつなぐ
位置にある部
屋。
大名や
将軍の
館では、
玄関や、それにつづくお
客を
迎える
部屋を
虎と
竹の
絵で
飾ることが
多い。
虎之間は36
畳もある
広い
部屋だ。
虎と
竹のふすま
絵は
幕府の
権威と
武士の
勇ましさの
象徴だ。
入側を
通る
大名たちが
建具のすきまからこの
部屋をのぞいた
時に
目にはいるよう、
虎は
部屋の
東面と
北面に
描かれていた。
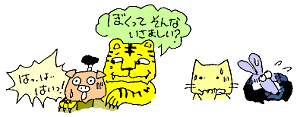
10.帝鑑之間
格天井
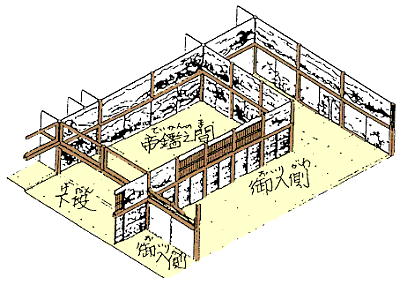
(注釈)で、ふすまには 唐(むかしの中国の王朝)の皇帝が描かれている。
10万石以上の譜代大名や交代寄合(3,000石
以上の旗本で役職につかない者。大名に準じる。)が詰める部屋。
本丸御殿の表には大広間から白書院・黒書院のエリアにかけて柳之間・雁之間・大廊下など大名の詰所となる部屋があちこちにある。
どの大名がどの部屋に詰めるかは、その格式によって、きっちり、厳しく定められていた。
(注釈)格天井;木を1メートルくらいの間隔で正方形に組み、上に板を張った天井。
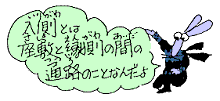
31.大奥新御殿(御休息之間など)
大奥新御殿の
上段・
下段・
ニ之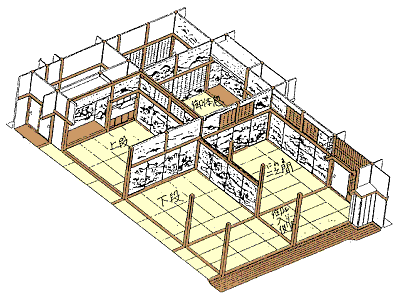 間
間・
御休息之間の4
部屋には、
春の
桜、
秋の
紅葉など、
四季の
風景が
色あざやかに
描かれていた。
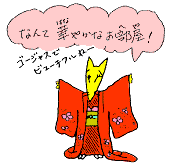
総構え完成(寛永17年・1640)のころの江戸城外観
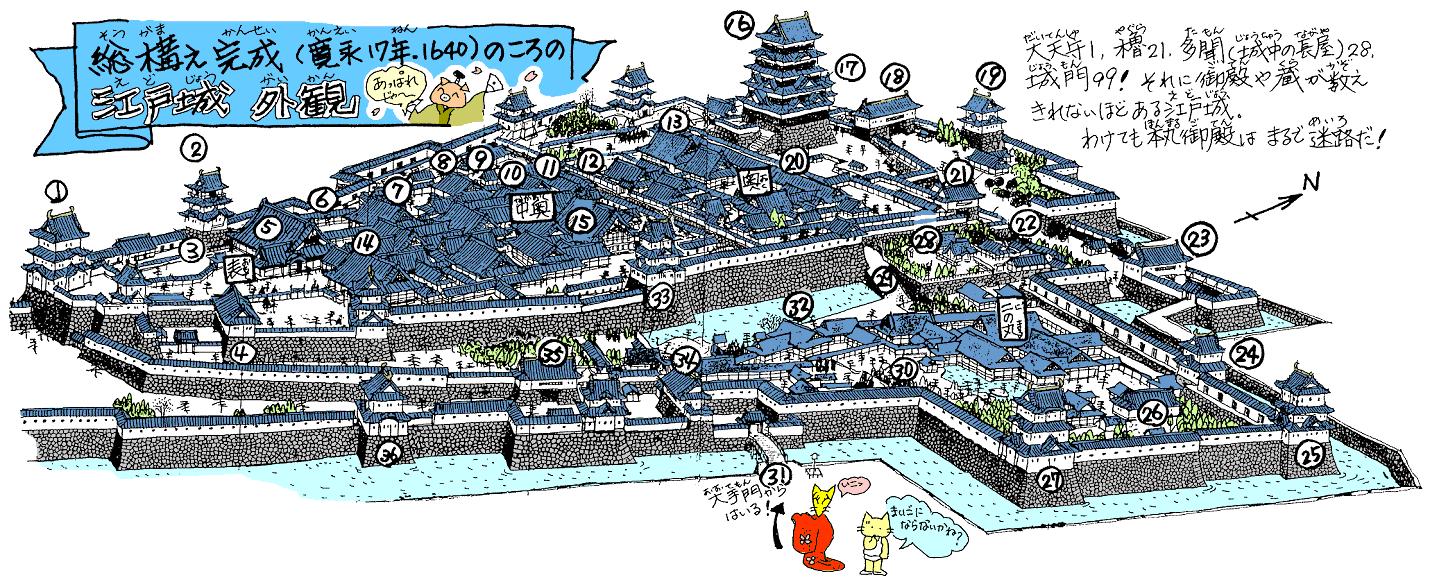
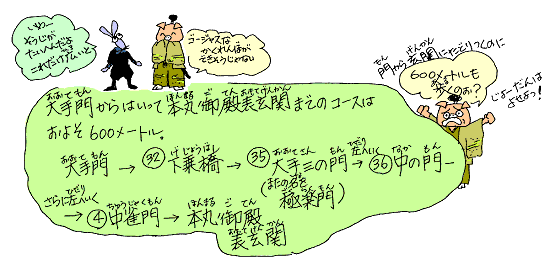
- 富士見櫓 慶長11年(1606)に建てられた三重櫓。伏見櫓、桜田巽櫓とともに今も残る。
- 月見櫓
- 能舞台
- 中雀門
- 大広間
- 松之廊下
- 白書院
- 黒書院
- 地震之間
- 御座之間
- 御休息之間
- 仕切り垣 奥と中奥の仕切り
- 御守殿
- 遠侍
- 大台所
- 大天守
- 乾櫓
- 北拮橋門
- 五十三間櫓
- 局
- 上梅林坂門
- 梅林坂 文明10年(1478)、道灌がここに菅原道真(天神さまだ)をまつった時、梅の木を数百本植えたので、その時からついた名かもしれない。
- 下梅林坂門
- 北櫓
- 艮櫓
- 文庫
- 松倉櫓
- 東照宮
- 汐見坂 二の丸から本丸へあがる坂。日比谷入江を埋め立てる前は、ここから海が見えた。それで「汐見」と名がついている。
- 茶亭
- 下乗橋
- 白鳥堀
- 台所前櫓 これも慶長11年(1606)建築か?三重櫓でありました。
- 大手三の門
- 中の門
- 寺沢櫓 いつごろの建築かは不明。明治6年(1873)ごろ、とりこわされたのかも…(不明なんです。)二重櫓だったのではないかという。
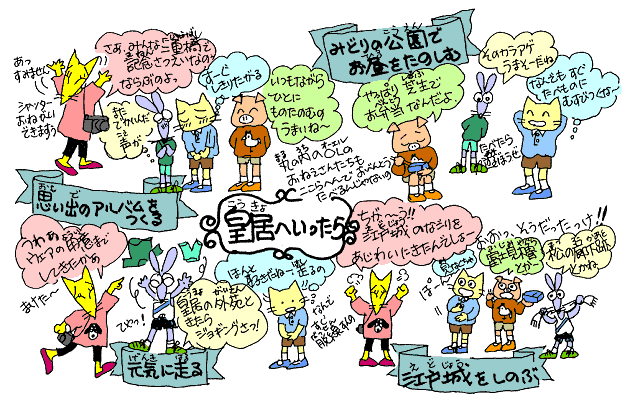
参考資料はパート1を見てね!
小平市に関すること
多摩に関すること
江戸・東京に関すること
玉川上水・小金井桜に関すること
その他
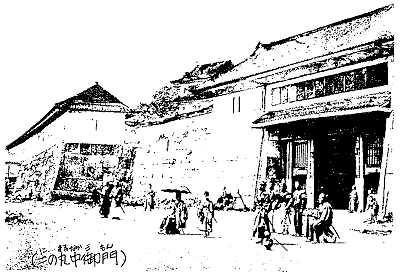
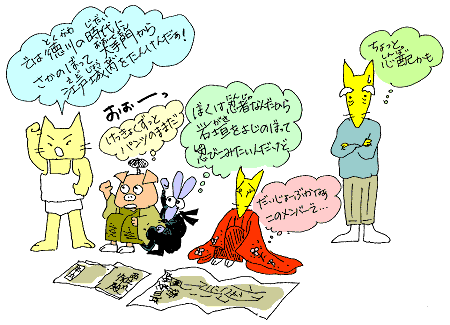
 タイムマシンがなくっても…
タイムマシンがなくっても…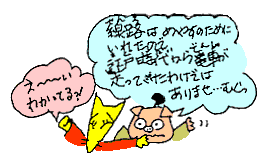
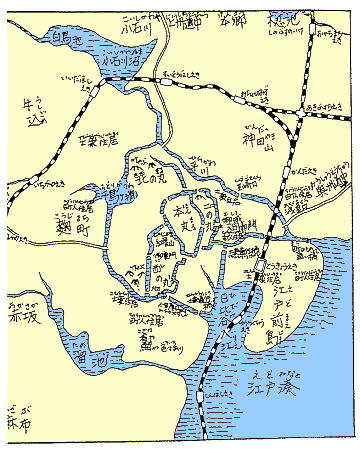
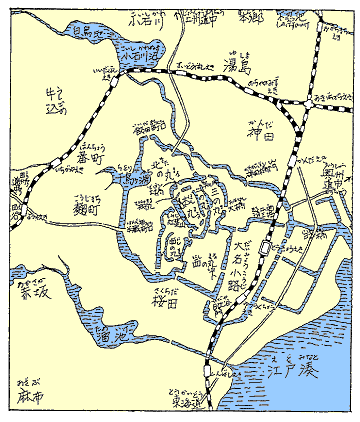
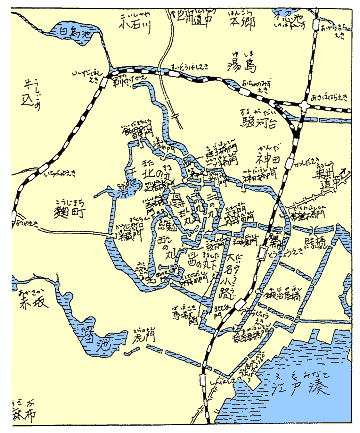
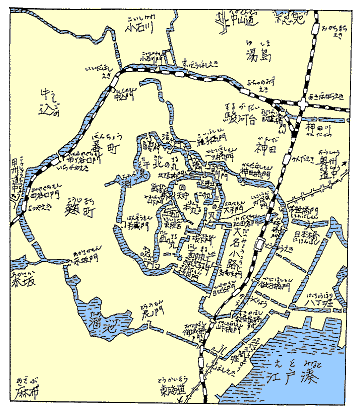

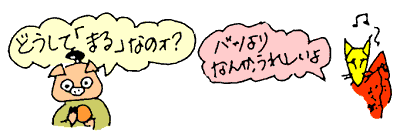
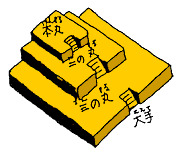
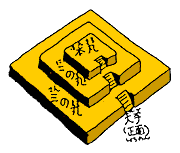
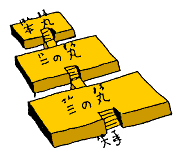
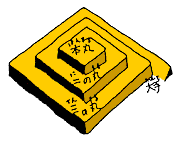

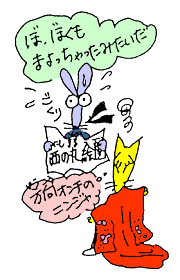 だいたい
だいたい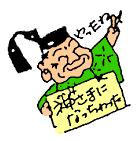
 (注釈)
(注釈)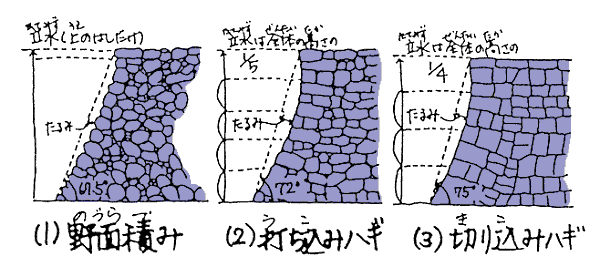
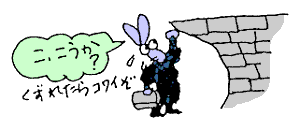 そして
そして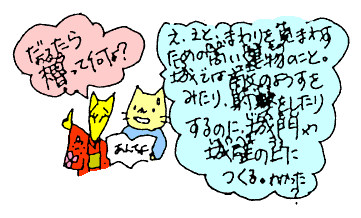
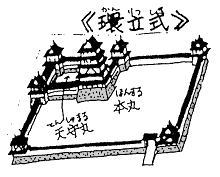
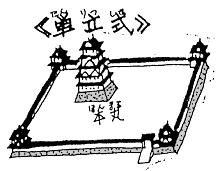
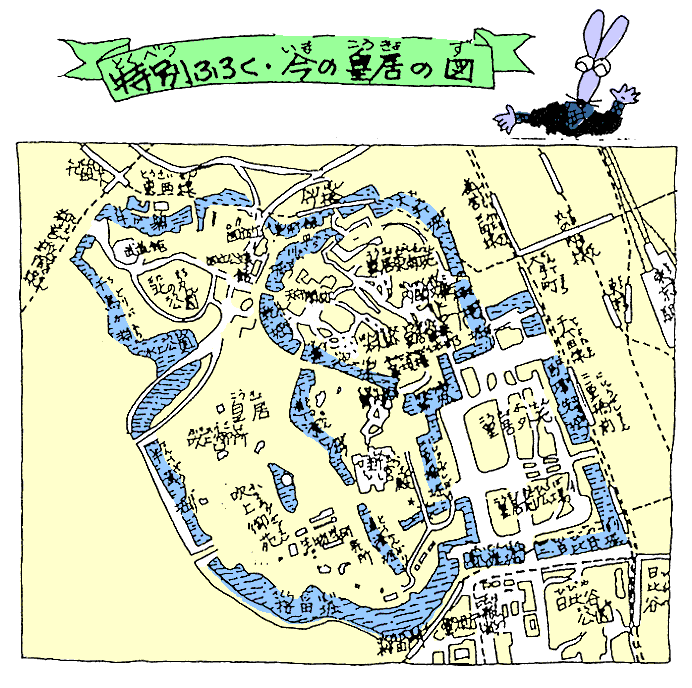
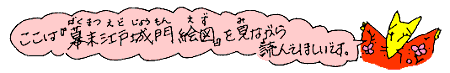
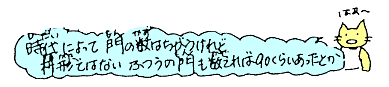
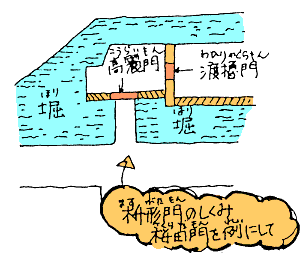

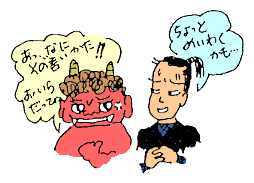

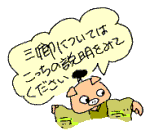
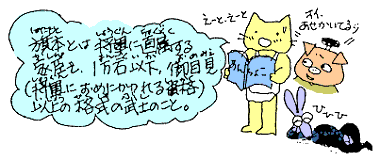
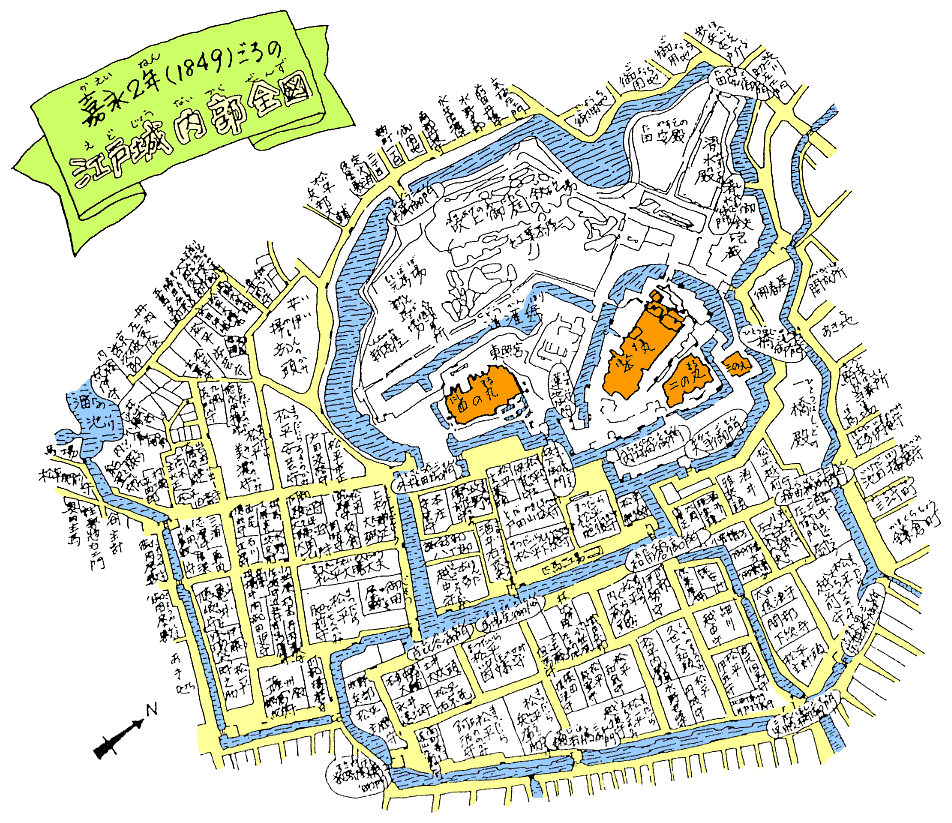
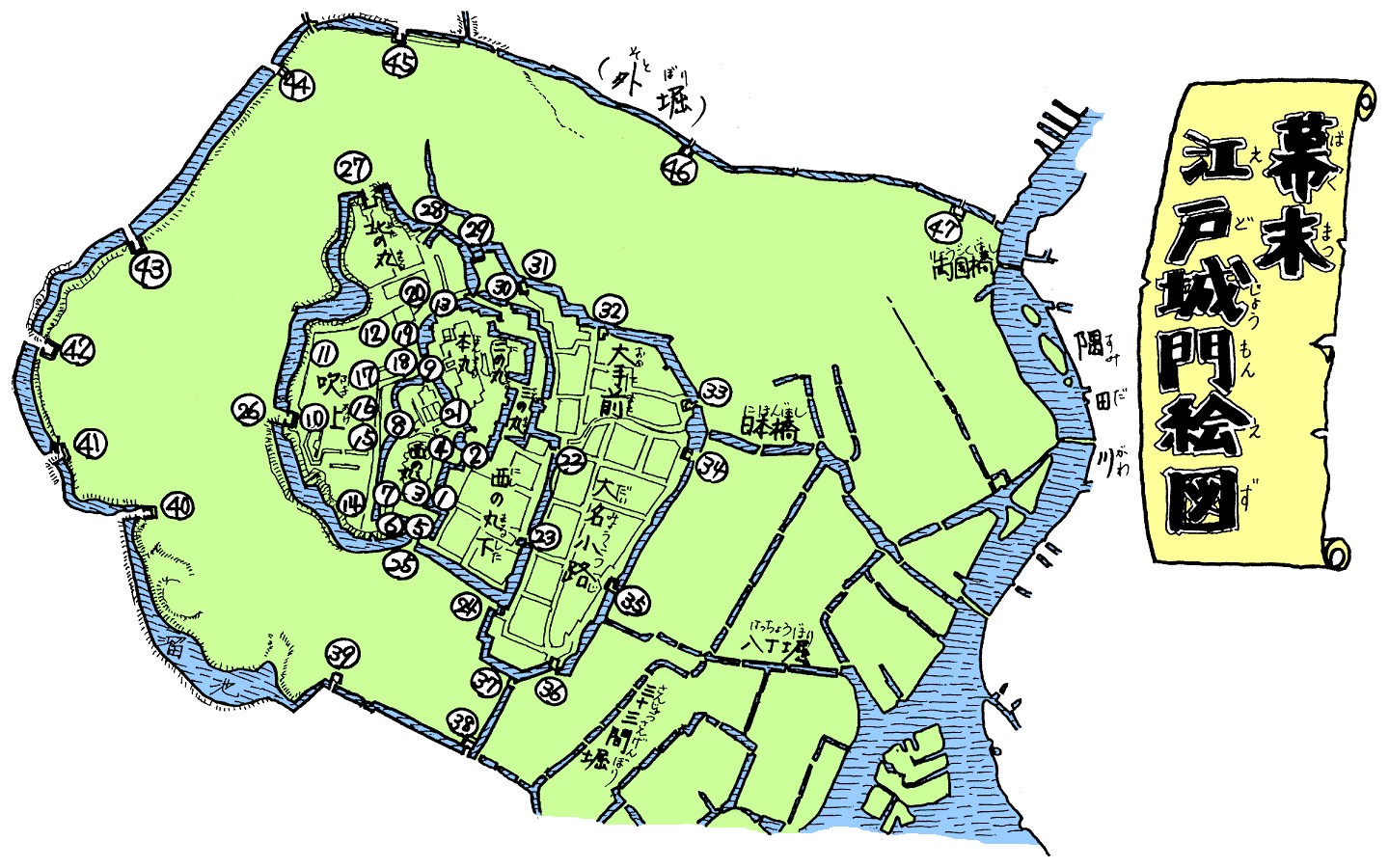
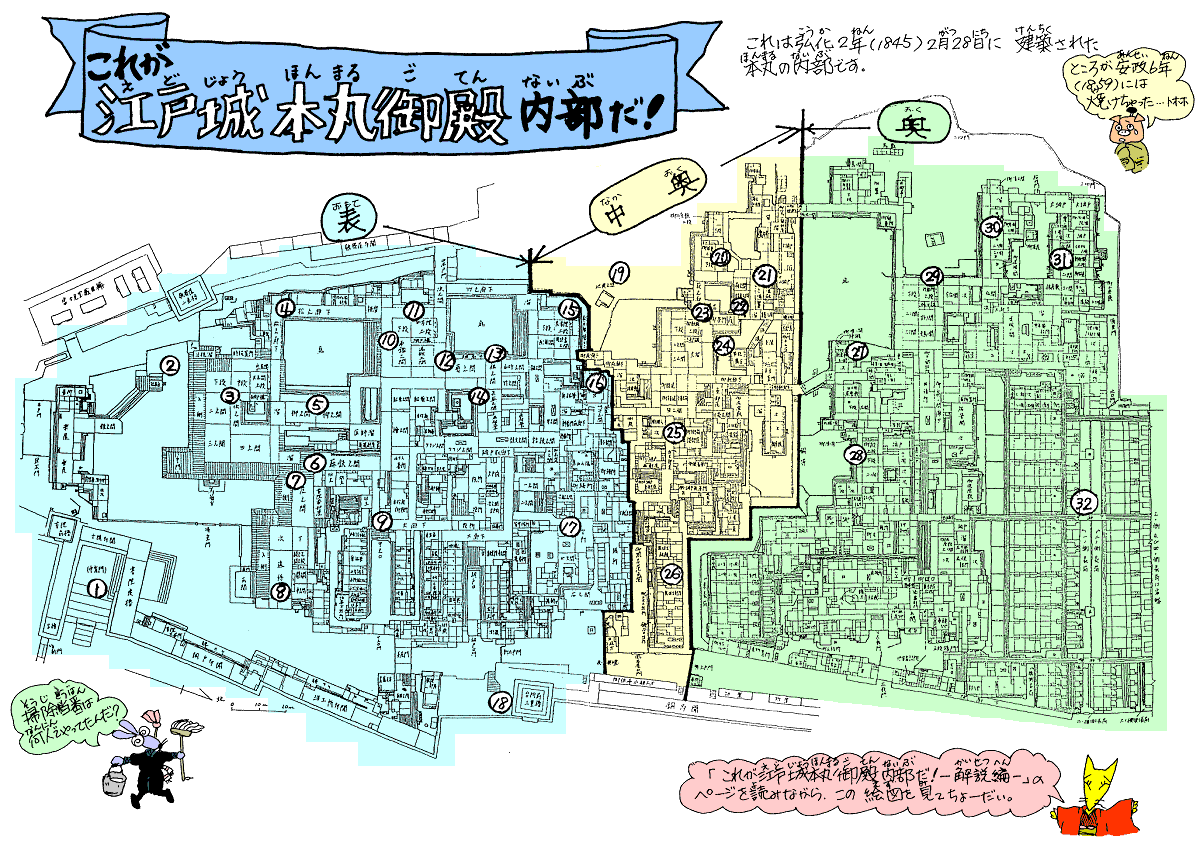
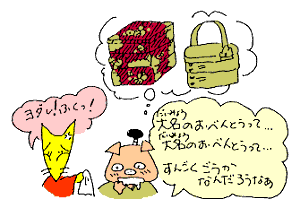
 (1)
(1)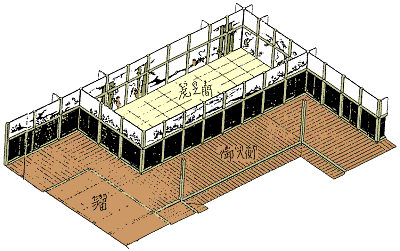 に大名たちは玄関からはいり、遠侍を通って大広間へ向かう。
に大名たちは玄関からはいり、遠侍を通って大広間へ向かう。