40. 花 の江戸 城 Part1
花 の江戸 城 へ
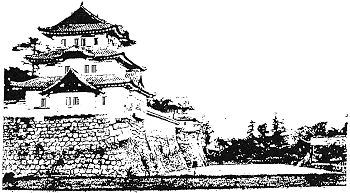 (
(
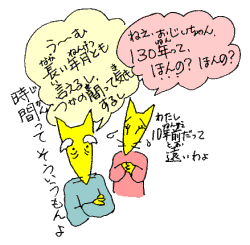
そして、その
「
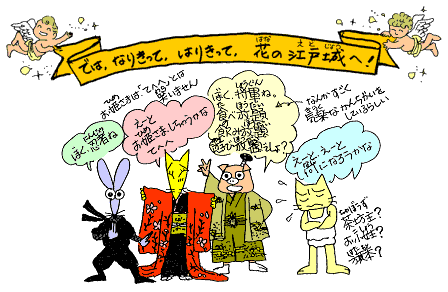
江戸城 年表
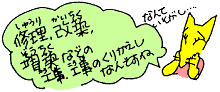
| 年 | できごと |
|---|---|
| 10 |
|
| 4 |
|
| 7 |
|
| 1 |
|
| 11 |
|
| 4 8 9 |
|
| 4 |
|
| 3 8 9 |
|
8 |
|
| 2 3 |
|
| 6 8 |
|
| 4 |
|
11 |
|
| 9 9 |
|
| 3 |
|
| 3 |
|
4 10 |
|
| 4 5 |
|
4 |
|
4 |
|
| 2 |
|
| 7 この |
|
| この |
|
| この |
|
| この |
|
| 7 |
|
2 7 |
|
| 8 |
|
| 9 |
|
| 9 |
|
| 8 |
|
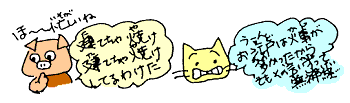 8 |
|
| 5 |
|
| 8 |
|
| 5 |
|
| 4 |
|
| 4 |
|
これ |
|
| 4 8 |
|
| 11 |
|
| 9 |
|
| 2 |
|
| 2 |
|
| 3 |
|
| 3 |
|
| 5 |
|
| 3 |
|
| 12 |
|
| 5 |
|
| 2 |
|
| 6 |
|
| 7 |
|
| 10 |
|
| 10 |
|
| 11 |
|
| 6 11 |
|
| 12 |
|
| 10 12 |
|
| 4 7 9 |
|
| 11 |
|
| 3 8 10 |
|
| 10 |
|
| 1 |
|
| 9 |
|
| 5 |
|
| 「 |
|
江戸 城 の歴史 その1
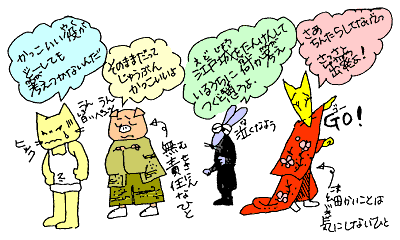
1.家康 がやって来 る前 の江戸
鎌倉 時代
「江戸 」の名 が歴史 に登場 するのは、武士 が活躍 した中世 。平家 の勢 いが盛 んだった頃 、武蔵国 に秩父 別当 重弘 という平氏系 の人 があった。その孫 の重長 は治承 4年 (1180)、石橋 合戦 の後 、源頼朝 について、重 く用 いられた。その勢力 は、今 の千代田区 を中心 に台東区 、文京区 、港区 、新宿区 あたりにまでおよんでいた。そして、この重長 が麹町 台地 に「江戸 館 」を建 てた。江戸城 のもととなる建物 だ。
そのころの江戸 は海 に面 した低湿地 の西 に武蔵野 台地 が広 がっていた。武蔵野 台地 はさらに西 から東 へ、品川 台地 、麻布 台地 、麹町 台地 、本郷 台地 、上野 台地 と、5つの小 さな台地 に分 かれる。台地 と台地 の間 には沼 や川 があって、江戸 湊 へと流 れこみ、たくさんの入江 ができていた。
そのころの
室町 時代
このころの江戸 は関東 管領 、上杉 定正 の支配 だった。その重臣 だった太田 道灌 は康正 3年 (1457)、かつての江戸 館 あとに江戸城 を築 いた。谷 を利用 して、たくさんの堀 をつくり、城 は子 ・中 ・外 (下)の三郭 からなっていた。中城 は本 丸 、子城 は二 の丸 、外城 は三 の丸 にあたる。まわりには道灌 の家臣 たちの根小屋 が置 かれ、物見 のための20の櫓 と5つの石門 が守 りをかためていた。
城 のまわりはにぎわい、城下町 も発達 した。けれど文明 18年 (1486)、道灌 が主君 の上杉 定正 に暗殺 されると、江戸 はさびれた田舎 になってしまった。
江戸城 は別名 「千代田城 」
『御府内 備考 』(注釈)によると、道灌 が、城 を構 える場所 を求 めて、たどりついた村 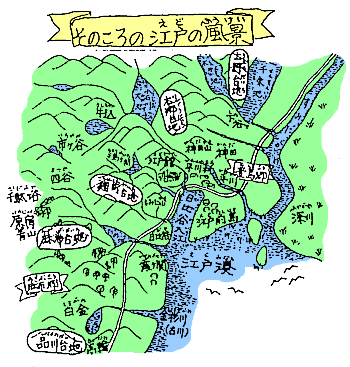 の
の名 をたずねたところ「千代田 、宝田 、祝田村 」の三 か村 だという。とても縁起 のいい名前 なので、ここに城 をかまえたら、栄 えることまちがいなし、と道灌 は心 を決 めたという。そして、城 は、徳川 家康 が入国 するまでは「千代田城 」と呼 ばれていた。
(注釈)『御府内 備考 』というのは幕府 が文政 12年 (1829)に完成 させた、江戸 府内 の地誌 。江戸城 や町 、神社 、お寺 について歴史 、由来 などの説明 がのっている。
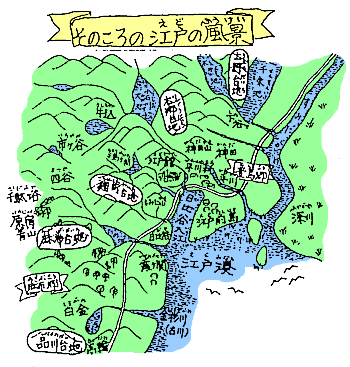 の
の(注釈)『
2.家康 、関東 入国 戦国 時代 のおわり
そして
(注釈)≪
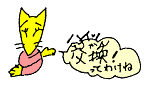
≪それまでの
3.江戸 の都市 計画

これらがそろった
(注釈)「
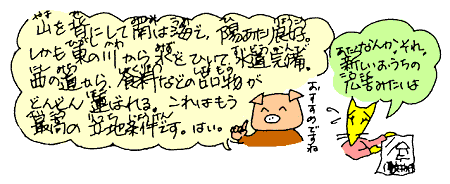
四神 全員 ご紹介
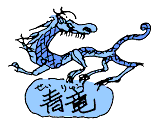
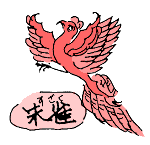
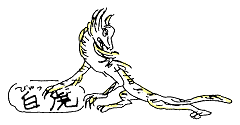
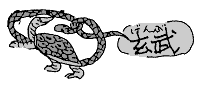
4.「の」の字 の都市 、江戸 江戸 時代
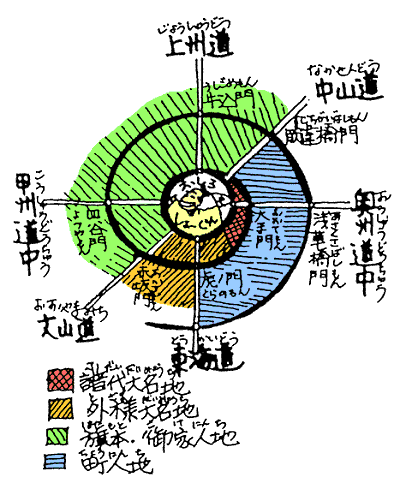
そこで
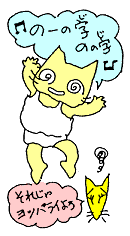
江戸 城 の歴史 その2
5.天下普請
それまでは、自分
配下 の武将 たちに城 の手 直 しや、城下町 づくりを命 じていた家康 だった。けれど、幕府 を開 いてからは全国 の大名 に命令 を下 し、天下一 の城 づくりをめざした。世 に「天下普請 」と言 われる大工事 だ。
まず初 めに慶長 8年 (1603)3月 、江戸 湊 を整備 し、船 着 き場 をつくった。それから神田山 をきりくずし、その土 で遠浅 の日比谷 入江 の埋 め立 てをした。
こうした町 づくりとともに江戸城 の工事 も、どんどん進 められていった。
秀忠 が二 代 将軍 を継 ぎ、家康 が亡 くなった(元和 2年 ・1616)あと、本 丸 が元和 8年 (1622)に完成 。もはや戦国 向 きではない、平和 な時代 の城 にできあがった。
元和 9年 (1633)7月 。秀忠 はその子 、家光 に将軍 職 をゆずって、西 の丸 に隠居 した。
三 代 将軍 家光 は、寛永 7年 (1630)に二 の丸 に茶室 のある御殿 と大庭園 を完成 させた。小堀 遠州 (注釈)の設計 による立派 な別荘 だ。
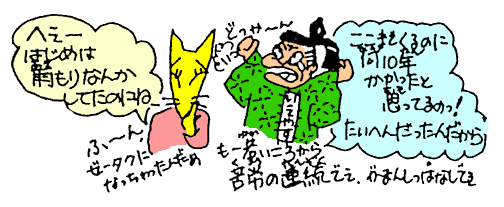 (注釈)
(注釈)小堀 遠州 江戸 の初 めの茶人 。千利休 ・古田織部 とあわせ三 大 茶人 といわれる。家康 から家光 まで将軍 三 代 に仕 え、作事 (工事 )奉行 として二条城 二 の丸 、大阪城 本 丸 などたくさんの建築 や庭園 をてがけた。

まず
こうした
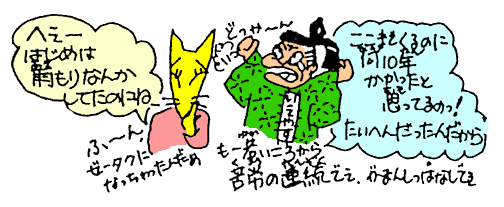 (注釈)
(注釈)1.第 1次 建設 期
2.第 2次 建設 期
3.第 3次 建設 期
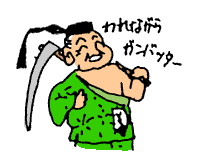
4.第 4次 建設 期
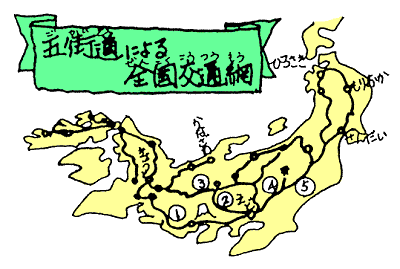
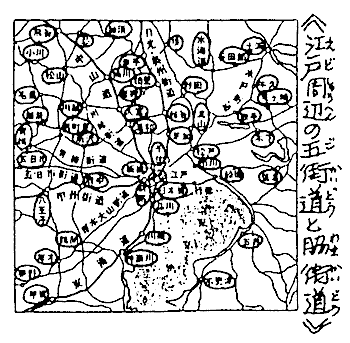
東海道 (品川 ~京都 )甲州 道中 (内藤 新宿 ~大諏訪 で中山道 と合流 )中山道 (板橋 ~草津 で東海道 と合流 )日光 道中 (千住 ~日光 )奥州 道中 (宇都宮 で日光 道中 と分 かれ、白川 へ)
家康 はこれらの五街道 と脇 街道 を組 み合 わせ、江戸 を中心 に全国 をむすぶ交通網 を整備 した。
6.明暦 の大火
おびただしい
と
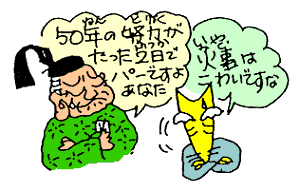
しかも、
お江戸 の範囲 -朱引図 -
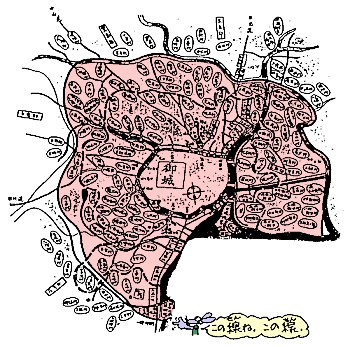
7.よみがえる江戸城

この
その
そして
この
明暦 大火 以後 の江戸城 および城下町 の防火 対策 のまとめ
権力 のシンボル、5層 の大天守 は再建 しない。
また、これより、本 丸 、二 の丸 、三 の丸 の御殿 も豪華 にすることはひかえ、政府 としての働 きの方 を重 んじる。御三家 を内郭 から引 っ越 しさせる。
その跡 地 である江戸城 の西北 に火 除 け地 をつくる。(宝永 4年 (1707)より、ここは「吹上 の御庭 」となる。)大名 屋敷 を内郭 から引 っ越 しさせる。
龍ノ口 、竹橋内 、雉子 橋内 、代官町 内 にあった大名 たちの屋敷 替 えをして、その跡 地 を幕府 の公用 とする。- お
寺 や神社 も内郭 から引 っ越 しさせる。 外郭 のうちにも新 たに火 除 け地 をつくる。町人 用 の防火 地帯 だ。新 しい市街地 をつくる。
小石川 小日向 の湿地 や赤坂 ため池 の一部 を埋 め立 て、町 づくりをする。
(京橋 木挽町 東 側 の海 を埋 め立 てて、できたのが今 の「築地 」。)隅田川 に新 しく橋 を設 ける。
大火 の際 、ここまで逃 げて来 て、川 を越 えられず焼 け死 んだ人 が多 かったのだ。万治 2年 (1659)に橋 は完成 。武蔵国 と下総国 を結ぶので「両国橋 」と名付 けられた。
江戸城 のおもかげ
(『
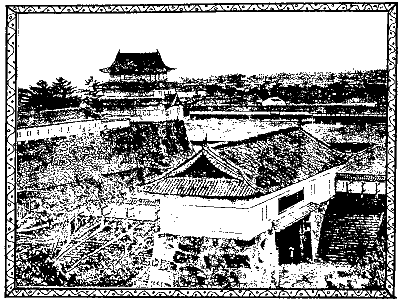
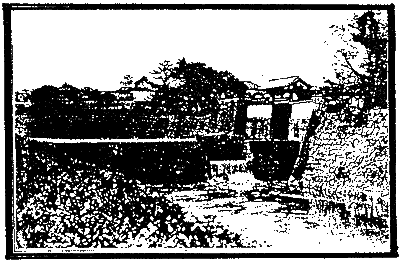
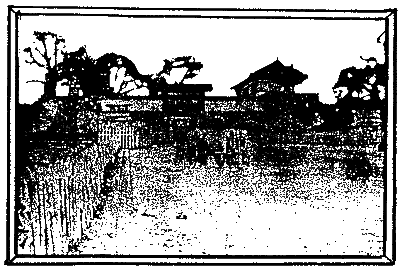
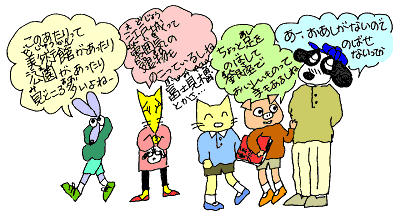
参考 にした本
「東京 百科 事典 」
「江戸 東京 町 づくり物語 」
「江戸 学 事典 」
「日本 歴史 大辞典 」
「江戸 と江戸城 」
「江戸城 物語 」
「江戸 東京 学 事典 」
「江戸 の町 」(上 )(下 )
「日本 城郭 の古写真集 」
「東京 -講談社版 日本 の文化 地理 」
「平凡社大 百科 事典 」その他 いろいろ
「
「
「
「
「
「
「
「
「
「
小平市に関すること
多摩に関すること
| 12.多摩戦国絵巻 | 18.多摩の絹の道 シルクロード |
| 20.風雲!新選組 | 21.楽しい施設ガイド |
| 25.東京のできるまで | 27.神奈川県から東京府へ多摩移管百年うそ?ほんと?クイズ |
| 29.多摩の芸能 | 32.八王子千人同心多摩をゆく |
| 35.多摩の酒造 | 39.江戸時代の東京 文化文政(1800年代初め)の三多摩編 |
江戸・東京に関すること
| 23.幸運招来! 東京七福神めぐり | 24.東京の水道 |
| 28.江戸をたのしむ | 30.わたしのまちの木・花・鳥とシンボルマーク |
| 38.江戸時代の東京 文化文政(1800年代初め)の特別区編 | 40.花の江戸城 Part1 |
| 41.花の江戸城 Part2 |
玉川上水・小金井桜に関すること
| 3.玉川上水をしりたい | 7.玉川上水とあそぼう! |
| 17.満開!小金井桜 | 31.野火止用水をゆけば |
その他
| 11.武蔵武士 | 22.コレラが町にやって来た |
| 33.これが武蔵国だっ! | 34.地震にそなえて |
掲載日 令和7年8月1日




















