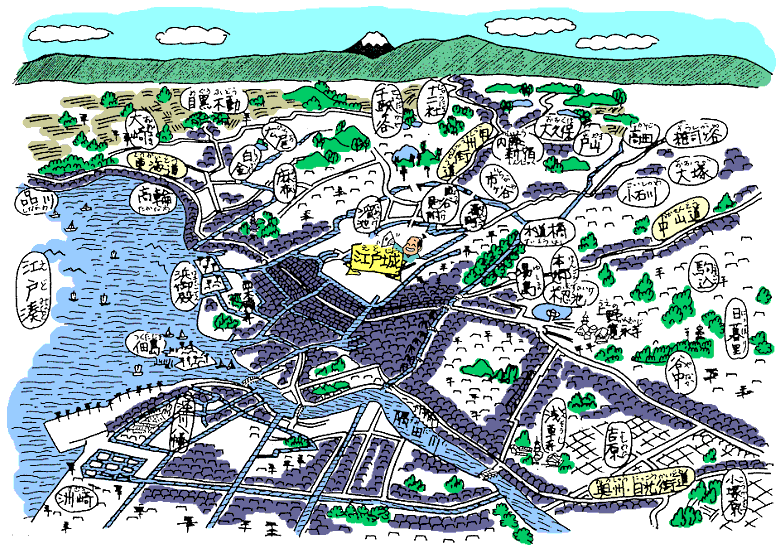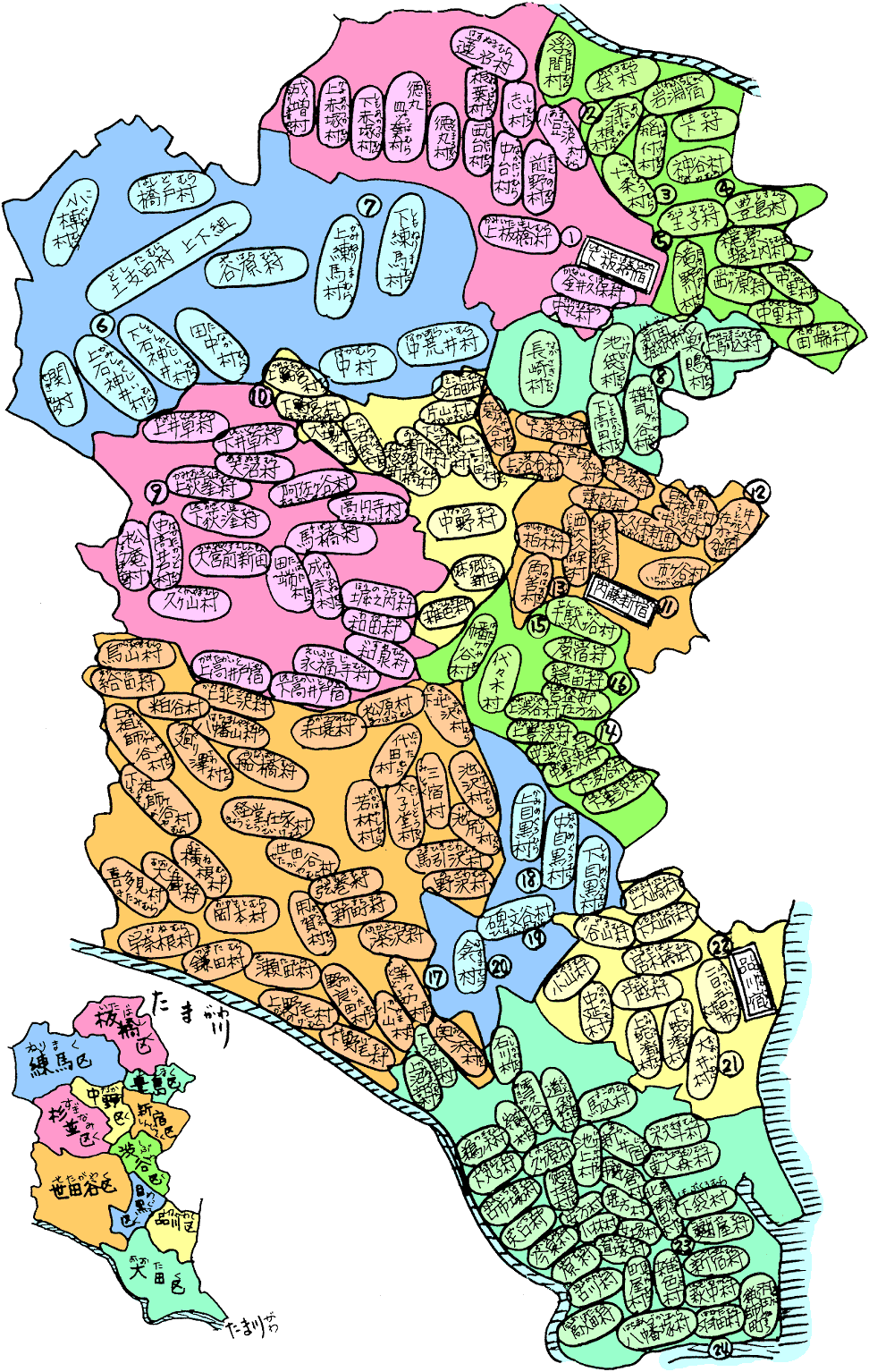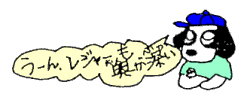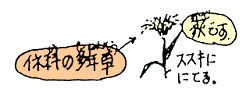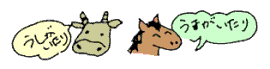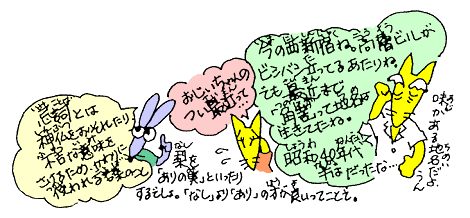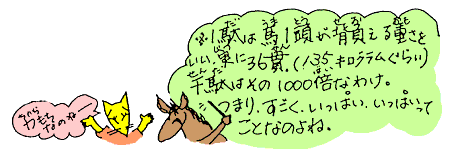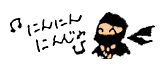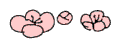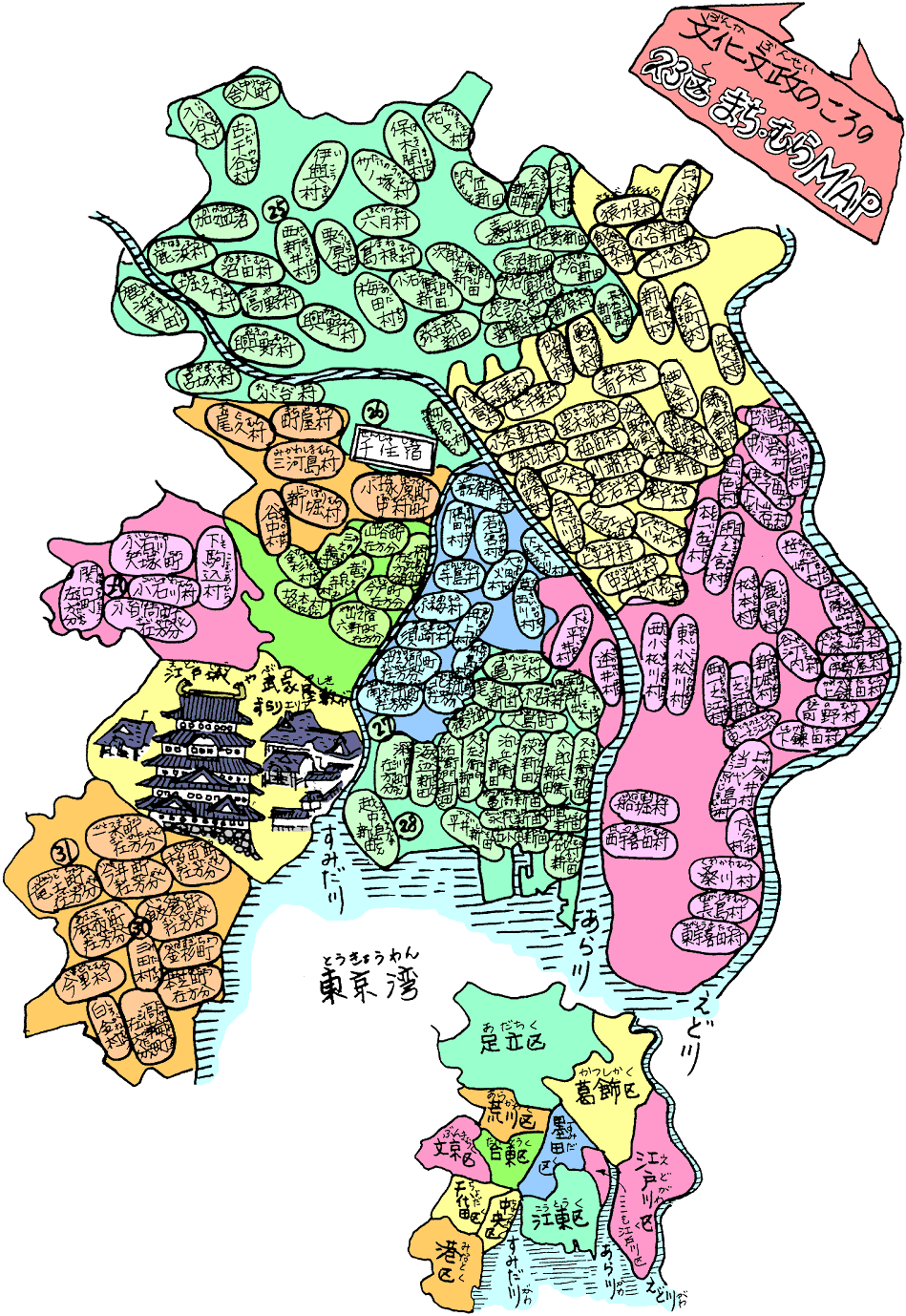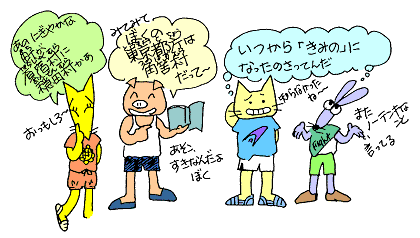江戸時代の東京特別区
天正18年(1590)の、家康の関東入国以来、江戸城(千代田区、今の皇居)を中心に都市建設は始まった。町はどんどん広がって、はじめは、江戸城とそのまわりくらいだった市域が、文政元年(1818)、江戸の範囲をはっきりさせるために作られた「朱引き図」という資料を見ると、だいたい今の山手線のところまでになっている。江戸は大都市だった。立派な大名屋敷が立ち並び、町人がひしめき合って、たくさんの人が住んでいた。
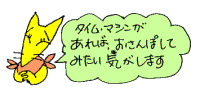 それでも西の空をあおげば富士山がすっきりとそびえたち、江戸城の前の海や川では魚がとれて、「江戸前」とよばれ、みんなからおいしい!と歓ばれた。そして、山手線の外側は、のどかな農村や漁村だったりするわけだ。高速道路が走り、高層ビルがたち並ぶ23区もほんのちょっと前までは、こんな風景だったんだね。
それでも西の空をあおげば富士山がすっきりとそびえたち、江戸城の前の海や川では魚がとれて、「江戸前」とよばれ、みんなからおいしい!と歓ばれた。そして、山手線の外側は、のどかな農村や漁村だったりするわけだ。高速道路が走り、高層ビルがたち並ぶ23区もほんのちょっと前までは、こんな風景だったんだね。
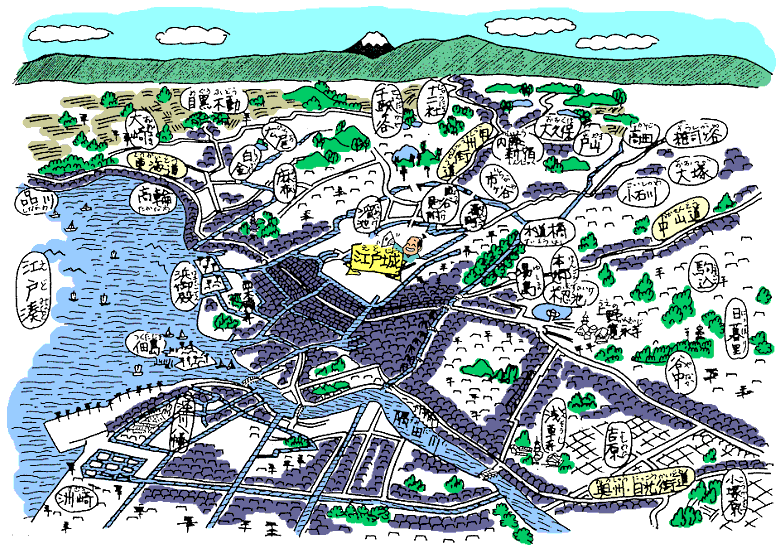
江戸時代のあの町この村その1
『新編武蔵風土記稿 』のころの23区
地名のいわれ、などなど…。
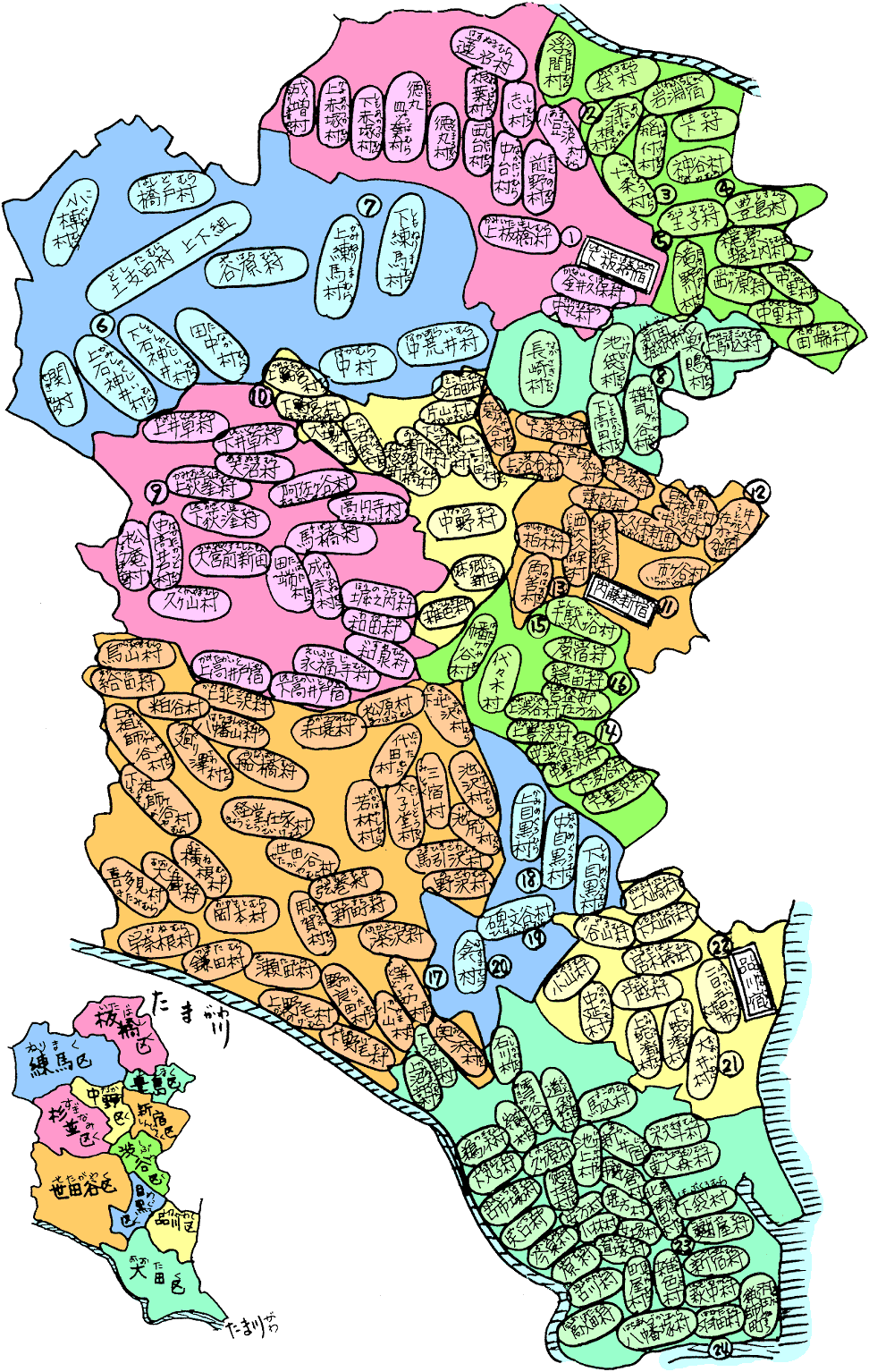
(今の)板橋区
1.板橋
石神井川にかかっていた橋にちなむ地名だとか。『源平盛衰記』(1247~49ごろ成立)に登場するほど歴史がある。江戸時代には品川、新宿、千住とともに「江戸四宿」といわれ、中山道の出発点だった。
北区
2.赤羽根
今は「赤羽」と書くけれど、江戸時代は「赤羽根」。むかしからこのあたり、赤土が多かったので「赤埴(あかはに)」(赤色の土のこと)とよばれていて、それが「あかばね」になったとか。ほかにもいろいろ説がある。
3.十条
条里制度による区画が地名として残ったのだという。条里制というのは孝徳天皇の大化元年(645)におこなわれた碁盤の目のようにきっちり整理された土地区画の方式。
4.豊島
むかし、海がここまではいりこんでいて、沿岸がいりくんだ島になっていたので、この地名がついたのではないか、と言われる。平安時代の末に秩父平氏の一族がここに移り住み、「豊島氏」を名乗るようになった。一族は鎌倉幕府の有力な御家人として栄えた。文明10年(1478)、太田道灌に滅ぼされるまでおよそ400年間、豊島一帯を支配した。
5.王子
地名は、豊島氏が紀州の熊野若一王子(王子神社)を勧請(神さまの霊をわけてまつること)したことによるという。江戸時代、8代将軍吉宗の政策で江戸近郊(町のまわりの田園地帯ってことね)の行楽地としてにぎわうようになった。
練馬区
6.石神井
むかし、このあたりの
村人
が井戸を掘った時のこと。土の中から青い石の棒がでてきたのだと。この不思議な石を人々は、小さな祠を建て、「石神様」としてまつった。これが「石神井」の地名のおこりだという。
7.練馬
『続日本記』(797年成立の歴史の本)に『武蔵国の駅、乗潴』と書かれていて、「のりぬま」がなまって「ねりま」になった、とか、赤土のねり場だったから、とか、水田の奥の沼がある地だったので「根の沼」なんだ、とか。ほんと地名っていっぱい説があるんだよね。もうひとつ、おまけに伝説では、この地に来た馬どろぼうがぬすんだ馬を訓練して市場へ出したのでこの名がついたという。馬をならすことを「ネル」と言ったんだって。「馬をネル」で「ねりま」。
豊島区
8.雑司ヶ谷
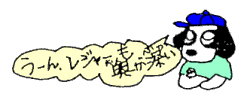 元弘
元弘・
建武のころ(1331~1337)、
宮廷の
雑色(
下級役人)の
柳下若狹守、
長島内匠、
戸張平左衛門が、
南朝の
衰えをなげいて、
職をしりぞき、
武蔵国に
下って、ここに
移り
住んだ。
以来、「
雑色谷」とよばれ、いつのまにやら「
雑司ヶ谷」に。
江戸の
元禄時代(1688~1704)ころから、レジャーとしてのお
寺・
神社まいりが
盛んになった。ここの
鬼子母神も、とってもにぎわったという。
杉並区
9.荻窪
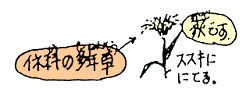 和銅元年
和銅元年(708)のこと。
尊い
仏様の
像を
背負った
行者が、このあたりの
原に
来ると
急に
背中が
重くなり、
歩けなくなった。これは
仏様に
縁のある
地だろうと、
野原の
萩をあつめてお
堂を
建てた。それが
地名のはじまり、とか。
中野区
10.鷺宮
『新編武蔵風土記稿』(1828年成立)には村の神社に「たくさんの鷺が生息しているので“鷺森”とか“鷺宮”とか言っていて、いつのまにか村の名になった」とある。昭和の初めころまで、白鷲の姿が見られたそうな。
新宿区
11.新宿
慶長9
年(1604)、
徳川幕府は
五街道を
定めた。そのひとつ、
甲州街道の
出発点は
初めは
高井戸宿(
今の
杉並区)だった。でも、もう
少し
江戸に
近い
方が
便利だと、
元禄10
年(1697)に
内藤新宿がつくられた。
高井戸宿に
対して
新しく
作ったので「
新宿」なんだよ。
ここには
内藤氏の
屋敷があった。
家康の
関東入国のさい(1590
年)、
警備のために
内藤清成が
初めて
訪れた
時、この
地は
原野だった。
12.牛込
むかし、このあたりは
牛を
飼う
牧場だったのでは…という。
上野国(
今の
群馬県)の
豪族、
大胡重春、
重行が
移り
住み
開拓した。
重行の
子、
勝行が
弘治元年(1555)より「
牛込氏」を
名乗るようになったという。
13.角筈
地名の由来は名主の家に伝わる話。この地の開拓者、与兵衛は優婆塞(正式な僧とならず、山林などで修行する人)だった。「角筈」というのは伊勢神宮の忌詞で優婆塞のこと。
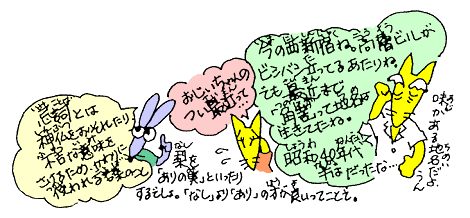
渋谷区
14.渋谷
むかし、このあたりは入江になった浜辺で「塩谷の里」と言ったとか。それが「しぶや」になったという説や、治承のころ(1177~1180)に相模国(今の神奈川県)の豪族、渋谷庄司重国の領地だったから、という説がある。
15.千駄ケ谷
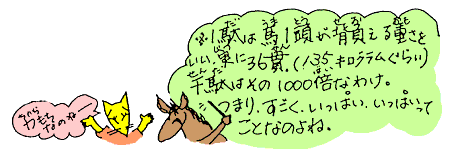 太田道灌が領地を見まわった時、このあたりの谷間に栽培されている稲が千駄もあるので「千駄ケ谷」と名付けたという。
太田道灌が領地を見まわった時、このあたりの谷間に栽培されている稲が千駄もあるので「千駄ケ谷」と名付けたという。
また、ここら
一面萱野原で「
一日に
千駄の
萱を
出す
所」という
意味でついたともいう。
江戸時代には
幕府の
煙硝蔵(
火薬庫)があった。
16.穏田
昭和45年(1970)に神宮前という名にかわった。「隠し田」だった、とか、小田原北条氏の家臣の恩田という人が住んでいたから、とか地名のいわれはいろいろ。家康が関東入国したよく年、天正19年(1591)に伊賀者に与えられた土地だ。のち、足利藩や鳥取藩などの屋敷地になるけれど、伊賀者の子孫たちが明治維新まで住んでいたという。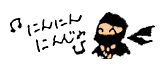
世田谷区
17.等々力
 多摩川
多摩川にそそぐ
谷沢川がつくる
谷で
一年中、
滝や
急な
流れが
水音をとどろかせていたので、この
地名が
生まれたという。
江戸時代は
郊外の
景勝地。(
景色のすぐれた
所)
目黒区
18.目黒
そのむかし、牧場を管理する人が畔道を通って馬を見守ったので「馬畔」と名がついた。(「畔」は“くろ”とも読むんだ。)
また、
関東でもっとも
古いお
不動さんである
目黒不動が
開かれたので、という
説も。
他に、「め」はくぼ
地や
谷、「くろ」は
嶺のことで
地形をあらわす
名だ、とか、すぐれた
黒馬がたくさん出たから、という
説もある。
19.碑文谷
『新編武蔵風土記稿』に「村の中を通る鎌倉古街道のわきに梵字(サンスクリット文字。古代インドの文字)をきざんだ碑がたてられていたため、この名がおこった」とある。もう一説には、忠玄という僧が大卒塔婆に碑文を書いてここに埋めたから、ともいう。
20.衾
馬の飼料の「ふすま」(小麦を粉にひくときにできる皮のくず)の産地なのでこの名がついた。また「伏馬」で、馬を埋葬した所では、という説も。
品川区
21.大井
『
延喜式』(900
年ごろ
成立)という
資料にのっているくらい
古い
地名。
延暦3
年(784)、
桓武天皇時代にここの
守護だった
大井氏の
名が
地名になったという。
他には、この
地方で
知られた
大井戸があったから、とも。また、
大きな
藺(いぐさ、のこと)がおい
茂っていたから
大藺になった、とも。
22.品川
目黒川の古い名である「品河」にちなむという。また、別の説では、このあたり出崎や入谷があって、品が良い地形だったので、おとなりの「高輪」に対して「品ヶ輪」と名付けたのが始まりとも。東海道の出発点。
大田区
23.蒲田
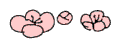 江戸時代
江戸時代、このあたりの
家々は
梅の
木を
植え、
実を
収穫していた。2
月には
梅の
花が
盛りで、
見物客もたくさん
来た。
別名「
梅村」と
言い、
絵師安藤広重の『
名所江戸百景』にはここの
梅屋敷も
描かれている。
「かまた」というのは「
泥深い
田」の
意味、アイヌ
語の「
泥の
中の
島」という
意味の
言葉なんだって。
24.羽田
戦国時代、小田原北条氏は、ここを江戸湾の重要な地点として、猟師(漁師)で組織した水軍を置いた。江戸時代には、幕府へ新鮮な魚をおさめる「御菜(おかずのことだ)八ヶ浦」のひとつでもあり、海運も盛んだった。
江戸時代のあの町この村その2
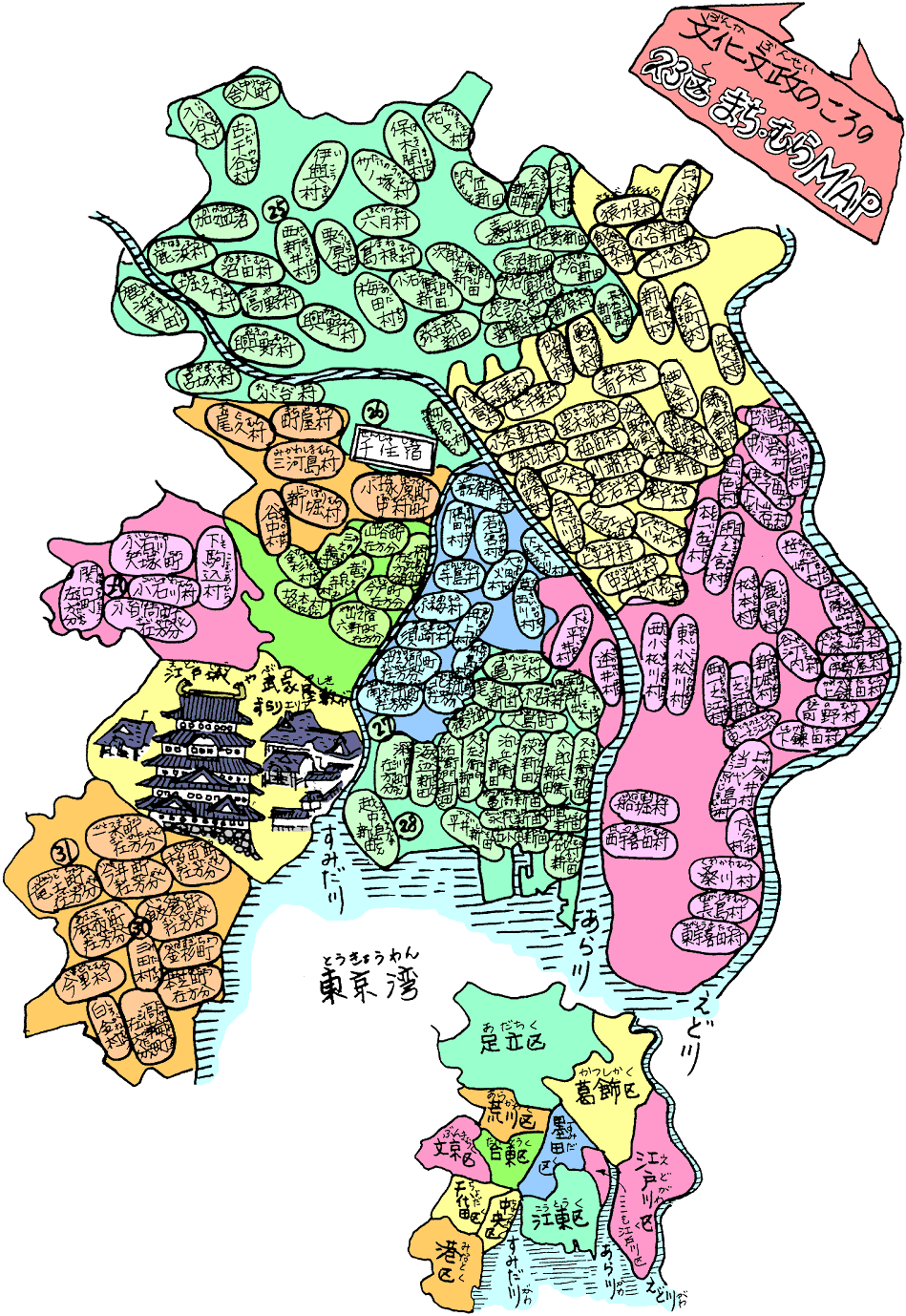
足立区
25.西新井
天長3年(826)、関東で教えをひろめ歩いていた弘法大師(注釈)が、人々を疫病から救おうと観音像を彫り、ここに埋めて庵を建て、祈った。たちまち疫病はおさまり、弘法大師を慕う村人は観音像をほり出し、あとの穴を井戸とした。この井戸は、弘法大師の開いた五智山遍照院総持寺の西に位置したので「西新井」とよばれるようになった、とか。
(注釈)
弘法大師とは、
平安時代の
僧。
真言宗を
開き、
高野山に
金剛峰寺を
建てた。すごく
字がうまい、ということでも
有名な
人。
26.千住
永禄2年(1559)、小田原北条氏のころに、「専住村」として記録に登場する。
寛永2
年(1625)、3
代将軍家光の
時、
日光街道の
出発点の
宿となって、
発展した。
日光東照宮へおまいりする
将軍家や
参勤交代の
大名たちの
行列が
通ったんだ。
江東区
27.深川
家康の
関東入国間もない
慶長の
頃(1596~1614)このあたりを
開拓したのは
深川八郎右衛門という
摂津国(
今の
大阪、
兵庫のあたり)の
人だった。
狩りに
来た
家康が
地名をたずねたが、まだ
名はなかった。
家康の「
深川」を
村の
名にせよ、という
言葉から
生まれた
地名だ。
28.越中島
ここはもともと「州」(川口にできた小島)だった。これが今の東京の「夢の島」みたいにだんだん埋められていった。明暦・万治(1655~1660)のころ、榊原越中守が賜わり、別邸にしたので、「越中島」とよばれた。正徳元年(1713)には旗本御家人たちに与えられ、「越中島町」となった。
文京区
29.小石川
今はもうわからないけれど、江戸時代以前は川があったんだって。小石の多い川だったのでこの名がついたそうだ。
港区
30.麻布
むかし、
麻を
栽培して、
布をこしらえた
土地だったので、この
地名がついた。
江戸時代の
初めごろは
郊外だったけれど、なかばころから
武家屋敷が
建つようになった。
31.竜土
寛永のころ(1624~1643)、ここに天から竜が降って来た、という伝説から生まれた地名だという。別の説では、2代将軍秀忠の時、海がすぐ東の愛宕山の下あたりまではいりこんでいた。海辺沿いの漁師の村がここに移され「漁人村」とよばれ、のち「竜土」の字に改められたのだ、ともいう。
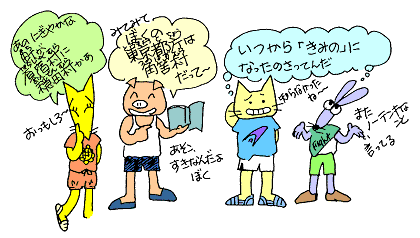
参考にした本
「新編武蔵風土記稿」
「角川地名大辞典」
「武蔵国全図」
「東京府郡全図」
「江戸東京地名事典」
「東京地名考」そのほかいろいろ…
小平市に関すること
多摩に関すること
江戸・東京に関すること
玉川上水・小金井桜に関すること
その他
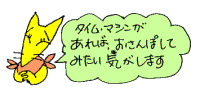 それでも
それでも