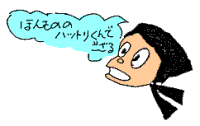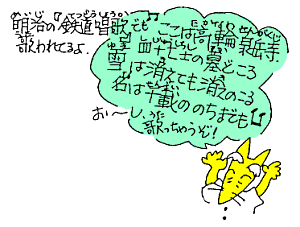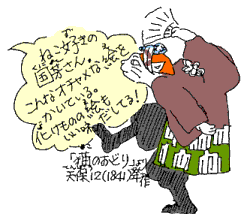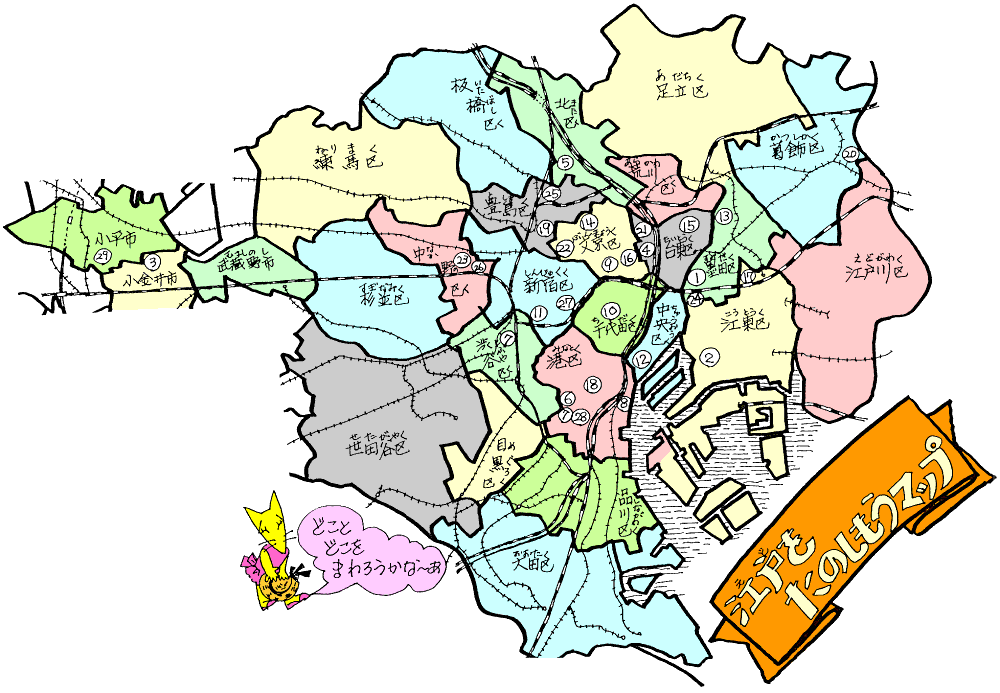江戸をたずねて


大正の関東大震災と、昭和の太平洋戦争で、むかしの姿を失ったという東京。ところがどっこい。ぶらり、歩いてごらん。町のあちらこちらで、歴史は息づいている。路地をまがると、江戸がひょいっと顔を出したりする。
遠いむかしのはずなのに、不思議になつかしい笑い顔をして。
博物館コース/公園コース
A.博物館コース
 江戸時代にタイム・スリップする!
江戸時代にタイム・スリップする!
1.江戸東京博物館
墨田区横網1-4-1 JR両国駅下車
開館 9時30分~17時30分(土曜日のみ19時30分まで)
休館 月曜日 入館料 大人600円 子ども300円
館内の日本橋をわたると、そこはもう江戸の町。芝居小屋「中村座」だの、両国かいわいの盛り場だの、大名屋敷だの。江戸・東京の歴史と文化が盛りだくさん。おみやげ屋さんにもぜひよりたい!
2.江東区深川江戸資料館
江東区白河1-3-28 地下鉄東西線門前仲町下車、徒歩15分。バスなら清澄庭園前下車、徒歩3分。
開館 9時30分~17時(入館は16時30分まで)
休館 第2、第4月曜日 入館料大人300円 子ども50円
通路を抜けたとたん、目の下に広がるのは、天保年間(1840年ごろ)の実物大の深川の家並み。
八百屋、水茶屋、米屋に長屋。ニワトリが朝を告げると物売りの声が…。んんんっ、長屋では赤ん坊も泣き出した。階段をおりて、せまい路地をさまよえば気分はもう、江戸の町人だ。
3.江戸東京たてもの園
小金井市桜町3-7-1
都立小金井公園内
JR武蔵小金井駅または
西武新宿線花小金井駅下車、バス10
分。
開園 4~9
月 9時30分~17時30分 10~3
月 9時30分~16時30分
休園 月曜日 入園料 大人400
円 子ども200
円
伊達家の
門、
江戸末期の
八王子千人同心の
家、
三鷹の
吉野家(
見事なカヤブキ
屋根!)などがならぶ。
屋外見学の
前に、ビジター・センター(もと
武蔵野郷土館)の
展示で
知識を
仕入れておこう。
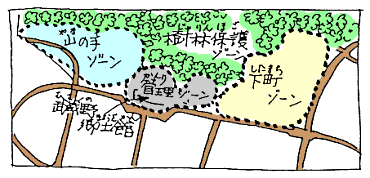
4.新宿歴史博物館
新宿区三栄町22 JR四谷駅または地下鉄丸の内線四谷三丁目下車
開館 9時~17時30分(入館は17時まで)
休館 第2、第4月曜日 入館料 大人300円 子ども100円
旧石器時代から昭和初期までの新宿の様子がわかる。
中でも「江戸のくらしと新宿」のコーナーには内藤新宿の模型があって、玉川上水の流れる四谷大木戸あたりを再現。「玉川上水」ときくと、小平市民としては、ちょっと他人の気がしないってば。
B.公園コース なんてゴージャス、大名の庭!
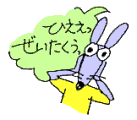 徳川幕府
徳川幕府は
全国の
大名を1
年おきに
江戸に
住まわせる「
参勤交代」の
制度をしいた。
そのため、
大名たちは、
江戸に
上屋敷(
本邸)だの、
下屋敷だのを
設けることになった。
庭園も
立派なものをつくった。
その
広大な
土地は、
今、
公の
施設や
大学の
敷地などになっている。でも、そのうち、いくつかは
東京の
代表的な
公園として
残り、わたしたちを
楽しませてくれる。
5.飛鳥山公園 お江戸の行楽地
北区王子1-1-3 JR王子駅下車
むかし、むかし、熊野飛鳥明神の社地であったので、「飛鳥山」の名がついたとか。
8代将軍吉宗はここに山桜70本を植え、江戸の人々に開放した。春には桜、秋には紅葉のにぎやかな行楽地だったんだ。
6.有栖川宮記念公園
港区南麻布5-7-29
地下鉄日比谷線広尾駅下車
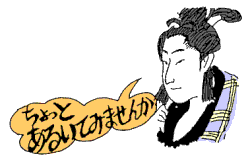
ここは
南部藩(
盛岡)の
下屋敷があったところ。
明治29(1896)
年に
有栖川宮家の
用地となり、
高松宮家に
継がれ、
昭和9(1934)
年から
開放された。
池をかこむ
緑も
豊かだ。
奥には
都立中央図書館があるよ。
7.明治神宮御苑
渋谷区代々木神園町1-1 JR原宿駅下車
開園 9時~16時
江戸の初めは加藤清正の、のちに彦根の井伊家の下屋敷となる。渋谷あたりは江戸市中と郊外のつなぎ目だったから、下屋敷が多かった。
明治天皇とおきさきの昭憲皇太后をおまつりする明治神宮が建てられたのは大正9(1920)年のこと。
8.旧芝離宮恩賜庭園
港区海岸1-4-1 JR浜松駅下車
開園 9時~17時
無休 入園料 150円
元禄年間(1688~1704)、老中大久保忠朝の上屋敷として庭園がつくられた。
大正13(1924)年から公園になったのだけれど、むかしは池に海水を引き入れていたんだって。
9.小石川後楽園
文京区後楽園1-6-6
JR飯田橋駅または
地下鉄丸の
内線後楽園駅下車
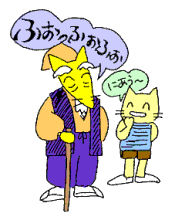 開園
開園 9時~17時
入園料300
円
あの「
黄門さま」、
水戸光圀がつくった。
寛永6(1629)
年、3
代将軍家光が
徳川御三家のひとり、
水戸頼房に
与えた
土地に
頼房の
三男、
光圀が
庭園を
完成させたというわけ。
黄門さま
自ら、
畑をたがやし、
作物を
育てた。そして
見学を
願う
江戸の
人たちには
快く
開放したそうな。こういう
人柄だったからいい
評判が
残ったのかも。
10.皇居周辺
千代田区 地下鉄東西線大手町駅とか九段下駅とかで下車
明治元年(1868)に開城するまで、ここいらは徳川幕府の本拠地だったんだよね。外苑、東御苑、北の丸公園、千鳥ヶ淵。緑とおほりにかこまれたこのあたり。歩いてみれば、ちょっとしたワンダー・ランド。
11.新宿御苑
新宿区内藤町 地下鉄丸の内線新宿御苑駅下車
開園9時~16時
休園 月曜日 入園料 大人200円 子ども50円
信州高遠藩(長野県)内藤氏の下屋敷だった。明治維新で国のものとなり、農業・蚕糸の試験場→皇室の植物御苑→一般開放とうつりかわった。開放されたのは昭和33(1958)年。
12.浜離宮恩賜庭園
中央区浜離宮庭園1-1 JRまたは地下鉄銀座線新橋駅下車
開園 9時~16時30分
休園 月曜日 入園料 200円
寛永のころ(1624~1644)にはここらへん、葦のはえる浜で、将軍の御鷹場だった。徳川3代将軍家光の子、甲府宰相綱重が、兄の4代将軍家綱からもらって下屋敷にした。何度もうめたてと庭づくりがおこなわれたようだ。「甲府浜屋敷」などとも呼ばれていたけれど、明治3(1870)年浜離宮と名をかえ、皇室のうたげに用いられた。戦後一般に開放。
13.向島百花園
墨田区東向島3-18-3 東武線玉の井駅下車
開園 9時~16時
休園 月曜日 入園料 100円
ここは、大名屋敷ではないんだ。文化元年(1804)、仙台生まれの商人、佐原鞠塢がつくったんだ。百もの花が乱れ咲く、という意味でつけた名まえなんだって。
当時一流の文化人だった大田蜀山人、谷文晁らが百花園をつくるのに協力している。江戸の人びとばかりでなく、11代将軍家斉、12代将軍家慶も遊びに来たことがあるというよ。
14.六義園
文京区本駒込6-16 JR駒込駅または地下鉄三田線千石駅下車
開園 9時~16時30分
休園 月曜日 入園料 200円
5代将軍綱吉の信頼あつかった柳沢吉保が、7年かけてつくりあげた庭園。
「六義」というのは中国最古の詩集『詩経』のいう詩の6つの理をいう。つまり、
「風(民の歌)・雅(宮廷の歌)・頌(宗教の歌)・賦(感想をそのままのべたもの)・比(たとえの歌)・興(自然にたくして感想をのべる歌)」
神社・お寺コース/有名人墓まいりコース
C.神社・お寺コース お江戸にゆかりのあの寺、この神社!
15.浅草寺、浅草神社
台東区浅草2-3-1 東武線、地下鉄銀座線、浅草線浅草駅下車
浅草神社は「三社さま」ともいわれる。社殿は慶安2(1649)年、3代将軍家光の手による権現造り。
金竜山浅草寺の総門雷門は正しくは風神雷神門といって、天慶5(942)年につくられた。もっとも、今の門は昭和35(1960)年に再建されたもの。寺への参道、仲見世通りは、そりゃもう楽しいおみせがずらり。
16.湯島天神
文京区湯島3-30 地下鉄千代田線湯島駅下車
受験生のお兄さん、お姉さんがおすがりする学問の神、菅原道真公をまつる。
社の左手前に「奇縁氷人石」がある。江戸時代、ここらへんは盛り場で、迷い子が多かった。石の前に、その子の特ちょうを書いた紙をはって、連絡を待ったとか。
17.亀戸天満宮
 江東区亀戸
江東区亀戸3-6-1
JR亀戸駅下車
ここも
湯島と
同じ、
道真公をまつる。
寛文2(1662)
年、4
代将軍家綱が
九州の
太宰府天満宮をまねてつくった。
湯島天神は
梅で
有名だけど、
亀戸の
方は
藤で
有名。
花のさかりには
池のまわりにおみせはならぶし、
人もどっと
出る。
18.増上寺
港区芝公園4-7-35 JR浜松町駅または地下鉄三田線芝公園駅下車
明徳4(1393)年開山。家康が江戸入りした天正ごろ(1573~1592)からは、将軍家の菩提寺(先祖の位牌をおさめる寺)となる。
東京タワーをバックにここに眠る将軍はこのメンバーだ。
2代 秀忠 6代 家宣 7代 家継
9代 家重 12代 家慶 14代 家茂
19.雑司ヶ谷鬼子母神
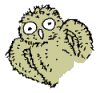 豊島区雑司ヶ谷
豊島区雑司ヶ谷3-15
JR目白駅下車
江戸時代から
子授け、
安産、
子育ての
神として
信仰されてきた。ここには
樹齢400
年以上というケヤキと、
樹齢500
年という
大イチョウがある。
鬼子母神は
自分にも1000
人の
子があるのに
人の
子をさらってはくい
殺していた。お
釈迦様は
鬼子母神の
可愛がっている
末っ
子をかくして、
子を
奪われた
親の
嘆きを
教えた。それからは
鬼子母神は
反省して、いい
神様になったんだって。
江戸のころのここの
名物は、
風車・
麦わら
細工の
獅子・すすきのみみずく・
川口屋の
飴。そのうち、
今も
残るのはすすきのみみずく。
20.柴又帝釈天
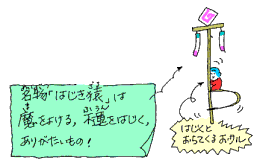 葛飾区柴又
葛飾区柴又7-10-3
京成電鉄柴又駅下車
江戸時代から、
庚申の
縁日には
大にぎわいの
場所だった。
本尊の
帝釈天像が
一時行方不明になったのが
安永8(1779)
年春。
庚申の
日に
見つかってからこの
日が
縁日と
定められたとか。
21.寛永寺
台東区上野桜木1-14 JR鴬谷駅下車
天台宗の関東総本山として寛永2(1625)年に建てられた。京都の比叡山にならって東叡山の山号をつけ。江戸城をしずめ、まもる役目をもたせた。3代将軍家光が上野のお山に桜を植えると、他の大名たちもならったから、たちまち、このあたりは桜の名所となった。
寺の黒門は戊辰戦争で旧幕臣の彰義隊が官軍と激しく戦ったところ。みせしめに隊員200人あまりのなきがらは、しばらく放っておかれたという。悲しい場所でもあるのだ。
ここの寺にも6人の将軍が眠っている。
4代 家綱 5代 綱吉 8代 吉宗
10代 家治 11代 家斉 13代 家定
22.護国寺
文京区大塚5-40 地下鉄有楽町線護国寺駅下車
「生類あわれみの令」を出して、「犬公方」とかげ口をたたかれた5代将軍綱吉の母、お玉の方(桂昌院)の祈願(願いをかける)のために建てられた寺。
- お犬さま、と言えば中野区の桃園。(今の中野駅周辺。)元禄8(1695)年、野犬を保護するための小屋がここに建てられた。16万坪の敷地に保護された犬は4万2,000頭あまり。宝永6(1709)年、「生類あわれみの令」がとりやめになったあとは桃の木が植えられ江戸の人々のいこいの場に。桃園の地名もそこに由来する。今は小学校や、地域センターにその名を残している。
有名人墓まいりコース
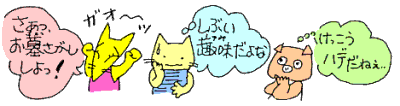
ドラマでおなじみ、あのひと、このひと!
24.ねずみ小僧次郎吉(1795~1832)
場所は両国回向院。
墨田区両国2-8-10 JR両国駅下車。
回向院は正しくは国豊山無縁寺といって人間や動物の無縁仏(とむらう人のいない仏さま)を多く供養してきた寺。
ねずみ小僧は江戸時代末の盗賊。中村次郎吉といって、江戸中村座の木戸番の息子だったとか。素行が悪く、27歳で親から勘当(縁を切られること)されちゃった。そのうち盗賊になってしまって、大名屋敷専門に荒らしまわること120回。天保3(1832)年5月につかまり、8月、品川で処刑された。
25.遠山金四郎景元(?~1855)
 豊島区巣鴨
豊島区巣鴨5-35
本妙寺にあるのが
名町奉行「
遠山の
金さん」こと
遠山金四郎景元の
墓。この
人、
文政12(1829)
年、ひょんなことからあきらめていた
家督をつぐことになって(つまり、あととりになったわけ)、
勘定奉行、
北町奉行、
大目付と
役目について、
弘化2(1845)
年に
南町奉行となる。
この
寺にはほかに
幕末の
剣客、
千葉周作や、
本因坊(
江戸時代からの
囲碁の
家元)
代々の
墓がある。
26.新井白石(1657~1725)
中野区上高田1-2 高徳寺。西武新宿線新井薬師駅下車。
江戸時代中ごろの学者で政治家。浪人の子で、苦しい生活の中で勉強にはげんだ。6代将軍家宣と7代将軍家継の政治を補佐した。
27.服部半蔵(1542~1596)
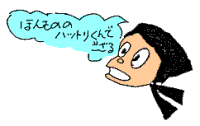 新宿区若葉
新宿区若葉2-9
JR四谷駅下車の
西念寺に
墓がある。
服部石見守半蔵正成は「
鬼半蔵」といわれ、
槍の
達人。
家康に
仕え、
与力30
人、
伊賀同心200
人を
率いて
江戸城の
警備にあたった。
皇居の
半蔵門はむかしここに
半蔵の
屋敷があったから、こういう
名まえがついたんだね。
28.赤穂浪士
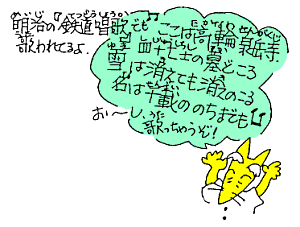 港区高輪
港区高輪2-11-1
地下鉄浅草線泉岳寺駅下車。
泉岳寺は
赤穂浪士の
墓があるので
有名なお
寺なんだよね。
義士館もあって、
彼らゆかりの
品やら
古い
書類なども
展示している。(もともと、
彼らの
藩主浅野氏の
菩提寺だ。)
赤穂浪士のお
話は、
今も12
月になるとよくテレビでやるよね。これ、
本当にあった
事件。
元禄14(1701)
年、
江戸城松の
廊下で
吉良上野介義央に
切りかかった
浅野内匠頭長矩は
切腹。
領地である
赤穂藩はおとりつぶし。
翌年の12
月、もとの
家臣である
赤穂の
浪士たちが
本所の
吉良邸に
打ち
入り、
上野介の
首をとって
主君の
仇を
討った。
浪士たちはその
後、
切腹を
申しつけられた。この
話はのちに「
仮名手本忠臣蔵」という
芝居にもなって、
人びとの
人気をよんだ。ドラマやお
芝居では、たいてい
意地悪なおじいさんに
描かれてしまうけど、
吉良上野介義央、
領地の
吉良(
三河国)では
名君の
評判が
高かったそうだよ。
29.一勇斎国芳(1797~1861)
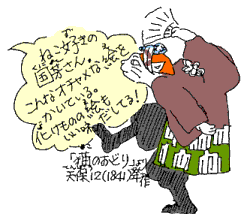 待
待たせてごめんね!
所は
小平市上水南町2-11-20の
大仙寺。もとは
台東区にあった
寺だが
縁あって
小平に
引っ
越して
来た。ここにはお
江戸の
浮世絵師一勇斎国芳が
眠る。
江戸っ
子で、
弱い
者にはやさしくて、
猫が
大好きな
人気者。
風景、
美人画、
役者絵、
狂画と
次々に
作品を
生みだし、お
江戸の
話題をさらったとさ。
絵師と
言えば、
葛飾北斎も
放っておけない。「
北斎漫画」は
有名だ。
嘉永2(1849)
年89
歳で
亡くなった。お
墓は
台東区浅草4-6-9の
誓教寺。
地下鉄銀座線稲荷町駅下車。
江戸をたのしもうマップ
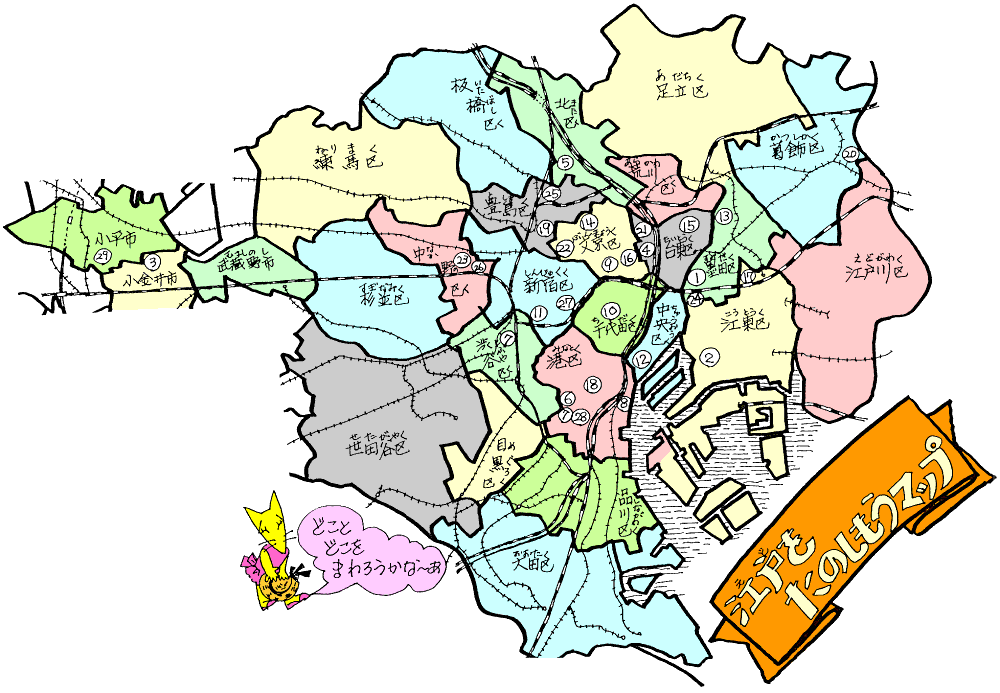
千代田区
10 皇居周辺
文京区
9 小石川後楽園
14 六義園
16 湯島天神
22 護国寺
豊島区
19 雑司ヶ谷鬼子母神
25 遠山の金さんの墓
北区
5 飛鳥山公園
台東区
15 浅草寺、浅草神社
21 寛永寺
墨田区
1 東京江戸博物館
13 向島百花園
24 ねずみ小僧次郎吉の墓
葛飾区
20 柴又帝釈天
江東区
2 深川江戸資料館
中央区
12 浜離宮庭園
港区
6 有栖川宮記念公園
8 芝恩賜公園
18 増上寺
28 四十七士(赤穂浪士)の墓
渋谷区
7 明治神宮御苑
新宿区
4 新宿歴史博物館
11 新宿御苑
27 服部半蔵の墓
中野区
23 新井薬師
26 新井白石の墓
小金井市
3 江戸東京たてもの園
小平市
29 一勇斎国芳の墓
参考にした本
「江戸学事典」(弘文堂)
「東京に活きる江戸」(光村図書出版)
「角川地名大辞典 東京」
「東京人 1993年5月号」(東京都文化振興会)
「歴史細見 東京江戸案内」(八坂書店)
「東京をあるく本」(文潮出版)
「日本歴史大辞典」(河出書房) ほかいろいろ
小平市に関すること
多摩に関すること
江戸・東京に関すること
玉川上水・小金井桜に関すること
その他



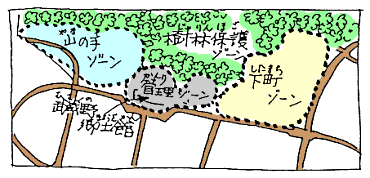
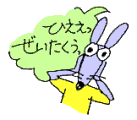
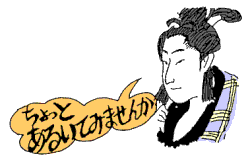 ここは
ここは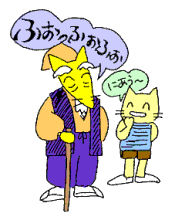

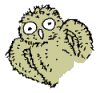
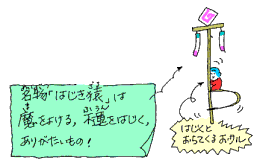
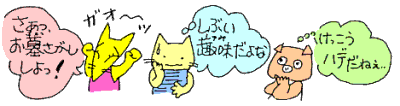 ドラマでおなじみ、あのひと、このひと!
ドラマでおなじみ、あのひと、このひと!