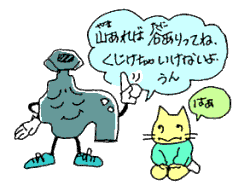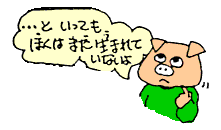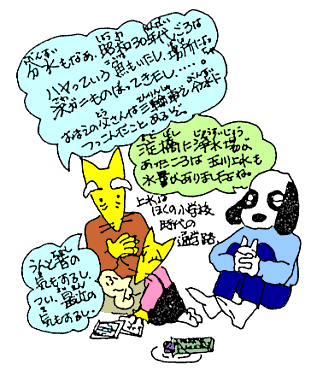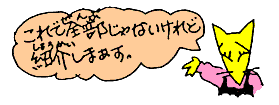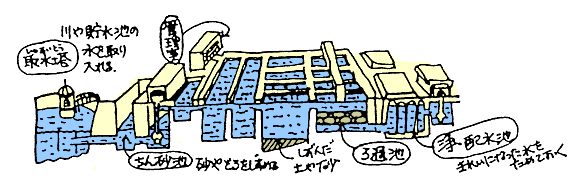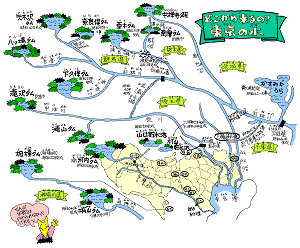東京の水道の歴史
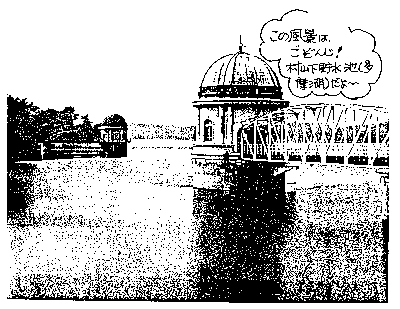
東京の水道の歴史は、天正18(1590)年の徳川家康の江戸入りから始まる。家康は、江戸に城下町をひらくのに先立って、上水の見立てを家臣に命令した。人が生活をしていくのにどうしたって水は欠かせないものね。その調査をもとにできたのが神田上水。それでも、なお江戸の人口は増えつづけ、飲み水は足りなくなる一方。そこで、玉川上水や、青山・亀有・三田・千川の上水が開かれていった。
 どんどんふくらんでゆく都市の飲み水を手に入れるために、東京の水道は誕生の時から、工事、工事の連続だった。そのうえ、幕末になって開国をしたら外国から伝染病がはいって来るようになった。伝染病を防ぐためには清潔な飲み水が必要だ。
どんどんふくらんでゆく都市の飲み水を手に入れるために、東京の水道は誕生の時から、工事、工事の連続だった。そのうえ、幕末になって開国をしたら外国から伝染病がはいって来るようになった。伝染病を防ぐためには清潔な飲み水が必要だ。
明治にはいると、江戸時代からずっと引きつづいてきた木樋(木のとい)の水道を近代的な鉄管にかえるという大事業が待っていた。
この新しい水道(改良水道)は日本人だけの力じゃなく、外国のいろいろな人たちの経験や知識や、技術を借りてできあがった。
その後も、関東大震災はくる、太平洋戦争で空襲を受ける、大型台風に見舞われるなど、さまざまな困難が東京の水道に襲いかかった。
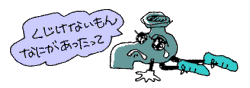 何度もの打撃から、その都度立ち上がり、増えつづける水の需要にこたえるため、新しい水源を探し、施設を建設して、今の東京の水道は出来上がっていったんだよ。大変な道のりだったんだよねえ。
何度もの打撃から、その都度立ち上がり、増えつづける水の需要にこたえるため、新しい水源を探し、施設を建設して、今の東京の水道は出来上がっていったんだよ。大変な道のりだったんだよねえ。
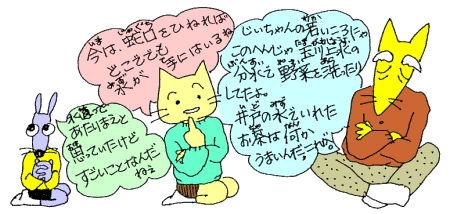
東京の水道今むかし その1
1.江戸時代前
太田道灌が江戸城を築いた1457年頃には、江戸は小さな村がポツンポツンとちらばっているだけ。飲み水には沼地の間を流れる小川や、数少ない堀井が利用されていた。
2.江戸上水のはじまり
天正18(1590)年8月1日、徳川家康は江戸にはいり、町づくりを始めた。
その時、ひと足先に家臣大久保藤五郎に上水の見立てを命じていた。この調査によって、江戸最初の上水、神田上水はできた。神田上水は井の頭池を水源に永福寺池、善福寺川、井草川などの水を加えて、小石川にいたる。
藤五郎はその功によって「主水」の名をもらった。ふつうは「モンド」と読むのだけれど、水に濁りは禁物、と「モント」を澄んで読むよう言いわたされたとか。
3.玉川上水
徳川幕府の体制が整い、江戸が政治の中心になってくると、人口はますます増える。飲み水はますます足りなくなる。承応2(1653)年、4代将軍家綱の時、多摩川の水を飲み水として引く水道工事が始まった。玉川上水だ。
時の関東郡代、伊奈半左衛門の監督のもと、庄右衛門、清右衛門兄弟が工事にあたった。
承応3(1654)年6月には羽村から四谷大木戸まで43キロメートルの上水路を完成。江戸の人びとの飲み水としてばかりでなく、分水によって武蔵野新田の飲み水や、かんがい用水として利用。新田の開発は玉川上水があったからこそできた。
4.江戸の華とは言うけれどやっぱり火事はこまるのだ!
江戸はまた火事の多い都市でもあった。とくに明暦3(1657)年、1月18日の大火は「振袖火事」とよばれ、江戸の3分の2を焼きつくし、死者10万人以上をだした。
この火事からの復興の時、江戸の大規模な防災計画をおこない、そのため市街地も南・西・北の郊外に広がった。
江戸の町が広がれば、飲み水もまた多く必要になる。そこでできたのが、青山・三田・亀有・千川の四上水。亀有以外の三上水は全て玉川上水からの分水だった。
この頃、江戸の人口は100万人をこえていたという。上水道はその人口の60パーセントに普及していたとみられている。
5.どうやってめぐっていたか、江戸の上水
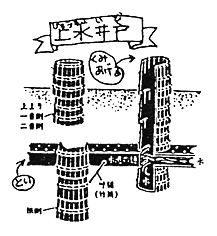 江戸
江戸の
上水は
川や
池の
水を
引いて、そのまま
飲み
水としていた。
江戸市内の
道路の
下には、
給水のための
石樋(
石のとい)や
木樋(
木のとい)が
網の
目のように
走っていた。(つまり
水道管だね。)それであちこちに
溜桝というのを
埋めて、
水をため、つるべなどで
水を
汲み
上げた。これが
上水井戸だ。
木樋は
檜や
松などで
作られた。
上水をきちんとしておくために、
毎年のように
羽村の
取入口の
堰や、
水門や
樋や
桝の
修理をおこなわなければならない。たくさんの
費用と
人手がかかった。
このため、
上水の
使用料として
水銀や
普請金(
工事の
費用)を
集めた。
6.明治維新と上水
慶応4(1868)年7月17日、江戸は東京となり、9月8日に元号も明治に改まる。
明治維新は水道にも大きな影響をおよぼした。維新の混乱で水道を保っていくのに必要な水銀(水道料金)がはいらなくなってしまったのだ。
当面、明治政府が費用を負担したけれど大変な金額だから、いつまでもそうするわけにはいかない。
明治4(1871)年5月、水税規則をつくって料金を集めると知らせたけれど、うまくいかず、再び水道料金を集めるようになったのは明治7(1874)年10月だった。
7.つかのまの玉川上水通船
明治3(1870)年4月から、わずか2年あまり、羽村から四谷大木戸の間を船が通った。江戸時代には、大事な飲み水、玉川上水に船を通すなど考えられないことだった。
けれど、明治新政府の薩摩や長州の役人は、まだ江戸の事情がよくわからない。どさくさにまぎれて地元からの「船を通したい」との願いは許可されてしまったらしい…。
船なら羽村から四谷まで1日足らずで行く。しかもたくさんの品物が運べる。砂利や石灰などをはじめ、多摩からは野菜・炭・薪・たばこ・茶・生糸・木綿など、東京からは塩や魚をのせてきた。人の往き来にも使われた。
しかし、あまりに上水の汚れがひどくなったので、明治5(1872)年5月末限りで通船はとりやめとなった。何度も再開の願いが出されたが、二度と許されることはなかった。
同じく5月には、玉川上水沿いの村々に「上水で洗い物をしたり、ごみなどを捨てたりして水を汚してはならない」と厳しい命令が下った。
8.明治初めのころの東京水事情
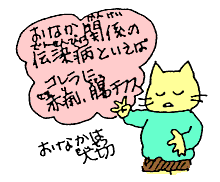 文明開化
文明開化のかけ
声とともに
東京は
急速に
発展した。でも、
町の
環境は
江戸時代のまま。
道路は
狭くまがりくねっている。
木造の
家がつらなって
火事も
多い。
水道も
木樋で
旧式のまま。
古くなって
腐った
上水の
木樋や
下水のどぶなどのため、
伝染病も
防げない。
井戸から
地下水を
汲み
上げて、
飲み
水にしている
人も
多かったけれど、
水の
質も
悪く、
夏場には
水不足になることもしばしばだ。
明治7(1874)
年頃から「
旧式水道を
改良してほしい」という
声が
強くなっていった。
9.改良水道がほしい!
明治5(1872)年5月から、神田・玉川の両上水は東京府が管理するようになった。東京府は明治7(1874)年に玉川上水の、明治8(1875)年と10(1877)年に、神田上水の水質検査をおこなった。この結果、水源の水質は良いけれど、木樋で引いた井戸水は、腐った所から汚れた水がはいったりして、悪くなっている、ということだった。
上水井戸とともに掘井戸(地下水を汲み上げる井戸)の水質検査もおこなって、上水井戸はその半分が、掘井戸は60パーセントが飲み水にむかない、というありさまだった。
水道を改良したいけれど、維新後まもなくで、予算がない。そこでとりあえずは、水の汚れを防ごうと警視庁から、
明治11(1878)年に「神田・玉川両上水取締禁止令」
明治14(1881)年に「千川上水取締禁止令」が出された。
10.ファン・ドールン登場
江戸時代まで、日本には近代的な水道はひとつもなかった。だから、その調査や計画には外国人の専門の技師を招いて教えをこうほかはない。
東京の水道は、内務省のお雇い技師、オランダ人ファン・ドールンが政府の命令で調査にあたった。
ファン・ドールンは明治7(1874)年5月に「東京水道改良意見」を、さらに明治8(1875)年2月には実地調査をまとめて、設計書を提出した。
その内容は、「多摩川を水源とし、玉川上水路を使って水を流し、浄水場を建て、ろ過池でろ過した水を浄水池にためて鉄管で市内に給水する」というもの。これはこれより後の東京の水道設計の基本となった。
明治9(1876)年12月、東京府に水道改正委員が設けられ、調査をおこなった結果を明治10(1877)年9月「府下水道改設の概略」として出版。改良水道の設計を検討した。
日本の近代水道
明治20年 横浜水道 通水開始
22年 函館水道 通水開始
24年 長崎水道 通水開始
28年 大阪水道 通水開始
31年8月 広島水道 通水開始
31年12月 東京水道 通水開始
33年 神田水道 通水開始
38年 岡山水道 通水開始
39年 下関水道 通水開始
11.いよいよ改良水道へ
明治19(1886)年のコレラ大流行は、改良水道を作ろう!という気運をおおいに高めた。
明治21(1888)年8月「東京市区改正条例」公布。
同じ年10月には内務省に東京市区改正委員会ができる。これは、東京市区の衛生・防火や交通などを良くするための設計や事業について話し合う委員会だ。
ここでも、改良水道はまっ先に考えなければならない問題として取り上げられた。
12.外国人技師たちの活やく
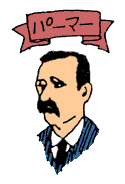 明治
明治20(1887)
年、
渋沢栄一ら9
人の
財界人は「
東京水道会社」の
設立を
計画した。そのための
調査と
設計を、
横浜に
日本最初の
近代水道を完成させたイギリス
人技師パーマーに
頼んだ。
明治21(1888)
年12
月に、
会社設立の
願いを
国に
出したけれど
明治23(1890)
年2
月に
公布された
日本最初の
水道の
法律「
水道条例」のために
不許可となった。「
水道は
市町村が
公営すること」とこの
法律で
決められたからだ。
「
東京水道会社」を
設立しようとしていた
人たちは、
東京の
水道のために
役立ててもらおうと、
自分たちの
設計書や
調査書を
東京市区改正委員会にプレゼントした。
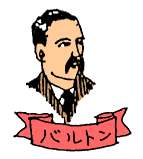 東京市区改正委員会
東京市区改正委員会では
内務省のお
雇い
技師、イギリス
人のバルトンが
中心となって
設計案をまとめた。それとともにパーマーの
案や、ベルリン
水道部長ヘンリー・ギルやベルギー
水道会社技師長クロースの
意見も
参考にした。
明治7(1874)
年のファン・ドールン
以来の
計画を
練りに
練って、
明治23(1890)
年4
月、ついに「
東京市水道改良設計」が
決定。「
玉川上水路を
利用して、
多摩川の
水を
浄水場に
引き、
沈でん、ろ
過できれいにしたのち、ポンプ、あるいは
自然の
流れによって
鉄管で
市内に
給水する」という
内容だ。(
浄水場は
初め、
千駄ケ谷を
予定していたけれど、
明治24(1891)
年12
月、
淀橋町に
変更になった。)
明治24(1891)
年11
月には
水道改良事務所が
開かれ、いよいよ
改良水道の
工事が
始まった。
13.なが~くかかった改良工事
ところが工事は順調には進まなかった。まず、資金となる東京市公債が思うように売れない。
明治24(1891)年10月からよく年にかけて「工事のためにお金の負担がふえるのはいやだ。工事をやめろ」と反対の声もあがった。用地の買収もはかどらない。
そんななかで明治26(1893)年10月22日、淀橋浄水場(今の新宿西口)は起工式(工事を始める式)をおこなった。
次に待っていたのは日清戦争(1894年)だ。このため、材料や人手が不足し、戦後はインフレで物価があがった。
さらに「鉄管不正事件」というのがおこった。
鉄管を売りこんできた「日本鋳鉄会社」が不合格品を合格品として納入したのだ。これは明治28(1895)年10月にばれて政治問題になった。
けれど、不合格の鉄管を外国から買った鉄管に入れ替えることで、明治31(1898)年11月、工事の大部分が終了。12月から通水が始まり、明治32(1899)年11月には給水地域が東京市内全域におよんだ。
この年12月17日、淀橋浄水場で落成式(工事が終ったことを祝う式典)をして、明治44(1911)年3月、東京の改良水道の創設工事は完成した。
この間、明治34(1901)年6月には神田・玉川両上水が、明治40(1907)年6月には千川上水が給水を止めた。
江戸時代からの上水は近代水道と選手交替したのだ。
14.それでも足りない東京の飲み水 -第1次水道拡張事業-
改良水道はおどろくほど衛生的で、便利で防火にも威力があった。「昔ながらの井戸の方がいい」と思っていた人や、「工事費や使用料を負担するのがいやだ」と思っていた人も、新しい水道を認めるようになり、給水の申し込みは日に日に増えていった。
都市の発展も予想以上で、明治42(1909)年ころには「東京市区改正委員会」ではやくも水道を拡張する計画が練られるようになった。新しい水源を求めて、大正5(1916)年には村山貯水池の工事が始まり、つづいて境浄水場などの施設の建設もすすめられた。
東京の水道今むかし その2
15.大東京の水道をひとつに
関東大震災(1923)以後、東京はものすごい勢いで復興。郊外電車やバスなどの交通の発達に伴って、まわりの町や村もめざましく発展した。
けれど、東京市の水道の給水区域は昭和の初めまで旧15区に限られていた。まわりの豊多摩、北豊島、南足立、南葛飾などの郡部の水道は、町や町村組合や株式会社が運営していた。郡部からはずいぶん前から市内と水道を一本にしてほしいという希望がでていた。
昭和7(1932)年10月、これら5郡(荏原・豊多摩・北豊島・南足立・南葛飾郡)82か町村が東京市に合併し、15区は一挙に35区となった。人口も497万人。当時世界第2位の大都市となる。
このことをきっかけに、町営や町村組合の10水道も東京市とひとつになった。残る3社の民営水道も、昭和20(1945)年までにじょじょに買収されていった。
旧郡部の給水サービスは大いに改善。水道料金も30パーセントも安くなった。
これだけあった郡部の水道
別々に運営されていて、何のれんらくも統一もなくバラバラだった…。
郡部の水道
| 運営 |
開始日 |
| 玉川水道株式会社(会社経営) |
大正7年11月開始 |
| 渋谷町水道(町営) |
大正12年5月開始 |
| 目黒町水道(町営) |
大正15年4月開始 |
| 江戸川上水町村組合(組合) |
大正15年8月開始 |
| 淀橋町水道(町営) |
昭和2年5月開始 |
| 千駄ケ谷町水道(町営) |
昭和3年5月開始 |
| 荒玉水道町村組合(組合) |
昭和3年10月開始 |
| 大久保町水道(町営) |
昭和4年3月開始 |
| 矢口水道株式会社(会社経営) |
昭和5年11月開始 |
| 戸塚町水道(町営) |
昭和5年12月開始 |
| 代々幡水道(町営) |
昭和6年10月開始 |
| 井荻町水道(町営) |
昭和7年3月開始 |
| 日本水道株式会社(会社経営) |
昭和7年10月開始 |
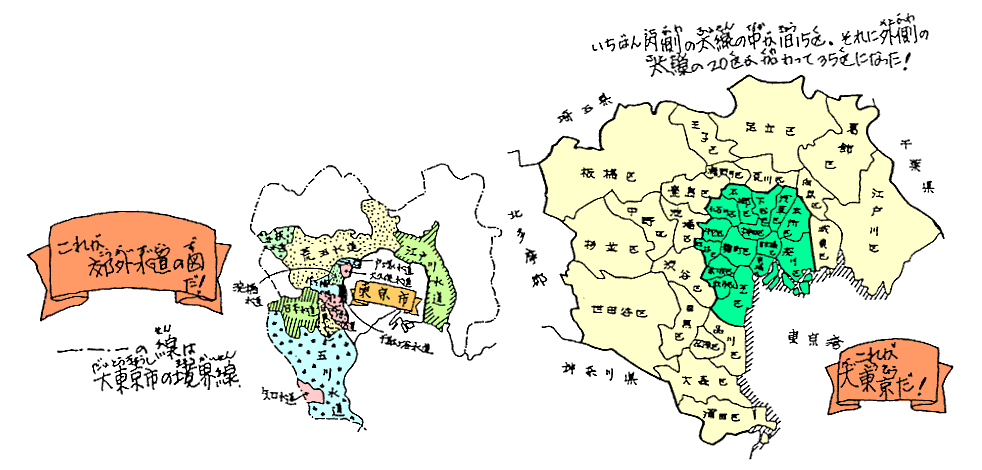
16.十万栓普及大宣伝
旧郡部の水道料金が安くなった分、東京市の水道の財政は苦しくなった。「収入を増やさなければ!」ということで昭和7(1932)年10月から昭和8年度の末までに水道栓を10万栓増やす計画がたてられ、はなばなしく給水普及の宣伝がおこなわれた。
15区から35区に広がった「大東京」出現の記念事業だったんだ。
これが給水宣伝歌謡曲だ!(当時さかんに歌われたらしい)
「水の東京」
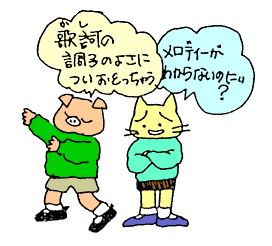
1
花の
東京で ソリャ
見せたいものは
ながす
産湯と コリャサ
珠の
肌
ソレ、
音はサンサンサラリトナ
サラリ サラサラ
多摩の
水
2
水の
山口 ソリャ
村山かけて
春は
桜の コリャ
水かがみ
ソレ、
音はサンサンサラリトナ
サラリ サラサラ
多摩の
水
(
以下5
番までつづく)
「多摩の流れ」
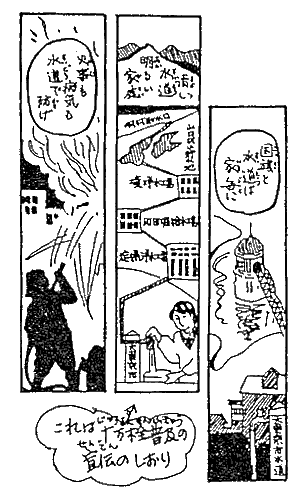
1
萌える
若草、
野はみどり
花を
浮かせて
水の
旅
今は
影なき
武蔵野の
狭山にうれし
茶摘唄
2
深山の
奥の
花の
露
月に
汲みとる
岩清水
同じ
思いを
一筋に
何時か
都の
露となる
3
今宵はここに わかれても
いつか
逢瀬の ぼたん
雪
溶けて
流がれて ゆくすえは
やがて
春待つ
多摩の水
17.太平洋戦争の中の小河内貯水池計画 -第2次水道拡張事業-
水の
需要は
増すばかり。
大正15(1926)
年頃には
東京市会で「
将来のため
水道百年計画をたてよう」と
決議された。
多摩川だけでなく、
新しい
水源を
手に
入れようとしたけれど、
利根川、
相模川などよその
県の
川は
権利の
問題もあってうまくゆかない。
 結局
結局、
多摩川にたよるしかなく、そこで
出されたのが
小河内貯水池計画だった。
昭和6(1931)
年、
計画が
発表されたが、これまた、
下流域の
用水組合から
抗議があがったり、
買収に
手間どったりして、ようやく
工事が
始まったのは
昭和13(1938)
年。ところが
今度は
戦争がおきて、
材料が
手にはいらない。
人も
集まらない。
昭和18(1943)
年10
月、
工事は
中止になってしまった。
戦後の
昭和23(1948)
年9
月、ようやく
工事が
再開して、
完成は
計画発表より26
年後の
昭和32(1957)
年6
月のことだった。
18.戦後の水道拡張事業 -増えつづける東京の人口-
昭和22(1947)年、水道局は将来どれだけの量の水が必要になるか、区部の人口の予想をたてた。
戦前686万人だった区部の人口は終戦の時270万人に減っていた。水道局はそれが昭和30(1955)年には540万人になると考え、それをもとに昭和23(1948)年1月、「東京都復興にともなう上水道計画-拡張事業を中心として-」を発表。
ところが、よく24年にもう一度検討してみたら、昭和30年の区部人口は626万人とでた。
この人数から必要となる水の量を計算して、昭和30年を目標に戦争で中止していた水道拡張事業を再開した。けれど人口の増加はさらにはげしく、昭和34(1959)年5月、区部の人口は予想をはるかに上まわり、770万人をこえた。昭和35年には、昭和50(1975)年を目標に区部人口、888万人とみたてた新しい拡張計画をつくった。
19.多摩川から利根川へ
東京の水道は、その誕生以来ずっと多摩川をたのみにしていた。でも、もう多摩川だけではまかないきれない。相模川・江戸川が加わりさらに利根川系まで水源をひろげ、給水の増加が計画された。
昭和40(1965)年3月1日、武蔵水路がひらかれ、待ちに待った利根川の水が東京にやってきた。貯水池、浄水場もつぎつぎ建てられ、利根川系はやがて、東京の水源の中心となるのだった。
20.淀橋浄水場のひっこし
昭和35(1960)年に決った「副都心計画」は、新宿・渋谷・池袋などの地域を整備して、都心の働きを分散させよう、というものだ。
この計画によって、新宿の淀橋浄水場34万平方メートル(約10万3,000坪)は東村山浄水場にひっこすことになり、跡地には役所や会社のビルが建った。
昭和40(1965)年3月31日、東京の改良水道の誕生の地、淀橋浄水場は67年間の歴史に幕を閉じた。それとともに、砂川から東村山浄水場に新しい導水路を引いたので、玉川上水も、そこから下流は飲み水を運ぶ役目をおえたのだった。
21.多摩の水道もひとつに!
戦後になって多摩は急に都市化していった。市町村の水道もそれにつれて発展した。
戦前、公営水道があったのは青梅市(昭和3年~)と八王子市(昭和4年~)の2市だけ。そのほかの多摩地区の水道は戦後に誕生したものだ。
立川市が昭和27(1952)年に給水を始めてからつぎつぎと水道事業がおこって、昭和30年代にはほとんどができあがり、昭和46(1961)年に日の出町の水道ができて多摩の全市町村に水道事業がととのった。
けれども、多摩川水系の川を利用しているのは一部きりで他の大部分は地下水にたよるものだった。
多摩は区部のベッドタウンとして異常に人口が増加していった。はじめのうちはどこでも井戸を掘って地下水を汲み上げていたけれど、そのうち水が出なくなった。地下水だけではもう無理だった。
新しい水源を見つけなければならないけれど、これは各市町村でバラバラにするよりも、東京都としてまとまってする方がいい、という要望がつぎつぎと都に出された。
そこで、東京都と多摩の市や町とで「多摩地区給水対策連絡協議会」がひらかれた。そして、料金などが市町村ごとにバラバラな多摩の水道もここで東京都の水道局とひとつになるべきだ、という考えが生まれてきた。
昭和45(1960)年7月、東京都の水道をひとつにするため、水道局に「多摩水道本部」がつくられる。
昭和46(1961)年12月、「多摩地区水道事業の都営一元化計画」とその実施計画をまとめて発表。
昭和48(1963)年11月1日より、東京都と多摩の水道の統合が始まる。
そして、今…
平成20年度(2008)の「東京都統計年鑑」では、
水道の普及率 は、 区部 :100パーセント
市部 :100パーセント
郡部町村 99.6パーセント
区部880万人、市部400万人、郡部6万人、合 わせておよそ1,300 万人もの人々に水道の水はとどけられているんだよ。
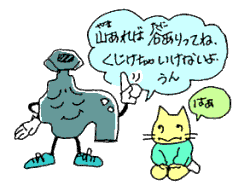
水道をおそった災害・戦争・大渇水
その1 関東大震災
大正12(1923)年9月1日正午に、関東をおそったこの大地震のため、水道施設は広範囲にわたって大損害をうけた。
なにしろ、東京市だけで、こわれたり焼けたりした家およそ30万戸、死者7万人がでた。
大急ぎで復旧工事をおこなったおかげで、この年12月には、ほぼ平常にもどった。
その2 大渇水(水がかれること)
昭和14(1939)年9月、多摩川の水源地に降った雨はいつもの年の半分だった。川の水量はだんだん減り、山口・村山貯水池は水がかれ、東京は水ききんとなった。
昭和15(1940)年6月まで、雨は少ないままで、東京に水道ができて以来の水不足におちいった。6月7日から、朝夕2時間ずつしか給水されず、地域によっては1時間しか水がでないこともあった。
6月8日には警視庁が「水の通牒(お知らせ)」を出す。庭のうち水、道路への水まきは禁止。風呂の水も2~3回使うこと。一度使った水もそのまま捨てず、便所などに利用するように。雨水も利用しよう。でも、衛生には気をつけること。…という内容だった。給水制限や節水のよびかけで、なんとか危機はのりこえて、この年8月15日には平常にもどった。
これ以後も、昭和22、23、32、33、36~38、39年と水不足の年が続いた。特に昭和39(1964)年、オリンピックの年の大渇水は昭和15年以来といわれ、新聞やテレビでは「東京砂漠」などとさわいだ。この時も給水制限がおこなわれたけれど8月20日から降ってくれた豪雨のおかげで助かったんだ。よかったね。
その3 太平洋戦争
太平洋戦争が始まったのは昭和16(1941)年8月。この頃から水道施設への爆撃や細菌弾、毒物の投下を予想して防衛対策を考えていた。
貯水池や浄水場がねらわれないように水面にイカダを組んだり、よしず(葦で編んだすだれ)を張ったりしてそれとわからないようにした。またポンプ室や、滅菌室、配水の本管があつまっている大事な場所は、防護壁などで補強した。
中でも村山下貯水池と山口貯水池は大規模に防護工事がおこなわれた。おかげで大もとの施設は被害が少なくてすんだけれど、末端の給水栓の被害は大きかった。焼夷弾攻撃による大火災で、当時94万栓あった給水栓の70パーセントが使えなくなった。浄水場から水を送っても途中で漏れてしまったからだ。
昭和20(1945)年8月15日、終戦。焼けたり、こわれたりした家77万戸、被害にあった人は300万人。復旧工事が急がれ、水道局も全力をあげて水漏れを防いでまわった。
小平の水道史
むかし
承応3(1654)
年6
月20日 玉川上水完成。
承応4(1955)
年3
月 野火止用水完成。
明暦2(1656)
年 この
年 小川九郎兵衛、
小川村の
開発を
願い
出る。
享保7(1722)
年7
月26
日 幕府、
新田開発をすすめるお
知らせを
出す。
これより
享保年間に、
小平の
新田、ぞくぞく
開発される。

飲み水として井戸も利用されていたけれど、新田をひらき、小平に住みついた人たちの生活を支えたのは玉川上水からの分水だ。中でも明暦2年に引かれた小川分水は小平の生命線で、ここからあちこちの新田に水が配られた。
上水の水はどこかで多くとれば、ほかの場所ですぐ影響がでる。分水の取り扱いは、大切なものだけに難しく、争いもおこりやすかった。明治になると玉川上水を利用する水路の北側の村々は「玉川上水北側新井筋」と名がつき、お互いに分水を使う時の約束事を明治8年9月につくった。明治11年には「組合」として、きまりを作り、代表の人が用水を管理した。
ちょっとむかし
明治19(1886)年、夏~秋 コレラ大流行
明治30(1897)年、この年 三多摩に赤痢大流行
明治になって、たびたび伝染病が流行すると、分水の水はしだいに飲み水として使われなくなっていった。
昭和の初めにはもっぱら洗たくや野菜洗いに利用されていた。
さて、井戸の方はあまり数はなかったらしい。このあたりは、水脈が深くて、掘るのが大変だったんだ。なわの両はしにおけを下げたつるべ井戸で、個人で持つより、共同のものが多かった。
各新田の井戸事情
小川村
明治40年頃の赤痢流行後、個人の井戸が数軒あらわれだした。けれど大半は、組にひとつ。共同井戸を作って、みんなで飲み水にしていた。
鈴木新田
ここには井戸が3つあった。ひでりで水が切れた時のためにと予備の水ためも3つ作られていた。
大沼田新田
1741(元文6)年に、川崎平右衛門が掘った井戸が2つあった。
野中新田
分水を飲み水にしなくなったのは昭和にはいってから。昭和15年頃、共同井戸が組ごとに作られて、野中には4か所井戸ができた。
回田新田
大正8年、小学校の井戸ができるまで、井戸はほとんどなかった。個人の井戸がふえてきたのは、戦後になってからだ。
小川新田
昭和2年頃から、個人の井戸がぼつぼつあらわれだした。
わりと最近の話
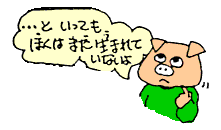 太平洋戦争
太平洋戦争がおわり、
東京の
復興が
始まった。
小平でも、
昭和22(1947)
年、
小川中宿に248
戸の
住宅が
新しく
建った。その
時32の
井戸を
掘ったけれど、
地下水が
深くて、ほとんど
使いものにならなかった。
住宅の
人たちは
仕方なく、
隣りの
厚生省職業補導所(
今の
東京都身体障がい者職業訓練校・
小川西町)の
井戸から
水を
汲み、
運んだ。
その
後、この
施設から、
中宿の
住宅のまん
中まで
給水管がのばされ、
共同の
水栓が
設けられたが、
人口はますます
増えて、これだけでは
足りなくなった。
昭和24(1949)
年8
月には、
旧陸軍兵器補給廠(
小川東町)の
給水施設を
使ってもいい、と
国から
許しが
出た。
中宿をはじめ、まわりの
地域の
人たちは、
給水の
事業計画をたて、
組合をつくろう、と
努力した。
昭和29(1954)
年1
月には「
小川水利協会」として
運営されることになった。
昭和33(1958)
年、
町営で
水道事業をおこなってほしい、という
願いが「
小川水利協会」から
出された。
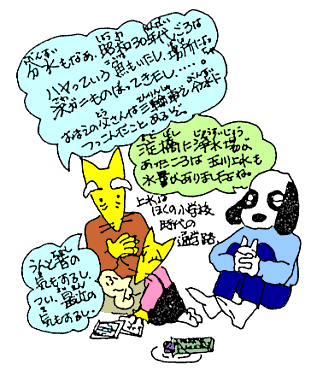 昭和
昭和34(1959)
年4
月1日 小平町営水道が
給水開始。
昭和35(1960)
年12
月18
日 小平町営浄水場(
小川東町)
完成。
けれど
昭和30
年代後半はさらに
宅地化はすすみ、
国分寺線小川駅を
中心とした
市営(
昭和37
年小平は
町から
市になった)
水道と、
学園地区の
民営の
簡易水道だけでは
追いつかなくなった。そこで、
昭和38(1963)
年4
月1日 第1
次水道拡張事業、
始まる。
昭和42(1967)
年4
月1日 第2
次水道拡張事業、
始まる。
その
間、
昭和39(1934)
年9
月には
小平市営水道第2
浄水場が
小川町1
丁目に
完成。
昭和46(1971)
年3
月25
日 小川東町の
第1
浄水場は
廃止となる。この
月市内の
水道普及率は87.9パーセント。
昭和48(1973)
年11
月1日 小平市、
東京都の
水道事業に
統合される。
そして今、18万人を越える小平の人々に、水道は100パーセント普及しているのだ!
東京都の水道施設
水源施設
関東周辺には東京に水を送ってくれる貯水池がいくつもある。でも、貯水池をつくるためには、もともとそこにすんでいる人たちが先祖代々からの土地を手離して退かなければならない。
たとえば村山貯水池は160戸、山口貯水池は345戸、小河内貯水池は945戸の家々が湖の底に沈んでいるんだ。
多摩川系
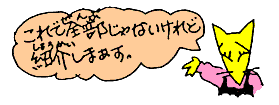
-
小河内貯水池 «奥多摩湖»
- 西多摩郡奥多摩町。戦前から戦後にかけて20年以上の年月と、その当時で136億円というばく大な費用をかけて完成した。
昭和13年11月 工事開始。
昭和32年11月 完成。
-
村山上貯水池
- 大正6年10月 工事開始。
大正13年3月 完成。
東大和市多摩湖
-
村山下貯水池 «多摩湖»
- 大正5年5月 工事開始。
昭和2年3月 完成。
-
山口貯水池 «狭山湖»
- 所沢市勝楽寺。
昭和2年11月 工事開始。
昭和9年3月 完成。
利根川水系
-
矢木沢ダム
- 群馬県水上町。利根川上流。
昭和34年4月 工事開始。
昭和42年8月 完成。
-
草木ダム
- 群馬県東村。利根川支流の渡良瀬川上流。
昭和51年11月 完成。
-
下久保ダム
- 利根川支流の神流川上流。埼玉県と群馬県にまたがる。
昭和43年11月 完成。
水源林
水源林は雨水がいっぺんに流されてしまったり、貯水池に土砂が流れこんだりするのを防いでいる。明治43(1910)年、青梅市に水源林事務所がひらかれ、東京都と山梨県にまたがる多摩川上流域には20,000ヘクタールもの広い広い水源林がある。
浄水場
浄水場のしくみ
浄水場とは川や貯水池から取り入れた水を飲み水になるようきれいにするところなんだよ。
ふつう「沈でん」「ろ過」「消毒」という3段階の処理をおこなう。
沈でん 川や貯水池から来た水の中にはいろいろな物が混じっている。そこで水をゆるやかに流したり、薬を使ったりして、水の中の細かいゴミやうかんでいるものなどをとりのぞく。
ろ過 沈でんではとりのぞけなかったこまかいものなどをとりのぞくため、さらに砂利や砂がしきつめてある層の中に水を通す。
消毒 水の中に残っている細菌類を殺菌するため消毒剤(塩素)で消毒する。
送水・配水 できあがった水道の水は浄・配水池にいったんためられ、ポンプで給水所あるいは直接家庭に送り出される。給水所では浄水場から送られてきた水をためておき、使われる水の量にあわせて給水する。
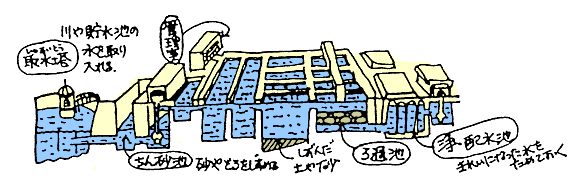
みんな、知ってる?
 昭和
昭和52
年度から8
月1日は「
水の
日」、8
月1日から
7日までは「
水の
週間」と
決められたんだよ。みんなが
水の
大切さを
知る
期間なんだ。
東京水道史年表
東京水道史年表
| 年 |
できごと |
| 1590(天正18) |
7月12日 徳川家康、江戸の飲み水のため、大久保藤五郎に上水の見立てを命じる。この調査をもとに神田上水ができた。 |
| 1654(承応3) |
6月20日 玉川上水できる。 |
| 1660(万治3) |
青山上水できる。数年後亀有上水もできる。 |
| 1664(寛文4) |
三田上水できる。 |
| 1666(寛文6) |
上水奉行を設け、上水の管理にあたらせる。
それより前は上水を開いた人や、その子孫が上水を運営していた。 |
| 1670(寛文10) |
玉川上水の巾を広げる。 |
| 1696(元禄9) |
千川上水できる。これで江戸は六上水となる。 |
| 1722(享保7) |
10月 青山・三田・亀有・千川の四上水廃止になる。 |
| 1779(安永8) |
11月28日 住民の願いにより、千川上水再び開通。 |
| 1786(天明6) |
千川上水、再び廃止。 |
| 1868(明治1) |
8月17日 東京府がひらかれる。 |
| 1870(明治3) |
4月15日 羽村~四谷大木戸まで玉川上水に船を通すことを許される。 |
| 1872(明治5) |
4月 上水が汚れるため、5月末以降、船を通すことを禁止する。
5月 玉川上水沿いの村々に上水を汚さぬようきびしく命令をだす。
8月 神奈川県に属していた多摩郡中野村ほか31か村(東多摩)の玉川上水沿いの村々を東京府に移す。 |
| 1875(明治8) |
2月 オランダ人技師ファン・ドールン、東京の改良水道設計書を提出する。 |
| 1876(明治9) |
12月 東京府に水道改良委員を置く。 |
| 1880(明治13) |
4月 水道改良委員、水道改良設計書をおこす。 |
| 1888(明治21) |
10月5日 内務省に東京市区改正委員会開設。話し合いで、水道を改良することは急がねばならないと決められる。
12月 東京水道会社設立の願い、渋沢栄一らから出る。設計者はイギリス人技師パーマー。 |
| 1889(明治22) |
5月 東京府に市制がひかれ、水道事業も東京市に引きつがれる。 |
| 1890(明治23) |
2月 水道条例公布
この法律により、東京水道会社の設立は不許可となる。
4月19日 東京市区改正委員会、改良水道案を内務大臣に提出。7月5日、認められる。 |
| 1891(明治24) |
11月1日 東京市改良水道事務所ひらかれる。 |
| 1893(明治26) |
10月22日 淀橋浄水場で水道工事起工式(工事をはじめる式)を行う。 |
| 1898(明治31) |
改良水道事務所、水道部と名を改める。 |
| 1899(明治32) |
12月17日 淀橋浄水場で落成式(完成を祝う式)を行う。 |
| 1901(明治34) |
6月 神田・玉川上水、東京市内への給水をとりやめる。 |
| 1907(明治40) |
4月1日 東京市水道使用条例、実施。 |
| 1923(大正12) |
9月1日 関東大震災。水道施設も大被害。 |
| 1924(大正13) |
3月 東京市水道部→水道局となる。
3月 村山上貯水池、完成。
この年4月から1929(昭和4)年3月までの5年間、関東大震災による破損の水道修復工事おこなわれる。 |
| 1927(昭和2) |
3月 村山下貯水池、完成。 |
| 1932(昭和7) |
10月 東京市35区となり、となりあう郊外の10公営水道を合併する。
水道普及10万栓計画、たてられる。 |
| 1935(昭和10) |
4月 給水普及の宣伝の歌謡曲、「水の東京」「多摩の流れ」を作る。このころさかんに歌われた。 |
| 1940(昭和15) |
6月 多摩川系の水がかれて、水不足となる。 |
| 1941(昭和16) |
12月8日 太平洋戦争始まる。 |
| 1943(昭和18) |
10月1日 都政施行。水道も都営となる。 |
| 1945(昭和20) |
8月15日 終戦。 |
| 1952(昭和27) |
10月1日 地方公営企業法により、水道事業は地方公営企業となる。 |
| 1957(昭和32) |
6月 小河内ダム完成。 |
| 1960(昭和35) |
8月 東村山浄水場、通水始まる。 |
| 1964(昭和39) |
8月 多摩川系、ものすごい水不足となる。自衛隊、警視庁、アメリカ軍が給水に出動した。 |
| 1965(昭和40) |
3月 武蔵水路の通水始まる。念願の利根川の水がこれによって東京にやって来た。
3月31日 淀橋浄水場、廃止。 |
| 1966(昭和41) |
10月 朝霞浄水場、通水始まる。 |
| 1967(昭和42) |
8月 矢木沢ダム、完成。 |
| 1968(昭和43) |
11月 下久保ダム、完成。 |
| 1970(昭和45) |
6月 小作浄水場、通水始まる。 |
| 1971(昭和46) |
4月 利根川河口堰、完成。 |
| 1973(昭和48) |
11月より、多摩地区の市や町の水道事業と東京都との統合始まる。 |
| 1975(昭和50) |
三園浄水場、通水始まる。 |
| 1976(昭和51) |
11月 草木ダム、完成。 |
| 1975(昭和60) |
三郷浄水場、通水始まる。 |
| 1990(平成2) |
この年、江戸上水の誕生から、400周年! |

どこから来るの?東京の水
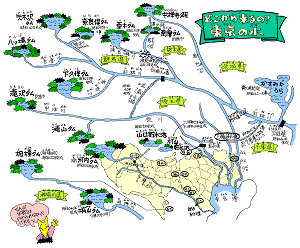
東京都の浄水場
上の絵図 の丸でかこんであるところが 浄水場だよ。
小作浄水場
羽村市羽。昭和45年通水開始。
東村山浄水場
東村山市美住町。昭和35年通水開始。
境浄水場
武蔵野市関前。大正13年通水開始。
杉並浄水場
杉並区。昭和8年完成。
井萩水道より東京市に買収。
砧上浄水場
世田谷区喜多見。昭和6年通水開始。
荒玉水道町村組合より東京市に買収。
砧下浄水場
世田谷区鎌田。昭和13年通水開始。
渋谷町水道より、東京市に買収。
玉川浄水場
世田谷区玉川田園調布。昭和7年通水開始。
昭和10年、玉川水道株式会社より東京市に買収される。(ただし昭和45年9月より休止中)
三園浄水場
板橋区三園。昭和50年通水開始。
金町浄水場
葛飾区金町浄水場。大正15年通水開始。
昭和7年江戸川上水道町村組合より東京市に買収される。
朝霞浄水場
埼玉県朝霞市。昭和41年通水開始。
三郷浄水場
埼玉県三郷市。昭和60年通水開始。
長沢浄水場
神奈川県川崎市。昭和34年通水開始。
「狛江浄水場」というのもあったけれど昭和44年廃止になった。
参考にした本
「東京都水道史」
「東京百年史」
「水道400年のあゆみ」
「水道の文化史」
「水道局報 近代水道通水80周年記念特集号」
「淀橋浄水場史」
「東京都の水道」
「都史紀要31 東京の水売り」
「東京の中の江戸名所図会」
「小平町誌」
「水道事業概要(小平市)」
「平凡社大百科事典」ほかいろいろ
小平市に関すること
多摩に関すること
江戸・東京に関すること
玉川上水・小金井桜に関すること
その他
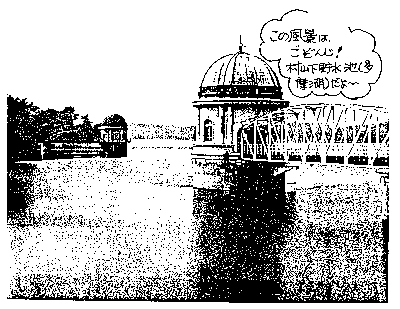
 どんどんふくらんでゆく
どんどんふくらんでゆく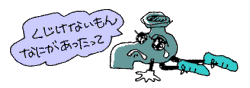
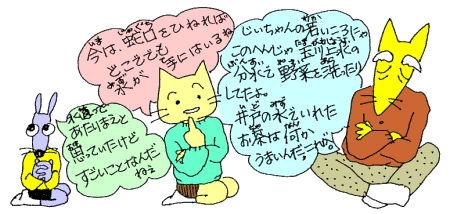
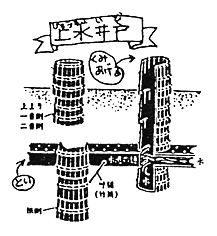
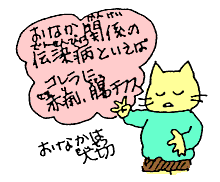
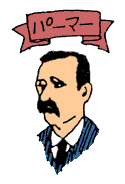
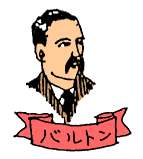
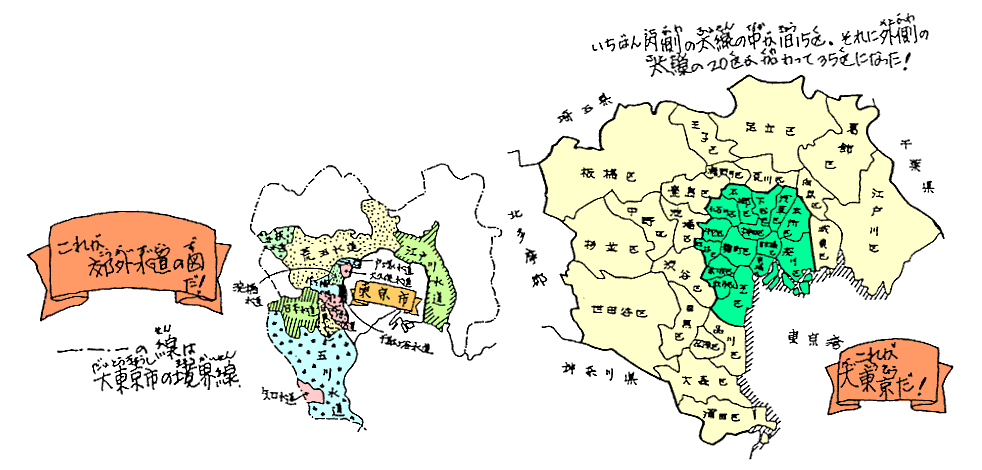
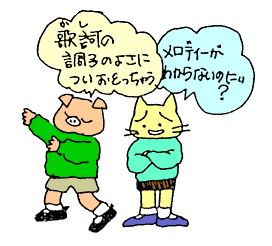 1 花の東京で ソリャ 見せたいものは
1 花の東京で ソリャ 見せたいものは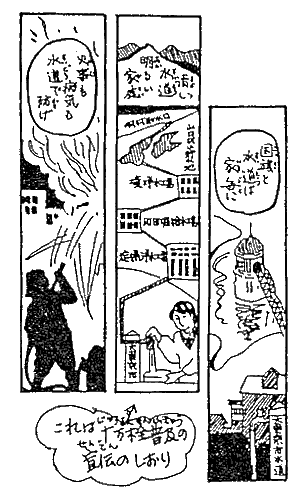 1 萌える若草、野はみどり
1 萌える若草、野はみどり