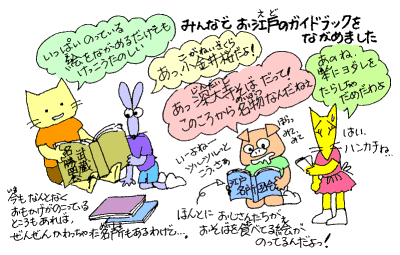江戸時代の三多摩
享保の改革で、1724年ころから1736年ころまでに新田開発がすすんだ(つまり武蔵野新田ね)三多摩には、文化文政のころ(1804~1830)になると古いの、新しいのとりまぜて、およそ390の村があったんだ。
そのころ書かれた地誌(その土地の文化や歴史や風土を説明したもの)である『新編武蔵風土記稿』(1822年多摩郡の部、完成)とか、『武蔵名勝図会』(1823年完成)とか、『江戸名所図会』(1834~1836年完成)とか、を見てみると、三多摩の村々の様子がくわしく紹介されている。
なにしろ、いずれも自分たちの足で歩きまわり、自分の目で見て、調べ、書いたものだから、時間もかけてるけど、内容もすごい。
この村にはこういう名産がある、とか、こんなふうに景色がいい、とか村のお寺や神社にはこんな宝物がある、とか、地名のいわれはこうだとか、こんな伝説があるぞ(けっこうおもしろい)とか…。
江戸時代もおわりに近い、当時の三多摩の村々をちょっとのぞいてみようよ。
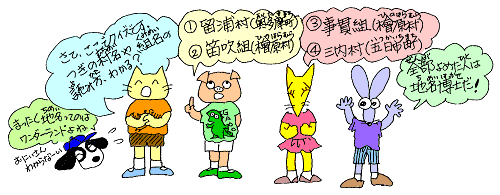
クイズのこたえはいちばんさいごにあります
江戸時代のあの村、この村その1
『新編武蔵風土記稿』のころの三多摩
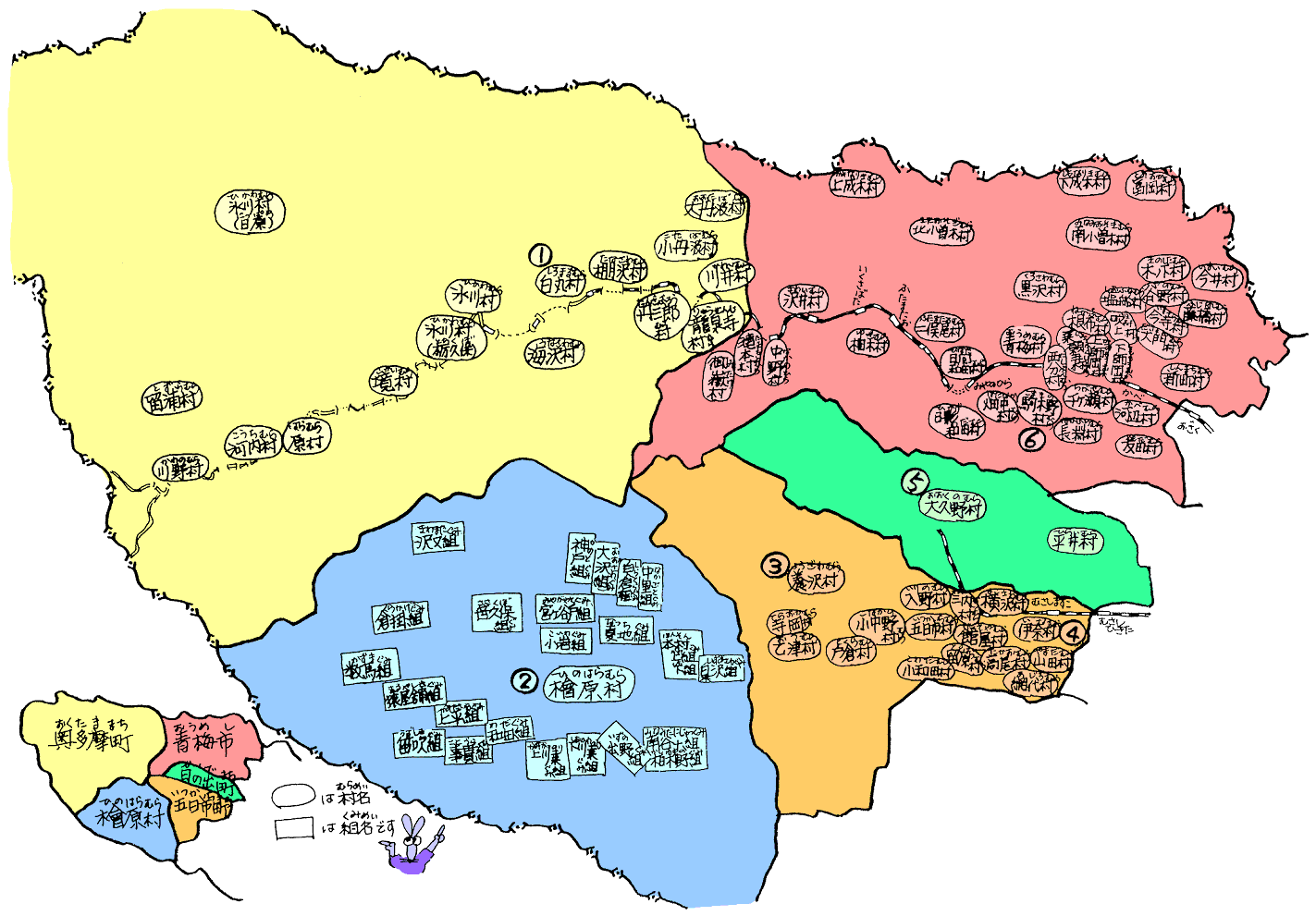
1.白丸(奥多摩町)
もとは「城丸」で、「じやう山(城山)」という砦があったことによる地名。
2.檜原(檜原村)
戦国時代には檜原城があって、八王子城主、北条氏照の配下の平山氏重が甲斐武田氏に対する守りをかためていた軍事基地だった。
甲州へむかう街道が通っていたけれど、江戸時代に五街道が整備されて甲州街道の道筋がかわったので、こちらは「古甲州街道」と呼ばれるようになった。
3.養沢(五日市町)
むかし、東国征伐にやって来た日本武尊の配下の人々が、ここの川でかわいたノドをうるおし、疲れをいやし、生気を養ったという。そこから「養沢」の名がおこった。
4.伊奈(五日市町)
むかし、信濃国(今の長野県)伊奈郡からたくさんの石工が移り住んだので、この名がついた。天正18年(1590)、家康入国の後は、江戸城の石垣づくりなどの御用をつとめたという。
別の説では、「谷間の村」という意味だともいう。
5.大久野(日の出町)
むかし、ここに
大久野という
山伏(
修験者。
野山をめぐり
歩いて
修行する
人)が
住んでいた。そこからついた
地名だという
言い
伝えがある。
林業が
中心で、
元禄以来(1688~)、モミの
木の
卒塔婆を
特産にしていた。
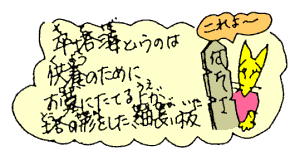
6.駒木野(青梅市)
むかし、
村人が
絹でおおってつかまえた
馬を
鎌倉幕府の
将軍に
献上したところ、それがすぐれて
良い
馬だった。そこで「
駒絹」という
地名がついたらしい。それがもとなんだね。
 畑
畑が
多く、
野菜や
穀物のほか、
綿や
煙草を
作っていて、
田んぼの
間には、
栗や
柿、
梨を
植えていた。また
多摩川の
鮎もとっていた。
江戸時代のあの村、この村その2
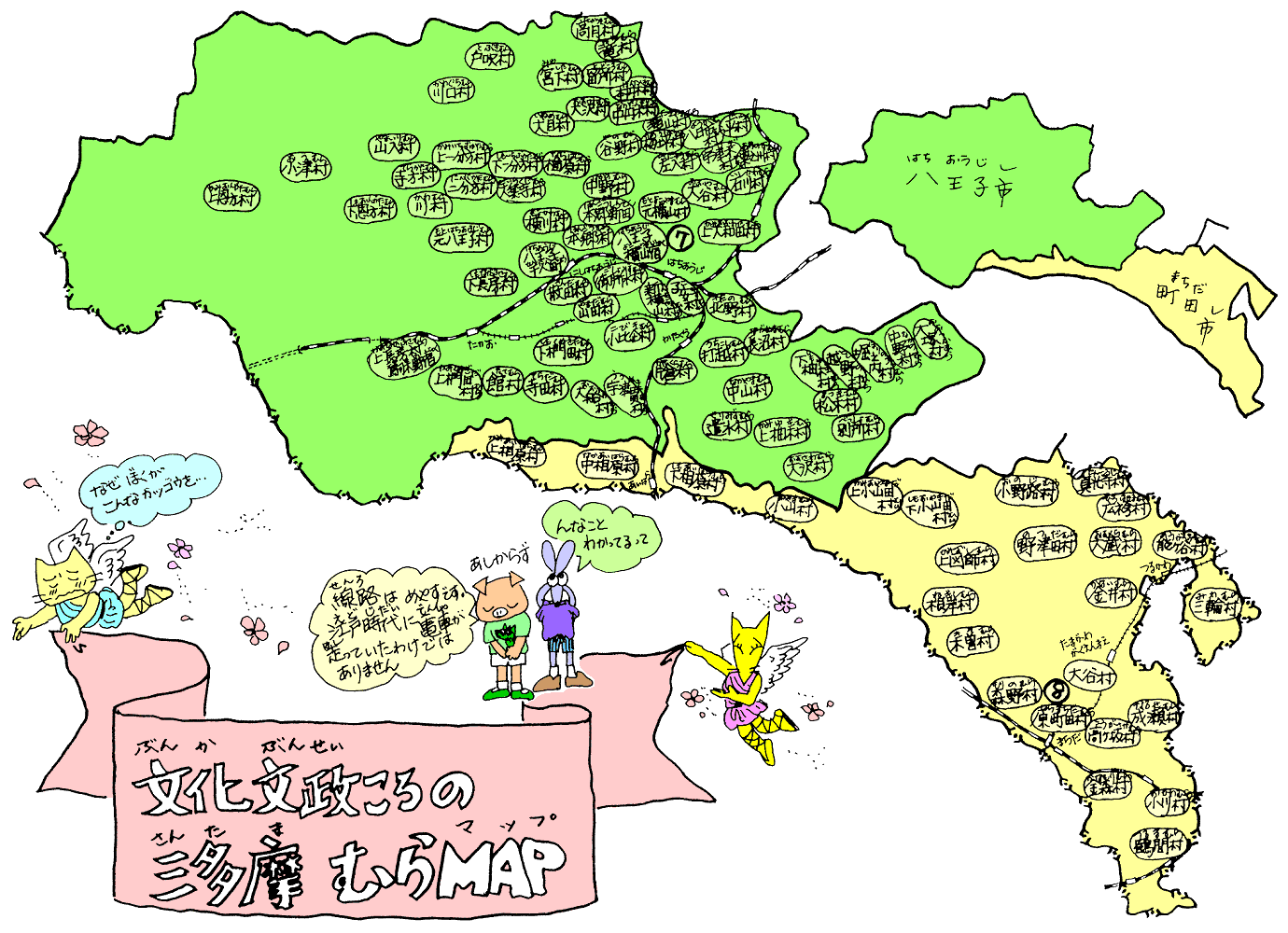
7.八王子横山十五宿(八王子市)
ここは
甲州街道の
駅のひとつ。
十五宿のうち、
横山宿が
第一なので「
横山十五宿」とよばれた。
「横山宿」 4日・14日・24日と、毎
月4の
日に
市がたち、
織物や、
魚・
野菜などが
売り
買いされた。
「新町」 いちばん
東はじの
宿。
「本宿」 武蔵七党のうちの
横山党の
土地で、
古くからひらけていた。
「八日市宿」 8日・18日・28日と毎
月8の
日に
市がたつので、この
名がついた。
「寺町」 寺が
多くあるので、この
名がついた。
「八幡宿」 八幡神社にちなむ
地名だといわれる。
「八木宿」 天正年中(1573~1592)に
八木源左衛門という
人の
屋敷があったのでこの
名がついたという。
小田原北条氏の
家臣だったのだろうといわれる。
「横町」 八幡宿と
八日市宿の
間を
北に
横切るので、この
名がついた。
「島之坊宿」 修験者、
島之坊の
先祖の
俊盛という
人が
文禄4
年(1595)ここに
坊(
僧の
住居)をたてたことにちなむ。つまり、その
坊の
名が「
島之坊」だったわけ。
「小門宿」 江戸時代のはじめ、
代官、
大久保石見守長安(としょかんこどもしりょう 32「八王子千人同心多摩をゆく」を
読めば、どんな
人かわかるよ)が
屋敷をかまえ、
東に
表門、
北に
裏門、そして
裏門のところには
訴えのための
百姓宿がならんでいた。「御門宿」「於門宿」と
書かれたけれど、
長安亡きあとは「小門」に
改められた。
「馬乗宿」 江戸時代のはじめ、
代官屋敷があって、その
門の
前で
乗馬のけいこをしたので、この
名がついた。
「子安宿」 天平宝字3
年(759)、
聖武天皇が
光明皇后の
安産を
祈って
建てた「
子安神社」にちなむ。

これに
「久保宿」「本郷宿」「上野原宿」を
加えて、
十五宿となります。
8.町田(町田市)
江戸時代に「本町田」と「原町田」の二つの村に分かれた。
農業のあいまに男の人は炭を焼き、女の人は蚕を飼った。
本町田村は毎月7の日、原町田村は毎月2の日に市がたって、江戸から遠く離れた場所なのに宿場のようににぎやかだったらしい。
江戸時代のあの村、この村その3
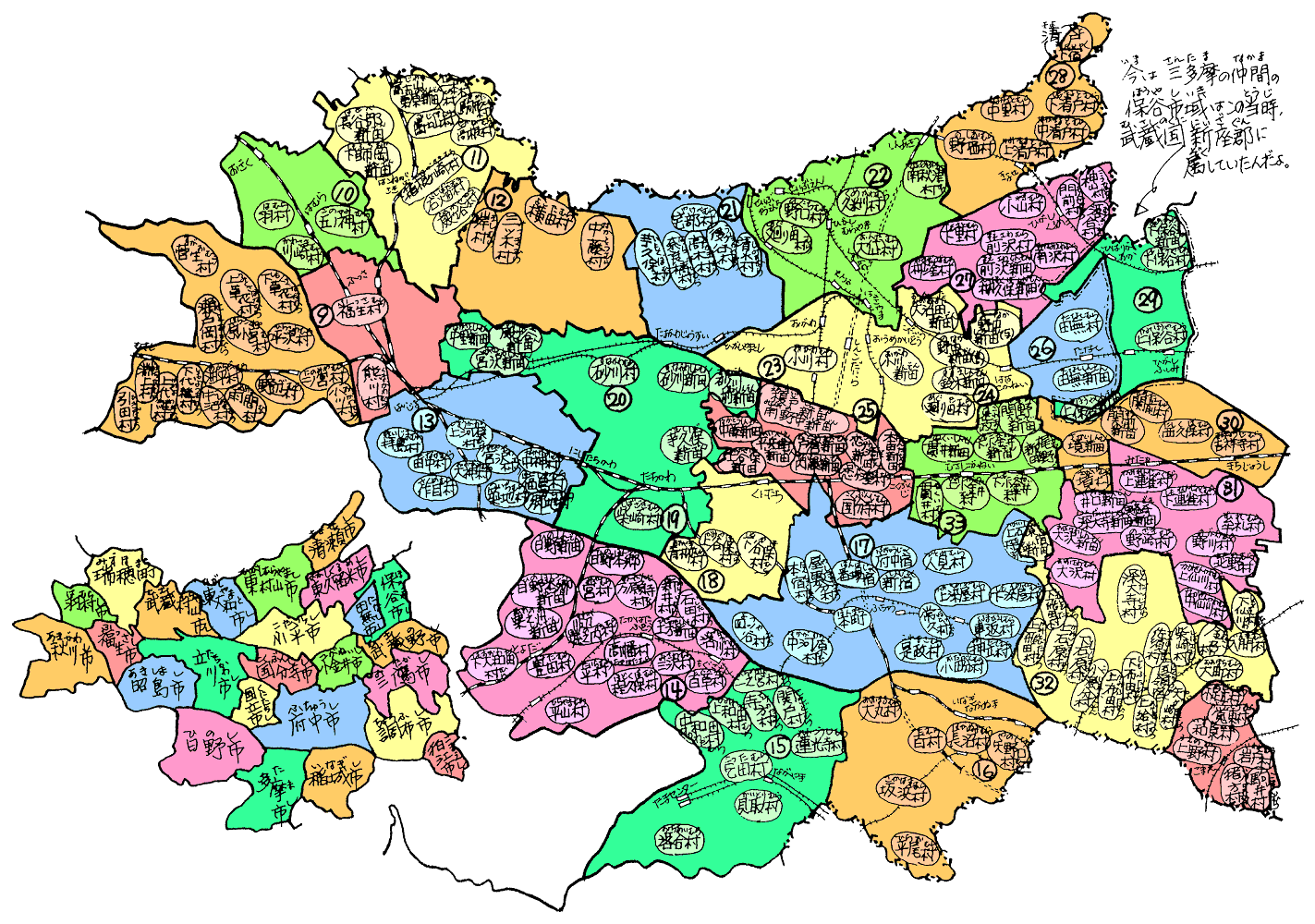
9.福生(福生市)
土地の人は方言で「フッチャ」といった。アイヌ語で麻を意味する古い言葉の「総(房)」や多摩川沿いの「阜沙」(みずぎわの丘の意味)がなまって「ふっさ」になったという説がある。
農業のあいまには多摩川に出て筏を作って流したり、魚をとったりしていた。
10.五ノ神(羽村市)
熊野社、第六天社、神明社、稲荷社、子ノ神社、と村の中に神社が5つあることから、この名がついた。
11.箱根ケ崎(瑞穂町)
古くから歌にもよまれている地名。「筥の池」が「狭山」のふもとにあって、狭山が岬のようにでいりしている地形なので、「狭山の根(もと)にある筥の池」ということで、「はこね」という。そして、狭山のはりだした様子は「崎」のようなので「はこねがさき」となった。
別の説では、狭山丘陵をハコ(神さまの住む)ネ(山)として、そのサキ(先)にある村なので、ともいわれる。
12.岸村(武蔵村山市)
むかしむかしの多摩川のなごりである残堀川が流れていて、その岸にあるのでこの名がついた、という。
北側の山のふもとに農家がちらばっている。風で畑の土が吹きちらされるので、防風のために宇津木(高さ1~2メートルの落葉樹。生垣などに使われる)を植えていた。
13.拝島(昭島市)
ここから11里(約43キロメートル)ほど多摩川上流の日原村(今の奥多摩町)から、むかし大日如来の像が流れてきた。夜には光をはなって輝くので村人はこれを拝み、村に迎えて大切にしたので、ついた地名だ。
農業のあいまに蚕を飼い、糸をつむぎ、織物をし鮎をとって江戸へ出て売っていた。
14.百草(日野市)
草の茂る場所だったので、むかしは「茂草」と書いた。「百草」と書くようになったのは江戸時代以降。
村の中の松連寺というお寺の経筒(経典を入れて経塚に埋めるために使う筒)に「長寛」(1163~1165)、「永萬」(1165~1166)、「建久」(1190~1199)などの年号が記してあるので、かなり古い村だってことだ。
15.乞田(多摩市)
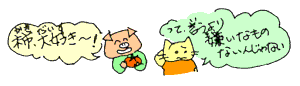
ここも
鎌倉・
室町時代から
見える
地名。
多摩市や
日野市はむかし「
吉富郷」とよばれたけれど、「吉富」という
字は「キツト」という
音にあてた
字だろうといわれていて、「キツト」は「
乞田」のことだ、という
説がある。
農業のあいまに
蚕を
飼い、
柿の
木をたくさん
植えて、
実を
江戸に
出荷していた。
16.矢野口(稲城市)
むかしは「谷野口」「谷ノ口」とも
書き、「
古沢村」とか「
砂田村」とか
呼ばれたりもしたそうだ。
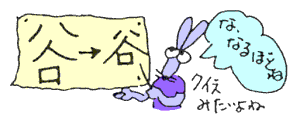 村
村の
言い
伝えでは
多摩川の
流れがよこぎる
村に、8
軒の
家があった。それで「
八人口」の3
字をひとつにして「谷」の
字になるので「
谷ノ口」と
言うようになったとか。
水田が
多い
土地で、
農業のあいまには
炭を
焼いた。
17.府中宿(府中市)
番場宿、本町、新宿の三宿を合わせて、こう呼ぶ。甲州街道の宿のひとつ。三宿でかわるがわる駅をひらいて、旅行者のための人手や馬を出していた。1ヵ月のうち12日間が本町で、のこりの日数を番場宿と新宿で分けて受け持った。
「番場宿」 名前の由来ははっきりしない。けれど小田原北条氏がここに川越街道の番所(見張り所)をおいていたから、とか六所宮(大國魂神社のこと)の競馬式がここでおこなわれたから、とかの説がある。
「本町」 府中宿の中心。江戸時代、番場宿と新宿が独立したために、こう呼ばれるようになった。
「新宿」 府中の三宿の中でできるのがいちばん遅かったので、こう呼ばれた。
18.青柳(国立市)
府中宿から一里(約3.9キロメートル)離れた甲州街道沿いの村。
むかし、この村は多摩川の南岸の青柳島というところにあって、寛文11年(1621)にここに移って来た。
青柳島は楊柳(カワヤナギやシダレヤナギ)が多くあるのでおこった地名だ。
19.柴崎村(立川市)
戦国時代から見える地名。小田原北条氏に属した立河氏の領地だった。普済寺がその館跡だと伝えられる。
20.砂川村(立川市)
岸村(今の武蔵村山市)の村野助右衛門という人がここを開拓して、のちに砂川氏をなのるようになった。「砂川」というのはここの古くからの地名だ。助右衛門さんの残した記録では慶長14年頃(1609)開拓されたらしい。
21.宅部(東大和市)
地名の由来はわからない。
「屯倉部」(大和朝廷の領地からとれた米をしまっておく倉。さらに朝廷の直接の領地を意味する)がなまって「やけべ」になったのではないか、という説がある。
今は、大部分の面積が村山貯水池にかかって水底に沈んでいる。
22.久米川(東村山市)
「久目川」「来目川」「貢馬川」とも書く。ここの北側を流れる柳瀬川を久米川とも呼んでいて、それが地名になったもの。
農業のあいまに蚕を飼い、薬草を植え薬種(薬の材料)を作ったりしていた。
23.小川(小平市)

このあたりは
武蔵野の
原野だったのでまわりじゅう
平らな
土地だ。
林と
陸田が
多い。
村の
中には
鎌倉から、
陸奥(
今の
青森県)へむかう
街道が
走っていて、
府中・
国分寺・
恋ヶ窪を
通って
小川に
至る。
岸村の
小川九郎兵衛という
人が
武蔵野の
石塔ヶ窪というところから
開発をしたのがはじまりで、
村も
九郎兵衛さんの
名によっている。
24.廻り田(小平市・東村山市)
今の東村山市にあった方の廻り田村が小平の廻り田新田の親村なんだ。
草をとるために野中新田から買い受けた土地だった。
『新編武蔵風土記稿』のころの小平の廻り田新田は、人家はわずか15軒。真桑瓜などを植え、江戸や八王子に売り出したりしていた。
25.恋ヶ窪(国分寺市)
「鯉ヶ窪」とも書く。湧き水が豊富で、野川の水源となっている。むかし、鎌倉から奥州(今の東北)へ向かう街道が通って、にぎやかな駅だったという。
夙妻大夫という女の人が恋人の畠山重忠(鎌倉時代の武士。武蔵の人)のウソの戦死の知らせに迷って自殺したという伝説が残っている。たしかに地名もそれっぽいね。
一方、国府(府中)に近い窪だから、とか、湧き水にめぐまれた窪で、鯉を飼い、旅人に提供したので、とかいう説もある。
26.田無(西東京市)
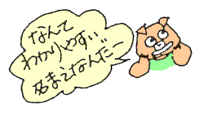 武蔵野台地
武蔵野台地にあって、
田んぼが
無いことからこの
名がついたという。
毎月1、11、21の1の
日と、6、16、26の6の
日には
市がたった。
27.柳久保(東久留米市)
今は「柳窪」と書くよね。ここは黒目川の水源で、土地が肥えていた。水田と陸田は半々ぐらい。
28.清戸(清瀬市)
八王子城主、北条氏照にとって、ここも重要な軍事拠点だった。だから戦国時代には番所が置かれていた。上・中・下の清戸村と、清戸下宿にわかれたのは、江戸時代になってから。下宿の南には「子は清水」と呼ばれる清水が湧いた。大人が飲むと酔っぱらうのに、子どもが飲んだら真水だった、という伝説の水だ。
29.保谷(西東京市)
「保屋」とも書く。地名は開拓者の名によるともいうが、確かではない。
30.吉祥寺(武蔵野市)
ここと三鷹の連雀は事情が似ている。
明暦の大火で江戸本郷本町(今の文京区)の吉祥寺の門前の住人が五日市街道沿いに移住してきたことからはじまる名だ。
31.連雀(三鷹市)
30吉祥寺で言ったとおり、明暦の大火が始まりなんだ。
神田連雀町の人々が火除地としてとりあげられた土地のかわりにここに移住して、ついた名だ。
32.飛田給(府中市)
『続日本後記』(869年成立。日本の歴史の本)に天長10年(834)5月、多摩郡と入間郡の境に悲田処(貧しい人や、みなし子を救う施設)を置いた、と書かれている。
ここは悲田処の給地(税金を免除された土地)で、もとは「悲田給」と書いたのを同じ音の「飛」を使うようになって、いつのころからか「飛田」となったのではないか、と伝えられる。
33.貫井(小金井市)
「温井」とも書く。湧き水が地盤をくぐって、ぬき通っている、という意味で「抜井」。
それから湧き水の温度が高いので「温井」、などなど、いろんな説がある。小平の鈴木新田を開発した鈴木利左衛門はこの村の出身なんだよ。
お江戸周辺ガイドブック
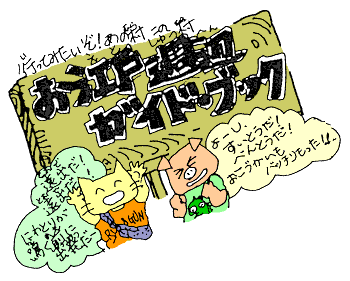
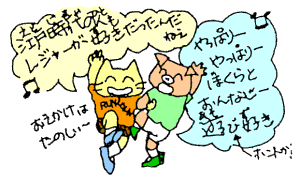 江戸時代は、幕府が編集 した 地誌『新編武蔵風土記稿』のほかにも、お江戸や、そのまわりの名所・旧跡を案内する本がたくさん出版された。
江戸時代は、幕府が編集 した 地誌『新編武蔵風土記稿』のほかにも、お江戸や、そのまわりの名所・旧跡を案内する本がたくさん出版された。
経済が発達したし、交通や治安が整備されたこともあって、この時代、見物旅行や、神社・お寺まいりのレジャーにでかける人が増えた。だから、こういった案内の本は(今でいうガイド・ブックだねー)、みんなから大歓迎されたんだ。
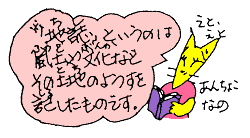 その中から『新編武蔵風土記稿』とほぼ同じ頃に出版された地誌、『武蔵名勝図会』と『江戸名所図会』のふたつから、当時の三多摩の見どころをいくつか拾ってみました。その内容といったら、神社のお祭りの年間スケジュールから、その地方で起きた不思議な出来事まで、「うーん、ここまで調べてのせたか!!」と思わずうなるシロモノだ。
その中から『新編武蔵風土記稿』とほぼ同じ頃に出版された地誌、『武蔵名勝図会』と『江戸名所図会』のふたつから、当時の三多摩の見どころをいくつか拾ってみました。その内容といったら、神社のお祭りの年間スケジュールから、その地方で起きた不思議な出来事まで、「うーん、ここまで調べてのせたか!!」と思わずうなるシロモノだ。
『武蔵名勝図会』
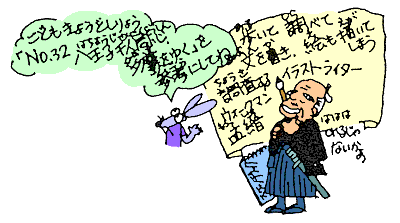 『新編武蔵風土記稿』の調査のため、武蔵国を歩きまわった八王子千人同心のメンバーの1人、植田孟縉が書きあらわした。調査の仕事にたずさわる中から生まれてきたのだから、『新編武蔵風土記稿』の兄弟分みたいなもの。『新編武蔵風土記稿』の多摩郡の部ができあがった文政5年(1822)のよく年に『武蔵名勝図会』は完成し、昌平坂学問所の林述斎に献上された。
『新編武蔵風土記稿』の調査のため、武蔵国を歩きまわった八王子千人同心のメンバーの1人、植田孟縉が書きあらわした。調査の仕事にたずさわる中から生まれてきたのだから、『新編武蔵風土記稿』の兄弟分みたいなもの。『新編武蔵風土記稿』の多摩郡の部ができあがった文政5年(1822)のよく年に『武蔵名勝図会』は完成し、昌平坂学問所の林述斎に献上された。
『江戸名所図会』
『新編武蔵風土記稿』が政府刊行の地誌ならこちらは民間編集の地誌の中で最大最高といわれる濃い内容の本。寛政年間(1789~1801)に神田の名主、斉藤幸雄が手がけてから、その孫の斉藤月岑が出版にもちこむまで、親子3代、40年以上もの月日をかけた大事業。天保5年(1834)と天保7年(1836)の2度に分け7巻20冊が出版されたんだ。さし絵は長谷川雪旦が受け持った。
江戸の人たちのガイドとしてはもちろん、遠い地方の人たちが江戸を知るための資料としても、人気があった。
ガイドその1.温泉
平井村・鹿の湯(日の出町)
湯本は、塩沢山宝光寺の本堂から300メートルばかり北の谷あいにあって、「鹿の井」という。
むかし、ここにキズを負った鹿がやって来て、治したといい、遠くの人も、話を伝え聞いて、山の中へはいって温泉をくんでくる。
宝光寺を開いた文済禅師が、みんなの苦労を思って仏陀に祈り、大般若経を唱えたところ、山のふもとに温泉が湧き出したのだそうだ。お湯は硫黄の気が少しあって、水の色は白い。切り傷、打撲、骨折、皮ふ病によく効く。
小河内郷の温泉(奥多摩町)
もとは小河内村として、ひとつだったのが、原村、河内村、川野村、留浦村の四か村に分かれた。
ここに熊野権現という神社があって、またの名を「湯の権現」、そのそばから温泉は湧いている。打撲、くじき、頭痛などに効果があって、春から秋まで治療におとずれる人たちがいっぱいいる。
 (鹿の湯の図。「武蔵名勝図会」より)
(鹿の湯の図。「武蔵名勝図会」より)
このころ、西多摩には「七ツ湯」といって、ほかに三内「藤の湯」、網代「玉の湯」、檜原「数馬の湯」、長浦「出湯」、小曽木「岩蔵鉱泉」という有名温泉があった。
ガイドその2.不思議だぞ!ほんとうか?!編
箱根ケ崎村・筥の池の蛇喰い次右衛門(瑞穂町)
筥の
池は「
狭山の
池」ともいった。むかしは
大きな
池だったけれど、
今は
水がかれてしまった。
草ぼうぼうの
地ではあるけれど、
遠く
峰からながめると
奥深い
趣きがある。
この
池が
水をたたえていた
頃、
村の
百姓で
次右衛門という
人がいた。
夏の
暑い
日、
池で
水あびをしたら、
蛇がからみつき、からだをしめあげてくる。
次右衛門は
勇ましい
人だったから
蛇を
喰いちぎった。すると
池の
水は
紅い
色になり、
空はかきくもって
鳴りひびいた。
この
蛇は
古くから
筥の
池に
住んでいたが、
次右衛門に
退治されてしまったので、
池の
水もかれたのだという。
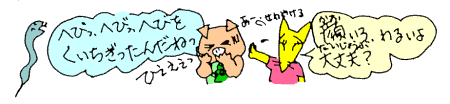
由木領中野村・自分の前世をおぼえている子ども(八王子市)
源蔵という村人の子の勝五郎は、自分の前世をおぼえているという。
勝五郎は文化12年(1815)10月10日の生まれだが、8才の時、14才になる姉と遊んでいて、「自分の前世を知っている」と言いだした。
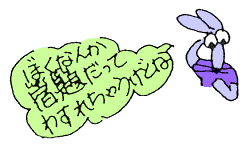 「自分は中野村より2キロメートル>ほど西北の程窪村に生まれた。父は勝五郎。母はおしづ。6才の時に天然痘にかかって死んでからこの家に生まれた」と言う。その次の年の文政6年(1823)の正月。母親とおまいりのかえり、程窪村を通りかかると、「これが自分の前世の家」と勝五郎は村の中の一軒を指さした。その家に母親がたずねてみると、勝五郎が話したとおりだった。
「自分は中野村より2キロメートル>ほど西北の程窪村に生まれた。父は勝五郎。母はおしづ。6才の時に天然痘にかかって死んでからこの家に生まれた」と言う。その次の年の文政6年(1823)の正月。母親とおまいりのかえり、程窪村を通りかかると、「これが自分の前世の家」と勝五郎は村の中の一軒を指さした。その家に母親がたずねてみると、勝五郎が話したとおりだった。
この不思議な話は伝えひろまり、訪ねてくる人も多い。江戸でも評判の話だ。
ガイドその3.やっぱりこれだね、神社・お寺編
府中宿・総社六所宮(府中市)
武蔵国の総社で、宿の中央に鎮座している。(つまり大國魂神社だよ。)
毎月1日・15日、五節句、冬至、夏至、追儺、除夜の祭りには、お神楽をする。
2月1日は花祭り。5月3日の夜は競馬祭り。5月4日、5日もお祭り。6月20日、お祭り。7月7日、帷子祭。7月12~13日は朝まで舞楽。8月1日、田面の神事。11月1日は新嘗祭。
高幡村・高幡山金剛寺(日野市)
大宝年中(701~704)に慈覚大師が開いたお寺。
本堂の東、不動尊古迹山のふもとに「鼻井」という井戸がある。この水は暦応2年(1339)に不動尊を山の上からここにおろしてきた時、尊像の頭がおちたところから自然に湧き出してきたもの。たとえ1000日の日照りにもひあがらず、数ヵ月、雨が降ってもあふれない。熱病、悪寒、はれもの、目の病いや、痛いところにつけたり、飲んだりすると治る。治らない人はいないぞ。
谷保村・天満天神(国立市) 谷保天神のことだよ
むかし、神社は本宿(谷保村の東隣り)の南の、天神島というと
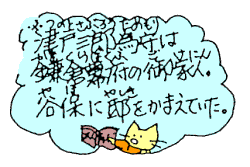
ころにあった。
養和元年 (1181)に
津戸三郎為守が
夢のお
告げにしたがって、ここに
移した。さらにその
後、
甲州街道の
筋がかわったので、
神社の
参道も
今のところにつけた。それで
入り
口よりもお
宮の
方が
低い
場所になっちゃった。あたりは
杉木立ちだ。
例祭は
正月、2
月25
日、8
月24~26
日で
獅子舞、
神楽などがあり、お
祭りの
人が
群れをなす。11
月3日には
夜祭りだ。
氏子は
新米を
奉納して、かがり
火をたく。
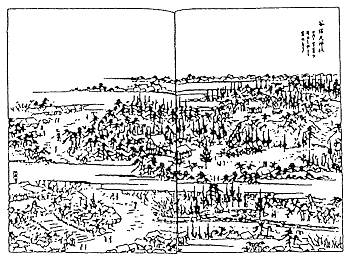
(『
江戸名所図会』より
旧甲州街道から
見た
谷保天神)
ガイドその4.自慢しちゃうぞ、この名物!
多磨(摩)川の鮎(府中・調布あたりから上は青梅、羽村市あたりまで)

ここいらの名産は鮎。秋の彼岸になると府中領より西の方から川上は三田領まで、鮎とりを命じられて、川筋の村々は毎年、幕府に納めている。ここの鮎は相模川の鮎などとは形も違い、味もいい。幕府御用の鮎は網でとって、いけすに飼っておく。そして決められた日に納める。大きすぎず小さすぎず、15センチほどのがいい。鳥の鵜をあやつってとると鮎にきずがつくので、御用の向きには使えない。
ほかに、ハヤ、マス、ナマズ、ウナギ、カジカ、ヤマメ、イワナなどがとれる。
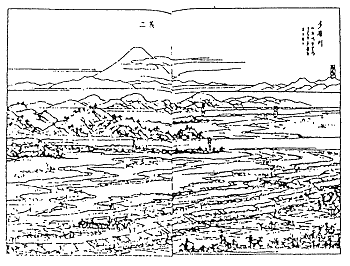 (『江戸名所図会』より 多磨川の図)
(『江戸名所図会』より 多磨川の図)
河辺村の玉川焼(青梅市)
「河辺焼」ともいう。楽焼といって、ゆびで形づくり、低い温度の火で焼く陶器だ。つくり始めて20年くらいだ。(江戸時代の文化文政のころから見て20年ということですよ。)江戸へも送って、「玉川焼」といっている。
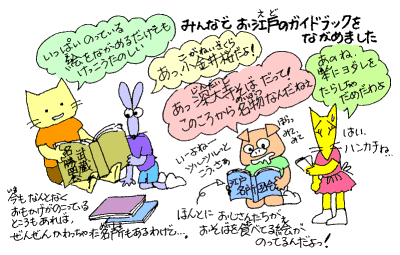
<クイズのこたえ>
- とずらむら
- うずしきくみ
- ことづらくみ
- さんないむら
参考にした本
「新編武蔵風土記稿」
「角川地名大辞典」
「武蔵名勝図会」
「江戸名所図会」
「多摩の歴史」
多摩の地名研究をされている保坂芳春先生にもたいへんおせわになりました。
小平市に関すること
多摩に関すること
江戸・東京に関すること
玉川上水・小金井桜に関すること
その他
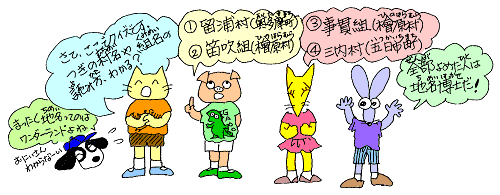
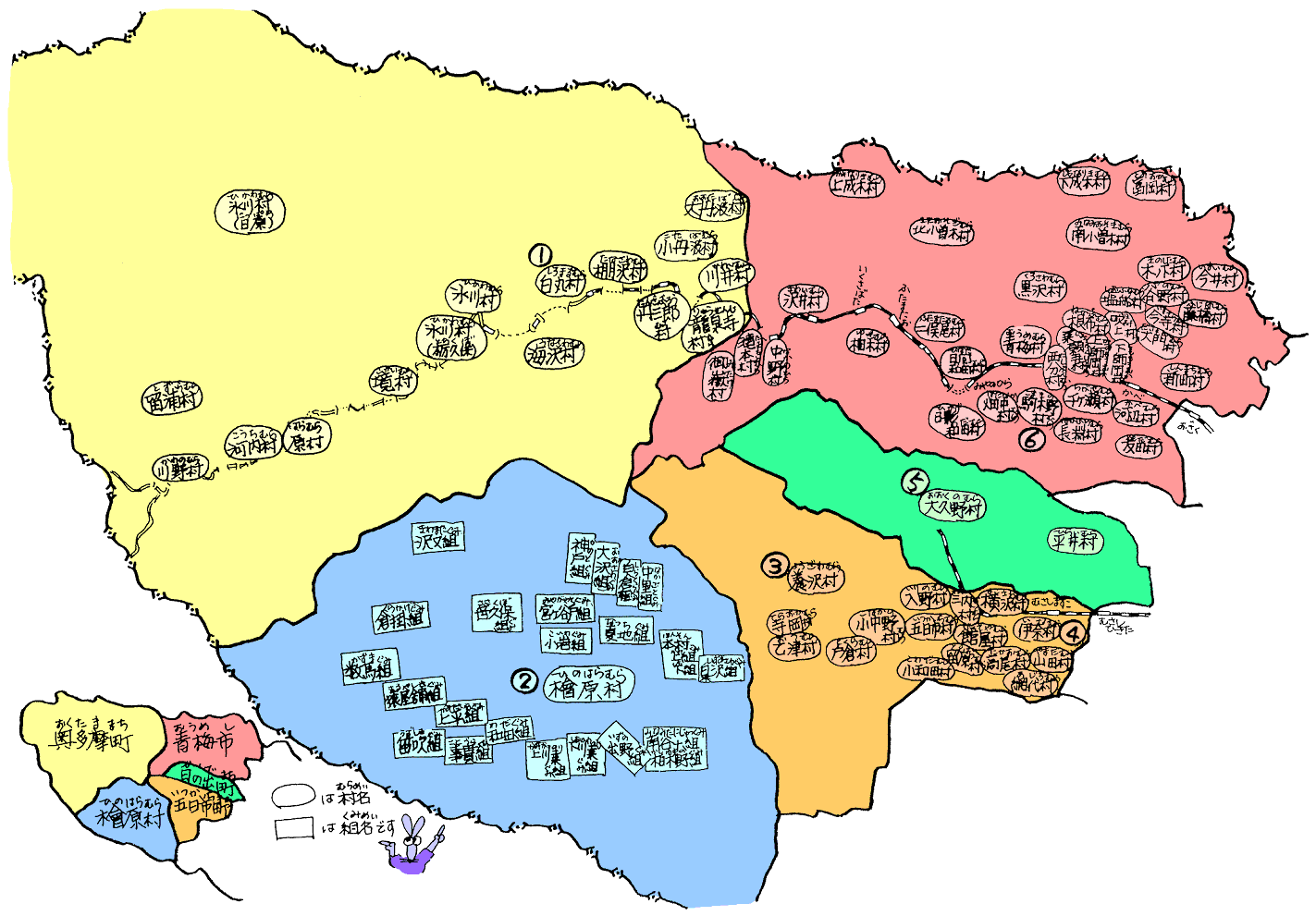
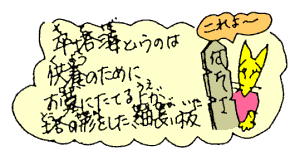

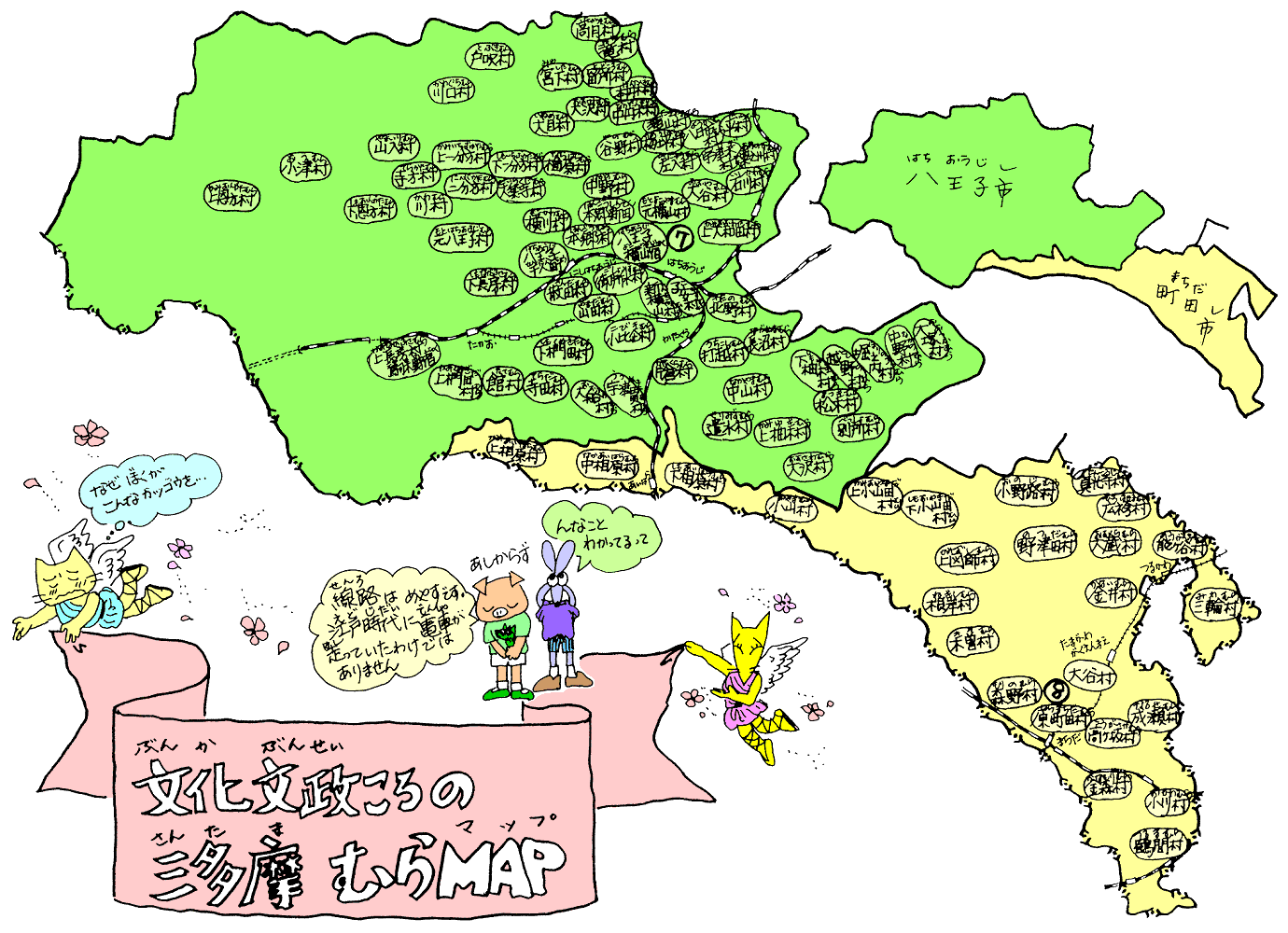
 これに「
これに「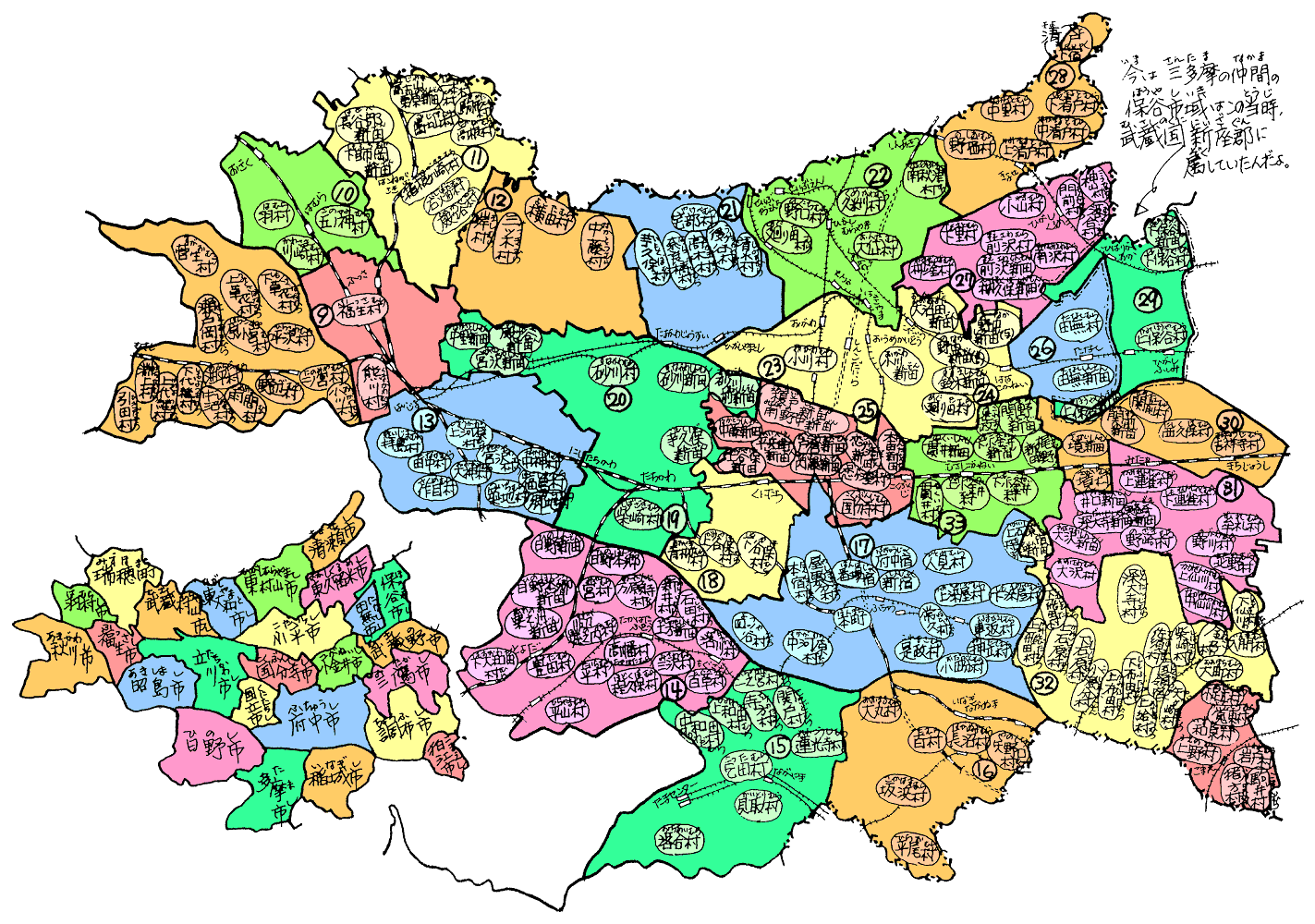
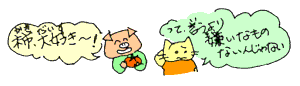 ここも
ここも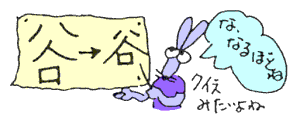
 このあたりは
このあたりは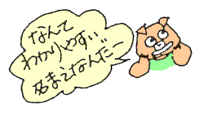
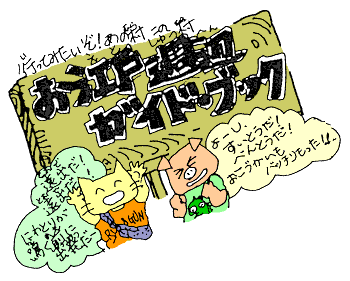
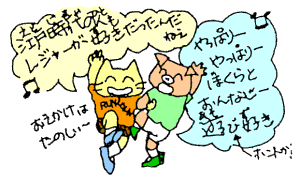
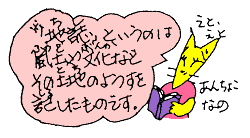 その
その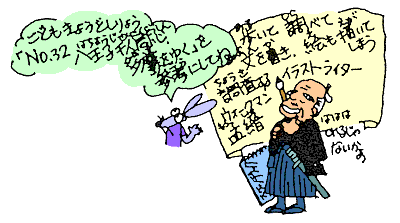 『
『
 (
(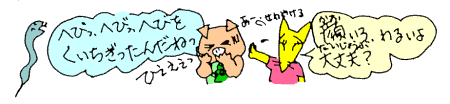
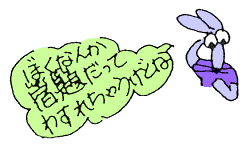 「
「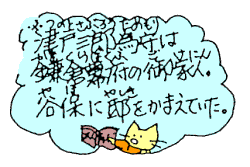 ころにあった。
ころにあった。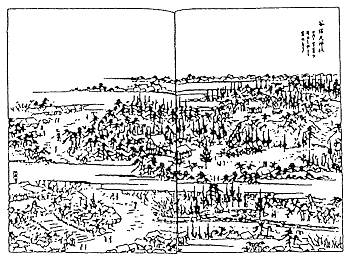

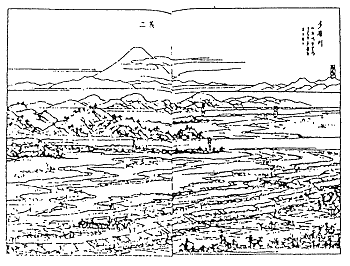 (『
(『