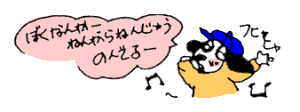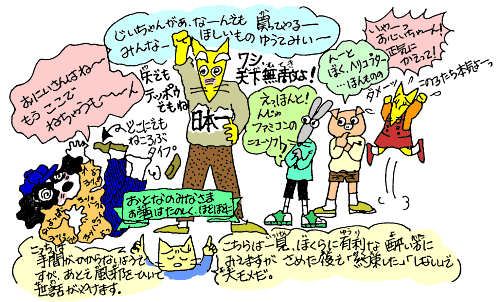多摩の酒造
寛政11(1799)年「山海名産図会」より“酒あげすましの図”
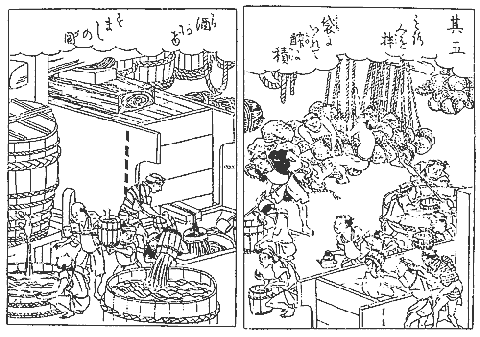
発酵した「もろみ」を袋に入れ、酒槽に積み、お酒をしぼるところ。

お酒の歴史って古いんだ。そのはじまりは、神話とか、伝説のかたちで伝えられてきているんだから。
世界中、そこの人々が主食にしているものをもとにして、お酒は造られる。ヨーロッパはオリエントから麦でつくるビールが伝えられていった。そして、もちろん日本のお酒はお米から生まれる。
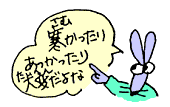 日本酒を造るのには晩秋から冬にかけての寒い時期が向いている。
日本酒を造るのには晩秋から冬にかけての寒い時期が向いている。
冷えた水で米を洗い、高温多湿にした室で麹をつくり、ひとつひとつの工程に丹精をこめて造る。
 技術と経験が求められる繊細な仕事だ。
技術と経験が求められる繊細な仕事だ。
東京でも、そういうお酒が造られている。しかもほとんどが多摩地区にある。(23区は北区に一場のみ。)
明治の頃は小平にもいくつも酒造(お酒を造るところ。造り酒屋ともいう)があった。戦前までは多摩全体で29あったそうだ。
今はその数も半分くらいになってしまったけれど、自慢したくなっちゃうよね。多摩の、心をこめた手づくりの仕事。
三多摩の酒造マップ
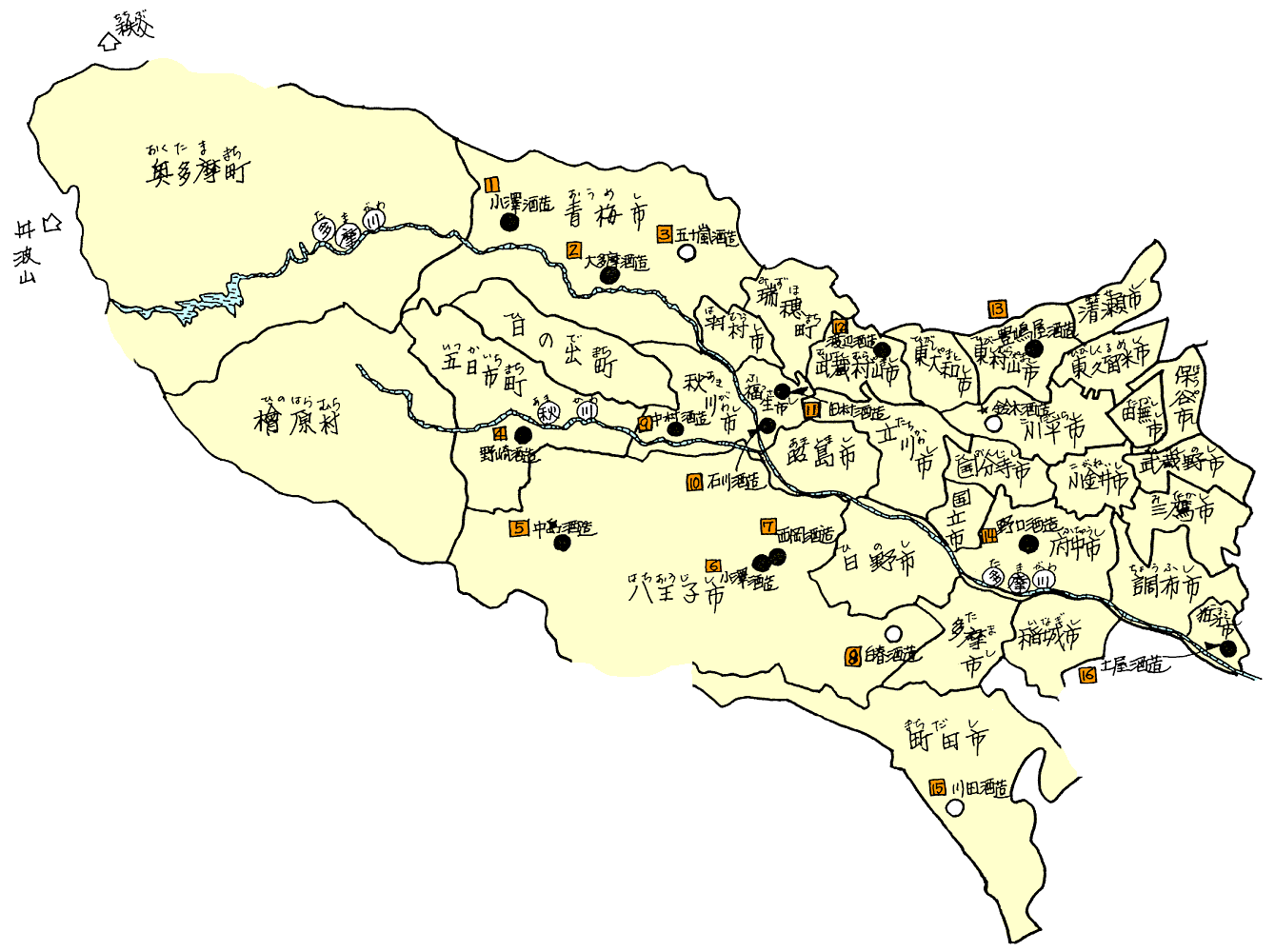
くろいまる:95年現在お 酒を造っている。
しろいまる: 今はやめてしまったけれど最近までお酒を造っていた。

- 酒造の場所
- お酒の銘柄(商品名)
- おぼえがき
1.小澤酒造

- 青梅市沢井2-770
- 「武陽 澤乃井」
- 小澤氏はもと武田の家臣だとか。いつからお酒を造り始めたかはわからないが、元禄15(1702)年に役人が「酒御改め」に訪れたとある。150年前にほられた横井戸があって、秩父の地中から湧く岩清水をたたえる。
2.大多摩酒造(休蔵中)

- 青梅市森下町499
- 「酔悦」「武蔵男山」
- 明治の半ばに創業。はじめ「泉川正宗」というお酒をつくっていて、昭和の初めに「玉の海」と名をかえ、昭和14(1939)年に「酔悦」となった。
3.五十嵐酒造

- 青梅市大門
- 「宇寿桜」「富久泉」
- 明治3年創業。「うす(薄)桜」は“かおりほんのりさくらいろ”の意味なんだ。
4.野崎酒造

- あきる野市戸倉63
- 「喜正」
- お酒の名は初代の喜三郎さんの名からとられている。秩父山系と秋川からの水をひいている。
5.中島酒造

- 八王子市下恩方町725
- 「日出山」「陣馬山」
- ここのご先祖は八王子城主、北条氏照の家臣だったとか。落城の時、主君氏照とともに切腹したけれど、息子を1人、恩方へ逃がした。その後ここいらの名主さんとなり酒造りは200年ぐらい前から。秩父山系の水を使う。
6.小澤酒造

- 八王子市八木町2-15
- 「桑乃都」
- 創業大正15(1926)年。青梅の小澤家から分家した。お酒の名は八王子にはなじみ深いもの。(八王子は古くから「桑都」と呼ばれていたんだ。)
7.西岡酒造

- 八王子市八木町5-40
- 「社会冠」「高尾錦」「千人隊」「新選組」「江戸っ子正宗」
- 八王子で醸造を始めて300年。ただし初めの200年はおしょうゆをつくっていた。「江州店」といって近江商人のおみせ。家族を故郷に残し、ご主人だけがおみせに働きにでるというめずらしい形をとっていたそうな。(単身赴任てやつだなー)
8.白春酒造

- 八王子市東中野
- 「白春」「つや娘」
- 大正10(1921)年創業。ここの水は丹沢水系。
9.中村酒造

- あきる野市牛沼63
- 「千代鶴」
- 創業は文政12(1829)年。かつてはすぐ近くを流れる秋川に鶴がおりて来たという。お酒の名はこのことにちなんでつけられた。
10.石川酒造
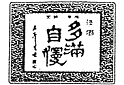
- 福生市大字熊川1-1
- 「多満自慢」「八重梅」
- 天保11(1840)年創業。福生には江戸時代の初めから住み、代々熊川村の名主をつとめた。慶応3(1867)年には水田開発の大事業を完成。明治にはいるとビール製造の技術をとりいれて「日本麥酒」というのを発売もした。『石川酒造文書』という本も出していて歴史的にも貴重な情報がおさめられている。
11.田村酒造

- 福生市大字福生626
- 「嘉泉」
- 福生村の名主、田村家の歴史は300年以上。玉川上水から2本だけひかれた個人用の分水の1本は田村家に流れた。おぼえがきによれば、創業は文政5(1822)年。
分水には水車をおいて、米の精製をしていたという。酒造りもそのあたりから出発しているらしい。
12.渡辺酒造

- 武蔵村山市中藤1-15-1
- 「吟雪」
- 代々おしょうゆを醸造していて、酒造りを始めたのは明治10(1877)年。どういう名まえのお酒にするか話し合っていた時にちょうど雪がふってきて、命名のきっかけになった。はじめ「雪華」それがのちに「吟雪」に。
13.豊嶋屋酒造

- 東村山市久米川町3-14-10
- 「金婚正宗」「お江戸日本橋」
- 慶長元(1595)年白酒造りがこの酒造のはじまり。初代重兵衛の夢枕に女神が立って白酒の造り方を教えたという。
もとは神田鎌倉町にあり、絵師安藤広重に「豊島屋白酒売出図」として描かれた。
東村山に移ったのは明治30年以降。
14.野口酒造
- 府中市宮西町4-2-1
- 「国府鶴」「江戸鶴」
- むかし大國魂の神である大国主命が府中を訪れた時、野口家がこころよく宿を貸したという言い伝えがある。それにのっとって、毎年5月の大國魂神社のくらやみ祭りでは、「野口の仮屋」の儀式がおこなわれる。もとは神職だったともいわれ、神様とのつながりの深い酒造。
15.川田酒造

- 町田市旭町
- 「大綬」「井出の澤」
- 町田市には元禄10(1697)年には、もういくつかの造り酒屋があったとか。
川田酒造は創業明治24(1891)年。はじめ神奈川県柿生で、明治30年代に町田に越して来たという。
16.土屋酒造(休蔵中)

- 狛江市岩戸南1-5-2
- 「鳳桜」「とうきょう地酒」「ちょうふ地酒」
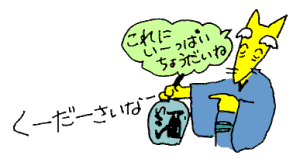 土屋家は江戸時代よりも前からこの地に住みついていたのだそうな。明治7(1874)年に酒造りを始めて、そのころは土地の人たちはとっくりをさげて買いに来たって。お酒に「鳳桜」と名をつけたのは昭和の初め。「ほうおう」と読んでいたのが戦後「おおとりさくら」と読むようになった。
土屋家は江戸時代よりも前からこの地に住みついていたのだそうな。明治7(1874)年に酒造りを始めて、そのころは土地の人たちはとっくりをさげて買いに来たって。お酒に「鳳桜」と名をつけたのは昭和の初め。「ほうおう」と読んでいたのが戦後「おおとりさくら」と読むようになった。
麹ってなあに?
米・麦・大豆などにコウジカビなどのカビをはやしたもの。
カビのつくりだす酵素がでんぷん・たんぱく質をそれぞれ、糖やアミノ酸に分解することを利用して、酒、みそ、しょうゆや、つけもの、お菓子などをつくるのに利用される。
麹を利用する技術は、東アジアの地域にかぎられる。ヒマラヤから日本を含む亜熱帯~暖温帯を中心に北は中国、南はインドネシアまで広がっている。
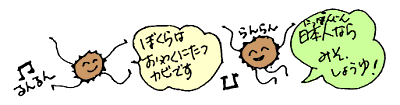
小平の酒造
小平でも、しょうゆの醸造や、酒造をする家は、江戸時代からあった。酒造は地主が小作米(農地を借りた人が借り賃として払った米)で営むことが多かった。たいてい11月半ばから、よく年4月半ばまでの間、新潟から呼ばれた杜氏が酒造りをおこなった。右の表の最後にのっている「當麻家」などは、多摩でも相当大きな商人だったらしい。しょうゆ、酒の醸造を手広くやっていた。「當麻家文書」によると、しょうゆは文化10(1813)年から始め、酒造は文化7(1810)年に役所の許しを得ている。最も事業が盛んだった文政11(1828)年には、1,070石(1石=やく180リットル)もの酒造をおこなった。
明治の初め頃までは、いくつもあった小平の酒造なのだけれど、明治14、5年頃の不況の時期にパタパタとやめてしまった。その中でただひとつ、鈴木酒造だけが昭和62(1897)年までつづいた。
明治の初め頃の小平の酒造
| 持ち主のなまえ |
あったところ |
免許のしゅるい |
持っていた土地の面積 |
| 立川 勝五郎 |
小川村 |
清酒 |
16町5反5畝3歩(49.653坪) |
| 宮寺 熊右衛門 |
小川村 |
清酒 |
16町4反0畝28歩(49.228坪) |
| 金子 鶴蔵 |
小川村 |
清酒 |
15町0反5畝22歩(45.172坪) |
| 小野 弥右衛門 |
小川村 |
濁酒 |
3町7反2畝12歩(11.172坪) |
| 加藤 銀蔵 |
小川村 |
濁酒 |
1町1反1畝16歩(3.346坪) |
| 吉田 徳兵衛 |
小川新田 |
濁酒 |
不明 |
| 當麻 弥左衛門 |
大沼田新田 |
不明 |
30町4反4畝18歩(91.338坪) |
鈴木酒造
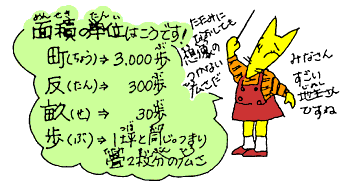
- 場所;小平市小川町1-781
- つくっていたお酒の銘柄;「冨久浦」
初代の茂作さんという人は、杜氏が多く生まれる新潟県は柏崎の出身。茂作さんも東京や埼玉の造り酒屋で働き、やがて、小川村の金子鶴蔵さんのところで親方になった。20年間働いて、明治17(1884)年、独り立ち。スタートは埼玉県入間市であった。「冨久浦」というお酒の名はふるさと新潟の美しい「福浦八景」と“久しく富み栄えるように”という願いをこめてつけた。小平に移って来たのは、その5年後。もとのつとめ先だった金子さんが酒造をやめるというので、蔵を買いとってのおひっこしだった。
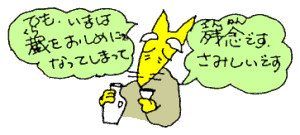
日本酒のちしき あれこれ
純米醸造
米と米麹だけで造った清酒。これが日本のお酒のもともとのつくり方だ。
本醸造(本造り、本仕込みとも)
米と米麹に醸造用アルコールを少し(白米1トンにつき120リットル以下)使う。糖類は加えない。
吟醸
玄米を40%以上精白した米からつくる。(ふつうに食べる白米だって精白率は7%だ!)
良いお酒をつくるには、米をよくみがくことが大切だった。吟醸酒には独特のよい香りがするんだって。
手造り
ずっと伝えられてきた昔ながらの醸造のしかたで造られたお酒をいう。
原酒
ふつう日本酒は発酵がおわると酒かすをとって、こし、その後水を加えて整える。原酒はその水を加えない元のお酒。アルコール度も20度前後と高い。
秘蔵酒
この名は5年以上貯蔵したお酒に限ってつけられる。
樽酒
杉の樽に入れて、木の香りをつけたお酒。
生一本
純米で、しかも自分のところで醸造したお酒に限ってつけられる名。
杜氏
蔵で酒造りをする人たちの頭のこと。むかしむかしは刀自(一家の主婦)がお酒を造ったので、この名がうけつがれたとか、また、中国で初めてお酒を造ったと言い伝えられる「杜康」という人の名によるともいう。杜氏は酒造りについてのいっさいの権限と責任を負う。お酒を造る工程はもちろん、下で働く人々もまとめあげなければならない。人格、知識、才能といろいろなことが要求されるのだ。
杜氏の有名な出身地がいくつかある。関西では丹波、但馬。関東では新潟の越後杜氏が有名。岩手県の南部杜氏、石川県の能登杜氏、岡山県の備中杜氏、島根県の出雲杜氏、長野県の諏訪杜氏、伊那杜氏などがある。
甘口と辛口
日本酒の甘口・辛口の区別ははっきりしたものではない。
糖分の量だけではなく、酸の量によっても飲んだ時の感じがちがってくる、という複雑でびみょーなもの。(酸が多いと辛く感じる。)
また、糖類を加えなくても、米の糖化を十分すれば甘口になる。
発酵を早めにとめれば辛口になる。
どうしてお酒と名がついた?
 杜康
杜康が
初めてお
酒を
造ったのが「
酉の年」だったからという
説もあるけれど。
「
酒」の
字は
酒壷をあらわす
形「

」がもと。「さけ」という
呼びかたは「
栄え」のつまったもの、とか
邪気を
避ける
意味の「
避け」から
転じたとかいわれる。
日本酒ができるまで
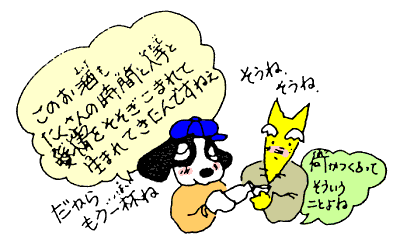
- 精米
- 洗米・浸漬
- 蒸米
- 麹
- 酒母(〓)
- 仕込み
初添え 仕込み第1回目
踊 初添えの次の1日をそのままにして発酵させること。
仲添え 仕込み第2回目。初添えから3日目に原料を加える。
留添え 仕込み第3回目。初添えから4日目。
- 圧搾
- 滓引
- 加熱
- 貯蔵
- 調合
- びん詰め
1.精米する
酒造りに精白したお米を使うようになったのは、室町時代頃かららしい。それまで、日本酒は玄米で造られていたようだ。けれど、よく精白したお米で造った方が色も、味も、香りもいいんだって。
2.お米を洗って、水に浸す
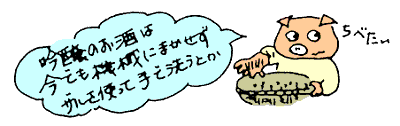 精白
精白したお
米は、よく
洗って、
表面についているヌカなどを
取りのぞく。
洗ったら、しばらく
水につけておく。
水をほどよく
吸わせると、うまく
蒸せるからなんだ。
3.お米を蒸す
蒸米機という
機械もあるけれど、
手造りの
場合は「
甑」(せいろの
一種)に
入れて
強い
蒸気で
蒸す。こうしてできた
蒸米は「
麹用」「
酒母用」「もろみ
用」と3
通りに
使われる。
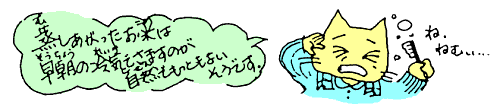
4.麹づくり
冷めた蒸米は麹室に運ばれる。そこで種麹(麹菌)をうえつけ、繁殖させて、麹をつくる。
5.酒母(お酒の〓)づくり
山卸…昔ながらの造り方。蒸米に麹・水をまぜて、すりつぶす。ときどきかきまぜ、暖かくしてやって、空気中の乳酸や酵母による発酵を待つ。この自然な方法でできる酒母は「生〓」という。でもできあがるのに1ヵ月近くもかかるし、その間の世話も大変。
速醸〓…まず乳酸や他の酸を、さらに酵母を人の手で加えて、つくる方法。これだと山卸にくらべて、だいぶ短い日数で酒母をつくることができる。
6.仕込み
酒母と麹と蒸米、水を加えて、三段階に分け、4日間かけて仕込む。さらに20日間発酵させて「もろみ」ができあがる。
7.もろみをしぼる
発酵のおわったもろみはしぼって、酒かすと分ける。今はしぼり機があるけれど、昔はみんな5升ぐらいずつ、麻だの綿だのの袋に入れ、酒船(酒槽とも書く。桶のこと。)に積みこんでしぼった。
(1升 :およそ1.8リットル)
8.おり引
しぼったお酒は、まだかなり白く濁っている。タンクに入れ7日から10日ぐらい置いておりがたまったら、取りのぞく。
【おり】液の底にしずむカスのこと。
9.火入れ
60~65 度までで、加熱殺菌。
10.貯蔵
熱いお酒をタンクに入れ、さまして、熟成させる。
11. お酒の種類によっては、ここで水が加えられ、アルコール分が調整される。
12.びん詰め
お酒をびんに詰めた後、再び火入れ。詮をして、ラベルを貼って出荷する。
酔っぱらいかたは変化する
お酒を飲むと、アルコールは胃腸から直接、しかもすばやく吸収され、血液の中にとけこんでからだじゅうをかけめぐる。「お酒に酔う」というのは吸収されたアルコールに対するからだや心の反応なんですね。お酒の酔い方は強い、弱いとか、人それぞれだけど。
飲んだお酒の量を血液の中のアルコールの濃度ではかり、体重60キログラムの人を基準にすると、だいたいこんなめやすでこんな酔い方になるらしい。大人になったら、気をつけたいもんだぞ。
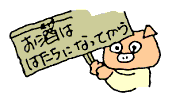
おとうさん必見! これだけ飲むとこんな酔い
| アルコール血中濃度と飲む量のめやす |
どんなになっちゃうかの説明 |
0.02~0.04パーセント
日本酒おちょうし、またはビール大びん1本 |
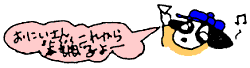 おいしく飲めて、お酒に対する特異体質でない限り、外目にはわかりません。 おいしく飲めて、お酒に対する特異体質でない限り、外目にはわかりません。 |
0.05~0.07パーセント
日本酒おちょうし、またはビール大びん1~1.5本 |
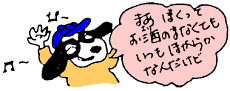 ほろ酔い はじまり ほろ酔い はじまり
からだがあったまってほがらかになる。 |
0.08~0.1パーセント
日本酒おちょうし、またはビール大びん2本 |
 ほろ酔い まっただなか ほろ酔い まっただなか
判断は正しくなくなり、おしゃべりになる。感情はもりあがっちゃって、自分をとどめる気持ちが弱くなり、行動は軽はずみになる。 |
0.1~0.15パーセント
日本酒おちょうし、またはビール大びん3本 |
 のんべ状態 のんべ状態
何も気にならなくなる。同じことをくりかえししゃべるようになる。 |
0.16~0.3パーセント
日本酒おちょうし、またはビール大びん5本 |
 言葉はろれつがまわらなくなりちどり足。くだをまき、怒りやすくなる。恥ずかしいという気持ちがなくなって、行動がらんぼうになる。 言葉はろれつがまわらなくなりちどり足。くだをまき、怒りやすくなる。恥ずかしいという気持ちがなくなって、行動がらんぼうになる。 |
0.4%程度
日本酒、1升(1.8リットル)、またはビール大びん10本 |
 泥酔状態 泥酔状態
力がぬけ、ころんで歩けなくなる。ひとりごとをいうが、支離滅裂。ついには意識なく眠りこんでしまう。 |
0.5%以上
日本酒1升以上 |
非常に危険な状態。呼吸マヒがおこればそのまま死んでしまう。 |

日本酒の歴史
(カッコ)内はその記録が成立した年
『古事記』(712)や『日本書記』(720)によると、日本の酒造りの技術は、5世紀の初め頃、百済を経て、中国から伝わったようになっている。
でも、もともと日本古来のお酒の造り方があるところに、外国からの技術がとり入れられた、という程度ではないかと考えられる。日本酒は日本独自のものだからね。
記録に残る酒造りとしては『日本書記』に「木花開耶姫が天甜酒をかもした」とある。また、『古事記』では、「速須佐之男命が八岐大蛇退治の時、お酒を使った」とある。
『播磨国風土記』(713~715)には「乾飯で酒をかもした」と日本で最初の“麹”の話がのっている。
縄文時代~(果実酒時代)

まず
初めは
山ブドウだのの
果物や、シイ、トチといった
木の
実でお
酒を
造っていたのではないかな。
果物は
糖分をふくんでいるから、
自然の
酵母でお
酒になる。でも、
木の
実のでんぷん
質は
糖分にかえてやらないと
発酵しない。そこで
木の
実は
口でよくかみ、だ
液のはたらきで
糖にかえ、“
口かみの
酒”を
造ったのだろう。
弥生時代~
日本酒の原材料、お米の作り方がはじめて、大陸から伝えられる。
古墳時代~
一般の
人びとが
造ったお
酒と
同じものだったかどうかはわからないけれど、
朝廷でも
宮内省の
造酒司というところで、
酒造りは
行われていた。
朝廷の
行事やならわしの
規則をかいた『
延喜式』(927)には、
昔からの
方法の
酒造りがくわしく
書かれている。
新嘗会といって、その
年の
収穫をもって
神を
祭る
儀式のためのお
酒だ。
この
当時の
人はねんがらねんじゅうお
酒を
飲んでいるわけじゃない。
朝廷の
儀式とか、
一般の
人たちもお
祭の
時とか、
機会は
限られていた。
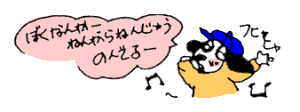 朝廷
朝廷の
酒造りの
技術はだんだんと
世間に
広まって、
奈良時代以降は、
力を
持ちはじめた
寺院や
神社でも
行われるようになった。
平安時代末~室町時代
経済が発達してくると、お酒も商品として見られるようになる。いつのまにか朝廷での酒造りはとりやめられ、かわりに権力者とか、寺院や神社とかが、特定の人に酒造りの権利を与えて、かわりに税金をとる制度になっていった。
室町時代末~江戸時代初め
このあたりで酒造りの技術はぐんと発達したらしい。『多聞院日記』というお寺の記録には酒造りの説明があって、このころすでに低温殺菌法である「火入れ」を行っていたのがわかる。
明治時代初め
びんづめの日本酒が初めて売り出される。
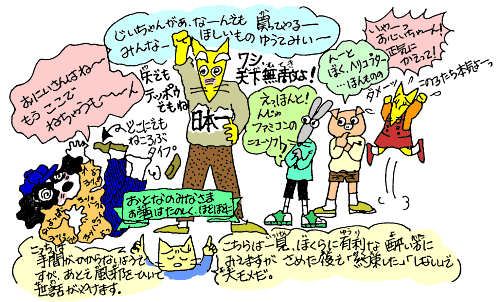
参考にした本
「日本の酒(岩波)」
「東京の地酒」
「日本の銘酒地図」
「日本酒の歴史」
「吟醸酒」
「地酒礼讃」
「酒の博物館」
「酒ざかり日本列島」
「現代日本酒名鑑」
「平凡社大百科事典」
「小平町誌」
「小平市三〇年史」
「たまのあゆみ 第44号 特集多摩の産物」ほかいろいろ
小平市に関すること
多摩に関すること
江戸・東京に関すること
玉川上水・小金井桜に関すること
その他
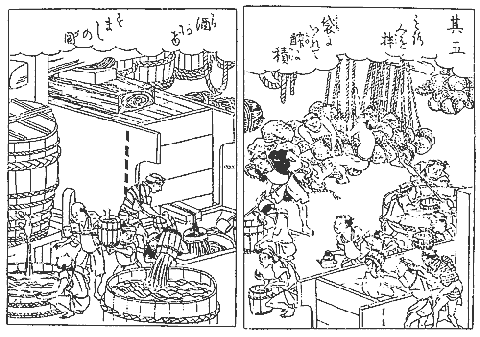

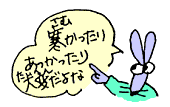

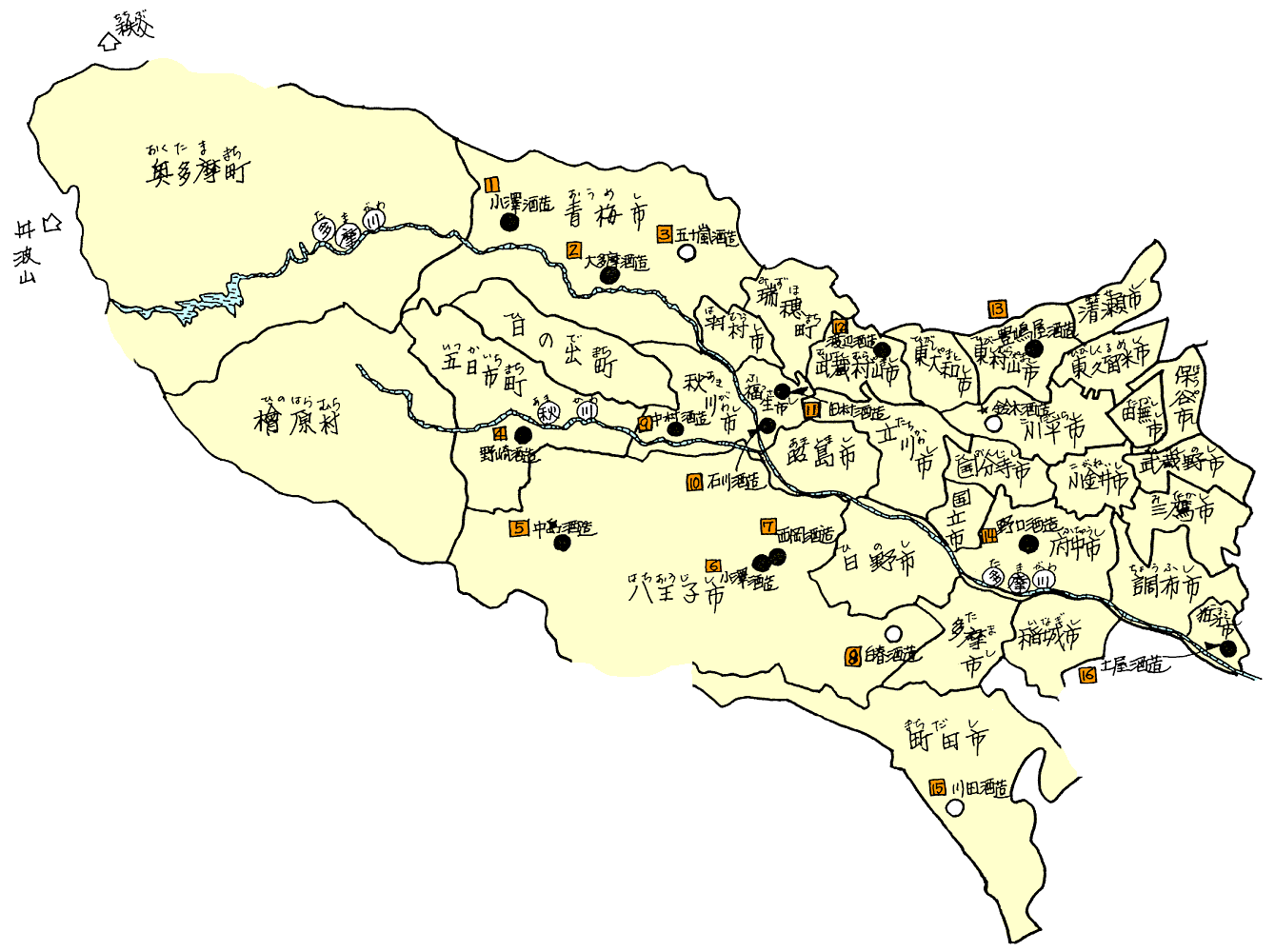










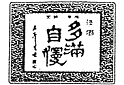





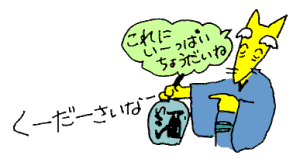
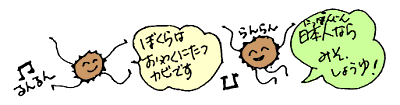
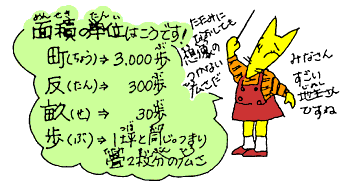
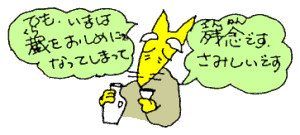

 」がもと。「さけ」という
」がもと。「さけ」という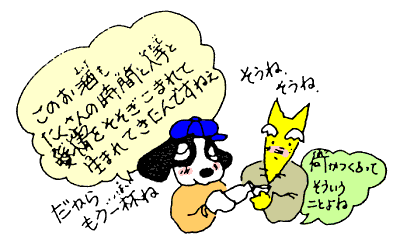
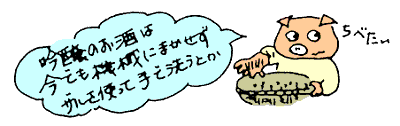
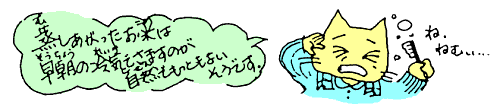
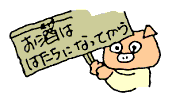
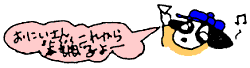 おいしく
おいしく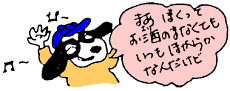 ほろ
ほろ ほろ
ほろ のんべ
のんべ


 まず
まず