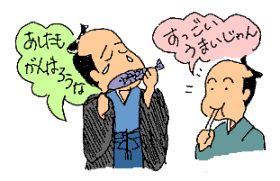八王子千人同心とは
そのむかし、江戸時代の多摩には「八王子千人同心」と呼ばれる人たちがいた。ふだんは大地を耕しつつ、ひとたび幕府から命がくだれば、刀を差し、武士として、懸命に働いた。
「なんだ。八王子の話なの~」と思うのは大間違いだ。
千人同心たちは、多摩のあちこちに散らばって、小平にだって住んでいた。(右の絵を見てちょうだい。)ちなみに、大沼田新田の千人同心はその名を当麻勇蔵さんという。そして、千人同心たちがなした仕事の中でも武蔵国の地誌の調査などは、今でもおおいに、多摩の歴史や文化を研究する人たちの役に立っているんだ。
遠い地方ならともかく、幕府が直接支配する土地で、半分武士、半分農民の組織が活躍した例は他にないんだそうだ。しかも、それが江戸の始まりから終りまで続いたんだからね。一体、どんな人たちだったんだろう?
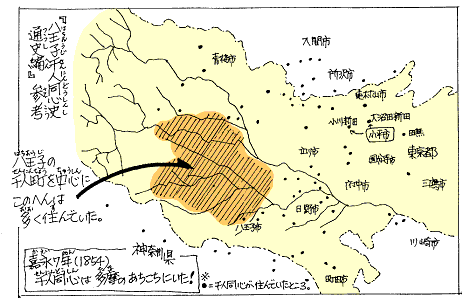
八王子千人同心年表
八王子千人同心年表
| 年 |
できごと |
| 天正10年(1582) |
3月 武田氏、滅びる。武田の旧臣、多く徳川氏に召しかかえられる。
6月 本能寺の変で織田信長、死亡。 |
| 天正18年(1590) |
6月23日 八王子城、落城。
7月 後北条氏、滅びる。
7月29日 甲州小人頭、小人250人、八王子城下に移って、甲州口の警備を命じられる。
8月1日 徳川家康、関東入国。 |
| 天正19年(1591) |
大久保長安、八王子の奉行となる。八王子宿建設。
12月7日 甲州口を守る小人250人増やす。500人になる。 |
| 文禄2年(1593) |
1月 原胤従ら10人の小人頭と、100人の小人衆、八王子城下から、拝領屋敷(八王子市千人町)に移る。 |
| 慶長3年(1598) |
8月18日 豊臣秀吉、死亡。 |
| 慶長5年(1600) |
1月1日 甲州口の守りをかためるため、小人を500人追加。1000人になる。
【八王子千人同心の誕生】
9月15日 関が原の戦い。千人同心も参加。 |
| 慶長8年(1603) |
2月12日 家康、征夷大将軍となり、江戸幕府を開く。 |
| 慶長19年(1614) |
10月 大坂冬の陣。 |
| 元和元年(1615) |
4月 大坂夏の陣。
5月 豊臣氏、滅びる。 |
| 元和2年(1616) |
4月17日 家康、死亡。久能山(静岡県)に葬られる。 |
| 元和3年(1617) |
3月 家康の遺骨、久能山から日光へ移る。 |
| 元和4年(1618) |
4月 八王子郷に代官18人が置かれ、関東30郡を治めることになる。【関東十八代官】 |
| 承応元年(1652) |
6月 千人同心、日光火之番(日光東照宮火消役)を命じられる。 |
| 寛政4年(1792) |
9月3日 ロシア使節ラクスマン、漂流民大黒屋幸(光)太夫を送って根室に来て、日本に通商を求める。 |
| 寛政11年(1799) |
1月16日 東蝦夷、幕府の直轄地(直接治める領地)となる。 |
| 寛政12年(1800) |
3月20日 原半左衛門胤敦、同心や、その子弟100人を率いて蝦夷へ出発。 |
| 享和元年(1801) |
2月10日 同心子弟30人、蝦夷へ出発。 |
| 享和2年(1802) |
2月23日 蝦夷に、蝦夷奉行おかれる。
5月11日 箱館奉行と名をかえる。 |
| 文化6年(1809) |
11月18日 原半左衛門胤敦、千人頭に復帰。 |
| 文化9年(1812) |
2月 原半左衛門胤敦、命をうけ、湯島の大成殿に上がり、多摩郡地誌の調査について話し合う。 |
| 文化11年(1814) |
4月 原半左衛門胤敦、日光勤番中に、地誌を調査する命をうける。
勤番から帰るとすぐそのための人選にかかる。 |
| 文化12年(1815) |
3月 青梅のあたりの地誌を調査する。
世田谷のあたりの地誌を調査する。 |
| 文化13年(1816) |
3月 新町村(青梅市)のあたりの地誌を調査する。 |
| 文政3年(1820)6月~文政4年(1821)4月 |
高麗郡の地誌を調査する。 |
| 文政4年(1821) |
植田孟縉、『武蔵名所図会』を完成させる。 |
| 文政5年(1822) |
4月 『新編武蔵風土記稿』の多摩郡の部、完成。湯島の聖堂に納める。
11月 『新編武蔵風土記稿』の高麗郡の部、完成。湯島の聖堂に納める。 |
| 文政6年(1823)正月~文政7年(1824)11月 |
秩父郡の地誌を調査。原稿できあがる。 |
| 文政8年(1825) |
『新編武蔵風土記稿』の秩父郡の部、完成。湯島の聖堂に納める。 |
| 文政10年(1827) |
原半左衛門胤敦、死亡。81歳。 |
| 天保元年(1830) |
『新編武蔵風土記稿』完成。幕府に献上される。 |
| 天保2年(1831) |
12月 原半左衛門胤禄、相模国津久井県(神奈川県)の地誌の調査を命じられる。 |
| 天保7年(1836) |
12月 原半左衛門胤禄、『新編相模国風土記稿』の津久井県の部、
10巻を献上する。 |
| 嘉永6年(1853) |
6月3日 ペリー、浦賀へ来航する。 |
| 嘉永7年(1854) |
3月3日 日米和親条約結ぶ。その後あいついで他の国とも条約を結ぶ。 |
| 安政3年(1856) |
10月 千人同心、鉄砲方・江川太郎左衛門英敏に入門する。
12月 千人同心へ、200挺の鉄砲が渡される。 |
| 慶応2年(1866) |
7月20日 第14代将軍、徳川家茂、死亡。
10月28日 千人同心、「千人隊」と名前をかえる。近代的な軍隊へとかわってゆく。 |
| 慶応3年(1867) |
10月15日 大政奉還。江戸幕府が朝廷に政権を返す。 |
| 慶応4年(1868) |
1月3日 鳥羽・伏見の戦い(戊辰戦争の始まり)。
4月11日 江戸城、開城。
閏4月10日 千人頭石坂弥次右衛門、自殺。
閏4月20日 千人隊の一部、上野彰義隊に加わる。
5月15日 上野戦争。彰義隊、官軍と戦う。
6月9日 千人隊、解体する。(組織がバラバラになること。)
7月17日 江戸は「東京」となる。
9月8日 元号「明治」となる。 |
八王子千人同心の歴史
1.武田氏の滅亡
天正10年(1582)3月、甲斐(今の山梨県)の武田氏は、織田信長、徳川家康の連合軍との戦いに敗れ、滅んだ。しかし、3か月後の6月には、本能寺の変で信長も死亡。甲斐国は家康の支配するところとなる。甲斐国を治めるにあたって、家康は武田氏の軍隊のつくり方や政治のしかたを積極的に取り入れた。そして、できるだけ、武田氏の旧臣(もとの家臣)たちを採用して、徳川家臣の中に組みこんでいった。
2.後北条氏の滅亡
天正18年(1590)7月、関東に勢力をもっていた後北条氏を滅ぼして、豊臣秀吉の天下統一は完成した。
秀吉は家康に領土替えを申し渡した。8月1日、家康は駿河(今の静岡県)から動き、関東に入国する。そして主君をなくした後北条氏の旧臣たちも、武田氏の旧臣と同じように徳川家臣に取り上げられていった。
3.国境警備の人びと
家康の関東入国をきっかけに、9人の頭に率いられた250人の男たちが、甲州口の警備にあたることになった。この人たちは全て、武田氏の旧臣だ。武田氏に仕えていた時代から、8~9人の頭が2~300人の同心をまとめて国境の警備にあたっていたのだ。
この250人の軍団が、八王子千人同心のもと、なんだ。甲州口の警備にあたって、八王子城下にやって来た。
文禄2年(1593)1月には、千人頭と組頭のおよそ100人は拝領屋敷(今の八王子市千人町)に移り住んだ。しかし、その他の多くの同心たちは広く、多摩の地域に散って住んだ。
4.八王子千人同心、誕生
天正19年(1591)、大久保石見守長安が八王子奉行となって、宿の建設がすすむ中、同心は250人増やされ、500人となった。
さらに慶長5年(1600)には、武田氏の旧臣ばかりではなく、後北条氏の旧臣や、その他の浪人など500人を加え、総勢1,000人。これで八王子千人同心の誕生だ。
ところで、なぜ、この時期に同心の人数が増やされたんだろう。
秀吉が天下をとった後も、決っして世の中は平和じゃなかった。
慶長3年(1598)3月15日、秀吉が死ぬと、徳川と豊臣の間は危険なふんいきになった。豊臣方の石田三成は徳川家に対抗する動きを見せはじめている。そして、この時期、甲斐国は豊臣側の家臣が治めていたから、甲州口から目を離せないわけだ。警備をさらに厳重にするためにも人手が必要だった。
慶長5年(1600)9月、関が原の戦いはおこった。天下分け目の戦いは徳川の勝利だった。しかし、豊臣は秀頼、淀君を中心にまだ大坂城に君臨している。ひきつづき千人同心は甲州口の警備に目を光らせた。
5.八王子千人同心と関東十八代官
後北条氏の支城の中でも、八王子の落城はもっともむごかった。そして、落城後も、八王子のまわりには落武者や野武士がうろついて、安心できない状態だったという。その八王子で徳川支配の新しい町づくりをするには、政治と警備をしっかりとかためなければならない。警備を担当したのが八王子千人同心だ。一方、政治を担当したのは関東十八代官と呼ばれる代官たちだった。彼らもまた命を受けて八王子に住み、関東地方を治めた。
十八代官も武田氏の旧臣がとても多い。それから千人同心と十八代官とをとりまとめ、指揮した大久保石見守長安という人も、これまた武田氏の旧臣だ。
八王子が武田の領地の甲斐国に近いという理由もあるだろうけれど、武田氏の旧臣には、地方を治めるのに、すぐれた能力を持った人が多かった、ということもあるのかもしれない。
6.大久保石見守長安
もともとは、武田氏に仕えた猿楽師という。(猿楽というのは、こっけいな味の芝居。能や狂言のもとになった。)のち、武士の身分にとりたてられた。
武田氏が滅んだあとは、家康に見出され、とりわけ、役人としての能力と、鉱山技術とを認められた。八王子奉行となったのは天正19年(1591)、慶長8(1603)年には、石見守となる。
また、主君であった武田信玄の娘、松姫を、千人同心たちとともにのちまでも見守った。
7.八王子千人同心の組織のしくみ
同心は千人頭が10人、組頭が100人、同心が900人いた。千人頭1人が、組頭10人を受け持ち、組頭1人が9人の平同心をまとめた。千人頭は200~500石取りの旗本の待遇だ。(1石はお米約180リットル)同心は御家人の待遇で、30俵1人扶持~10俵1人扶持の給料をもらった。
10俵1人扶持は家族5人がなんとか食べてゆける給料だった。そして、この給料の基本は、明治維新で千人隊が解散するまで、ほとんど変らなかった。ぎりぎりの給料で武士としてのていさいも整えなければならないのだから、足りない分は農業をしてかせいだ。
拝領屋敷に住むおよそ100人の組頭クラス以外の大部分の同心は、農村に住み、同心の仕事の時以外は農民として働いた。農業をすることを幕府も認めていたんだ。武士と農民の区別がはっきりとしてきたこの時代に、半分武士で、半分農民という千人同心のあり方はとてもめずらしいものだ。
しかし、大宰春台という儒学者は『経済録』(1729年発行)という本の中で、こう言っている。「このごろの武士はぜいたくばかりして、武士の本分を忘れている。その点、千人衆はわずかな給料しかもらっていないけれど、田舎に住んで、耕作し、親や妻子を十分養っている。百姓の苦労を知り、文武に励み、主君に忠誠をちかう、これが本当の武士だ。」
8.八王子千人同心の仕事
八王子千人同心の仕事は、甲州口の警備だけではなかった。慶長5年(1600)の関が原の戦いに参加して、家康と秀忠(2代目将軍)の護衛にあたっているし、慶長19年(1614)と元和元年(1615)の大坂夏の陣・冬の陣でも秀忠の護衛をしている。
また、将軍たちが日光(徳川家康をまつった東照宮がある)にお参りに行く時や、京にのぼる時にも、たびたびお供をしている。
しかし、徳川幕府の力が確かなものとなり、戦乱の心配もなくなった慶安年間以降(1648~)は、甲州口の警戒の心配もかなり少なくなった。そこで、幕府は千人同心に日光の火災の警備を命じた。また寛政時代(1788~)になると蝦夷地(今の北海道)の警備と開拓にも目を向けるようになった。
日光火之番
日光の火の番には、2人の千人頭が50人ずつ、計100人の同心を率いて向かう。往復に8日かかり、火の番は50日おこなう。だいたいこの2ヵ月を単位に交替して番を勤めた。
承応元年(1652)6月に命じられてから、慶応4年(1868)閏4月、日光を官軍にあけ渡すまでの216年間に、およそ1,030回もの日光火の番を勤めた。
蝦夷地の警備と開拓
寛永の頃から、しばしばロシア人が日本に南下して来るようになった。幕府は蝦夷地(北海道)の守りを固めなければならなくなった。その頃の蝦夷といえば、住みつく日本人は少なく、代々、松前藩が治めてきた土地だった。けれど、こういう事情で、寛政11年(1799)、蝦夷は、幕府が直接治めることになり、享和2年(1802)には、その本拠地として、箱館(函館)に奉行所が置かれた。
蝦夷を外国から守るには、土地を開拓し、人が住みついて、警護をしなければならない。
寛政11年(1799)3月、千人頭原半左衛門は、同心の次男、三男を率いて、蝦夷地の守りと開拓の仕事につきたい、という内容の願いを幕府に出した。願いは許され、よく年1月、原半左衛門は100人の同心や、その子弟を連れて、蝦夷地へ向かった。享和元年(1801)にはさらに30人加わった。また安政5年(1858)には、およそ300人が渡っている。けれど厳しい自然と気候の前に、多くの犠牲を出すこととなった。
八王子千人同心は、軍隊としてばかりではない。文化の面でも、いろいろな活やくをした。
寛政の改革(1787~93)で学問にも、武術にも励むことがすすめられ、千人同心でも剣道や槍など、武術の修行が盛んになった。学問の面でも、千人頭や組頭の子弟は江戸昌平坂学問所に通った。
昌平坂学問所
またの名を昌平黌ともいう。寛永7年(1630)、林羅山が上野忍岡に邸地をたまわって、聖廟(昔の中国の有名な学者、儒学の祖の孔子をお祭りするところ)を建てたのが始まり。元禄3年(1690)11月20日、聖廟は神田台に引っ越す。これが湯島聖堂だ。
寛永9年(1797)には、林家8代目の述斎が幕府に、官立(つまり国立だ)の学問所をここに開くことを提案する。
この年の12月1日には「昌平坂学問所」という名がついて旗本、御家人やその子弟のための最高の教育の場になった。「身分の高い低いは問わない。次男、三男でも志があればよい」という、当時としては自由な気風だった。
八王子千人同心でも、千人頭はじめ、同心やその子弟で入学をした者はそうとうな人数だとみられている。
千人同心の文化人の中でも、ひときわ名高い、植田孟縉、塩野適斎もここで学んでいる。
あちこちの藩から優秀な学生が集まり、幕末にはたいそう活気があった。しかし、明治維新で新政府の手に渡り、明治3年(1870)に休校となり、よく年には、閉じられてしまった。
9.幕末の八王子千人同心
安政2年(1855)、千人同心は、老中阿部正弘から、西洋銃の修行を命じられた。慶応2年(1866)には「千人隊」と名前を変え、幕末の動乱の中、西洋式の軍隊を目指す。
千人同心たちもまた、大きな時代の流れに巻きこまれてゆくのだった。
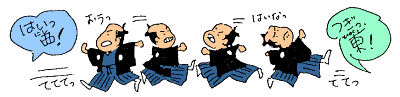 この時期の千人同心はほんと!忙しい
この時期の千人同心はほんと!忙しい
- 天狗党(甲府の賊)の追討に向かう。(1864年11月)
- 芸州・広島へ出陣。(1866年4月)
- 日野農兵隊と共に武州一揆の鎮圧に向かう。(1866年6月)
- 相模国(神奈川県)で暴れている浪人たち、八王子に来るといわれ、全員残らず追討に向かう。(1867年12月)
慶応4年(1868)3月、官軍は甲州勝沼で近藤勇の甲陽鎮撫隊をやぶり、その月11日、八王子にはいった。
千人隊は官軍参謀板垣退助に兵器をさしだし、新政府につつしんで従った。隊士の中には上野彰義隊に加わったり、函館の五稜郭にこもって、最後まで戦う者もあった。また、最後の日光火の番の頭となった石坂弥次右衛門義礼は、日光を官軍にあけわたした責任をとって自害。60歳だった。
この年6月9日、280年近く続いた八王子千人同心の歴史は終わりを告げる。ある者は徳川家に、またある者は新政府に属することとなったけれど、大多数は武士を捨て、農民を選んだ。
『新編武蔵風土記稿』
八王子千人同心がのちの世にのこした仕事
植田孟縉、塩野適斎、並木以寧、設楽三蔵、松本斗機蔵などの組頭たちはまた、千人同心の中でも私塾を作り、子弟たちに漢学や書道を教えた。組頭は、組をまとめてゆくためにも学問に、武術に励む必要があったからだ。
文化文政の頃には、幕府の地誌編さんの仕事に参加して『新編武蔵風土記稿』や『新編相模国風土記稿』という本のため、調査にあたっている。知識と体力のいる仕事なのだけれど、やりとげられたのも、ふだんのこういう努力の結果かもしれないね。
塩野適斎 千人同心・有名人 その1
字は所左衛門。名は轍。安永4年(1775)、八王子千人同心の組頭の河西家に生まれ、同じ組頭の塩野家の養子になる。文学者としても、剣術家としても、すぐれた才能があった。
文化11年(1814)9月から『新編武蔵風土記稿』のための調査の仕事に参加した。
また、長い間、調べたり、集めたりした史料をもとに、文政10年(1827)に『桑都日記』(正編)を、天保5年(1834)には『桑都日記 続編』をあらわした。
他にも盛んに文章を書いた。弘化4年(1847)11月16日、73歳で死亡。八王子市内の極楽寺に葬られた。
植田孟縉 千人同心・有名人 その2
宝暦7年(1757)12月8日、熊本自庵の子として江戸屋敷で生まれ、安永4年(1775)11月、19歳の時、八王子千人同心組頭、植田元政の養子になった。字は十兵衛。
塩野適斎らと一緒に『新編武蔵風土記稿』の仕事にたずさわる。その間、文政6年(1823)10月には『武蔵名勝図会』(多摩郡を中心とした地誌)をあらわして、昌平坂学問所の林述斎に献上している。
また、日光火の番のあいまに調べて書いた地誌『日光山志』(5巻)では日光の植物や動物をていねいに観察して写生。
『日光山志』は天保8年(1837)、孟縉81歳の時、幕府の許しを得て刊行された。渡辺崋山、椿椿山など、当時の有名な画家がさし絵をかいている。
他にも、
『 鎌倉攬勝考』(10巻 ): 鎌倉の地誌。
『 日光名勝考』(10巻 ): 日光の地誌。
『 鎌倉名勝図会』(10巻 ): 鎌倉の地誌。
『 浅草寺旧跡考』(5巻 ): 寺院の旧跡について書かれたもの。
『 横山史跡拾遺』(5巻 ): 八王子の横山の史跡について書かれたもの。
といった著作があって、なんてエネルギッシュな人なんだ! と驚いてしまう。
天保14年(1843)12月14日、87歳で死亡。八王子市内の宗徳寺に葬られた。
『新編武蔵風土記稿』とは、何なんだ?
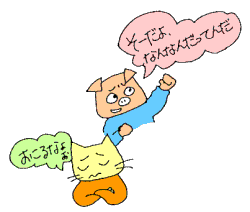
「
風土記」とは、
地方ごとに
風土や
文化など、その
土地の
様子を
記したもののことをいう。つまり、「
地誌」だね。
日本では、
和銅6
年(713)、
元明天皇の
詔で、
諸国に
地名の
由来だの、
産物だの、
伝説などの
記録を
出させ、
編さんしたのが
風土記の
初めて。でも、その
中できちんと
残っているのは『
出雲国(
今の
島根県東部)
風土記』ぐらい。
文化7
年(1810)、
林述斎は
新しい
風土記を
作りましょう!と
幕府に
提案。さっそく
昌平坂学問所に
地理局をつくり、
編さんの
事業にとりかかった。
『
新編武蔵風土記稿』は、その
地誌編さん
事業の
最初のものとして、できあがったんだ。
頭に“
新編”とあるのは、
和銅の
頃の
風土記に
対して、「
新しく
編さんした」という
意味。“
稿(
下書きの
意味)”の
字が
最後についているのは、これを
資料として、
完成書をつくろうと
思っていたからなんだ。(
実現しなかったんだけどね。)
けれど
文化文政時代の
武蔵国の
村々を
書きつくし、
現在、このへんの
歴史・
文化を
研究するのに
欠かせない、ねうちのある
資料だ。
全巻266
巻(うち、
編さん
者の
名を
記した
付録が1
巻)。
文化7
年(1810)に
稿をおこし、
文政11
年(1828)に
稿を
終え、
少し
誤りを
正して、
天保元年(1830)、
幕府に
献上された。
 費
費やした
時間、20
年。
仕事にたずさわった
人は40
名あまり。
編さんにあたって、
幕府は
村々の
役人に
連絡して、「
地誌取調書上」(
調査書だね)を
提出させ、
武蔵国以外の
国や
郡からも
必要な
資料を
集めた。そして、この
調査書をもとに2~3
人1
組で、
調査員が
直接村々に
出向いて、
住んでいる
人たちに
聞いたり、ひとつひとつ
事実を
確かめていった。だから、
内容はとてもくわしく、かつ
正確だ。
調査のさいには「
自然に
人物、
神社、
寺、
名所、
旧跡、
旧家(その
村につづく
古い
家柄)、
古文書にいたるまでことごとく
調査し、
記録」するように
命令がでていたからね。
『
新編武蔵風土記稿』が
完成した
天保元年(1830)には、
息つくひまなく『
新編相模国風土記稿』の
編さんが
始まっている。
天保12
年(1842)に
完成。126
巻。
そして
八王子千人同心は『
新編武蔵風土記稿』の
多摩郡と、ついで『
新編相模国風土記稿』の
津久井郡(
今の
神奈川県北部)の
実地調査を
命じられたのだった。
これが『新編武蔵風土記稿』のなかみだ!!
さて、『新編武蔵風土記稿』。実際のなかみにはどんなことが書いてあるのかな、と。では、小平市のはじまり、小川村のところをちょいとのぞいてみようかな。
小川村は、多摩郡の東北、村山郷にある。東は小川新田(今の喜平町のへん)、南は南野中新田と榎戸新田(国分寺市)、西は砂川(立川市)、芋窪、高木(東大和市)の村々、北は野口村(東村山市)。砂川村から野口村のあたりは、野火止用水が境界だ。
東西およそ一里(四キロメートルくらい)。南北は二町(二二〇メートルくらい)余り。四方平らな土地で、人家は二二〇軒。林が多く、水田はなく、陸田だけだ。
村の中には古い街道があって、道幅は二間(三・六メートル)ばかり。府中から国分寺、恋が窪などの村を通ってここに通じ、北へ折れると久米川の方へ行く。鎌倉から陸奥(青森県)への道だ。
この村が開かれた時のことをたずねると、小川九郎兵衛という人が岸村にいて、武蔵野の石塔ヶ窪という所を開発する願いを出した。小川という人が開いたので、小川新田といったけれど、その後、子孫が新田を開いたので、小川村というようになった、という。
高札場(高札をたてる場所) 村の中ほど
橋 小川橋ほかニか所。玉川上水にかかっている。
水利(水の便利)
玉川上水・砂川村からはいり、小川新田にそそぐ。
野火止用水・これも砂川村からはいり、となり村との境界になっている。
神社
神明宮 小川村の鎮守。例祭は九月十九日。神主は殿ヶ谷村(瑞穂町)の阿豆佐美天神の神主、宮崎なんとか、という人の配下の、宮崎加賀という人だ。
日吉山王社 江戸麹町山王の神主、樹下氏の配下、山口大和という人が神主だ。
寺院
小川寺 江戸市ヶ谷(新宿区)月桂寺の末寺。碩林という僧が開いた。建てたのは小川九郎兵衛なので、その名をとって、小川寺とする。臨済宗。
妙法寺 中藤村(武蔵村山市)長円寺の末寺。開いた僧はわからないが、今の名主、弥四郎の祖先と吉野又兵衛の二人が力を合わせてつくったそうだ。
小川一小(小川町一丁目)のあたりにあったけれど、明治四二年八月国分寺市にひっこした。
旧家
百姓弥四郎 今の名主。祖先の小川次郎助義は治承の頃(平安時代)戦さで手がらをたてた。その子孫九郎兵衛がこの村をひらく。もと、後北条氏家臣。武蔵七党の西党に小川の名あり。
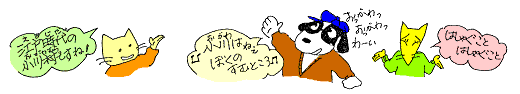
多摩郡の調査をした千人同心メンバー表
原半左衛門胤敦(この仕事の責任者。千人頭。)
原半左衛門胤廣(胤敦の弟で、その死後、原家11代目をつぐことになる。)
原新七郎胤禄(胤廣の後継ぎで、原家12代目…つまり原家は3代にわたってこの仕事にたずさわったわけ。)
植田十兵衛孟縉(山本組、組頭。)
塩野所左衛門轍(原組、組頭。つまり適斎。)
秋山喜左衛門定克(石坂組、組頭。)
筒井恒蔵元恕[怒](河野組、組頭。)
風祭彦右衛門公寛(志村組、組頭。)
八木孫右衛門[甚右衛門とも]忠譲(志村組、組頭。)
神宮寺豊五郎正敷(荻原頼母組、組頭。)
河西井三郎愛貴(山本組、組頭。)
原利兵衛胤明(原組、組頭。原半左衛門家の親せき筋ではないか、と。)
林述斎が地誌編さんの事業をはじめて2年後の文化9年(1812)2月、千人頭、原半左衛門胤敦は、命を受けて、湯島の大成殿でおこなわれる多摩郡の地誌の編さんについての話し合いに加わるようになった。さらに文化11年(1814)4月には、地誌の調査をするよう命令がおりて、原半左衛門はただちに参加者の顔ぶれを選んだ。メンバーは皆、組頭として、ひときわ学問もあり、ものの見方もしっかりしている人たちばかりだった。
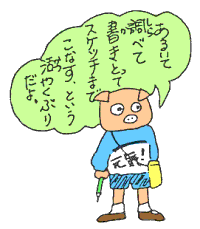 千人同心がかかわった地誌の調査は、
千人同心がかかわった地誌の調査は、
武蔵国のうち 多摩郡 40巻
高麗郡 10巻
秩父郡 20巻
以上の編さんを文政8年(1825)までに終え、『新編武蔵風土記稿』は完成。さらに天保4年(1833)から天保7年(1836)までは原胤禄を責任者に『新編相模国風土記稿』の津久井県(郡)の調査をおこなった。実に20年の月日だった。
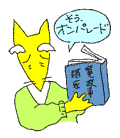 その人物の名前について、ど~しても読みがわからないものについては、『寛政重修諸家譜』の読み方にしたがいました。これは江戸時代、寛政年間(1789~1801)に幕府が編さんした、お目見え以上の武士たちの家系の本で、名まえ、名まえのオンパレードだ。
その人物の名前について、ど~しても読みがわからないものについては、『寛政重修諸家譜』の読み方にしたがいました。これは江戸時代、寛政年間(1789~1801)に幕府が編さんした、お目見え以上の武士たちの家系の本で、名まえ、名まえのオンパレードだ。
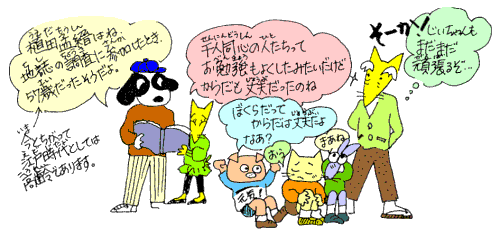
「桑都日記」に見る多摩郡調査の日々
わたし、塩野適斎は、同僚原利兵衛胤明とともに命をうけて、多摩の地誌の調査をしているのである…。
4月8日 雨
戸倉村にて
名主、
常右衛門に
道案内をたのんだら…
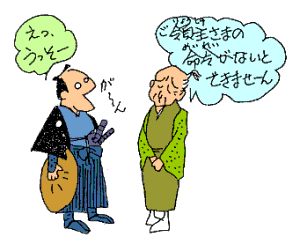 乙津村
乙津村にて
名主、
弥兵衛いわく、「この
里は13の
部に
分かれて、
部ごとに
1人ずつ、
村役人がいます。
全員あつまってからでないと、あなたのご
質問に
答えるわけにはゆきません。」

その後…
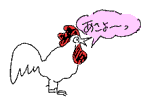 13人全員集まってから、この村についていろいろ質問する。半分もすまないうちにニワトリが鳴いて午前5時。つい夢中になって徹夜してしまった。
13人全員集まってから、この村についていろいろ質問する。半分もすまないうちにニワトリが鳴いて午前5時。つい夢中になって徹夜してしまった。

4月9日 ちょびっと雨
霧雨の
中、
吊り
橋を
渡る。
梁に
柱はなくて、
長さは18メートル。
水底まで9メートル。
渡る
時、
目がくらみ、
足がちぢむ。おそれおののいて、
息を
殺して
渡る。

4月10日 出かけるのに苦労なほどの大雨!
合羽を
着て、
杖を
持ってゆく。
坂道のぬかるみに1
歩あるいては
立ち
止まり、
木の
下で
休み、
石の
上でうずくまり、
書きしるしている。

4月11日 ようやく晴れ
養沢から
御岳山に
向かう。とちゅう
高さ6メートルの
岩がどーん。
腹ばいになってのぼる。

4月12日 晴れ
御岳神社の調査をしてから、大岳山に登る。標高1,267メートル。のぼりはけわしく、岩場では木をかけて渡ったり、腹ばいになって渡ったり。
戻りに近道をしたら、踏み跡はあるけれど、道はないっ!
胤明はふくらはぎをくじいたり、何度もころんだりして、もう大変。とっても、とっても疲れた1日だった…。

4月13日 晴れ
胤明と
記録をとりつづけ、
休まず。
御岳村滝本の
名主の
家で
夕食に
山女魚がでて、とってもおいしかった!
夜、10
時まで
聞きとりをする。
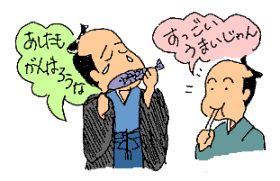
4月14日 晴れ
 沢井村
沢井村をめざし、
永久橋という
橋を
渡る。この
橋もすごかった。
舟に
乗っているみたいにめちゃくちゃゆれる
橋で、おまけにまん
中のつなぎ
目は
古くなって、くさっている。
この時、2人が歩いた地域は今の五日市町~青梅市のあたり。その奮闘ぶりがしのばれる、適斎の日記でありまする。
参考にした本
「八王子千人同心史」
「わが町の歴史 八王子」
「多摩のあゆみ 第23号 特集八王子千人同心」
「江戸幕府八王子千人同心」
「八王子市史 下巻」
「江戸時代の八王子宿」
「八王子物語 中」
「新編武蔵風土記稿」
「桑都日記 続編」そのほか、いろいろ…。
小平市に関すること
多摩に関すること
江戸・東京に関すること
玉川上水・小金井桜に関すること
その他
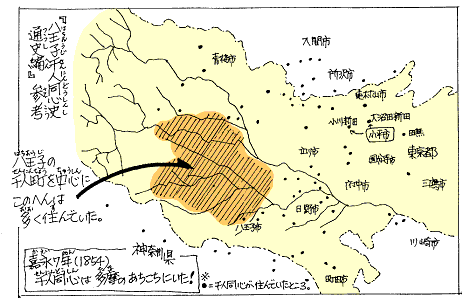
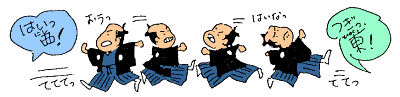 この
この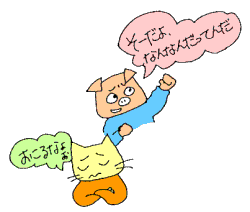 「
「
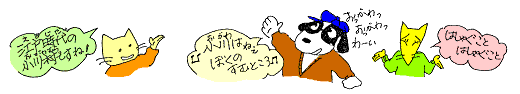
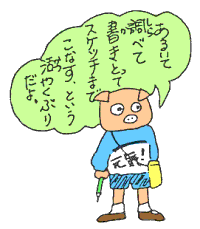
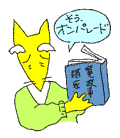 その
その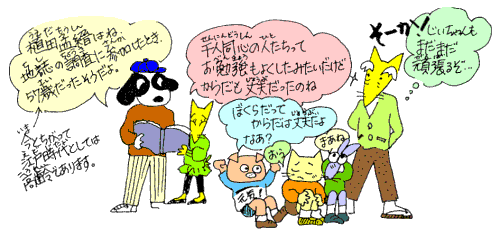
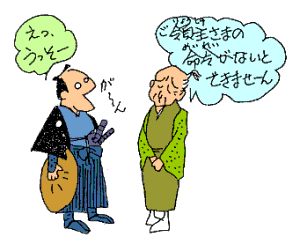

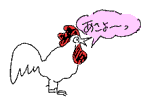 13
13