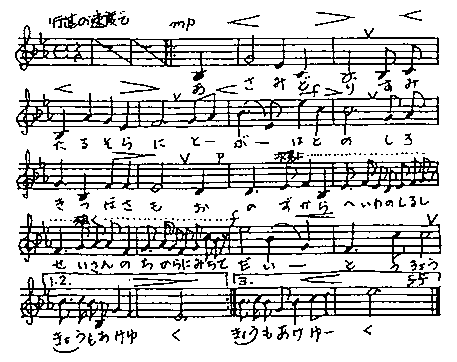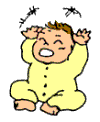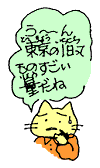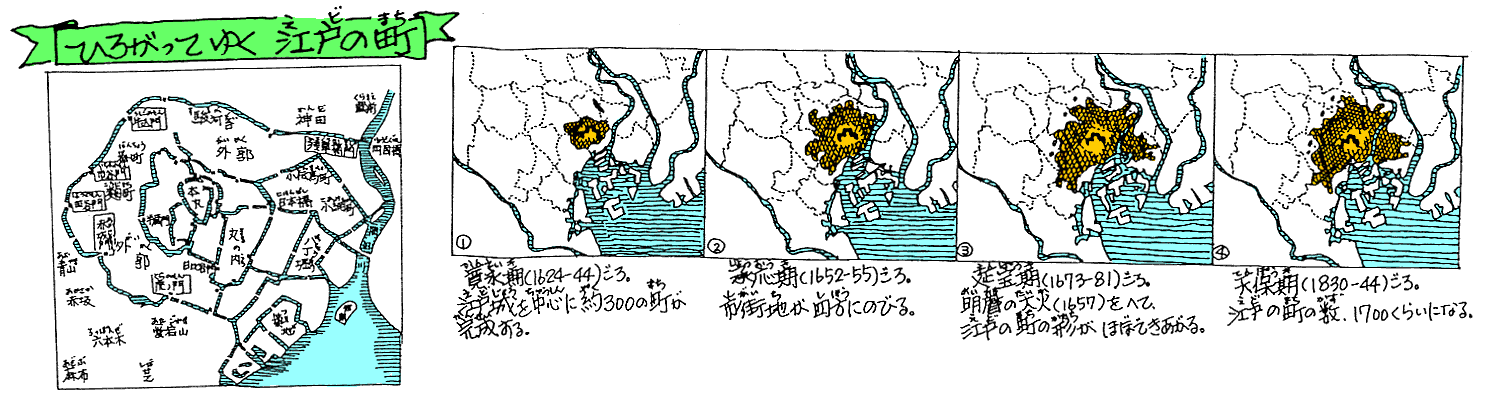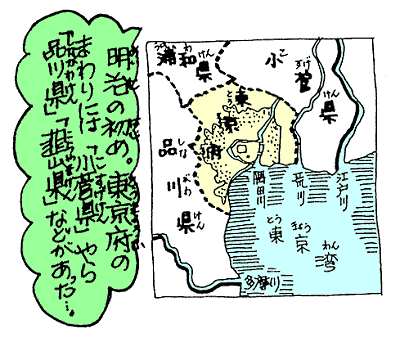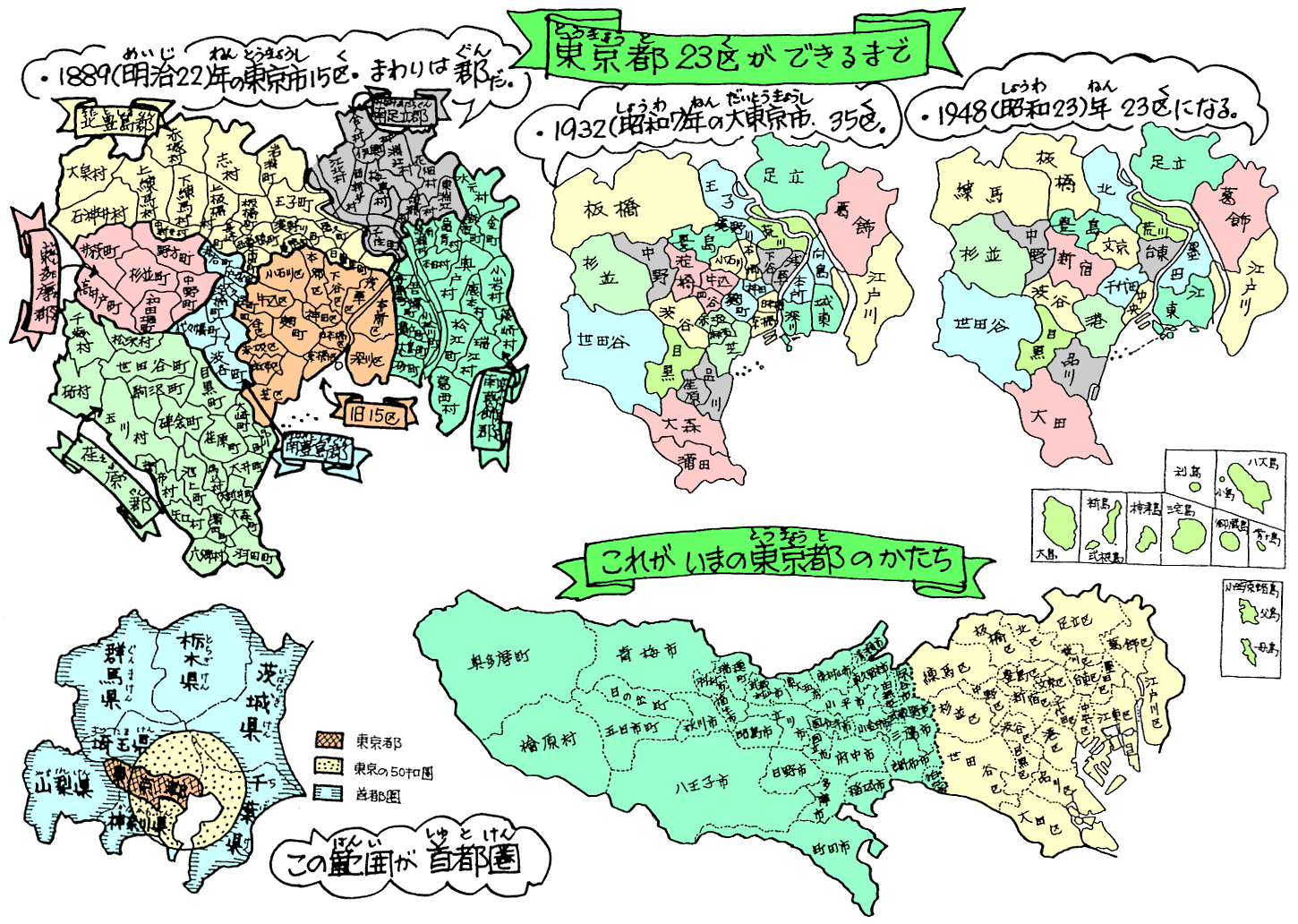東京のなりたち
東京って、はじめから東京だったわけじゃない。「東京」という名前だって明治になってからついたものだもの。西の京(京都)に対して江戸を東の京にしよう、という意味で「東京」と呼んだのが、この町の地名になってしまった。
形だってどんどん変わっていった。東京のもとになったのは、江戸の町なのだけれど、それはごく限られた範囲でしかなかった。江戸城を中心に山手線の内側くらいのものだった。
関東大震災や、交通の発達、コレラの流行などその時代、その時代のいろいろな事情が東京を大きくしていったんだ。
ほぼまあるくまとまっていた江戸の町は、明治になって東京府になると、まわりの郡部が加わり、明治の半ばには三多摩が神奈川県から編入され、今のように東西に長い形になった。
形ばかりでなく、風景もずいぶん変わったようだ。まず関東大震災(大正12年)で東京市内に残っていた江戸のおもかげは焼きつくされてしまったというし、太平洋戦争(昭和16~20年)では、明治、大正と築きあげた町なみが谷と丘ばかりの焼野原になってしまったという。
東京はそのつど再建されてきたけれど、戦後のめざましい変化のきっかけはなんと言っても東京オリンピック(昭和39年)だ。この時、幹線道路の整備や、施設の建設がおこなわれて、町づくりがすすんだ。
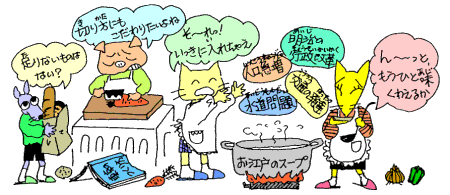
東京まちづくり年表


東京まちづくり年表
| 年 |
できごと |
| 先土器時代 |
東京に人間が住みはじめる。小平の鈴木遺跡、杉並の高井戸東遺跡、調布の野川遺跡はこのころのもの。 |
| 縄文時代 |
大森貝塚などができる。 |
| 弥生時代 |
稲作文化が伝わる。 |
| 奈良時代 |
武蔵国府が置かれる。(今の府中市)
武蔵国分寺が建てられる。(今の国分寺市) |
| 平安時代 |
武蔵の豪族、秩父氏から出た一族が江戸に住みつき、江戸氏を名のる。(1100年頃) |
| 1457(長禄元) |
4月 太田道灌、江戸城を築く。 |
| 1486 |
7月26日 扇谷上杉定正、家臣の太田道灌を殺す。 |
| 1524(大永4) |
1月14日 北条氏綱、上杉氏をやぶり、江戸城にはいる。 |
| 1590(天正18) |
7月 小田原北条氏滅ぶ。
8月1日 徳川家康、江戸入りする。 |
| 1592 |
家康、江戸城の修築にかかる。 |
| 1603(慶長8) |
2月12日 家康、征夷大将軍となり、徳川幕府をひらく。 |
| 1624(寛永元) |
この頃から、大名が妻や子を江戸に住まわせるようになる。 |
| 1635(寛永12) |
大名の参勤交代の制度が整う。 |
| 1657(明暦3) |
1月18日 「明暦の大火」。江戸城の本丸、二の丸、三の丸も焼けおちる。 |
| 1722(享保7) |
江戸の町の数、1672町にまで増える。 |
| 1818(文政元) |
9月26日 「江戸朱引図」作られる。これによって江戸の範囲をはっきりさせる。 |
| 1867(慶応3) |
10月15日 15代将軍徳川慶喜、大政奉還する。 |
| 1868(慶応4・明治元) |
4月11日 江戸城、無血開城する。
7月17日 詔により、「江戸」は「東京」となる。
9月8日 元号が「明治」となる。(一世一元の制)
9月20日 明治天皇、京都を出発し、10月13日、東京に到着。「江戸城」を「東京城」と改める。 |
| 1869(明治2) |
2月19日 東京を朱引内(市街地)と朱引外(市外の村々)にわける。
3月16日 市街地を50区(1区あたり1万人めやす)に分ける。
3月28日 一度京都にもどっていた明治天皇、再び東京城(皇城)にはいり、太政官を置く。(東京遷都)
12月25日 東京~横浜で電報のとりあつかい始まる。 |
| 1871(明治4) |
7月14日 廃藩置県おこなわれる。 |
| 1872(明治5) |
2月26日 銀座・京橋・築地に大火事。
4月 大区小区制、おこなわれる。
5月22日 多摩郡のうち、南・北・西多摩郡の大部分を神奈川県に移管する。
9月10日 東多摩郡が神奈川県から東京に編入。
9月12日 新橋~横浜に鉄道開通する。 |
| 1873(明治6) |
10月 銀座の大通りにレンガ街ができる。 |
| 1874(明治7) |
1月25日~3月8日 東京府内の大区小区制を改め、11大区103小区に編成。
12月18日 銀座にガス灯がつく。 |
| 1878(明治11) |
1月11日 伊豆七島が静岡県から東京府へ編入。
7月22日 郡区市町村編成法、公布。
11月2日 大区小区制、とりやめとなり、東京府は15区6郡となる。
11月8日 郡区市町村編成法により、神奈川県に北・南・西の三多摩郡が成立。 |
| 1880(明治13) |
10月8日 小笠原諸島が内務省から東京府へ編入。 |
| 1882(明治15) |
6月25日 新橋~日本橋に東京馬車鉄道が開業。 |
| 1883(明治16) |
7月28日 上野~熊谷に日本鉄道(今の高崎線)が開通。 |
| 1885(明治18) |
3月1日 品川~赤羽に、日本鉄道山手線(今の山手線・赤羽線)が開通。 |
| 1888(明治21) |
8月 東京市区改正条例、公布。 |
| 1889(明治22) |
2月11日 大日本帝国憲法、公布。
4月1日 市制・町村制、公布。
4月11日 新宿~立川に甲武鉄道(今の中央線)が開通。 |
| 1890(明治23) |
5月17日 府県制・郡制、公布。 |
| 1893(明治26) |
4月1日 三多摩が神奈川県から東京府へ編入。 |
| 1894(明治27) |
8月1日 日清戦争、はじまる。(1895年4月17日まで) |
| 1896(明治29) |
4月1日 南豊島郡と東多摩郡が合併して、豊多摩郡となる。 |
| 1898(明治31) |
10月1日 市制特例がとりやめられ、東京市役所が開かれる。 |
| 1899(明治32) |
7月1日 東京府に郡制を施行。郡役所が置かれる。 |
| 1903(明治36) |
8月22日 品川~新橋に市街電車(路面電車)が走りはじめる。 |
| 1904(明治37) |
2月10日 日露戦争、はじまる。(1905年9月5日まで) |
| 1911(明治44) |
8月1日 東京市、市街電車を買収して市営にする。 |
| 1914(大正3) |
12月20日 東京中央停車場(今の東京駅)が完成。 |
| 1919(大正8) |
4月5日 都市計画法、公布。 |
| 1921(大正10) |
4月27日 東京市長、後藤新平「8億円計画」を発表。 |
| 1922(大正11) |
10月6日 蒲田~池上に池上電気鉄道(今の池上線)が開通。 |
| 1923(大正12) |
3月11日 目黒~丸子に目黒蒲田電鉄(今の目蒲線)が開通。
9月1日 関東大震災。 |
| 1924(大正13) |
1月18日 東京市営バスの運転はじまる。「円太郎」のあだ名がつく。
10月8日 小笠原諸島が内務省から東京府へ編入。 |
| 1927(昭和2) |
12月30日 上野~浅草に日本初の地下鉄(今の営団地下鉄銀座線)が開通。 |
| 1930(昭和5) |
3月24日 (関東大震災からの)帝都復興祭はじまる。 |
| 1931(昭和6) |
9月18日 満州事変おこる。 |
| 1932(昭和7) |
10月1日 東京市ととなり合う、5郡82町村を合併。東京市は15区から35区になる。大東京市の誕生だ! |
| 1933(昭和8) |
8月1日 渋谷~井の頭公園に京王帝都電鉄井の頭線が開通する。
この夏、「東京音頭」が全国に流行する。 |
| 1937(昭和12) |
7月7日 日中戦争はじまる。 |
| 1939(昭和14) |
浅草~渋谷に地下鉄開通。 |
| 1941(昭和16) |
12月8日 太平洋戦争はじまる。 |
| 1943(昭和18) |
7月1日 東京府・東京市がひとつになって、東京都が誕生。 |
| 1945(昭和20) |
3月10日 東京大空襲。
8月15日 太平洋戦争おわる。 |
| 1946(昭和21) |
11月3日 日本国憲法、公布。(昭和22年5月3日施行) |
| 1947(昭和22) |
3月15日 東京35区を22区に整理する。
8月1日 板橋区の一部が分かれて、練馬区となり、東京23区になる。 |
| 1952(昭和27) |
9月17日 10月1日が「都民の日」と定められる。 |
| 1953(昭和28) |
4月 東京都、高速道路計画をたてる。
9月1日 町村合併促進法、公布。 |
| 1956(昭和31) |
4月26日 首都圏整備法、公布。 |
| 1957(昭和32) |
8月 東京都の都市人口、世界第1位となる。(851万人8、622人)
12月16日 夢の島でゴミの埋め立てをはじめる。 |
| 1958(昭和33) |
12月23日 東京タワー完成。333メートルの高さの塔は当時世界一だった。 |
| 1962(昭和37) |
2月 東京都の人口、1,000万人をこえる! |
| 1964(昭和39) |
9月17日 浜松町~羽田空港に東京モノレール開通。
10月1日 東京~新大阪に東海道新幹線が開通。
10月10日~24日 オリンピック東京大会が開かれる。 |
| 1965(昭和40) |
3月31日 淀橋浄水場、閉じられる。
新宿は副都心として開発されることになる。 |
| 1968(昭和43) |
4月12日 千代田区に日本初の超高層ビル(地上36階)「霞が関ビル」完成。 |
| 1969(昭和44) |
6月9日 東京都公害防止条例定められる。 |
| 1970(昭和45) |
この夏から都内各地で光化学スモッグの被害がでる。
10月26日 公害局ができる。 |
| 1971(昭和46) |
9月28日 都知事「ゴミ戦争宣言」をおこなう。 |
| 1972(昭和47) |
10月26日 東京都、「自然の保護と回復に関する条例」を公布。 |
| 1979(昭和54) |
8月31日 マイタウン構想懇談会が初めて開かれる。 |
| 1983(昭和58) |
東京都、「東京地域公害防止計画」を発表。 |
| 1984(昭和59) |
東京都、「緑の倍増計画」を発表。 |
| 1985(昭和60) |
9月30日 東京都庁、西新宿へ引っこしが決定。 |
| 1987(昭和62) |
6月3日 東京都、「臨海部副都心開発基本構想」を発表。 |
| 1991(平成3) |
3月9日 西新宿の東京都新庁舎の落成式(完成の祝いの式)、おこなわれる。 |
| 1993(平成5) |
8月26日 東京湾にレインボーブリッジが開通する。 |
| 1995(平成7) |
11月1日 臨海副都心と都心部を結ぶ「ゆりかもめ」が開業する。 |
| 1997(平成9) |
4月21日 東京湾アクアラインの下り線の工事がおわる。 |
| 2000(平成12) |
12月12日 都営地下鉄大江戸線が全線開業する。 |
| 2001(平成13) |
4月1日 東京都公害防止条例を全面的にかえた「都民の健康と安全を確保する環境に関する条例」を一部をのぞいて施行する。 |
| 2005(平成17) |
2月16日 地球温暖化防止のための京都議定書を発効する。 |
東京のできるまで 江戸時代
家康が来る前の江戸
奈良~鎌倉時代まで、武蔵国の中心は府中だった。そのころの江戸は、名前のとおり「入江の入り口」。草のおい茂る漁村でしかなかった。そこに秩父流平氏の一族が住みついて「江戸氏」を名のった。1180(治承4)年、「吾妻鏡」(鎌倉幕府の記録)の中に江戸太郎重長の名がのって、“江戸”は、歴史の中に初めて姿をあらわす。
室町時代にはいると扇谷上杉の家臣、太田道灌が江戸氏をしりぞけ、この地にはいった。そして、1457(長禄元)年4月、江戸氏の館跡に江戸城を築く。しかし、その評判をねたんだ主人の上杉定正に1486(文明18)年、道灌は殺されてしまった。
その後、伊豆におこった後北条氏が勢力を伸ばし、1524(大永4)年正月には、北条氏綱が江戸城に入城。戦国時代の江戸は後北条氏の支配にはいる。
武蔵国の一地方にすぎない「江戸」が日本の中心となっていくのは徳川家康の登場をまたなければならない。
太田道灌 (1432年~1486年)
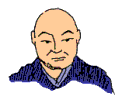 相模国
相模国の
生まれ。
室町時代の
武将。
扇谷上杉家の
重臣であった。
江戸城をはじめ、
岩槻城・
河越城の
建築をおこなう。
若いころから、めきめきとその
実力をあらわしたが、
主人、
上杉定正にねたまれ、55
才の
時、
殺されてしまった。
道灌はすぐれた
武将であっただけではなく、また、
歌を
愛する
人でもあった。
「わたしの
粗末な
家のあるところは
松原がつづき、
海が
近く、
軒の
端には
富士山の
姿が
見えます。」と
当時の
江戸の
風景を
歌によみ、
天皇から「
武蔵野は
野草が
茂るばかりと
思っていたけれど、このような
言葉の
花も
咲くのだなあ」と
感心された。
道灌は
武蔵野の
花や
草をよく
歌によんだ。
徳川家康 (1542年~1616年)
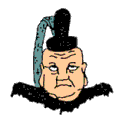 江戸幕府
江戸幕府、
初代将軍。
6
才のとき
尾張の
織田家の、
次いで
駿河の
今川家の
人質となる。このときの
苦労ががまん
強い
性格をつくった?
1560
年、やっと
国元の
岡崎にもどり、
織田信長と
手をむすんで
三河を
平定した。1582
年には
武田氏をほろぼして、
駿河も
手に
入れる。1590
年、
天下統一をめざす
豊臣秀吉に
協力して
小田原の
後北条氏を
攻めおとしたあと、その
領地だった
関八州を
与えられ、
江戸に
居城を
移した。
秀吉としては
一大勢力である
家康を
京の
都から
遠い
地方に
国替えさせて、
豊臣家の
安泰をはかろうとしたんだろう。
けれど
秀吉の
死後、
家康は
征夷大将軍となって
幕府をひらき、
豊臣方と
戦ってこれをやぶり、
天下統一をはたした。
江戸時代
家康のまちづくり
1590(天正18)年、後北条氏が滅び、豊臣秀吉が天下統一。その年8月には大大名、徳川家康が国替えとなって江戸にのりこんで来た。そのころの江戸は、城の東は入江や茅野原の湿地、西には雑草だらけの原野がつづくというありさまだった。
1603(慶長8)年に征夷大将軍となり、江戸に幕府を開くと家康は天下人として城と町の大整備を開始。
大名たちに命じて人手をあつめ、神田山(今の千代田区駿河台)をきりくずし、東の海辺を埋め立てて、市街地をつくった。今、下町と呼ばれるあたりだ。
江戸城の修理・建築は1604(慶長9)年から1638(寛永15)年まで34年間続いた。青梅街道は、江戸城の白壁をぬるための石灰を青梅の成木から運ぶため開けていったとか。
こうして江戸は人とお金を使い、家康・秀忠・家光の3代かかって町の基礎をつくりあげた。
勤交代で人口増加
3代将軍家光の時、「妻子在府の制」(大名の妻と子は江戸に置く。つまり人質)と「参勤交代」が制度として整った。大名は自分の国と江戸とに、1年置きに住まねばならず、江戸にはそのための屋敷が建てられ、家臣たちも住みついた。さらにその人たちが使う品物を作ったり、売ったりする町人も集まり、江戸はにぎやかになってきた。
明暦の大火とまちづくり
1657(明暦3)年正月18日、大火事がおこり、江戸の町は灰になってしまった。江戸城の大天守だって焼けおちた。
幕府は江戸の建て直しの大計画をたてた。一番の目的は「防火」だ。密集地の整理がおこなわれた。まず、大名屋敷をはじめ、寺や神社など、江戸城のまわりの建て物はみんな城外に移された。町の中には「火除地」という、火事を広げないための空き地を多く設けた。広小路と言われる大きな通りも作った。
こうして江戸の中心から、建て物が順ぐりに押し出され、押し出されして、この時、江戸の町の範囲は風船みたいにふくらんだ。
振袖火事のいわれ
明暦の大火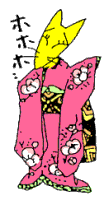 は、別名「振袖火事」という。
は、別名「振袖火事」という。
 浅草の大きな商人の娘が、上野の花見で見かけた若者にひと目ぼれ。恋わずらいがもとで1655(承応4)年1月16日に死んでしまった。その娘の振袖が古着屋から別の娘にわたると、その人もよく年の1月16日に病死。次にこの振袖を手に入れた娘もよく年の1月16日にこれまた病死。そこで3人の娘の家が一緒になって本郷丸山町の本妙寺境内で問題の振袖を焼いたところ、火のついたまま、にわかの風に舞いあがり、寺の屋根を焼き、大火事のはじまりになったとか。
浅草の大きな商人の娘が、上野の花見で見かけた若者にひと目ぼれ。恋わずらいがもとで1655(承応4)年1月16日に死んでしまった。その娘の振袖が古着屋から別の娘にわたると、その人もよく年の1月16日に病死。次にこの振袖を手に入れた娘もよく年の1月16日にこれまた病死。そこで3人の娘の家が一緒になって本郷丸山町の本妙寺境内で問題の振袖を焼いたところ、火のついたまま、にわかの風に舞いあがり、寺の屋根を焼き、大火事のはじまりになったとか。
江戸はどこまで? -黒引き・朱引き-
明暦の大火の後、外へ外へと押し出され、江戸の町の範囲ははっきりしなくなってきた。
1818(文政元)年、11代将軍家斉の時、次のように決めた。
江戸町奉行が直接治める範囲を黒い線で引いたものを黒引きという。それより少し広く、まわりの村々を含んで朱の線で引いたものを朱引きという。そして、この朱引きの中を江戸御府内とする。
町奉行の治める範囲は、今の山手線より、ちょっと内側になる。朱引きなら、上の黒引きの範囲に、新宿・墨田・江東区全部と、荒川・板橋・渋谷・品川区の一部分が加わる。今の23区より少し小さい。
幕府の人口増加対策など
1611(慶長16)年頃には16万人くらいだった江戸の人口は元禄頃 (1688年~1704年)には90 万人に、8代将軍吉宗の享保頃 (1716年~1736年)には100~120 万人になったといわれる。こんなにたくさんの人々を抱えるのは大変なことで、幕府はいろいろな対策をたてた。
吉宗の時には、この大都市の防火のため「町火消」の制度をもうけたし、1878年、松平定信が老中になると「七分金積立」といって節約した町の費用の10分の7のお金を積み立てさせ、困っている人たちを救うために使う制度をもうけた。
また、天保の改革 (1830年~1843年)の 時には、増え続ける人口をなんとかしようと「旧里帰農」(江戸で仕事をせずぶらぶらしている人たちを故郷に帰して農業につかせる)という対策がたてられた。でも、あまり効果はなかったらしい。
東京のできるまで 明治・大正
東京遷都(東京に都をうつすこと)
幕府が倒れ、明治維新になると新政府では、首都をどこにするかが問題になった。公家の力が強い京が都では、思いきった改革ができないだろうと考えたからだ。
大久保利通は大阪を都にしよう、と唱えた。海に面していて交通の便がいいし、大阪商人に経済的に協力してもらいたい望みもあった。
のちに郵便制度を作った前島密は、江戸を都にしようと唱えた。せっかく築き上げられた江戸の町をこのままさびれさせるのはもったいない。江戸を都にすれば、新しく都をつくるより費用が少なくてすむ、と言うのだ。
大木喬任、江藤新平は、西の京、東の江戸の両方を都にしようという「東西ニ京論」を唱え、これがとりあげられた。
1868(慶応4)年7月17日、「今から江戸を東京(東の京)にしよう」という詔が出され、つづいて10月13日、明治天皇が江戸城入城。東京城と名を改めた。
江戸から東京へ
1868(慶応4)年4月、江戸にはいった新政府は、よく月地方を府・県・藩に分けた。幕府の治めていた地域は府や県として政府の直接の管理のもとに置き、藩はとりあえずもとの藩主たちに治めさせることにした。
7月17日の詔によって東京府が置かれた。初めの頃の東京府は、だいたい、かつての町奉行支配の区域、つまり、黒引きの内側だった。
外側は小菅、大宮などの県が置かれた。三多摩のあたりも品川県や、韮山県や、入間県などに複雑に分けられた。
江戸の土地の60パーセントは武家、20パーセントが神社や寺、20パーセントが町人のためのものだった。明治維新には、武家がちりぢりになって、一時江戸の町はさびれた。
けれど1872(明治5)年頃から、再び人口が増えだし、文明開化の時代になった。東京~横浜に汽車が通り、銀座にはイギリス人建築家ウォートルスの設計によるレンガ街がつくられた。かつて大名屋敷、旗本屋敷のあった地区には学校や役所、軍の施設が作られた。
1903(明治36)年には市街に路面電車が通り、山の手から下町への交通が便利になった。
1914(大正3)年には、オランダのアムステルダム中央駅をモデルにしたという東京駅が6年がかりで完成。東京の玄関となった。
廃藩置県 1871(明治4)年7月
全国の藩をとりやめて、府や県に統一し、政府の支配の下に置いた。江戸時代の藩というのは藩主が治める独立国のようなもので、参勤交代などがあるにしても、幕府が全国を直接支配するということはなかった。だから、これは大改革だったんだ。
また、ここで、韮山、品川、小菅、大宮の県はとりやめになって、今の三多摩のほとんどは神奈川県に属することになった。
最初の東京府に、荏原郡、豊島郡と多摩郡、足立郡、葛飾郡の各一部が加わって、11月には新しい東京府がスタートした。
大区小区制 1872(明治5)年4月
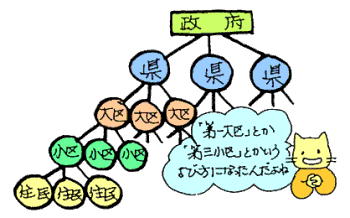 1872(明治5)年4月、廃藩置県に先立って、「戸籍法」という法律がつくられると、今まで自然にできあがってきた村や町はとりやめとなり、庄屋・名主・年寄などの役もなくなった。
1872(明治5)年4月、廃藩置県に先立って、「戸籍法」という法律がつくられると、今まで自然にできあがってきた村や町はとりやめとなり、庄屋・名主・年寄などの役もなくなった。
かわりに全国を大区、その下をさらに小区に分けて、政府が選んで小区には戸長、大区には区長を置いた。
この制度は、1872(明治5)年4月からの大区小区制にうつって、東京府も11大区103小区に分けられた。けれど自分たちの村や町を番号で呼ぶことにみんななかなかなじめなかった。
郡区町村編成法 1878(明治11)年7月 東京15区の誕生!
むかしからの町や村をこわしておこなわれた大区小区制はあまりうまくゆかなかった。そこで、もともとの町や村のあり方を考えにいれてこの「郡区町村編成法」が定められた。「第一大区」だの「第三大区」だのという呼び方もやめて、むかしからの町名・村名にもどした。
それから、県と町村の中間には郡を置くことにした。
東京府は11月2日に、麹町・神田・日本橋・京橋・芝・麻布・赤坂・四谷・牛込・小石川・本郷・下谷・浅草・本所・深川の15区に分けられた。(この区は昭和22年に今の23区の分け方・呼び名にかわるまで70年近くつづいた。)
また、多摩はこの時、東・西・南・北の4郡に分けられた。
東京市区改正条例 1888(明治21)年8月
東京の道路や区画、施設などを整えるため、つくられた法律。東京の本格的な都市計画のはじまりだ。パリなどの先進都市をモデルに、政府が中心となって事業をすすめた。
これは近代日本最初の都市計画でもあったから、こののち、ほかの都市も、こうした条例をもうけるようになった。
市制町村制 1888(明治21)年4月公布 1889(明治22)年4月実施 東京市の誕生!
これによって、人口が2万5,000人以上の地域や、都市として発展しそうな地域には市制をしくことになった。
東京府内の15区も「東京市」になった。けれど市制町村制が実施されるわずか10日前の明治22年3月22日。政府は、東京・大阪・京都の三市を「特別市」として扱う法律を出した。
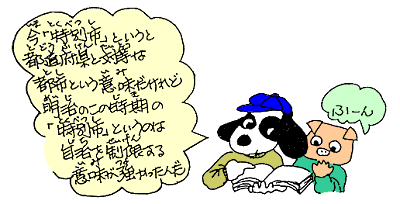 この三大都市には自治を認めず、政府が直接監督する、というのだ。特別市には市長も助役も置かない。東京市長がおこなうはずの仕事は、政府の役人である東京府知事がおこなった。
この三大都市には自治を認めず、政府が直接監督する、というのだ。特別市には市長も助役も置かない。東京市長がおこなうはずの仕事は、政府の役人である東京府知事がおこなった。
東京市会は特別市制のとりやめの願いを出しつづけた。
東京・大阪・京都にも一般市制がしかれたのは1898(明治31)年10月1日だった。
三多摩移管 1893(明治26)年4月1日 -神奈川県から東京府へ-
1878(明治11)年の郡区町村編成法で4つに分かれた多摩郡のうち、北・西・南の三多摩は神奈川県に属していた。
三多摩を東京府に移そう、という話は、東京府民の飲み水の管理のことから起こった。
水源である多摩川や玉川上水は、その上流が神奈川県になっている。だから、問題がもちあがるたび、東京府はいちいち神奈川県にかけ合わなければならない。
そのうえ、1886(明治19)年のコレラ大流行の時、多摩川上流で患者の汚れ物を洗たくした、というニュースが流れる。さらに1891(明治24)年には神奈川県が東京府に連絡なしに、大事な水源林を切る許可を出す、という事件もおこった。
西・北多摩郡を東京府に移して、水源の管理を直接したい!という運動は盛り上がった。
そこに、「歴史的につながりのある南多摩も一緒にどうぞ」との神奈川県知事の申し出もあって三多摩は、そろって東京へ…。
けれど三多摩は自由民権運動の中心地。東京府に移されたら勢力が弱まる、と強い反対もおこった。
いろいろすったもんだして、1893(明治26)年2月28日の衆議院の委員会では、三多摩を東京府に移す案は否決された。それが同じ日の本会議ではひっくりかえり、結局この年4月1日付で、三多摩は東京府に属することになった。
開国の頃から生糸の出荷などで横浜とのつながりが強かった多摩だった。けれど1889(明治22)年、甲武鉄道(今の中央線)が新宿~八王子に通じると東京はより身近になった。交通の発達も、東京と多摩を結びつけた原因の一つなんじゃないかな。
ところで、その後も、三多摩の問題はおさまらない。なんと大正12年頃まで、いろいろな案が出されては消えたんだ。
武蔵県 三多摩が東京に移ってわずか3年後の1896(明治29)年。政府は東京市と府下の郡とを分けて、東京市を東京都に、郡の部分を武蔵県にしようとした。東京市を直接政府が管理することがねらいだった。東京市も、郡もそろって反対してこの案はつぶれた。
千代田県 そのよく年の1897(明治30)年。今度は東京市が郡を東京府から切り離す運動をおこした。郡を抱えていると財政的に負担が大きい、というのが理由だった。東京市の特別市扱いを取りやめるとともに、郡はまとめて千代田県としよう、と提案。郡はこぞって反対し、この案も実現しなかった。
多摩県 1923(大正12)年の関東大震災の後で政府が提案。東京市を東京都として県と同じ扱いにし、郡は多摩県にするというものだった。この案もつぶれた。
大正時代
後藤新平と東京大改造
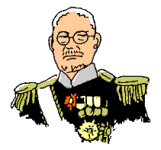 1919(大正8)年、都市計画法が定められる。これは、東京15区と荏原、豊多摩、北豊島、南足立、南葛飾の5郡と北多摩の一部を含む大規模な範囲のものだった。この都市計画がおこなわれた地域は10年後の昭和7年に大東京市(今の23区にあたる)になった。
1919(大正8)年、都市計画法が定められる。これは、東京15区と荏原、豊多摩、北豊島、南足立、南葛飾の5郡と北多摩の一部を含む大規模な範囲のものだった。この都市計画がおこなわれた地域は10年後の昭和7年に大東京市(今の23区にあたる)になった。
つづいて1920(大正9)年12月7日、次の総理大臣と見られていた大物政治家、後藤新平が東京市長になった。「一生に一度、国家の大犠牲となって一大貧乏クジをひいてみたい」というのが東京市長をひきうけた後藤の気持ちだった。1921(大正10)年5月に「東京市政要綱」を発表。内容は、8億円かけて、東京市を改造しよう、という大計画だった。当時の東京市の1年間の予算は1億2~3,000万円。日本政府の予算だって15億円くらいだ。「後藤の大風呂敷」と世間はあきれた。
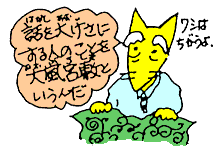 残念ながら、この計画はすすまず、後藤は2年ほどで東京市長をやめた。それでも東京の都市計画のもとはこの時つくられたと言える。
残念ながら、この計画はすすまず、後藤は2年ほどで東京市長をやめた。それでも東京の都市計画のもとはこの時つくられたと言える。
関東大震災と広がる東京
1923(大正12)年9月1日、午前11時58分。関東地方を大地震がおそった。東京の被害を大きくしたのは、地震のあと発生した火災だ。火は3日間燃えつづけ、東京の町を焼きつくした。
政府は、内務大臣の地位にあった後藤新平を中心にして、帝都復興(東京の建て直し)計画をすすめた。後藤はこの機会に再び東京を理想都市にする計画を練った。そのために必要な予算はなんと40億円。しかし、希望の額はけずりにけずられ、国と東京府、東京市で出し合うお金を合わせても7億円。後藤新平が東京に描いた夢は消え去った。
関東大震災の後は、郊外に引っ越す東京市民がどっと増え、山手線の外側や中央線沿いは田んぼや畑が、どんどん住宅地にかわっていった。震災の前まで、住宅地といえば、小石川(文京区)、牛込・四谷(新宿区)、赤坂・麻布(港区)あたりであったのが、震災後には大塚、目白、渋谷、目黒など山手線の外へと広がっていった。
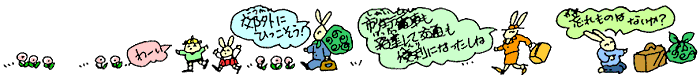
東京のできるまで 昭和~
大東京市あらわれる!
1920(大正9)年、東京市のまわりに5万人の人口をこえる町は3つだけだった。それが、関東大震災後の1930(昭和5)年には21に増えた。私鉄が発達して郊外への交通が便利になったことも、東京が外へ広がってゆくことを助けたんだ。そして1932(昭和7)年10月1日。ついに東京市の区域を広げる計画が実現。
まわりの5郡(荏原、南足立、豊多摩、南葛飾、北豊島)の82町村が合併。東京市はそれまでの15区に新しく20区(品川、目黒、荏原、大森、蒲田、世田谷、渋谷、淀橋、中野、杉並、豊島、滝野川、荒川、王子、板橋、足立、向島、城東、葛飾)が加わって35区になった。
面積はいっきょにこれまでの6.8倍に、人口も2.4倍の497万人となり、当時ニューヨークについで世界第2位の人口をもつ大都市になった。
東京都の誕生
1941(昭和16)年12月8日、太平洋戦争が始まった。そのさなか、1943(昭和18)年7月1日、東京市と東京府はなくなって、それらをひとつにした「東京都」が誕生した。
「東京は首都だから、ほかと違う特別な制度を設けるべき」とか、「府と市とで二重の政治がおこなわれるのはめんどうだ。ひとつにするべき」とかいう声は明治30年頃からあがっていた。けれど、この時期に「東京都」が生まれた一番の理由は、戦争から首都を守るためだった。
1944(昭和19)年11月からは本土空襲もたびたびとなり、東京には、のべ1万機により、120回ほどの空襲がおこなわれた。市街地の半分以上は焼野原になり、戦争の被害を受けた東京住民は300万人以上。戦争がおわった1945(昭和20)年10月には、そういった戦災やら、疎開やらで、東京の人口は戦前の半分以下になっていた。
東京の復興
戦争による被害は大きく、食糧不足もつづき、戦後の東京の立ち直りはかんたんではなかった。けれども1945(昭和20)年12月30日には、政府は戦災を受けた地域の復興計画を決めた。目標は「東京が大きくなりすぎるのを防ぐ。そのためには区部の人口を350万人におさせる。おさえた分の人口は東京のまわりの都市に受け入れてもらう。」というものだった。
 けれど、1945(昭和20)年11月には277万人だった区部人口はわずか2年で381万人に増え、あとはもううなぎのぼりに増えつづけるのだった。
けれど、1945(昭和20)年11月には277万人だった区部人口はわずか2年で381万人に増え、あとはもううなぎのぼりに増えつづけるのだった。
戦後の三多摩
関東大震災のあと、多摩地区は開発がすすんだけれど、急激にかわっていったのは、なんといっても太平洋戦争がおわってからだ。
終戦までに、多摩郡で市になっていたのは、八王子、立川、武蔵野の三市だけだった。それが1950(昭和25)年には三鷹が、よく年には青梅が、1954(昭和29)年には府中、昭島、町田が、1955(昭和30)年には調布、小金井が市になった。
それ以外の町や村も、合併をしたりして、昭和30年代後半から昭和40年代にかけてつぎつぎと市になっていった。
そして、住宅や工場、学校、病院、研究所などの施設がどんどん建って、農村から都市のすがたへとかわっていった。
23区(特別区)のはじまり
連合軍に占領されているさいちゅうの1946(昭和21)年10月、東京都制が改正された。都知事と区長はみんなの選挙で決められることになった
1947(昭和22)年3月15日には東京の35区は22区に組みなおされ、5ヶ月後の8月1日には板橋区から練馬区が分かれて、今の23区になった。23区は特別区として、他の道府県の区とは違って市に準じた扱いとなった。つまり、市と同じはたらきを持つんだ。特別区の制度は東京が大都市なので設けられた。
こんなふうにかわった
麹町区・神田区 千代田区
日本橋区・京橋区 → 中央区
麻布区・赤坂区・芝区 → 港区
牛込区・四谷区・淀橋区 → 新宿区
本郷区・小石川区 → 文京区
下谷区・浅草区 → 台東区
向島区・本所区 → 墨田区
城東区・深川区 → 江東区
品川区・荏原区 → 品川区
大森区・蒲田区 → 大田区
王子区・滝野川 → 北区
目黒区、世田谷区、渋谷区、中野区、杉並区、豊島区、荒川区、板橋区、足立区、葛飾区、江戸川区はそのまま。
首都圏をととのえなくっちゃ…
東京は政治や経済の中心だ。人口も集中する。そこで都心に人口が集まらないよう、東京のまわりに衛星都市をつくって、人や仕事を分散させよう、東京が無計画に広がるのを防ごう、ということになった。
1956(昭和31)年4月、日本の政治・経済・文化の中心にふさわしく東京を整えることを目的に、「首都圏整備法」という法律ができた。
さらに1958(昭和33)年7月には「首都圏整備基本計画」が出た。これは1946年のイギリスの大ロンドン計画にならったもの。
この時、新宿、渋谷、池袋を副都心として再開発することも決められた。
まわりの地域にグリーン・ベルト地帯をつくって、市街地がこれ以上ふくれあがるのをくい止めるのがこの計画の大きなねらいだったけれど、なかなかうまくゆかなかった。
首都圏ってなんだ!
東京駅を中心に、半径100~120キロメートルくらいの範囲で、東京都とつながりの強い地域をいう。県でいうと神奈川、埼玉、千葉、茨城、栃木、群馬、山梨あたり。
かわっていく東京
1964(昭和39)年の東京オリンピックをきっかけに、東京の都市づくりは猛スピードですすんだ。羽田から都心への首都高速道路はできる。青山通りや甲州街道は道はばを広げる。神宮外苑、代々木には大きな運動競技場ができる。のっぽビルがにょきにょき建つ。自動車が増える。東京の風景は大きくかわった。経済も「高度成長期」をむかえて、おおいに発展。でも、同時に、水や空気の汚染など、公害問題ももちあがってきた。さて、これから東京はどんなふうになってゆくだろう?
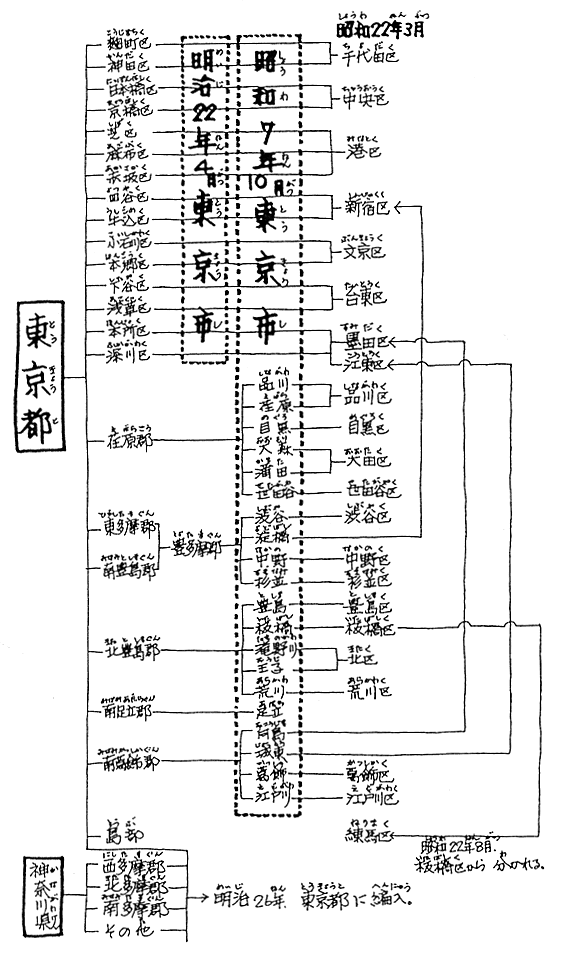
上にものびる大東京
- 1962(昭和37)年 東京タワー、港区に完成。当時、世界一高いタワーだった。333メートル。
- 1968(昭和43)年 霞が関ビル、千代田区に完成。日本最初の本格的な高層ビル。147メートル、36階。
- 1978(昭和53)年 池袋副都心、巣鴨拘置所跡地にサンシャイン60が完成。240メートル、60階。
にょきにょき建った新宿副都心
1965(昭和40)年に引っこした淀橋浄水場跡地に…
- 1971(昭和46)年 京王プラザホテル47階
- 1974(昭和49)年 住友ビル52階
三井ビル55階、KDDビル32階
- 1976(昭和51)年 安田火災海上ビル43階
- 1979(昭和54)年 NSビル30階
- 1980(昭和55)年 ホテルセンチュリーハイアット28階
- 1991(平成3)年 東京都庁48階
ほかにも「新宿センタービル」とか「野村ビル」「グリーンタワービル」など、のっぽビルがいっぱいだ!
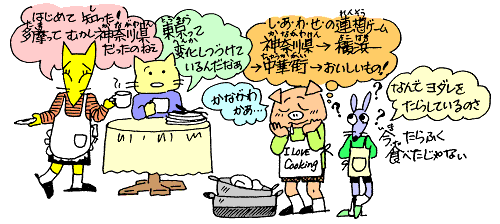
東京都のあれこれ
東京都のマーク
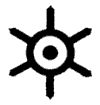
1889(
明治22)
年12
月、
東京市議会で
決めた
市のマークを
東京都がうけついだ。
東京の
発展を
願って、
太陽を
中心に、
六方に
光がはなたれているようすをあらわしている。
東京都の花・ソメイヨシノ
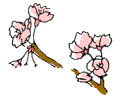
1984(
昭和59)
年6
月、「
都の
花選考会」で
正式に
決まった。ソメイヨシノは
江戸の
末ごろから
昭和の
初めにかけて、
染井村(
今の
豊島区)の
植木職人がヤマザクラの
品種を
改良したもの、と
言われる。
咲きそろった
姿も、
散りぎわも
美しい。
東京都の木・イチョウ
 古代植物
古代植物の
生き
残りと
言われ、
日本と
中国の
一部にだけ
現存する。
公害にも
火にも
強く、
街路樹によく
使われる。
1966(
昭和41)
年11
月に
都の
木に
選ばれた。
東京都の鳥・ユリカモメ
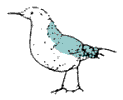
またの
名をミヤコドリ。からだは
白く、くちばしと
足が
朱色の
美しい
鳥。10
月の
末ごろ、シベリア、カムチャッカ
方面から
渡って
来て、つぎの
年の4
月に
帰ってゆく
渡り
鳥。1965(
昭和40)
年10
月に
都の
鳥に
選ばれた。
「都民の日」が10月1日のわけ
1888(明治21)年4月、市制町村制が公布になって東京府の中にも、東京市が生まれることになった。山手線の内側の旧15区だ。ところがよく年の施行(法律が実際に行われること)の直前に、東京・大阪・京都の三市は、府知事が市長を兼ねて監督する、という「特別市制」があてはめられてしまった。そこで東京市は市会を中心に自治をとりもどすための運動をつづけ、1898(明治31)年、ようやく一般の市と同じ扱いになった。
この年10月1日、東京府の庁舎の中に東京市役所が開かれ、この日は開庁記念日として祝われていた。
1922(大正11)年、後藤新平市長の時、自治記念日として市の独立を祝うことに決められた。
東京都の歌・あさみどり
募集によって1947(
昭和22)
年に
作られた。
歌詞はその
当時、
立川の
学校事務長だった
原田重久さんという
人が
作って、
詩人の
深尾須磨子さんが
手を
加えた。
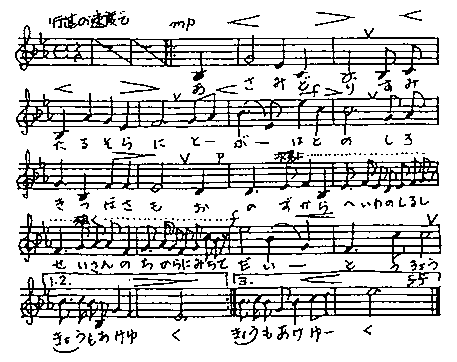
「あさみどり」
- あさみどり すみたる空に
飛ぶ はとの 白きつばさも
おのずから 平和のしるし
生産の力に みちて
大東京 きょうも あけゆく
- あたらしき 政治のみやこ
東西の 文化のすいを
育てゆく 自由のひかり
永遠の 理想に燃えて
大東京 きょうも あけゆく
- 美しき われらのみやこ
豊かなる みどりの園に
黒潮の ひびきもかよう
あめつちの はてなきところ
大東京 きょうも あけゆく

東京の1日
人口 13,043,441人(
平成22
年7
月1日現在)
男 6,480,765人
女 6,562,676人
世帯数 6,323,492
世帯
平成21
年度1日あたりの
他県からの
転入 1,129
人
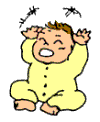 他県
他県への
転出 980
人
出生 295
人
死亡 270
人
結婚 224件
離婚 49件
新聞・郵便
 新聞発行部数
新聞発行部数 673
万部(
平成2
年10
月1日
現在)
郵便引き
受け
数 (国内)1,725
万通
食料
 米消費量
米消費量 1,787トン
野菜消費量 5,149トン
果実(くだもの)
消費量 2,186トン
鮮魚消費量 475トン
冷凍魚消費量 782トン
その
他の
水産物消費量 1,064トン
精肉消費量 329トン
牛乳消費量 1,257キロリットル
 一世帯、1日あたりにつかうお金の平均額 11,726 円
一世帯、1日あたりにつかうお金の平均額 11,726 円
病院
 入院患者
入院患者 のべ11
万2
千人
通院患者 のべ16
万2
千人おとしもの
なくしたほう
お 金 3,173 万円
もの 3,555 点
ひろったほう
お 金 960 万円
もの 4,086 点
交通(乗客数)(20年度)
JR 330 万人
私鉄 298 万人
地下鉄 316 万人
都電 2 万人
バス 20 万人
ハイヤー・タクシー 123 万人
自家用車 569 万人
航空(羽田空港 )33,332,031 人
船舶(東京港 )1,619,739 人
ゴミ
 産業廃棄物
産業廃棄物 (工場などででるゴミ)12,260トン
ゴミ
収集量 16,674トン
し
尿処理量 (うんちやおしっこ)2,439キロリットル
下水処理量 538
万立法メートル
エネルギー
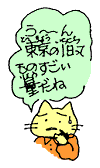 電力消費量
電力消費量 51,525,059キロワッット
ガス
消費量 859
億キロカロリー
灯油販売量 4,612キロリットル
ガソリン
販売量 10,097キロリットル
水道給水量 504
万立法メートル
絵で見る東京のなりたち
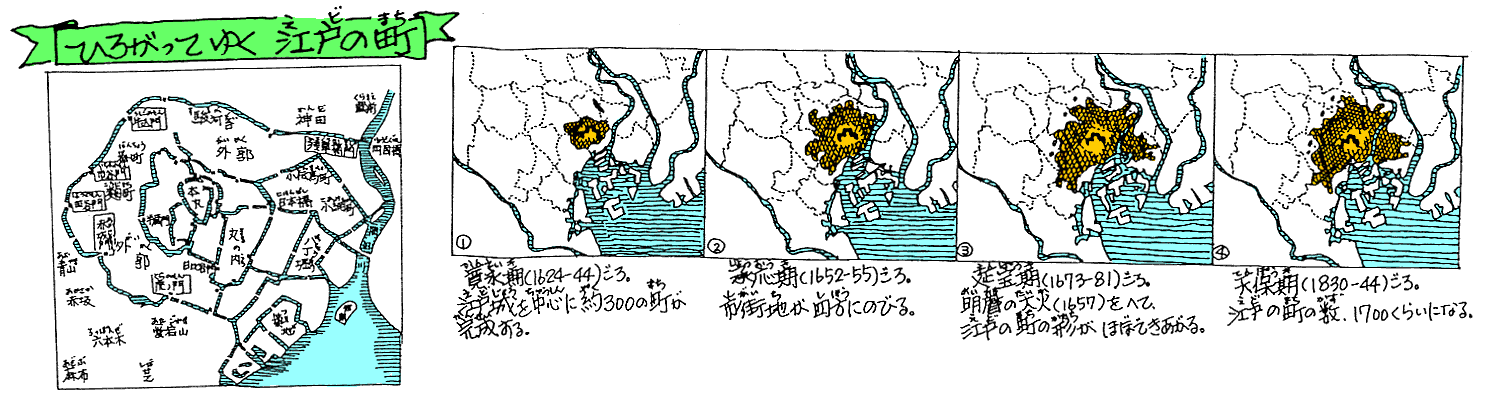
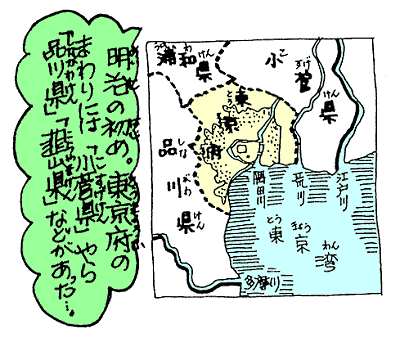
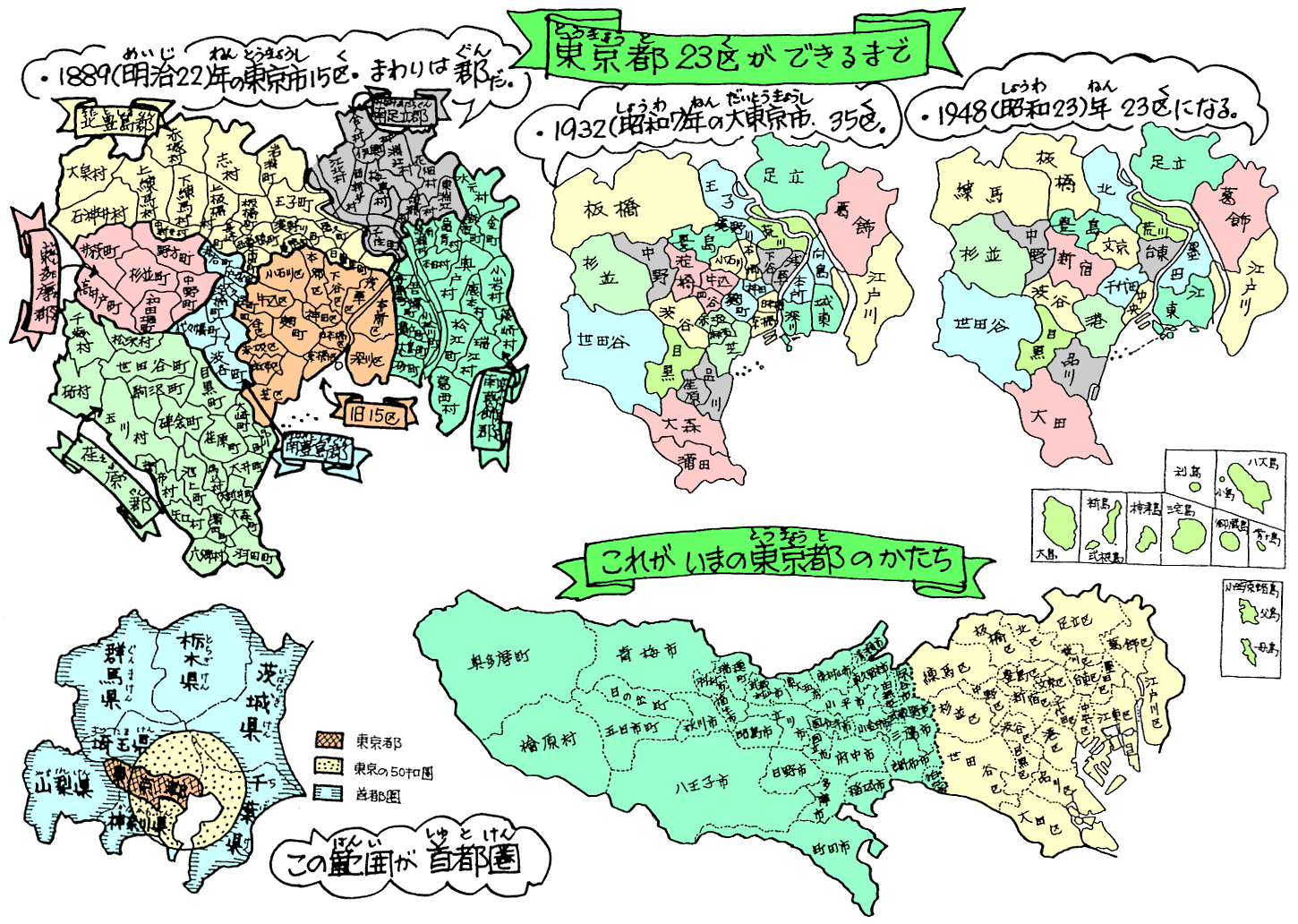
参考にした本
「江戸・東京学辞典」
「東京百科事典」
「東京のあらまし」
「都政のあらまし」
「日本地名大事典13 東京」
「ぼくらの東京都」
「東京都の歴史」
「東京を築いた人々」
「東京雑学事典」
「江戸東京まちづくり物語」
「多摩のあゆみ」第54号
「江戸東京年表」などなど
小平市に関すること
多摩に関すること
江戸・東京に関すること
玉川上水・小金井桜に関すること
その他
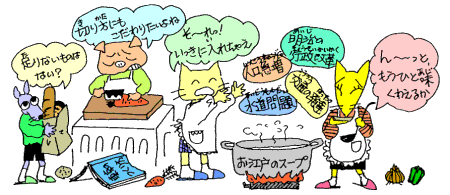


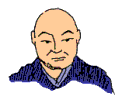
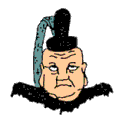
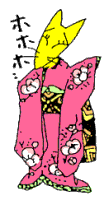

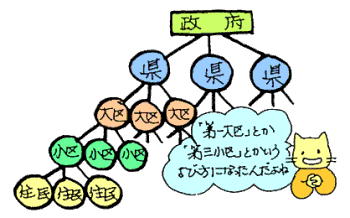 1872(
1872(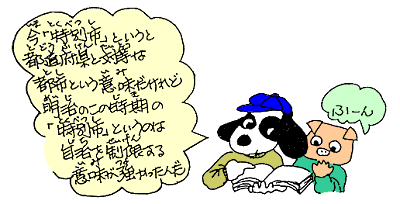 この
この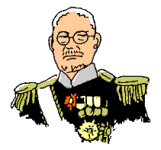 1919(
1919(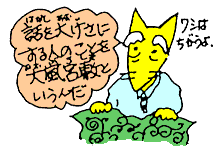
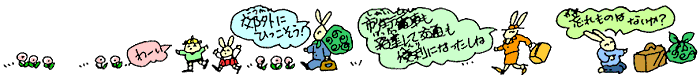
 けれど、1945(
けれど、1945(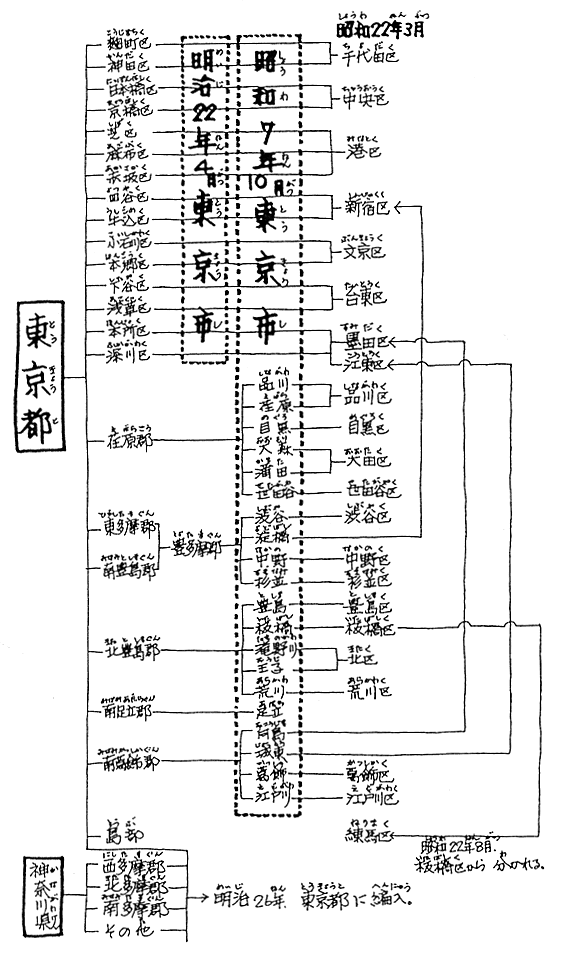
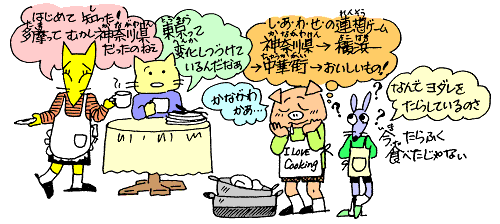
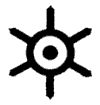 1889(
1889(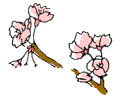 1984(
1984(
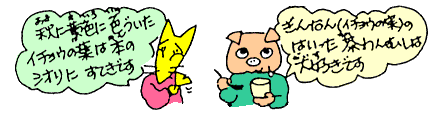
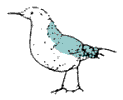 またの
またの