絹の道
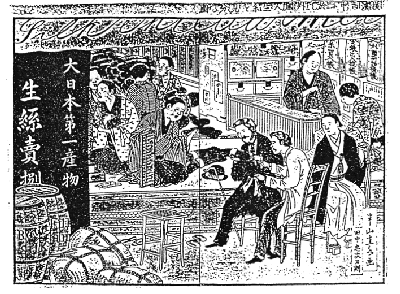
「横浜市中において外国人生糸を見分る図」
むかし、むかし、大むかしから、ユーラシア大陸には漢(今の中国)の都からタクラマカン砂漠を横切ってヨーロッパへつながる道があったとさ。
長く険しい道だけど、東西の人や文化が往き来した。紀元前2世紀頃からは中国から運ばれる絹貿易が盛んになったものだから、のちの世で「絹の道」(シルク・ロード)と名がついた。
絹は何にもまさる布として、アウレリアヌス帝時代(270~275年)のローマではその重さと同じだけの金が支払われたんだと。ヨーロッパの人たちはしばらくの間この美しいものが蚕という虫が吐き出す糸から作られるとは知らなんだ。
 貴族、金持ち…世界中の人々から絹は愛され、大切にされた。
貴族、金持ち…世界中の人々から絹は愛され、大切にされた。
幕末から明治にかけて、多摩にも「絹の道」があったとさ。絹を織るための生糸を運んだ道だったんだと。日本が世界の国々にひらかれると、山梨・長野・群馬などから八王子に集められた生糸は、これらの道を通って港横浜に運ばれていったそうな。
横浜からは、外国船が運んで来た新しい知識や考え方が流れてきた。生糸と人と文化が往き来した多摩の「絹の道」。
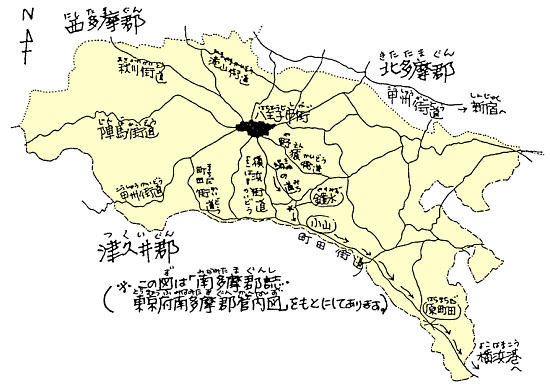
日本開国のころ
養蚕・製糸
- 紀元前17~11世紀なかば。中国の殷の時代、すでに黄河流域で養蚕がおこなわれていたらしい。
- 1~3世紀。中国から日本に養蚕が伝わる。
- 5世紀なかば。機織りの技術も伝わる。
江戸時代 養蚕は主に中部・関東・東北でおこなわれる。
- 1860(安政7)年。前年の横浜開港によって生糸・蚕種がヨーロッパへの最大の輸出品となる。
- 1860(万延元)年うるう3月。幕府は「五品江戸廻令」を出す。
この年、ヨーロッパで蚕の病気が流行。日本の生糸のねだんはあがる、あがる。
- 1867(慶応3)年。蚕種の輸出のねだん、去年に比べて26倍にはねあがる。密輸もさかん。
生糸は大人気!
明治時代 1868年9月、改元。明治になる。
- 1872(明治5)年。官営富岡製糸工場、動きだす。
- 1873(明治6)年5月。八王子に生糸改会社できる。輸出する生糸の質を少しでも良くするためだ。
- 1874(明治7)年。この年、鑓水村の生糸商人、商売と道中の無事を祈り、絹の道に道了堂を建てる。(浅草の花川戸から移してきたものだ。)
- 1884(明治17)年。アメリカの絹織業が発達。日本の生糸はアメリカに輸出されるようになる。
- 1894(明治27)年。日清戦争おこり、まゆ、生糸のねだんはむちゃくちゃあがる。蚕糸業ますます盛ん。
- 1911(明治44)年。日本の生糸の生産高、世界第一位となる。
その後の多摩の養蚕…
- 1930(昭和5)年。生糸の業界も世界恐慌のあおりをうける。
- 1941(昭和16)年。太平洋戦争はじまり、生糸の輸出禁止。製糸工場はつぎつぎと軍需工場にかわっていった…。
横浜開港 欧米の目はアジアへ!
- 1853(嘉永6)年6月3日。ペリー、浦賀に来航。
- 1854(安政元)年1月16日。ペリー、再来。 3月3日。日米和親条約むすぶ。
- 1856(安政3)年。アメリカ駐日総領事タウンゼント・ハリス、下田に来航。
- 1858(安政5)年6月19日。日米修好通商条約むすぶ。日本の鎖国時代のおわり。
- 1859(安政6)年6月。神奈川(横浜)・長崎・箱館の3港をひらき、アメリカをはじめ、イギリス・フランス・ロシア・オランダら外国と貿易はじまる。
世界情勢
- 18~19世紀。ヨーロッパでイギリスを中心に産業革命はじまる。
原料を求めて、また、大量に作り出される商品を売りさばくため、イギリスやフランス、アメリカらはアジアへ進出しはじめる。
- 1840~42年。イギリスと清(今の中国)の間でアヘン戦争。
- 1856年。アロー号事件おこる。これをきっかけにイギリス・フランス対清の第2次アヘン戦争おこる。
結果、清はこれらの国のなかば植民地となってしまった。
この間、アメリカも着々とアジア進出をねらう。
交通 産業革命は運輸の手段をかえた!
- 1804年。イギリスのリチャード・トレビシック、世界最初の蒸気機関車を走らせる。
<以後、鉄道は欧米にアッという間にひろがってゆく>
- 1870(明治3)年4月15日。
玉川上水を荷を運ぶための船が通りはじめる。月に6回。5と9のつく日に船は通った。(八王子の市のよく日なんだねえ、これが。)多摩はもちろん、長野や山梨の生糸も運ばれた。
- 1872(明治5)年3月。上水の汚れにびっくりした東京府。国に申し入れて通船は中止になる。
この年9月、新橋~横浜間に鉄道開通。
 1875(明治8)年。八王子の商人から「絹の道」を馬車の通れる道に、との願いが神奈川に出る。
1875(明治8)年。八王子の商人から「絹の道」を馬車の通れる道に、との願いが神奈川に出る。- 明治10年代。多摩では馬車がただひとつの交通機関。
- 1889(明治22)年8月。新宿~八王子間に甲武鉄道開通。(今の中央線のことだよ。)これで多摩は、横浜より東京が身近になる。
- 1908(明治41)年9月。明治27年からず~っと願い出ていた横浜鉄道。やっとゆるされ、八王子~横浜間開通。
だが、すでに、多摩は、1893(明治26)年4月、名実ともに東京府に組みこまれていたのだった。
横浜の港が開かれて
1.横浜開港
江戸時代も弘化年間(1844~47)にはいると日本のあちこちに外国船が姿を見せはじめた。
欧米の国々がアジアに進出してきたのだ。中でもアメリカは、清(今の中国)との貿易で太平洋を横断するため、中継ぎの港として、日本に注目した。
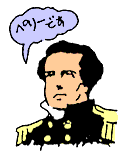 嘉永6(1853)年6月3日、アメリカの東インド艦隊司令官、マシューズ・ガルブレイス・ペリーが4隻の軍艦をひきいて浦賀沖に姿を見せた。
嘉永6(1853)年6月3日、アメリカの東インド艦隊司令官、マシューズ・ガルブレイス・ペリーが4隻の軍艦をひきいて浦賀沖に姿を見せた。
今にも合戦がはじまるかと江戸の町はもう大混乱。デマは乱れ飛ぶ。旗本・御家人は武器の買い出しにかけまわる。物価はあがる。疎開する人もでる。パニックになった。ペリーは、「また来年くる。」と約束して、10日間で出ていったけれど。
よく年、1月16日。ペリーが再び江戸湾を訪れ、何度もの話し合いののち、3月3日、ついに日米和親条約をむすぶのに成功。
下田・箱館を開港して
アメリカの船に水・食糧・石炭・薪を供給すること。
下田にアメリカからの駐在員をおくこと。
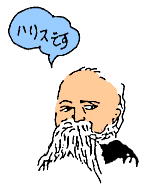 というのが主な内容だ。
というのが主な内容だ。
安政3(1856)年7月、日米和親条約にしたがって、アメリカから駐日総領事としてタウンゼント・ハリスが下田にやって来た。今度は日本と通商条約を結ぶため、ハリスは頑張った。
おとなりの清で勢力を伸ばしているイギリスとフランスが日本にやって来る前に、アメリカは有利な約束をむすばなくっちゃ、と急いでいたのだ。
安政5(1858)年6月19日。日米修好通商条約をむすぶ。ハリスはいくつかの港・市場を開くことを望んだ。
そして神奈川・長崎・箱館が開港場となった。
2.プレゼントの交換

ペリーの2
度目の
来日のとき、
日本とアメリカでプレゼントの
交換をした。
アメリカからは
電信機だの
銀板写真だの
望遠鏡だの「これが
科学技術だ!!」というふうな
品物が
贈られた。
中でも6
才ぐらいのこどもを
乗せて
走れる
蒸気機関車の
模型は
日本人をびっくりさせた。
日本は、お
返しに
絹織物・
陶器・
塗りものなど
伝統工芸品や
美術品を
送った。アメリカ
艦隊へのプレゼント、
米200
俵は
江戸からよんだ
力士にボートまで
運ばせ、すもうをひろうした。
3.外国との貿易
開港といったって、田畑・沼をつぶして作った野っ原。急いで商人をあつめ、体裁をととのえなけりゃならない。幕府は開港場で商売をしたい人の出かせぎ、移住を呼びかけた。安政6(1859)年1月のことだ。
よく月、2月には、幕府の御用商人三井が外国奉行から命令をうけ、横浜に店を出した。
安政6(1859)年6月2日、長崎・箱館とともに横浜開港。いよいよ外国との貿易のはじまりだ。しかし、最初は日本の商人も、外国の人が何をほしがっているのかわからない。瀬戸物・小間物・塩・海産物…とさまざまな品物がならんだ。
おりしも1850~60年代、ヨーロッパの生糸生産国の中心、フランスとイタリアで蚕の病気が流行。よそからたくさん輸入しなければならなくなって、開国した日本の生糸はヨーロッパの市場に加わることになった。また健康な蚕種(蚕の卵のこと)もおおいに求められた。
生糸が売れると知ると、日本の商人たちも生糸を集めてまわった。養蚕の中心は関東西部から中部地方だったから、最寄りの港である横浜は生糸輸出の中心地となった。
1862(文久2)年には、生糸は横浜港での輸出総額の8割を占めていた。
4.五品江戸廻令
開港以来、商品は買いあさられ、生産地から直接開港場に送られるため、物価は上がり、国内では日用品さえ不足した。京都の西陣、足利の桐生などの織物業者をはじめ、武州でも多摩・入間・比企郡などの織屋農民たちは原材料の生糸が手にはいらなくなって、これ以上生糸輸出が続いたら仕事が成り立たない、生活していけない、というところまで追い詰められた。
そこで万延元(1860)年うるう3月、幕府は「五品江戸廻令」を出した。雑穀・水油・蝋・呉服・生糸の五品に限り、まず江戸の問屋にまわし、国内で必要な分をとってから、残りを横浜へ送るようにという命令だ。外国との貿易と国内の品物の流れを幕府がしっかり管理するつもりだったのだ。
けれど、自由に商売したい地方の商人と取引相手の外国人商人からも反対を受け、この命令はあまり効果があがらなかった。
5.生糸のあつまる町 八王子
「浅川を渡れば 富士のかげ清く 桑の都に 青嵐吹く」
西行法師(鎌倉時代の人)の歌をはじまりに八王子は「桑の都」の名で呼ばれた。桑都日記(八王子の塩野適斎が書いた、1582~1824年までの千人同心の記録と解説)には「野っ原は広大で桑は1000万株。そこに住む人たちはみな養蚕でくらしている」と書かれている。
桑の都は蚕を育て、生糸から絹織物を作る町になった。
八王子織物は江戸の元禄時代ごろから始まり、1700年代のなかばには、その名が全国に広がった。
もともと4の日、8の日の月6回ひらかれていた八王子の市は横浜が開港されると生糸商人が活やくするようになった。甲州街道の宿駅である八王子は、まわりの養蚕地帯から生糸をあつめやすい。横浜にも近い。条件がぴったりだったんだね。
6.目こぼしの道「絹の道」
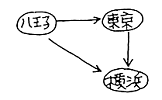 生糸商人
生糸商人は、
生糸をカゴで
背負ったり、
天秤でかついだり、
小さな
甲州馬の
背中に
乗せたり、といろいろな
方法で
集められ、
八王子から
横浜の
港へと
運ばれた。「
絹の
道」とは
生糸を
運ぶこれらの
道すべてをさす。
絹の
道は、
甲州街道のような
公の
道とは
違い、
里道だ。
例えば、その
一つ。
八王子から
鑓水、
原町田を
通って
横浜へ
向かうルート(
鑓水道了道という)。
距離こそ、
横浜までいちばん
短いけれど、
道巾はせまいところは3
尺(90センチメートル)くらい。
馬車も
通れず、
多摩丘陵を
越えるなど
歩き
辛いところもあって、けっこうしんどい
道だったらしい。
八王子から
馬車で
甲州街道を
通って
東京に
出、そこから
鉄道で
横浜へ
行く
方が
距離は
遠くても
楽、という
話もある。
けれど、
公道である
甲州街道を
行けば
宿ごとに
荷を
積みかえねばならないきまりだとか、
口銭10
文とか、
別の
手間とお
金がかかる。
絹の
道はそういう
面倒のない
裏道、
抜け
道、お
目こぼしの
道だった。
7.蚕の種屋さん
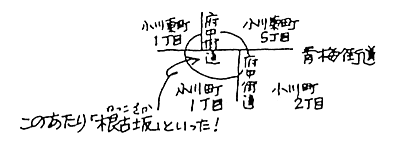 蚕
蚕の
卵は1.3ミリメートルくらいのだ
円形で「
種」とよばれた。
卵を
紙に
産みつけさせた
蚕種紙を
農家に
売る
仕事を「
種屋」といった。
小平でも
明治25
年にこの
商売が
始まっている。
中でも
根古坂の
小野弥十郎は
大正10(1921)
年、
全国蚕種製造者番付で
関東の
大関といわれるほどの
規模だった。
8.鑓水商人
 開港
開港した
横浜には2
種類の
商人がいた。
一つは
三井のように
江戸・
大阪など
都市の
大商人。もう
一つは
地方の
小規模な
商人だ。
貿易が
始まったころは、
商売の
才能があれば、
資金が
少なくとも、
取り
引きに
加わることができた。
産地から
安い
時に
生糸を
買い
占め、
値あがりを
待って
横浜で
売る。
冒険のような
商売のしかたで、
一晩で
財産を
築くこともできたが、
一歩間違えるととりかえしのつかないことになる。スリルがあったろうなあ。
絹の
道沿いの
八王子鑓水村は
多摩きっての
生糸商人を
何人も
産んだ。この
村には、
大きな
屋敷だの、
接待のための
異人館だのが
建てられ、
生糸を
買う
外国商人が
訪れた。
今、
鑓水には「
絹の
道」ときざまれた
石碑と、ここの
生糸商人たちが
商売と
道中の
無事を
祈って
浅草から
移してきた
道了堂が
建っている。
9.神奈川から東京へ
明治4(1871)
年11
月14
日から
明治26(1893)
年3
月31
日まで
西多摩郡・
南多摩郡・
北多摩郡の
三郡は
神奈川県だった。
だから、
役所の
届出などは
神奈川県庁のある
横浜へ
出向くし、
品物の
流れも
横浜へ
向かうし、
気持ちの
上でも
多摩と
神奈川、
横浜とのつながりは
深かった。
明治22(1889)
年8
月11
日。
新宿~
八王子間を
甲武鉄道(
今の
JR中央線)が
開通。この
距離を
約1
時間13
分で
走ったというから、かなり
早い。それが
毎日4
往復。
甲武線は
多摩と
東京を
身近にした。さらに
明治26
年4
月1日からは
多摩は
東京府に
移った。
品物は
東京の
市場へ
向かうようになる。
一方、「
絹の
道にも
鉄道を」と、
明治20(1887)
年、
横浜の
大商人原善三郎らが
川崎~
八王子間の
工事を
願い
出たがけり
続けられ、
八王子~
横浜間、
横浜鉄道(
今の
JR横浜線)として
許しが
出たのは
明治37(1894)
年12
月のことだった。
横浜鉄道は
商品の
流れをもう
一度横浜に
向かわせる
願いがかかっていた。が、
甲武鉄道のスピードと
輸送の
範囲の
広がり(
明治36
年6
月には
甲府まで
開通)は、
多摩と
横浜を
再び
結びつけることを
許さなかった。
品物は
東京へと
向かい
続け、
養蚕も
交通が
便利になったため、
他県の
大製糸資本がのりこんでくるようになり、
多摩の
養蚕農家はそれらに
組みこまれていった。
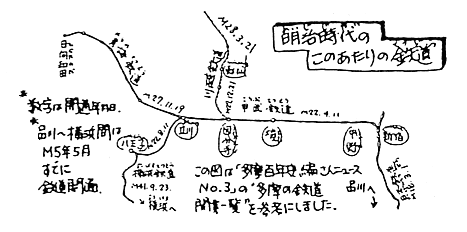
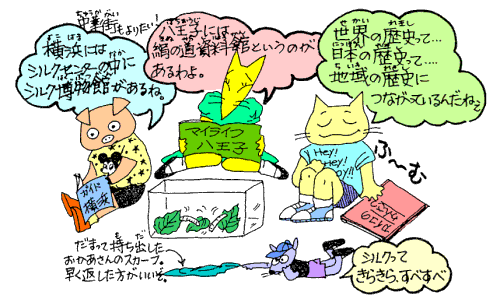
絹の道資料館
- 八王子市鑓水989-2
- 八王子駅北口から「橋本行き」バスで自然公園前下車 徒歩15分
- あいている時間 ごぜん午前9時~ごご午前4時30分
- おやすみの日 月よう日、祝日のつぎの日、年末年始
- 入館無料
シルク博物館
- 横浜市中区山下町(山下公園そば) シルクセンター内
- あいている時間 ごぜん9時~ごご4時30分
- おやすみの日 月よう日、年末年始(12月28日~1月4日)
- 入館料 大人500円、高校・大学生200円、小・中学生100円
カイコから生糸ができるまで

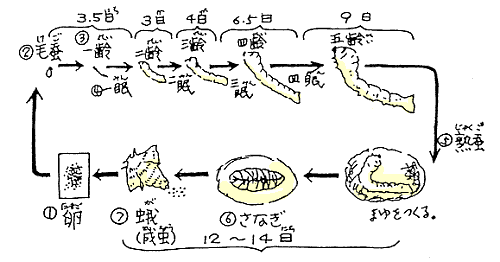
1.卵
はじめ
黄色く、
何日かすると
濃い
藤色かねずみ
色に。1.3ミリメートルくらいのだ
円形。「
蚕種」とか「
種」とか
言われる。
2.毛蚕
卵からかえったばかりの蚕の幼虫は大きさは3ミリメートルくらい。からだに毛がはえて黒く、アリのようだ。これを毛蚕という。2~3日で毛が落ちたようになって全体が黄色っぽくなる。
3.齢
蚕は1回目の脱皮までを1齢。2回目の脱皮までを2齢。5齢になるとまゆをつくる。
4.眠
新しい
外皮を
作る
間、
桑を
食べず
頭を
持ち
上げ、
止ったままの
状態になる
時期がある。
眠っているように
見えるので、これを「
眠」という。
新しい
皮ができると
古い
皮をぬぎすてる。(
脱皮)
脱皮は4
回おこなわれる。
蚕のひふはからだの
成長に
合わせて
大きくなることがない。
大きくなってゆく
幼虫は、その
度きつくなったひふをぬぎすてていくんだ。
5.熟蚕
5齢の末期をいう。このころになると桑を食べなくなり、からだがすきとおる。卵からかえって熟蚕になるまでおよそ4週間。その間にからだの長さは25~30倍。体重はなんと1万倍になる。
6.さなぎ
熟蚕は2日間休みなく糸をはいてまゆをつくり、さらに2日ほどたつとまゆの中で脱皮してさなぎになる。
まゆを
振ってみてカラカラと
手ごたえがあったら、さなぎになった
証拠だ。
7.成虫
さなぎになって2週間くらいで、大人になってまゆから出てくる。
でも、
長い
間人間に
飼いならされてきた
蚕は、
羽があっても
飛べなくなっているし、
口も
退化している。
だから、
交尾して
卵を
産んだあとは
何も
食べないまま、1
週間ほどで
死んでしまうんだ。

夕方から夜明けにかけ、めすは休むひまもなく500個もの卵を産みつづける。
おかあさんは大変だよ…。
蚕の体重のふえ方
蚕の体重のふえ方
| 齢 |
ふえ方 |
| 1齢(毛蚕) |
1倍 |
| 2齢はじめ |
20倍 |
| 3齢はじめ |
120倍 |
| 4齢はじめ |
730倍 |
| 5齢はじめ |
2,640倍 |
| 熟蚕 |
10,000 倍 |
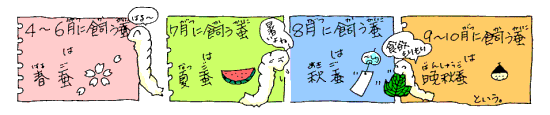
カイコを育てる

1.部屋の準備
部屋を
掃除して、
蚕を
飼うための
棚を
作り、
竹かご(エビラ)をならべる。
部屋は
消毒をする。
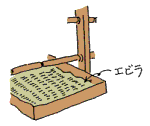
2.掃き立て
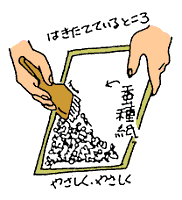
エビラの
上にオダテという
薄いゴザを
敷き、その
上に
蚕座紙という
紙を
敷いて
蚕座を
作る。そこに
卵からかえった
毛蚕を
鳥の
羽根のほうきでやさしく、やさしく
掃きおとす。
蚕種紙
種屋さん(蚕種製造者)は、蚕の卵を紙の上に産み付けさせて蚕種紙を作る。農家はそれを買って、卵をふ化させ、養蚕をおこなう。
3.桑の葉を与える
 蚕
蚕は
桑の
葉を
食べて
大きくなる。
桑畑から
毎日のように
桑をとってきて
食べさせる。
特に
小さいころは
葉を
細かくきざんであげなければならないし、1
回に
食べる
量が
少ないから、
食事の
回数を
多くしなければならない。1
日に5~8
回。おちびの
間は
夜中だって
桑の
葉を
与えるんだ。
たくさんの
蚕がいっせいに
桑を
食べるのは
雨の
降る
音に
似ているそうだ。
 育てる!
育てる!
桑を食べさせるだけではないよ。何日かおきに蚕座にたまる食べのこしやうんちの掃除もしなけりゃ。
4.まゆを作る
4齢をすぎて、からだがすきとおった蚕は、木や紙、わらなどで作ったマブシとよばれるまゆ作りの場所に移される。蚕は頭を8の字にふりふり糸をはいてまゆを作る。
3~4日するとまゆが出来上がり。振ってカラカラ音がしたら、まゆ作りがおわったしるし。
5.出荷
マブシからまゆをあつめ、わらくずなどを取りのぞき、出荷する。
まゆをあつめる場所で売られて…
6.製糸工場へ
横浜開港のころは、農家の副業でしかなかった生糸づくり。
明治5(1872)年、官営の富岡製糸工場が設立されると、それを真似てあちこちに小規模ながら機械製糸場ができた。
生糸輸出がおどろくほど伸びたのはこれらの製糸場があったからだ。
- 良くないまゆはとりのぞく。
- まゆを蒸して、中のさなぎを殺し…
- まゆを乾燥させる。
- 鍋でまゆを煮て、糸の取り出し口を見つけ…
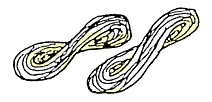 ひきだした糸を何本かより合わせて小さな枠にまきとる。
ひきだした糸を何本かより合わせて小さな枠にまきとる。- そのままでは糸同士がくっつくのでもう1度大きな枠にまきなおす。
- 枠からはずすと生糸のかせのできあがり!
 製糸工場は、その周辺からはもちろん、好景気で人手不足になってくると、かなり遠いところからも女工さんをやといいれた。12~13才ぐらいから働きに出た女の子たちは、自分は一生着ることのないだろう絹を織る生糸をせっせとつむぐのだった。
製糸工場は、その周辺からはもちろん、好景気で人手不足になってくると、かなり遠いところからも女工さんをやといいれた。12~13才ぐらいから働きに出た女の子たちは、自分は一生着ることのないだろう絹を織る生糸をせっせとつむぐのだった。
八王子あたりの機織りうたに♪早く日が暮れて 早く夜があけて 3月2日がくればよい♪というのがある。3月2日は年季あけの日とされていた。このころは年季奉公で最初にとりきめた期限はつとめあげなければならなかったんだ。
明治~昭和初に使われていた養蚕・製糸の道具
<桑しょいかご>  つみとった桑の葉を持ちかえるのに使うかご。
つみとった桑の葉を持ちかえるのに使うかご。
<桑もぎ>  桑の小枝が多い春に使うとか。
桑の小枝が多い春に使うとか。
<桑切り機> 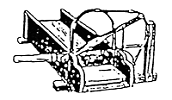 桑の葉を細かくきざむのに使う。
桑の葉を細かくきざむのに使う。
<ねん糸機> 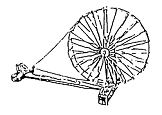 糸をより合わせるのに使う。
糸をより合わせるのに使う。
<座繰機> 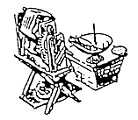 なべの中でまゆを煮、糸をひきだして巻きとる。
なべの中でまゆを煮、糸をひきだして巻きとる。
明治10年以降出現。明治30年以降は輸出生糸は機械製糸となった。
参考にした本
「東京百年史 第1巻」
「図説横浜の歴史」
「神奈川県史」
「神奈川県の歴史 下」
「横浜の歴史」
「平凡社こども世界百科」
かがくのとも傑作集「かいこ」
科学のアルバム「カイコ」
「秋川市蚕糸業史」
「日野と養蚕」
「小平町誌」
「郷土こだいら」
「東京の交通」
「日本の鉄道」
「鉄道の時代」
「八王子物語」
「史跡でつづる東京の歴史」
「わがまちの歴史八王子」
「絹の道」
「多摩のあゆみ」第55号
「シルク・ロード・ハンドブック」ほか、いろいろ。
小平市に関すること
多摩に関すること
江戸・東京に関すること
玉川上水・小金井桜に関すること
その他
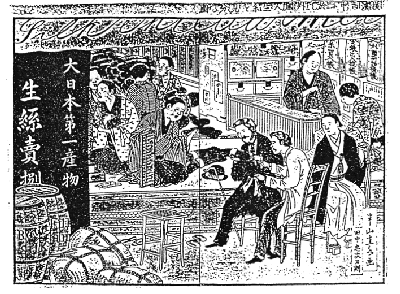

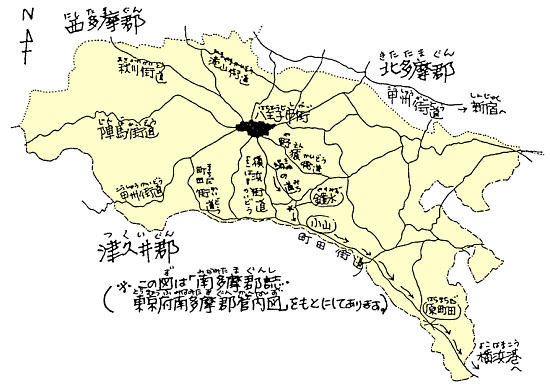
 1875(
1875(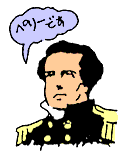
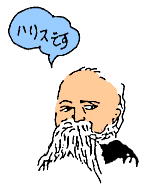 というのが
というのが ペリーの2
ペリーの2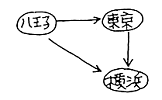
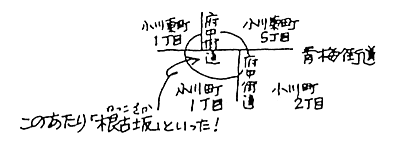

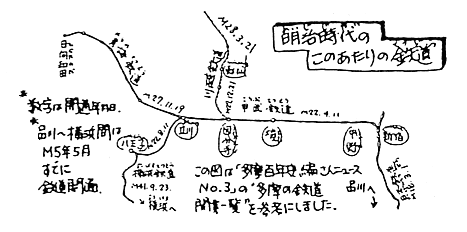
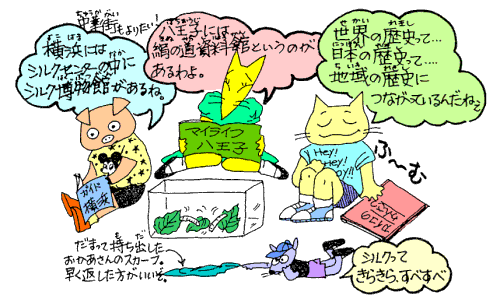

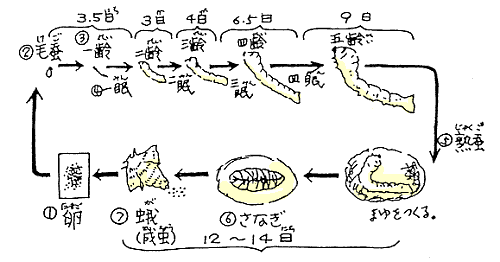
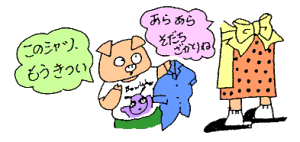

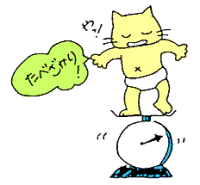
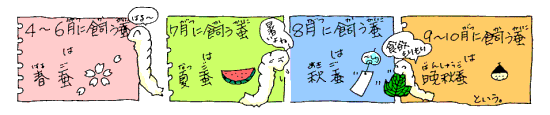

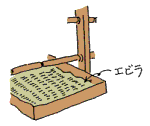
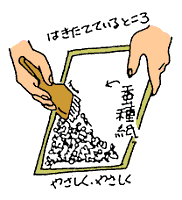 エビラの
エビラの

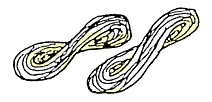 ひきだした
ひきだした
 つみとった
つみとった
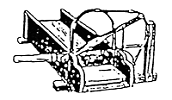
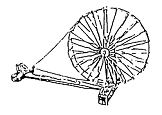
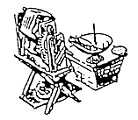 なべの
なべの



















