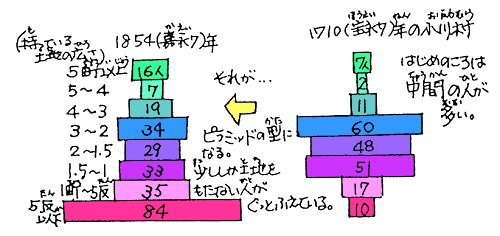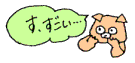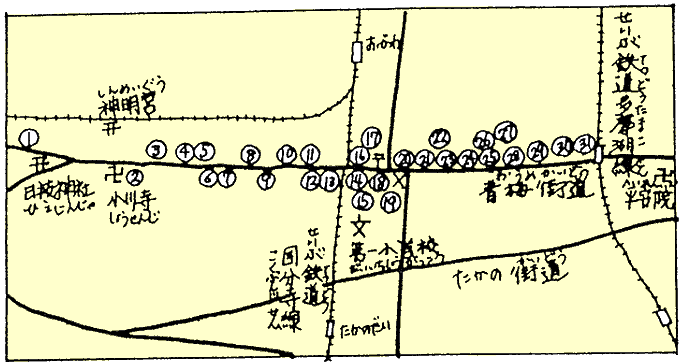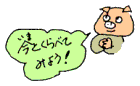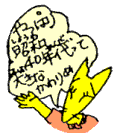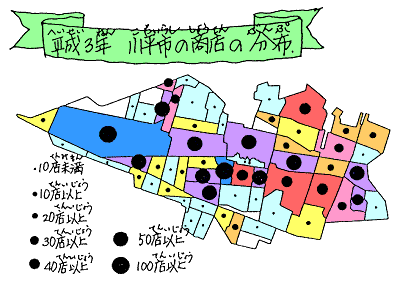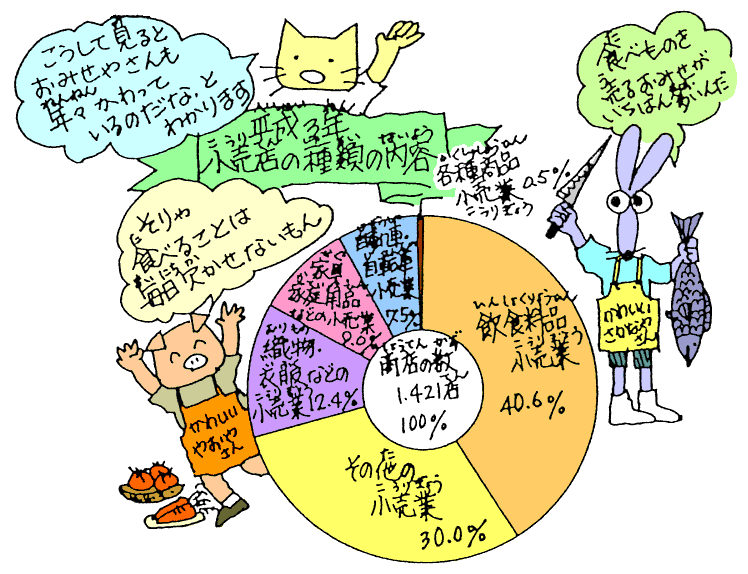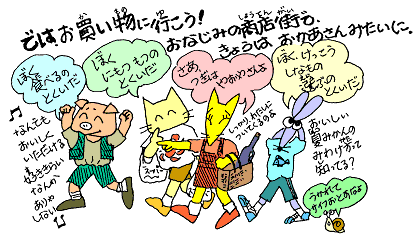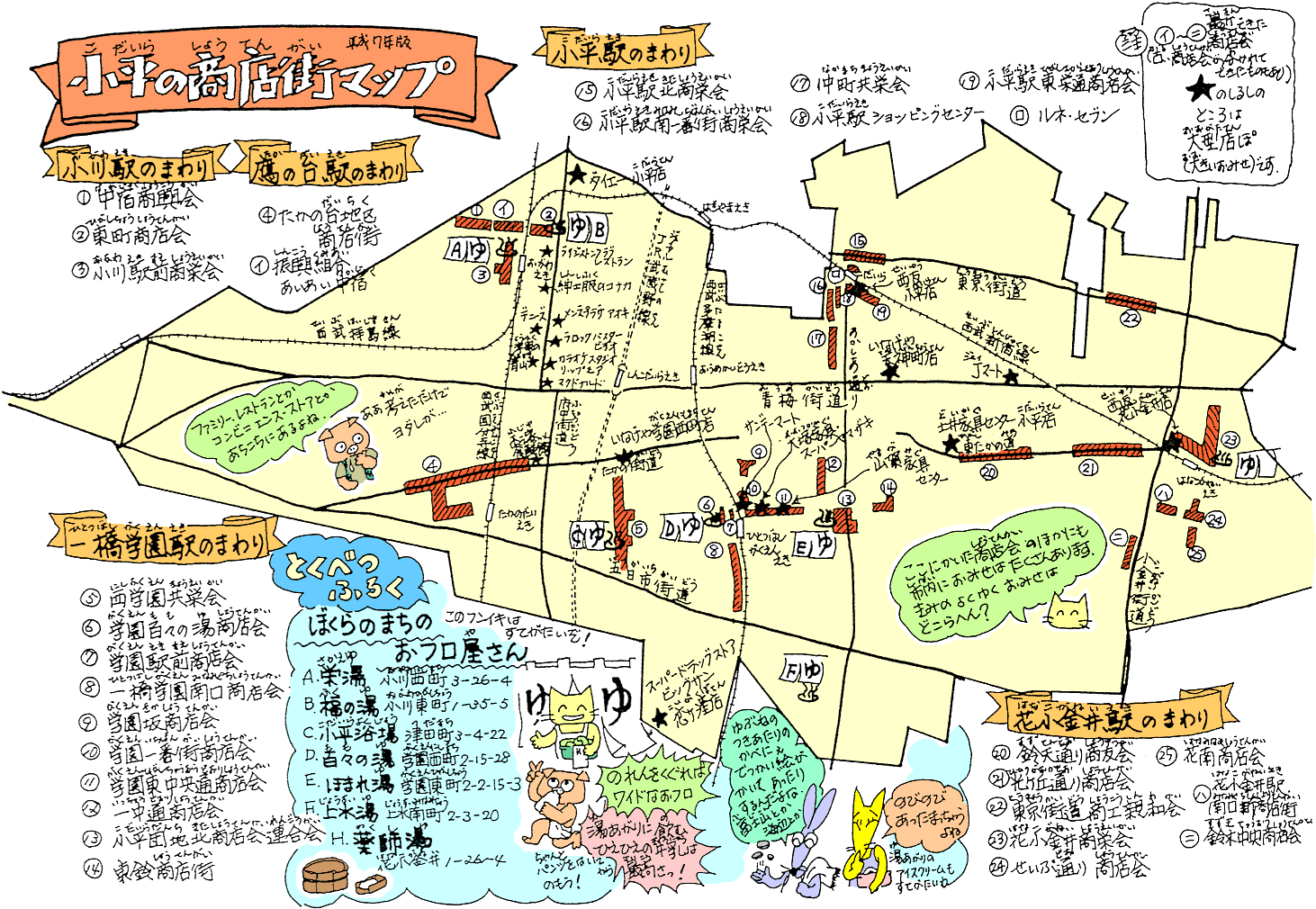町丁別小平市の商店(卸売・小売・飲食店)の数
ぼくらも消費者(おかいものする人)
家のまわりには、いろいろなお
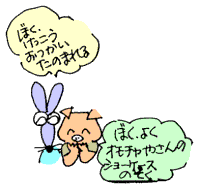
みせやさんがあるよね。やおやさん、
魚屋さん、クリーニング
屋さん、おそば
屋さん、
花屋さんに
電気屋さん。おみせやさんの
仕事をひっくるめて
商業って
言うんだ。
小平だって
初めから、こんなにたくさんのおみせがあったわけじゃない。
新田開発の、
村の
時代までさかのぼって、どんなふうに
商業が
発達していったのか
見てみようよ。
町丁別小平市の商店(卸売・小売・飲食店・宿泊業)の数
平成18(2006)年10月1日現在 (「平成20年度統計書」より)
小平市の商店の数
| こうもく |
数 |
| 合計 |
1,959店 |
| 中島町 |
10 |
| 上水新町1丁目 |
4 |
| 上水新町2丁目 |
3 |
| 上水新町3丁目 |
11 |
| たかの台 |
72 |
| 小川町1丁目 |
132 |
| 小川町2丁目 |
76 |
| 栄町1丁目 |
0 |
| 栄町2丁目 |
1 |
| 栄町3丁目 |
4 |
| 小川西町1丁目 |
5 |
| 小川西町2丁目 |
18 |
| 小川西町3丁目 |
31 |
| 小川西町4丁目 |
69 |
| 小川西町5丁目 |
8 |
| 小川東町 |
2 |
| 小川東町1丁目 |
50 |
| 小川東町2丁目 |
3 |
| 小川東町3丁目 |
6 |
| 小川東町4丁目 |
7 |
| 小川東町5丁目 |
31 |
| 上水本町1丁目 |
2 |
| 上水本町2丁目 |
16 |
| 上水本町3丁目 |
4 |
| 上水本町4丁目 |
4 |
| 上水本町5丁目 |
5 |
| 上水本町6丁目 |
9 |
| 上水南町1丁目 |
7 |
| 上水南町2丁目 |
18 |
| 上水南町3丁目 |
7 |
| 上水南町4丁目 |
1 |
| 喜平町1丁目 |
14 |
| 喜平町2丁目 |
7 |
| 喜平町3丁目 |
6 |
| 津田町1丁目 |
9 |
| 津田町2丁目 |
6 |
| 津田町3丁目 |
8 |
| 学園西町1丁目 |
102 |
| 学園西町2丁目 |
75 |
| 学園西町3丁目 |
20 |
| 学園東町 |
7 |
| 学園東町1丁目 |
124 |
| 学園東町2丁目 |
56 |
| 学園東町3丁目 |
66 |
| 仲町 |
62 |
| 美園町1丁目 |
103 |
| 美園町2丁目 |
34 |
| 美園町3丁目 |
14 |
| 回田町 |
17 |
| 御幸町 |
13 |
| 鈴木町1丁目 |
61 |
| 鈴木町2丁目 |
52 |
| 天神町1丁目 |
51 |
| 天神町2丁目 |
16 |
| 大沼町1丁目 |
14 |
| 大沼町2丁目 |
41 |
| 花小金井南町1丁目 |
55 |
| 花小金井南町2丁目 |
34 |
| 花小金井南町3丁目 |
7 |
| 花小金井1丁目 |
127 |
| 花小金井2丁目 |
8 |
| 花小金井3丁目 |
25 |
| 花小金井4丁目 |
39 |
| 花小金井5丁目 |
38 |
| 花小金井6丁目 |
33 |
江戸時代のこだいらの商業
江戸時代
新田開発で、農民が集まり、成り立っていった小平の村々。やがて生産力が高まり、生活も落ち着いてくると、「農業をしながら商売もする」という人があらわれだした。こういうのを『農間商渡世』って言うんだ。『村明細帳』の記録を中心にこのころの小平で、どんな商売がおこなわれていたか見てみようね。
小川村
1816(
文化13)
年ころ
農業の
間に
商売をする
家 13
軒
酒・
酢・しょうゆ・
灯油・
紙・ろうそく・
小間物・ぞうり・わらじ・あめ
菓子・
塩魚などの
商いをする。
職人
大工職人4
人、
木挽職人2人、
屋根屋職人4
人、
桶屋職人2人
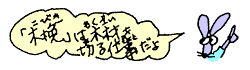 水車
名主小太夫
水車
名主小太夫と
年寄俊蔵がひとつずつ
1842(天保13)年ころ
商売をする家 19軒に増える。
回り田新田
1828(文政11)年ころ
15軒の農家のうち、7軒が農間商か、職人をかねる。
大沼田新田
1821(文政4)年ころ
商人は5人…油しぼり・ぬか商い、綿商い(2人)、酒造・しょう油商い(名主・弥左衛門の商売)、小間物商い
職人 屋根職人4人
鈴木新田
1827(文政10)年のころにすでに109軒の農家のうち31軒が商業か職人を兼ねている。
1850(嘉永3)年ころ
商売家10軒 居酒・そば(4軒)、菓子・青物(野菜)、酒・せともの・荒物、紙類・水油、酒・しょうゆ・紙・木綿類、穀物・質・薬種、酒・うどん・一ぜんめし
職人 屋根ふき職人(3人)、大工職人(5人)、建具職人(1人)
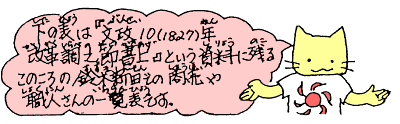
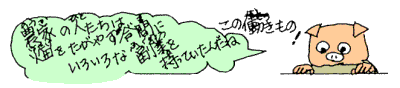
商売などをやっている人
| いつから |
やっている人 |
商売などの内容 |
| 1778(安永7)から |
百姓勘兵衛 |
酒・しょうゆ・蕎麦・荒物など |
| 1778(安永7)から |
組頭吉兵衛 |
酒・しょうゆ・穀物・荒物・紙・木綿 |
| 1798(寛政10)から |
百姓兵左衛門 |
豆腐屋 |
| 1798(寛政10)から |
百姓作右衛門 |
荒物・小間物など |
| 1796(寛政8)から |
百姓権兵衛 |
酒・しょうゆ・荒物・木綿類 |
| 1793(寛政5)から |
百姓源八 |
酒・しょうゆ・うどん・蕎麦 |
| 1808(文化5)から |
百姓平八 |
素麺拵 |
| 1808(文化5)から |
百姓弥平治 |
ひな人形祝道具 |
| 1808(文化5)から |
百姓彦八 |
酒・しょうゆ・うどん・蕎麦・荒物 |
| 1808(文化5)から |
百姓清次郎 |
糸・繭・紫根の中買、酒・しょうゆ・うどん |
| 1815(文化12)から |
百姓文右衛門 |
うどん・蕎麦 |
| 1818(文政元)から |
組頭庄治郎 |
酒・しょうゆ・小間物など |
| 1818(文政元)から |
百姓鉄五郎 |
青物(野菜のこと)売買 |
| 1818(文政元)から |
百姓藤右衛門 |
糸綿商売 |
| 1818(文政元)から |
百姓舛五郎 |
豆腐造り |
| 1818(文政元)から |
百姓織右衛門 |
肴売 |
| 1818(文政元)から |
百姓由太郎 |
うどん・蕎麦 |
| 1818(文政元)から |
百姓直右衛門 |
荒物・釘鉄物類 |
| 1820(文政3)から |
百姓千蔵 |
青物(野菜)売買 |
| 1820(文政3)から |
百姓磯右衛門 |
古着屋 |
| 1821(文政4)から |
百姓幸治郎 |
紺屋 |
| 1823(文政6)から |
百姓久五郎 |
古道具箱物類 |
| 1823(文政6)から |
百姓久右衛門 |
豆腐造り |
| 1804(文化元)から |
百姓七左衛門 |
菓子屋 |
| 1788(天明8)から |
百姓又右衛門 |
大工職人 |
| 1803(享和3)から |
百姓彦四郎 |
茅屋根職人 |
| 1813(文化10)から |
百姓万五郎 |
大工職人 |
| 1818(文政元)から |
百姓彦治郎 |
茅屋根職人 |
| 1818(文政元)から |
百姓伊平治 |
綿打職人 |
| 1798(寛政10)から |
百姓佐兵衛 |
髪結床 |
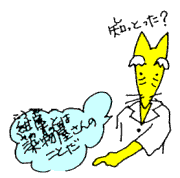
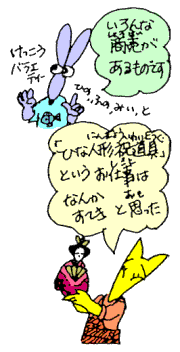
小川家の農間渡世
水車を
使って
商売をする「
水車かせぎ」や、
酒造り、しょうゆしぼりなどの
仕事は
幕府から
許された
特別な
権利だった。だから、こういう
商売は、
村の
有力な
農民が
独占していた。
小川村名主の
小川家では、
1706(
宝永3)
年、
酒造株(
酒造りの
権利)を
持ち、
1765(
明和2)
年には、
水車を
設け、
安永ごろ(1771~1781)からは、
幕府の
御用請負人として
遠州(
今の
静岡県西部)や
信州(
今の
長野県)の
材木切り
出しの
仕事を
請け
負ったりした。
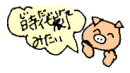
いろいろと、
手広く
商人として
活動したようだ。
村の市場
享保の時代にはいって、武蔵野は新田開発が進み、人口も品物の流れも増えていった。
1734(享保19)年5月、小川村名主弥次郎は、鈴木新田名主利左衛門とともに、村に市場を開きたいと願い出た。いちいち江戸の相場(ねだん)を確かめてからでないと、穀物を売り買いできないのは不便だから、地元に市をたてて、取り引きをかんたんにしたい、というのが理由だった。
許しがでたのは、5年後の1739(元文4)年10月。けれど、小川村でも、鈴木新田でも、あまり市場はにぎわなかった。と言うのも、みんな、大都市・江戸や、まわりの町へ作物を持ちこんで取り引きする方に力を入れたからなんだ。
水車かせぎ

1815(
文化12)
年9
月、
鈴木新田の
長右衛門、
水車をかける
願いを
出す。
1816(
文化13)
年8
月、
野中新田の
文右衛門、
仁左衛門、
水車をかける
願いを
出す。
1817(
文化14)
年2
月、
鈴木新田の
勘七、
水車をかけるについて、
村役人に
書類を
出す。
1837(
天保8)
年、
大沼田新田の
年寄、
伝兵衛、
水車の
貸し
付けを
始める。
1853(
嘉永6)
年、
野中新田の
長右衛門が
名主、
善左衛門から
水車を
借りる。
というように、
水車でかせぐ
人たちがつぎつぎと
出てきた。まわりの
村々から
穀物などを
買い
入れ、
水車で
精白したり、
製粉したりして、それを
売る、という
商売だ。それまで
小麦粉や
蕎麦粉は
石うすを
手でまわして、
作っていた。けれど
江戸で
求められる
量が
増えたことが
生産の
力を
高めていった。
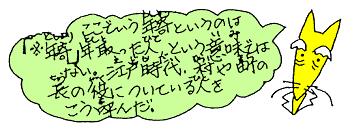 江戸
江戸のうどん
屋、そば
屋は、
自分で
粉をひくのをやめて、
粉屋から
材料を
買うようになる。
江戸の
粉屋で、
農村に
水車を
持つものがあらわれ、また
農村の
農民の
中からも、
水車で
製粉し、
江戸に
送って、
自分で
商売する
者があらわれだした。
水車かせぎは
農村の
経済の
発達が
原因でもある。
江戸時代の
半ばから、
農村でも
自給自足のくらしから、ものを
買うことが
多くなって、
商業・
工業をおこなう
農民があらわれたんだ。とりわけ
江戸のまわりの
村々ではそれがめざましかった。
水車かせぎは
豪農をより
豪農にした。
村の商人が江戸商人の独占をうちやぶった事件
農民が
自分の
作物を
運んで
行って、
直接売ることを「
直売」という。
武蔵野の
村々が
直売をすすめると、
問題はあれこれ
持ち
上がった。
まず、
荷物の
運送でお
金をかせぐ
宿駅や
業者は、
農民の
直売を
嫌った。けれど、
農民の
方だって、
自由な
交通をさまたげる
宿駅や
運送業者の
独占を
快く
思っていなかった。
江戸の
入り
口、
内藤新宿(
今の
新宿)では、1771(
明和8)
年から、
自分で
荷を
運ぶ
者が
通る
時口銭(
税金だ)を
取っていた。1782(
天明2)
年、
多摩郡42
村が
団結して、
代表を
奉行所に
送り、
口銭をやめることをうったえた。
この
争い、
宿駅の
方が
折れて、42
村にかぎり
口銭は
取らない
約束となった。
また、1827(
文政10)
年には、
野中新田の
農民、
重右衛門が
江戸麹町(
今の
千代田区)にみせを
借り、
直接、
買い
手と
商売を
始めた。
重右衛門はもともと、
産地から
問屋へ
作物を
売る
荷主だったけれど、
問屋の
支払いが
遅れがちなのを
嫌って、みせを
開いたのだった。
江戸の
穀物の
問屋仲間は1828(
文政11)
年、
重右衛門を
奉行所にうったえた。
問屋仲間を
通さず、
勝手に
商売をしている、というわけだ。しかし、
重右衛門は
主張した。
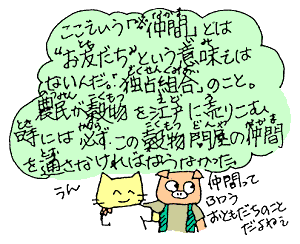
「
小麦粉、
蕎麦粉は
売っているけれど、
穀物は
売っていない。
穀物問屋の
妨害はしていない。」
重右衛門の
言い
分は
通り、
武蔵野の
代表的作物の
小麦を、
製粉すれば、
直接江戸に
持って
行って
売って
良いことになった。
江戸の
問屋仲間はまわりの
農村から
流れこむ
商品をもはや
止めることはできなくなった。
江戸の
商人による
独占は
農民の「
直売」にくずれさった。1841(
天保12)
年、
老中水野忠邦は
天保の
改革のひとつとして
株仲間の
解散を
命じた。
このように、
村の
商人たちはだんだんと
成長していった。
やがて…
手広く
商売する
人たちがでてくると、その
反対に
土地を
売ったり、
借金したりする
貧しい
農民も
増えてきた。1754(
宝暦4)
年の
小川村の『
村明細帳』という
記録では「めだって
大きな
土地持ちはない」と
書いてあるけれど、
時代がくだるにつれて
所有地の
少ない
人がぐっとふえる。
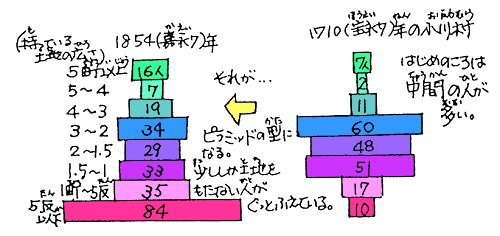
明治時代以降のこだいらの商業
明治時代以降
江戸時代後半から、商業がおこった小平。明治維新後は時代の変化で、さらに活動が盛んになったと思われる。けれど、残念ながら、その当時の商業の様子をはっきりさせる資料は残っていないんだ。
昭和の初め(戦前)
小平は昭和10(1935)年ころまでは、全戸数の8割が農家だった。
商業は、食料品や雑貨とか、毎日のくらしに必要な品を扱うみせが、街道沿いにならぶ、という様子だった。
太平洋戦争中(1941~1945)
この時期は、「統制経済」といって、生活に欠かせない品々が国の管理のもとに置かれた。
配給制、切符制なので、1人にわりあてられる品数や量は限られ、自由な商売ができなかった時代だから、商業はふるわなかった。
戦後(1945~)
戦争がおわると、
小平では
次々と、
団地や
都営の
住宅が
建った。すると、
今まで
街道を
中心にちらばっていた
商店が、
駅だの、これらの
住宅だのを
中心に
形作られるようになってきた。

昭和30年代以降(1955~)
 昭和
昭和35(1960)
年6
月、「
商工会法」という
法律が
施行された。
これに
基いて、
全国各地で
法人商工会が
作られていった。
小平町でも
昭和36(1961)
年4
月25
日、
商工会の
創立総会が
開かれた。そして7
月8日。
会員数477
人、
東京都で
第6
番目の
法人商工会となった。
小平商工会が
今の
住所である
小川町2-1268に
会館を
建てたのは
昭和48(1973)
年のこと。はじめの
頃は
小平町役場(のち、
小平市役所)の
中に
事務局(いろいろな
事務をとりまとめてするところ)があったんだそうだよ。
さて、
人口の
増加にともなって
商業は
発展していった。
昭和37(1962)
年から
昭和63(1988)
年の
間に、
小平は
人口が2.6
倍、
世帯数は3.3
倍、そして、
商店の
数は519から2、193に
増えたから、なんと、4.2
倍!
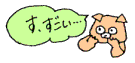
とりわけ
増加が
激しかったのは
昭和40
年代(1965~1974)だ。
ファミリー・レストランや
大きなスーパー・マーケットが
市内に
登場しはじめたのもこのころ。
昭和50
年代にはいるとコンビニエンス・ストアもあらわれるようになった。

商工会議所・商工会って、なあに?
商工会議所・商工会は、商業や工業を営む人たちで作る団体だ。その地域の商工業をより良く発展させるためにある。そのための調査をしたり、見本市を開いたり、意見交換や勉強会をおこなったり、とさまざまな活動をしている。
商工会議所のおこりは、古代までさかのぼるけれど、その名が最初についたのは1599年に設立したフランスはマルセーユの商工会議所。日本では、1791(寛政3)年につくられた「江戸町会所」が始まりとされる。寛政の改革の際誕生して、江戸町人(地主たち)の積立金でつくられ、運営も町人(大商人など)がおこなった。飢饉や災害に備えての積立とか、武士や町人に低い利子でお金の貸付をしたり、とかいろいろな経済活動をした。そして1878(明治11)年には今日の東京商工会議所のもととなる「東京商法会議所」ができた。
戦後は「商工会議所法」(昭和28年公布)、「商工会法」(昭和35年公布)といった法律に基いて設立されることになった。
(商工会議所・商工会は、うけもつ地域の範囲に違いがあるだけで目的や設立の条件はほとんど同じです。)
≪昭和30年の青梅街道の商店≫
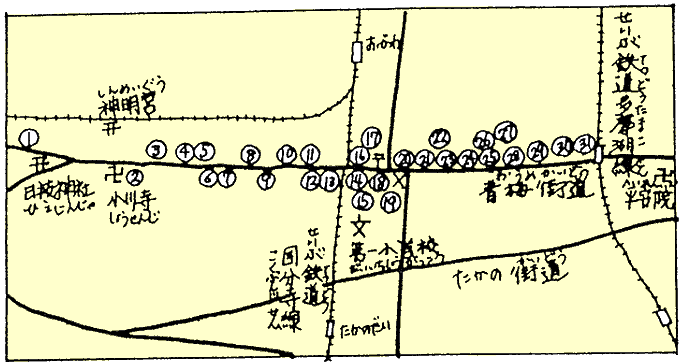
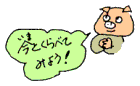
この
番号のところには、こんな
商店があった!
- 炭
- 食料品雑貨
- 洋服仕立
- 床屋
- 居酒屋・たばこ
- 不明(集会所か?)
- ガソリン
- 運送業
- 自転車
- 電気器具
- もち菓子
- 雑貨
- 建築請負
- 製めん
- 文房具・菓子
- 自転車
- 自転車
- 酒
- ガソリン
- 魚
- 桶
- 自動車
- 製めん
- 建具
- たばこ
- もち菓子
- 床屋
- 精米
- 石材
- 材木
- 菓子
数字で見る小平の商業のうつりかわり
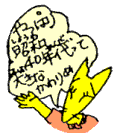
小平市の商店の数の移りかわり
| 調査した年 |
卸売店 |
小売店 |
飲食店 |
合計 |
| 1962(昭和37) |
26 |
425 |
68 |
519 |
| 1966(昭和41) |
97 |
857 |
159 |
1,113 |
| 1972(昭和47) |
126 |
1,384 |
438 |
1,948 |
| 1979(昭和54) |
255 |
1,586 |
699 |
2,510 |
| 1985(昭和60) |
270 |
1,501 |
506 |
2,277 |
| 1991(平成3) |
296 |
1,421 |
476 |
2,193 |
| 1999(平成11) |
277 |
1,360 |
|
1,637 |
| 2007(平成19) |
189 |
966 |
|
1,155 |
開店した年で分けた商店(卸売店・小売店)の数
| 調査した年 |
昭和19年以前に開店した店 |
昭和20~39年 |
昭和40~49年 |
昭和50~63年 |
平成元年 |
平成2年 |
平成3年1月から平成3年6月まで |
合計 |
| 1976(昭和51) |
77 |
597 |
1,445 |
248 |
|
|
|
2,367 |
| 1982(昭和57) |
48 |
460 |
781 |
552 |
|
|
|
1,841 |
| 1985(昭和60) |
48 |
454 |
705 |
564 |
|
|
|
1,771 |
| 1988(昭和63) |
47 |
415 |
618 |
616 |
|
|
|
1,696 |
| 1991(平成3) |
34 |
373 |
557 |
589 |
77 |
59 |
28 |
1,717 |
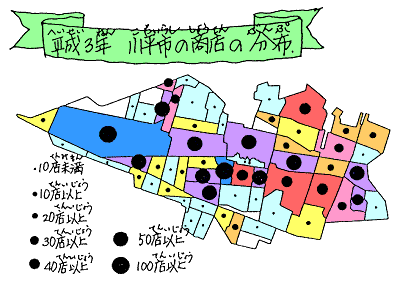
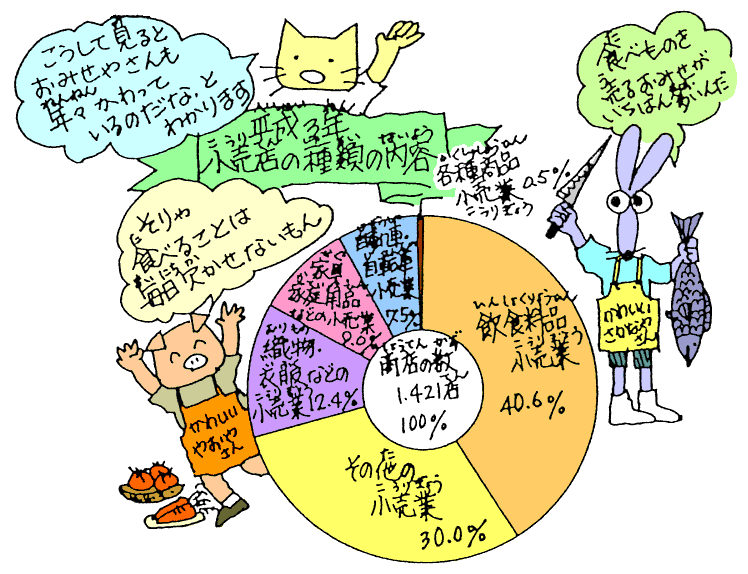
小平の商業年表
小平の商業年表
| 年 |
できごと |
| 1656(明暦2) |
この年、小川九郎兵衛、小川村の開発を申し出る。 |
| 1706(宝永3) |
9月 八王子八幡宿の伊丹屋六郎左衛門から、小川弥市、酒造株の一部をゆずりうける。 |
| 1724(享保9) |
5月 小川新田、大沼田新田、鈴木新田、野中新田の開発始まる。 |
| 1765(明和2) |
この年、小川弥次郎、小川分水に水車をしかける。 |
| 1772(明和9) |
この年、大沼田新田名主、弥十郎と伝兵衛、大沼田分水に水車をしかける。 |
| 1775(安永4) |
この年、小川新田の宮崎釆女、屋敷に水車をしかける。 |
| 1778(安永7) |
この年、鈴木新田の善兵衛、水車をしかける。 |
| 1810(文化7) |
この年、当麻弥左衛門が酒造を始める。 |
| 1821(文政4) |
このころ、小川村の農間渡世は、炭・薪の運搬や、日雇い、馬のくつ・わらじ作り。女の人は木綿の布織りをした。 |
| 1827(文政10) |
この年、野中新田(今の花小金井)の重右衛門、株仲間を無視して、麹町に蕎麦粉、小麦粉の問屋を開業する。
この年、鈴木新田の農間商人、職人は30軒になる。 |
| 1842(天保13) |
この年、小川村の農間商人、19軒となる。 |
| 1892(明治25) |
このころ、小川の蚕種業おこる。(かいこの種屋さんだ) |
| 1925(大正14) |
この年、小平学園の土地分譲が始まる。 |
| 1940(昭和15) |
4月 米・みそ・しょうゆ・塩・マッチなど、生活用品の切符制が始まる。 |
| 1941(昭和16) |
12月 太平洋戦争、始まる。 |
| 1945(昭和20) |
8月 太平洋戦争、終わる。 |
| 1946(昭和21) |
3月、旭ケ丘営団住宅、完成。 |
| [これより、戦後、市内に都営住宅、社宅などがつぎつぎと建設。] |
| 1961(昭和36) |
4月 小平町商工会、設立。 |
| 1964(昭和39) |
7月 土井家具センター小平店、天神町1丁目にできる。
10月 東京オリンピック、開かれる。
この年、東京都商店コンクールで中宿商興会が優良賞、受賞。 |
| 1968(昭和43) |
12月 西友小平店、美園町にできる。 |
| 1971(昭和46) |
11月 オダキューOX小平店、学園東町にできる。(現在は、閉店)) |
| 1973(昭和48) |
3月 小平商工会館、完成。
4月 いなげや学園西町店できる。 |
| 1974(昭和49) |
5月 山賀家具センターできる。 |
| 昭和40年代は小平の人口がもっともはげしく増加。商業もそれにともなって発展した。 |
| 1977(昭和52) |
12月 いなげや天神町店できる。 |
| 1978(昭和53) |
11月 サンデーマート、学園東町にできる |
| 1979(昭和54) |
5月 ダイエー小平店、小川東町にできる。 |
| 1981(昭和56) |
4月 Jマート、天神町にできる。(現在は、閉店) |
| 1982(昭和57) |
5月 西友花小金井店できる。 |
| 1983(昭和58) |
11月 第1回商業まつり、開かれる。 |
| 1987(昭和62) |
3月 ビックサン恋ヶ窪店、上水本町にできる。(現在は、サンドラッグ) |
| 1989(平成元) |
9月 第1回小平商工会サービス業まつり開かれる。 |
人名の読み方は『寛政重修諸家譜』を参考にしています。
商店の歴史
商店、つまりおみせは町とともに生まれ、育つ。
日本ではおみせは平安時代(794~1192)からあったと記録に残っている。ただし、商業がぐんと発達したのは、江戸時代にはいってから。そのころの大阪などは米を扱って、正徳年間(1711~1716)には、問屋がおよそ5,000軒。仲買店9,000軒がたちならんだという。
江戸のみせは何度もの大火事をへて、土蔵造り(外の面を土で厚くぬった造り。燃えにくい。)が多くなった。この造りは大正の関東大震災まで東京のあちこちで見られた。
明治にはいるとれんが造りもあらわれた。また、木造でもショーケースをつくったり、軒に看板をかかげたりするようになった。
商店街のなりたち
商店街はなりたちから、3つのタイプにわけられる。
1.歴史的な商店街
むかしながらの町わりや、城下町の市、神社・お寺の門前のおみせをはじまりとする。
2.都市開発による商店街
郊外のニュータウンなどの、大駐車場のあるショッピング・センターなどがこの例。
3.毎日のくらしの中で自然にかたち作られた商店街
この例は多い。住宅のあつまる地域と鉄道の駅や主要な道路などとの結びつきでできあがってゆく。
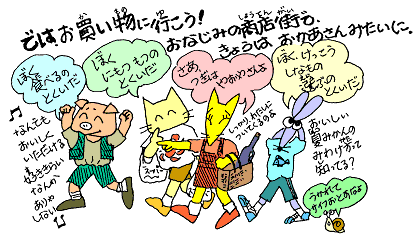
小平の商店街マップ
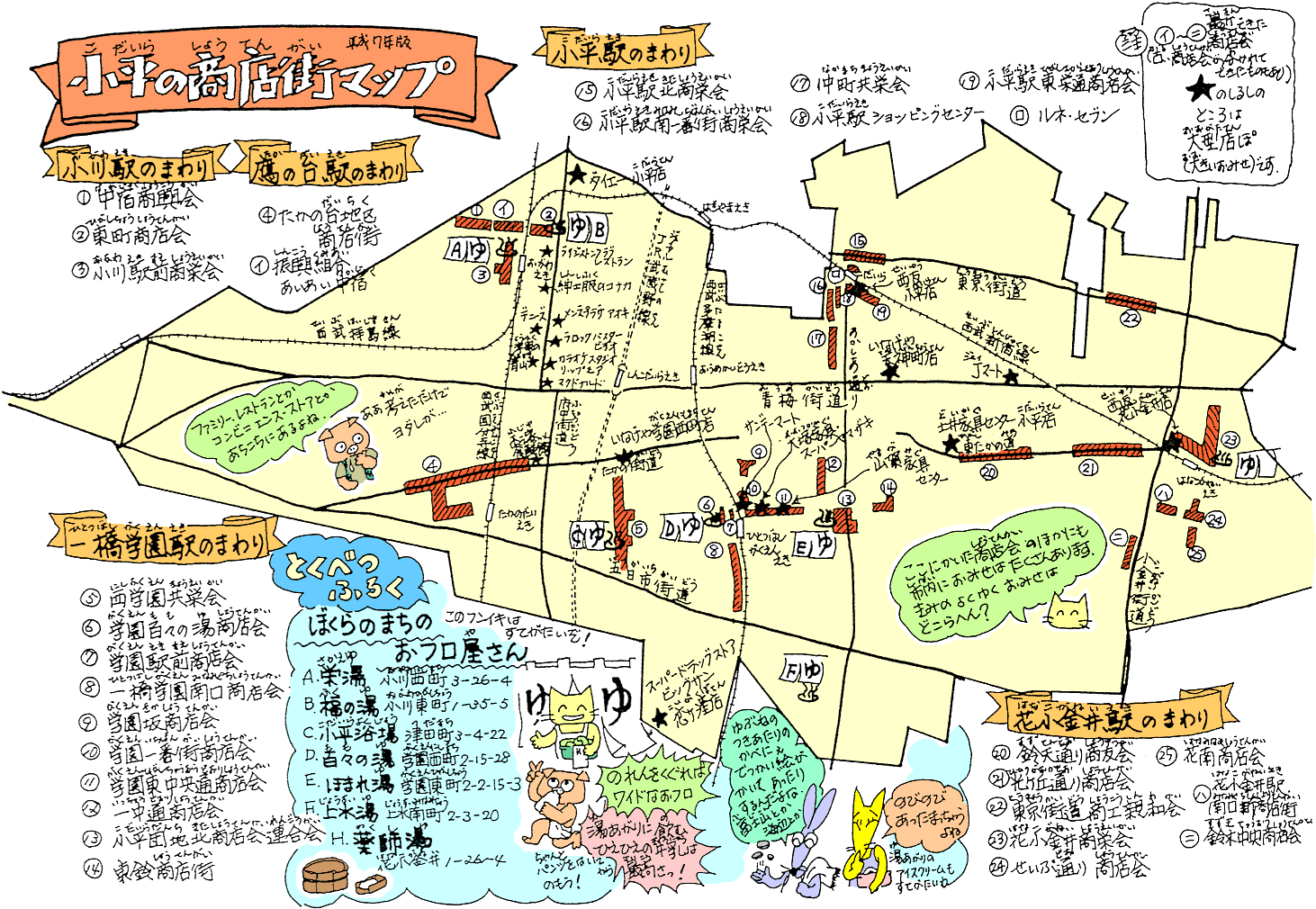
参考にした本
「小平町誌」
「小平三〇年史」
「小平市住宅地図」
「NTTタウンページ」
「小平商工会地域ビジョン報告書 昭和57年」
「小平市の商工業 平成5年刊」
「昭和57年統計書」
「平成6年統計書」
「昭和54年 小平市の商工業」
「武蔵野の水車小屋」
小平市に関すること
多摩に関すること
江戸・東京に関すること
玉川上水・小金井桜に関すること
その他
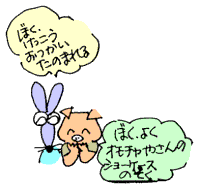 みせやさんがあるよね。やおやさん、
みせやさんがあるよね。やおやさん、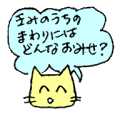
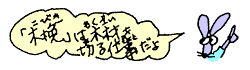
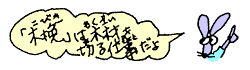
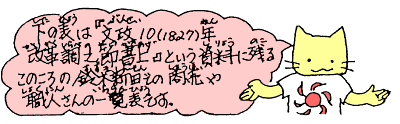
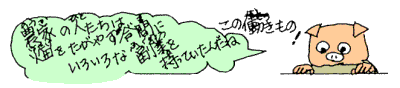
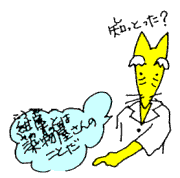
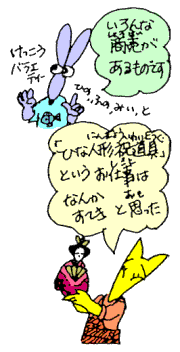
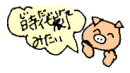
 1815(
1815(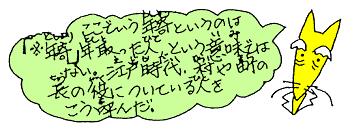
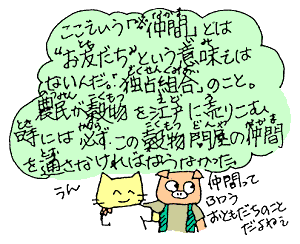 「
「