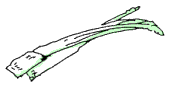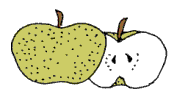小平の農業データ
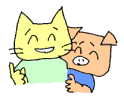 きみの家のそばに畑はあるかい? 畑では今、何が育ってる? ねぎかな? 梨かな? キャベツかな?
きみの家のそばに畑はあるかい? 畑では今、何が育ってる? ねぎかな? 梨かな? キャベツかな?
小平市内のあちこちに畑はあるのに、何が作られているのかってけっこう知らないもんだよね。
江戸時代の新田開発から今日まで、ぼくらの町ではどんな作物が育って来たのか、調べてみたよ。時代とともに変化してきた小平の農業。
平成20年小平の農業データ
平成20年小平の農業データ その1
農地面積:253ヘクタール
平成20年小平の農業データ その2
| 作付面積野菜ベスト5 |
作付面積(ヘクタール) |
収穫量(トン) |
| 1.さといも |
13 |
137 |
| 2.ほうれんそう |
11 |
127 |
| 3.ブロッコリー |
11 |
113 |
| 4.大根 |
10 |
419 |
| 5.キャベツ |
8 |
374 |
平成20年小平の農業データ その3
| くだもの |
果樹の面積(ヘクタール) |
収穫量(トン) |
| ぶどう |
2 |
21 |
| 日本梨 |
9 |
233 |
| うめ |
7 |
9 |
| くり |
16 |
17 |
| ブルーベリー |
6 |
18 |
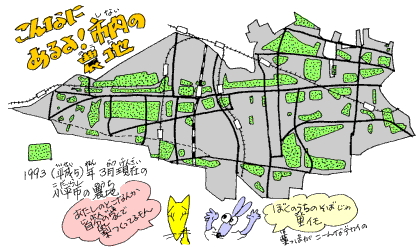
小平の農業の歴史
江戸時代
これは『
村明細書上帳』からの
記録だけれど、このころの
小平の
各村の
農作物ってこういうふうだった。
小川村 1816(文化13)年ころ
田んぼ なし
畑でおかぼ(
稲)、
大麦、
小麦、
蕎麦、
荏、
辛子、
菜、
大根、
胡麻、
大豆、
小豆、イモ
類
大沼田新田 1821(文政4)年ころ
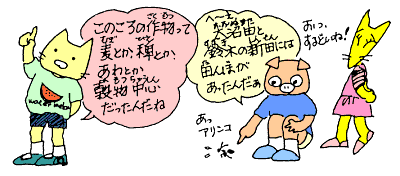 田
田んぼで
稲を
作付している。
畑で
大麦、
小麦、
粟、
稗、
蕎麦、
荏、
胡麻
鈴木新田 1850(嘉永3)年ころ
田んぼで
晩稲(ふつうよりおそくできる
稲)
畑で
大麦、
小麦、
粟、
稗、
大豆、
小豆、イモ、
菜、
大根、
胡麻、
荏、辛子
水にめぐまれない武蔵野の新田に田んぼは少ない。1699(元禄12)年、開発まもない小川村の『作物風損害書上』という記録には、粟、稗、イモ、蕎麦、おかぼ、大根、といった作物の名があがっている。その後も、江戸時代の小平の村々は雑穀中心の畑作をおこなっていた。
享保のころからは、荏・胡麻が作られるようになった。これは生活に欠かせない灯油の原料なんだ。それから甘薯(サツマイモ)も新しい作物として登場。1799(寛政11)年には大沼田新田で辛子が、1821(文政4)年には小川村で大豆・小豆が作られた。また、1836(天保7)年には長雨大風雨で受けた被害に、うり、とうなす(カボチャだよ)、すいかなどの名があがっている。この時期には売るための農作物がでてきているんだね。
明治時代
小川村 1878(明治11)年ころ
米、大麦、小麦、粟、裸麦、稗、蕎麦、蕃薯(サツマイモ)、里イモ、繭、藍葉、製茶、菜種
大沼田新田 1879(明治12)年ころ
米、大麦、小麦、粟、蕎麦、甘薯(サツマイモ)、里イモ、繭、藍葉、製茶、菜種
野中新田善左衛門組 1879(明治12)年ころ
米、大麦、小麦、粟、蕎麦、甘薯(サツマイモ)、里イモ、繭、藍葉、製茶、菜種
野中新田与右衛門組 1879(明治12)年ころ
おかぼ、
大麦、
小麦、
粟、
蕎麦、
甘薯(サツマイモ)、
里イモ、
繭、
藍葉、
製茶、
菜種
回り田新田 1878(明治11)年ころ
米、大麦、小麦、粟、稗、蕎麦、甘薯(サツマイモ)、馬鈴薯(ジャガイモ)、おかぼ、繭、生糸、藍葉、製茶、菜種
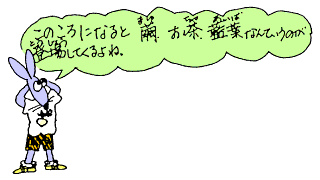
藍 染料として使われる藍の生産は、江戸時代から始まっていたけれど、明治にはいって盛んになった。勢いが衰えたのは明治20年代の後半。ドイツから科学染料アニリンが輸入されだしてからだ。
養蚕 明治政府の「産業をおこし、国を富ませて、強くしよう」という政策は、まず軽工業を発達させた。製糸業もそのひとつ。それにともなって農村の養蚕も盛んになった。明治の20年ころからのびてきて、1917(大正6)年~1931(昭和6)年がピーク。小平でも、農業の中心だった。
お茶 小平は、茶処、狭山丘陵の地続きだったから、早くからお茶栽培がされていた。でも第一の目的は、強い風の吹く武蔵野台地の防風垣としてだ。だから高級品をつくろう、というより、葉っぱがあるから製茶するというかんじだった。北多摩郡の製茶の量は大正の中ごろが一番多かった。そのうち、養蚕に手間がかかるようになって製茶はやめになり、生葉を売るようになった。
大正~昭和初期
甘薯(サツマイモ)と、養蚕のための桑が増え、かわりに粟、蕎麦、稗などはほとんど姿を消した。この時期の小平の農業は養蚕、甘薯、麦が中心なんだ。
大麦は押麦やひきわりで、小麦は粉に加工されて主食になったり、うどんとして商品にされた。
野菜は昭和4(1929)年には大根、ぼごう、すいか、なす、つけななどが栽培されている。
けれど昭和4(1929)年に世界恐慌、昭和12(1937)年に日中戦争、昭和16(1941)年に太平洋戦争と、蚕糸業をゆさぶる出来事がつづく。戦時中は「蚕の桑より食糧を」となって、養蚕はすたれた。
大正から昭和の初めにかけて、最も盛んだったころは小平に16軒もあった蚕種業者(蚕の種屋さん)も、昭和12(1937)年には全てやめてしまった。
戦後
昭和32、3(1957、8)年ころの小平の農作物
小平すいか(昭和33年、作付面積東京第1位)

昭和25、6年ころから伸びる。「新都」「新三笠」などの品種が栽培された。昭和28、9年が最も盛んだった。
秋作の大根 (昭和33年、練馬、八王子についで東京第3位)

はくさい (昭和33年、東京第4位)

うど
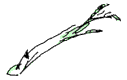 古くから吉祥寺あたりで栽培されていた。小平でも昭和28年には5ヘクタールほど作付された。
古くから吉祥寺あたりで栽培されていた。小平でも昭和28年には5ヘクタールほど作付された。
その他、なす、きゅうり、トマト、ほうれんそう、まくわうり…など。
小平の畜産
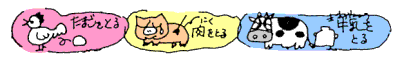 戦前
戦前も、うさぎ、にわとり、
豚、
山羊、
牛など
飼われていたけれど、
昭和の30
年代には
養豚、
養鶏が
盛んになった。
酪農は
農家の
戸数としては
多くないけれど、
最も
盛んな
時期には200
頭をこす
乳牛がいた。しぼった
牛乳は
酪農組合の
共同の
収乳場(
牛乳を
集める
場所。
小川町2
丁目と
回田町にあった。)に
集められた。
昭和35
年ころから
専業化が
進んで、
小平のような
兼業の
酪農はだんだんと
衰えた。
昭和40年(高度経済成長)以降
この
時期の
小平は
都市化が
進み、住
 宅
宅が
急速に
増え、かわりに
農家や
農地は
減っていった。
甘薯(サツマイモ)や
麦は
作られなくなった。かわりにトマト、きゅうり、うどなどの
近郊作物の
栽培にうつり、さらにくだもの、
花卉(
鑑賞用の
植物)、
植木などがとりいれられてきた。
今の
小平の
農業は
野菜やくだものが中
心だ。
それぞれの農作物、こんなお仕事
うど
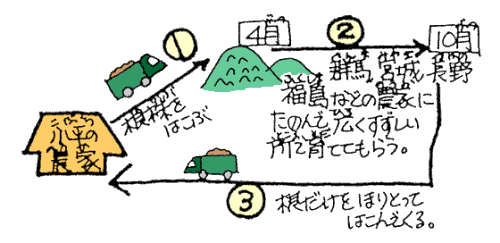
11月 根かぶをむろに入れ、土をかぶせる。
12月 むろの中でうどが伸びる、機械でうどを運び上げ、
12~1月 箱づめして、出荷。
その他の野菜
1~3月 去年の秋に種をまいた、こまつな・ほうれんそうを収穫。
3月 畑を耕したり、消毒したりして、春の植え付けの準備。
4月 元肥をほどこし、里イモ、ジャガイモの種イモを植え付ける。トウモロコシの種をまく。
5月 トマト、なす、きゅうりなど、夏野菜の苗を植える。消毒やイモ類の土寄せの作業など。
初夏~盛夏(なつ、まっさかり!) 夏野菜、ジャガイモの収穫。
7月 秋・冬どりのキャベツの種まき。
8月 キャベツの定植。大根、にんじん、ブロッコリーなどの種まきと定植。
秋~冬 消毒、追肥。大根、にんじん、ブロッコリー、里イモなどの収穫。
梨
小平の梨は昭和22(1947)年、西窪代三郎さんが稲城の友だちから梨の木を分けてもらって、研究栽培をしたのが始まり。
冬 剪定(木の成長や平均した実のりのために枝を切り整理してあげること)
 春~夏 受粉・芽かき・摘果(大きさをそろえるため実が小さいうちにまびくこと)・袋かけ・肥料をやる・消毒
春~夏 受粉・芽かき・摘果(大きさをそろえるため実が小さいうちにまびくこと)・袋かけ・肥料をやる・消毒
夏のなかば~秋 収穫
花卉・植木
昭和30年代以降、本格的になった。昭和43年には、花卉栽培が盛んな地域である小川町1丁目に「温室団地」の第1号が建てられた。こうして昭和45年までに5つの温室団地が完成。園芸農業に大いに役立っている。
数字で見る小平の農業のうつりかわり

農家の戸数
小平のはじまり、小川村の1713(正徳3)年ころのようす。開発してから50年くらい。(「村明細書上帳」より)
農家の戸数
| ないよう |
戸数 |
| 本百姓(田畑や屋敷を持ち、年貢を納める農家) |
173戸 |
| 脇百姓(本百姓より一段低い地位にある農家) |
10戸 |
| 水呑(自分の畑をもたず、土地を借りている農家) |
19戸 |
| 合計 |
202戸 |
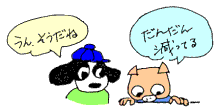
専業農家と兼業農家
| 年 |
専業農家 |
兼業農家 |
合計 |
| 昭和 元年 |
695
|
117 |
812 |
| 5年 |
698 |
77 |
775 |
| 13年 |
456 |
316 |
772 |
| 21年 |
417 |
402 |
819 |
| 30年 |
581 |
439 |
1,020 |
| 35年 |
404 |
479 |
883 |
| 40年 |
287 |
481 |
768 |
| 45年 |
141 |
556 |
697 |
| 50年 |
71 |
481 |
552 |
| 55年 |
57 |
455 |
512 |
| 60年 |
54 |
450 |
504 |
| 平成 2年 |
42 |
460 |
502 |
| 5年 |
30 |
450 |
480 |
| 7年 |
56 |
389 |
445 |
| 12年 |
70 |
364 |
434 |
| 17年 |
5 |
393 |
398 |
専業農家 :
農業からの
収入だけでくらしをたてている
農家。
兼業農家 :
農業以外の
仕事からも
収入をえている
農家。
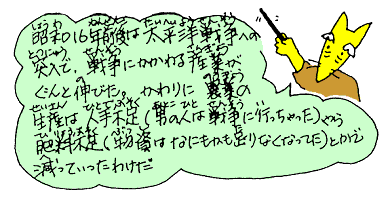
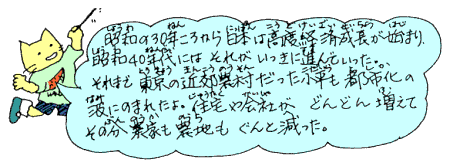
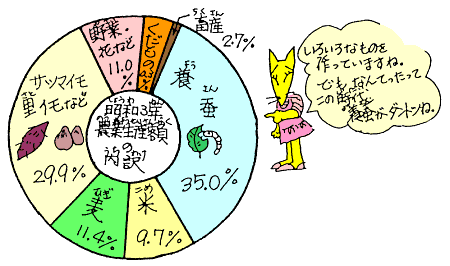
新田開発が進んで生産力が高まり、農家の人たちの生活がおちついてくると、作物の種類もふえ、あまった分は江戸へ持って行って売るようにもなった。
農作物の商品化は明治にはいって、さらに進んだ。甲武鉄道の開通(明治22年)などによる交通の発達や工業の成長による経済の発達がその原因なんだ。品物を速く運送できるようになったし、自分たちが品物を買うためのお金も必要になる。東京のまわりの農村は都会に向けて商品になる野菜を作るようになった。小平では昭和の初めからじょじょに、終戦後は急速に商品作物の栽培が伸びていった。
≪小平のおもな農作物の収穫面積のうつりかわり≫
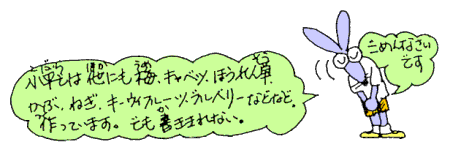 何
何も
単位がはいっていない
数字はヘクタール
空欄はデータがない、という
意味です。
小平のおもな農作物の収穫面積のうつりかわり
| しゅるい |
昭和35年 |
40年 |
50年 |
55年 |
60年 |
平成2年 |
9年 |
14年 |
19年 |
| 穀類(米や麦) |
625 |
280 |
33 |
18 |
15 |
10 |
3 |
3 |
1 |
| 甘薯(サツマイモ) |
162 |
93 |
22 |
16 |
10 |
3 |
4 |
3 |
3 |
| トマト |
12 |
4 |
2 |
2 |
2 |
2 |
4 |
4 |
3 |
| きゅうり |
14 |
8 |
4 |
3 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
| すいか |
46 |
18 |
1 |
2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 大根 |
97 |
31 |
15 |
13 |
13 |
13 |
13 |
11 |
10 |
| ごぼう |
69 |
41 |
5 |
3 |
4 |
3 |
1 |
1 |
1 |
| サトイモ |
26 |
7 |
15 |
19 |
22 |
25 |
18 |
17 |
13 |
| 白菜 |
39 |
23 |
11 |
7 |
7 |
5 |
6 |
5 |
5 |
| うど |
|
36 |
29 |
20 |
15 |
22 |
8 |
6 |
3 |
| 梨 |
|
6 |
10 |
10 |
11 |
13 |
11 |
11 |
10 |
| お茶 |
|
29 |
18 |
12 |
8 |
2 |
0 |
0 |
0 |
| 鉢物・観葉植物(鉢) |
|
24,800 |
219,500 |
121,500 |
104,800 |
27,800 |
23,800 |
549,000 |
63,100 |
| 植木(本) |
|
122 |
9 |
12 |
15 |
75,600 |
96,612 |
2,597,000 |
61,300 |
農作物のルーツ・小平の農業団体
農作物のルーツ
里イモ
インドのあたりが
原産地。キ
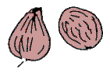
リストの
時代にエジプトに
伝わり、イタリア、スペイン、アラビアに
輸入。
中国にも
古くから
伝わって、それから
日本に
渡って
来たらしいけど、いつなのかはわからない。
醍醐天皇の
時代の『
本草和名』という
資料にその
名がのっているから、
資料ができた898
年よりも、
以前に
伝わっていたのはまちがいない。
ジャガイモ
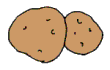
またの
名を
馬鈴薯。
原産地は
南アメリカはペルーのアンデス
山の
高地。1523
年ころ、スペイン
人の
手でヨーロッパに
伝えられた。
日本にはオランダ
船が1576(
天正4)
年と1603(
慶長8)
年に
持って
来て、
国内の
各地に
広まった。
初めは
食用じゃなくて
観賞用だったんだって。
食べるようになったのは18
世紀にはいってから。
一般的になったのは
明治以降なんだ。
観賞用;
見て
楽しむためのもの
すいか
すいかのはじまりの
地はイ
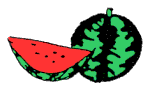
タリアとも、アフリカとも
言われる。
古代エジプトの
壁画にも、すいからしいくだものが
描かれている。4,000
年くらい
前から
栽培されている
歴史のあるくだものなんだ。
1597
年にイギリスに
渡り、
南アメリカ、
北アメリカと
伝わっていった。
日本への
到着がいつごろかはこれまた
不明なんだけど、1579
年、
中国から
種が
伝えられたという
説も。
一方、
弥生時代の
末だとも。
今みたいにおいしいすいかになったのは1887(
明治20)
年ころから。もともとは
青くさかった。
うど
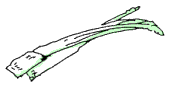 本州
本州・
北海道・
沖縄の
野や
山に
自然にはえていた。
江戸時代の
中ごろから
利用されるようになったらしい。ただし、
山菜としてはもっと
古くから
食べられていたのだろう。
朝鮮半島から
中国東北部まで
分布しているけれど
中国の
資料にある
品種・
生産方法は
日本のものだそうな。
日本特産の
野菜なんだね。
藍
青い色の染料植物。インドシナ南部が原産地。アジアに早くから広まって、日本にも中国から輸入されて利用された。
まくわうり
 中国
中国の
北部、
朝鮮半島に
古くからあって、
栽培も
紀元前からおこなわれていたらしい。
日本には
弥生時代に
伝わった。また5
世紀なかばごろには
朝鮮半島から
帰化人によってももたらされ、
日清・
日露戦争(
明治時代)のときにも、
軍人の
手で
多くの
品種がもちかえられた。プリンスメロンなどはこの
仲間。
梨
梨には日本梨、西洋梨、中国梨などがある。日本梨のおおもとと思われる野生の梨は、中国・揚子江の沿岸、朝鮮半島南部、九州の南部に見られる。けれども、中国から輸入したものを栽培したのか、日本の野生の梨を改良していったのかはさだかではない。『日本書記』の持統天皇7年(693)3月のところに、梨の栽培をすすめる記録がある。栽培の歴史だけで1,500年くらいあるらしいんだ。
小平の農業団体
小平市農業協同組合
大正4(1915)年設立 小平村信用購売組合
大正8(1919)年設立 小平村五字信用購売販売利用組合
昭和18(1943)年統合 小平町農業会となる。
昭和22(1947)年、農業協同組合法の公布で農業会は解散
小平町農業協同組合設立
小平町五字農業協同組合設立
昭和24(1949)年、この2団体が合併。
今の小平市農業協同組合のもととなる。
小平市果樹組合
昭和39(1964)年設立。梨をはじめ、ぶどう、キーウィフルーツ、ブルーベリー、りんごなどのくだものを栽培する農家の組合。勉強会をしたり、市内の幼稚園児に梨のプレゼントをしたりしている。
小平市園芸組合
昭和24(1949)年、「花卉生産研究会」からスタート。
昭和30(1955)年ころから、植木の生産も始めて、今の名まえに改められた。
即売会やコンクールなどをおこない、地域の緑化にも協力している。
小平市野菜組合
昭和49(1974)年設立。
即売会や品評会、研究会などをおこなっている。
小平うど生産出荷組合
昭和32(1957)年設立。
共同販売や勉強会のほか、うどを広めるために、料理講習会もひらく。
学校給食にも提供をしている。

小平の農業年表
小平の農業年表
| 年 |
できごと |
| 1654(承応3) |
6月20日 玉川上水完成。 |
| 1656(明暦2) |
この年、小川九郎兵衛、小川村の開発を願いでる。(よく年、開発を始める。) |
| 1676(延宝4) |
8月 小川で名主と農民の争いおこる。(よく年4月におさまる。) |
| 1724(享保9) |
5月 小川新田、大沼田新田、鈴木新田、野中新田の開発始まる。 |
| 1730(享保15) |
12月 家作料、開発農具料をめぐって新田農民と幕府の間に争いおこり、年貢が大幅に減らされる。 |
| 1738(元文3) |
この年、武蔵野新田、大凶作。 |
| 1741(元文4) |
この年、川崎平右衛門、大沼田新田に井戸を2つ掘る。大沼田新田に水田5反1畝27歩ができる。(およそ5、138平方メートル) |
| 1742(寛保2) |
4月26日 川崎平右衛門、武蔵野新田の農民に紫、菜種を配り、作付させる。 |
| 1743(寛保3) |
この年、大沼田新田に、水田9畝15歩つくられる。(およそ940.5平方メートル) |
| 1750(寛延3) |
4月 武蔵地方で雹(氷のつぶ)が降り、家や農作物に大被害。 |
| 1770(明和7) |
この夏、かんばつ(日照りつづきで水がかれること)。小川村は不作のため、年貢を納められなかった。 |
| 1782(天明2) |
この年、小川村名主弥次郎、番所の命を受けて、境新田と関前新田(今の武蔵野市)に、甘薯(サツマイモ)の植えつけをする。 |
| |
天明年間(1781~89)は毎年のようにききんにみまわれる。 |
| 1799(寛政11) |
このころ大沼田新田でからしをつくる。 |
| 1821(文政4) |
小川村の農作物に大豆・小豆が加わる。 |
| 1848(弘化5) |
館林八王子村農民幸七が藍種を持って来て、小川新田熊宮宮崎家で藍の作付法を広める。 |
| 1874(明治7) |
このころ、小平で養蚕さかん。 |
| 1877(明治10) |
このころ、小平でお茶づくりがさかん。 |
| |
明治なかごろ、豚を飼いだす。 |
| 1886(明治19) |
このころ、小平の村々の農家の7~9割が養蚕をおこなう。 |
| 1889(明治22) |
4月 小平村誕生。 |
| 1894(明治27) |
このころ、畑の仕事着に、男の人はもも引をはきはじめる。 |
| 1921(大正10) |
このころ、女の人の仕事着に、モンペが使われはじめる。 |
| 1927(昭和2) |
小川三番の農家で馬鈴薯(ジャガイモ)、ごぼう、大根、里イモ、白菜、すいかなどの野菜やくだものが作物にとり入れられる。 |
| 1928(昭和3) |
この年、養蚕と甘薯(サツマイモ)が農業収入の65パーセントを占める。 |
| 1935(昭和10) |
このころ、小平の農家で野菜の栽培が広まる。 |
| 1936(昭和11) |
この年、農林省獣疫調査所小平分室、上鈴木(今の上水本町6丁目)に開設。 |
| 1941(昭和16) |
4月 蚕糸科学研究所小平支所、小川(たかの台)に開設される。 |
| 1944(昭和19) |
2月 小平町誕生。 |
| 1946(昭和21) |
2月 第1次農地改革実施
10月 第2次農地改革実施 |
| 1947(昭和22) |
5月 農林省獣疫調査所小平分室、農林省家畜試験場となる。
6月 農林省農薬検査所、開設。(鈴木町2丁目) |
| 1948(昭和23) |
5月 小平町農業協同組合、小川(小川町1丁目)に開設。 |
| 1949(昭和24) |
10月7日 下鈴木(今の花小金井南町2丁目、嘉悦女子短期大学のところ)に小岩井小金井農場が開場。
この年、小平市園芸組合、設立。 |
| 1957(昭和32) |
この年、小平市うど生産出荷組合、設立。 |
| 1964(昭和39) |
この年、小平市果樹組合、設立。 |
| 1965(昭和40) |
この年、農業経営者クラブ、結成される。 |
| 1968(昭和43) |
5月29日 温室団地の1号が小川町1丁目に完成する。 |
| 1974(昭和49) |
この年、小平市野菜組合、設立。 |
参考にした本
「小平町誌」
「小平三〇年史」
「こだいら農産物情報マップ」
「こだいらの農業 平成5年度」
「統計書こだいら」
「原色野菜図鑑」
「原色果実図鑑」
「小平市収蔵民具資料目録」
「小平市史料集第1集 村明細帳」
小平市に関すること
多摩に関すること
江戸・東京に関すること
玉川上水・小金井桜に関すること
その他
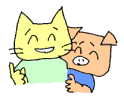 きみの
きみの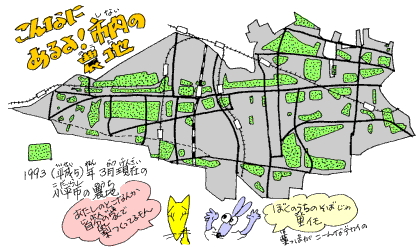
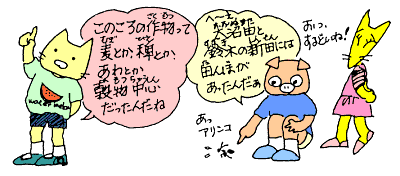
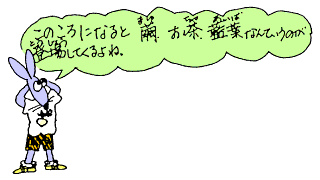



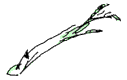
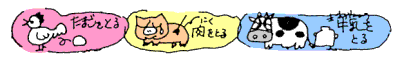

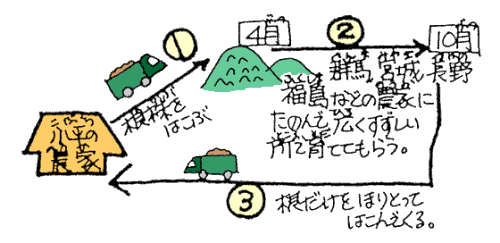


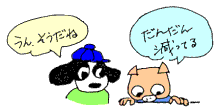
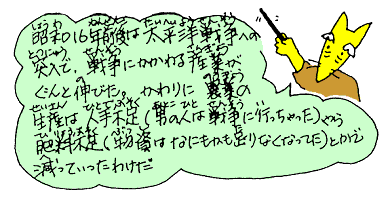
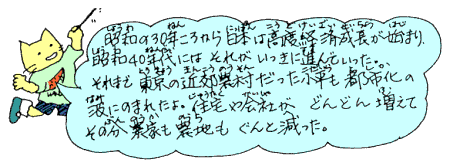
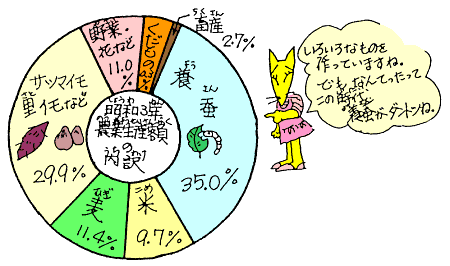
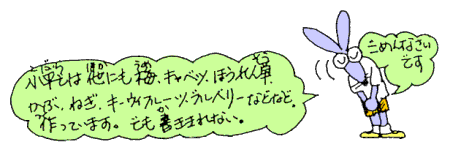
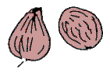 リストの
リストの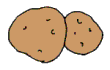 またの
またの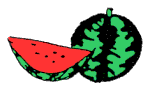 タリアとも、アフリカとも
タリアとも、アフリカとも