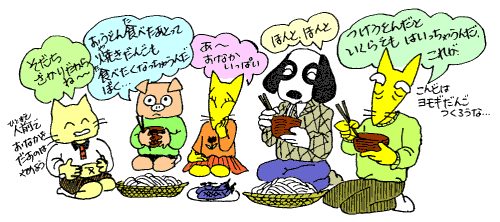小平のうどん
小平では水田はほとんどなかった。むかしはだいたい自給自足(自分たちの必要な物は自分たちで作る)生活だったから、陸稲(畑で作る稲)を栽培するようになるまでは、めったにお米を口 にできなかった。
主食はあわ・ひえ・大麦・小麦が中心だった。
野菜がいろいろ作られるようになる前は、お金にかえられる主な作物は小麦だったから、小麦はとても大切にされた。
小麦をうどん粉にするのだって、水車か手ウスでたんねんにひいて細かいふるいでふるわなければならない。この手間だってなかなかでなかったから、こうして作られたうどんはめずらしがられ、大切にされる大 ごちそうだった。
「 物日」といって、祝いごとや、祭りなどのある日には、三食のうち、一食か二食はうどんを食べたし、婚礼や葬式などにもうどんは必ず出 された。
「うどんが 打てなかったら、まだ嫁に行けない」なんてことも言われた。
でもひとよせ(多くの人を招く)の時のうどん作りは男の人がやった。こういう時は、うどん粉で5貫~10貫(1貫は3.75キログラム)のうどんを打つのだから、大仕事だ。力がいるので男の人が受けもったんだ。
ふだんの食べ物とはちがったものを「変りもの」という。小平では、その代表 はうどんだ。
ほか、お 赤飯、まんじゅうなども変りものだ。変りものをこしらえた時には両どなりと近くの親せきなどに持って行った。
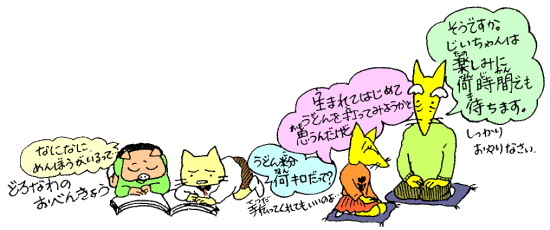
小平の食生活
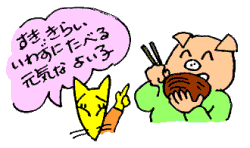
明治以前
大麦のひきわり(あらくひいたもの)にひえをまぜた「ひえ飯」が主食。
明治初め~末ごろまで
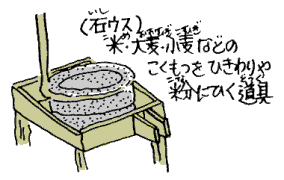 主食
主食は「あわ
飯」。これはあわ3
割に
大麦のひきわりを7
割まぜたもの。
麦は
水車小屋でついて、よく
干してから
俵につめておき、
雨ふりなどのひまな
時に
石ウスでゴロゴロひく。
他に「
小金井飯」といて、あわとさつまいもをたきこんだものもよく
食べた。
日清戦争(1894年)のころ
このころ、小平にもお米がはいってきた。外米といって、外国でとれたお米だ。お米2割にひきわりの麦を8割でまぜて主食にした。
白いごはんが食べられるのは、お客に招かれた時か、病気の時ぐらい。
「物日」などにはたまにお米をまぜて食べたりしたけれど、たいていはうどんを作って食べた。
明治の末ごろから
このころから、あわがなくなって米と麦のまぜ飯になる。陸稲は小平では明治の初めごろから栽培していたけれど、せいぜい自分の家で食べる分くらいだった。
こうした3度のごはんのほか、午前10時と午後3時のお茶の時間にはさつまいもやさといもをふかして食べた。
食器のはなし
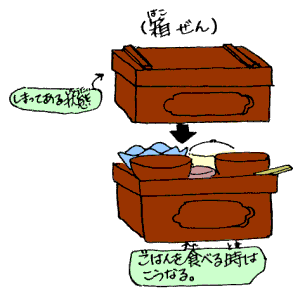 農家
農家では、ふだんの
食器はめいめいが「
箱ぜん」を
持ち、その
中にしまっていた。
食事の
時にはフタを
裏返して
食台にし、その
上に
食器を
置いて
食べる。
箱ぜんの
中にはごはんのちゃわん、みそ
汁のわん、
小皿などを
入れておいた。
ごはんを
食べたあとの
食器は、
最後のお
茶でよく
洗ってそのまましまっておくことが
多かった。
お
嫁入りの
時には
自分の
箱ぜんを
嫁入り
道具の一つとして
持って
行ったものなんだ。
婚礼やお
葬式にはふだんのものとは
別にお
客用の
食器が
作ってあった。
大きな
家だと
自分で
持っていたりしたけれど、ふつうはとなり
組単位でお
金を
出し
合って
共同の
食器を30~50
人分くらいそろえてみんなで
使った。
食事をする
場所は、
箱ぜんを
使っていたころは
流しのそばの
板の
間だった。
大正時代に
飯台(
食卓)で
食事をするようになって
箱ぜんはだんだん
使われなくなってしまった。
棒打ちうた
- 大嶽山に くろ雲が ホイホイ
あの 雲が かかれば 雨かあらしか ホイホイ
- お前さんの年は なんの年 ホイホイ
16でささぎの 年でなりごろ ホイホイ
- 棒打ちの茶菓子にゃ 何がよい ホイホイ
いもでよし さつまでよし あんころもちならなおよし ホイホイ
- 17連れて寺参り ホイホイ
お 手にゃ じゅず たもとにゃ文のやりとり ホイホイ
- おてんと様の申し子で ホイホイ
7 月の日でりに かさもかぶらず ホイホイ
- 小川の宿は 長い宿 ホイホイ
長いとて 物干しざおにゃなるまい ホイホイ
- お寺の前の じゃくろ花 ホイホイ
咲きみだれ 御門のとびらに かがやく ホイホイ
- めでたいことが かさなりで ホイホイ
嫁はとる 妹はよそへ やるはず ホイホイ
- あの山のかげで なく鳥は ホイホイ
声もよし 音もよし 山のひびきで ホイホイ
- 今年ゃ 豊年 穂に穂が咲いて ホイホイ
なやになー 米麦 山をなす ホイホイ
うどんとともに “小平の1年”
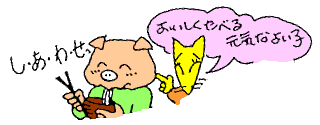
正月3が日 1月1日~3日
朝はお雑煮。切りもちにサトイモ、大根、にんじん、油あげやホウレンソウのはいったおすまし。そして昼はうどん。
七草がゆ 1月7日
朝、春の七草(せり・なずな・ごぎょう・はこべ・ほとけのざ・すずな・すずしろ)を入れたおかゆを食べる。そして昼はうどん。
お蔵びらき 1月11日
おそなえもちをおろしてくだき、お雑煮にして食べる。昼はやっぱりうどん。
蚕びまち 1月14日
蚕が盛んだったころあったお日待ち。村のみんなで寄り合って手打ちうどんを食べ、お酒を飲んですごした。
「お日待ち」は新年会、出初め式、代参など村のあつまりのある日。人々は宿(当番の家)にあつまって、うどんを打ったり、お煮しめを作ったりして食べて、飲んで楽しくすごす。
桃の節句 3月3日
ひしもちを作る。お雑煮を作るならわしもある。昼はうどん。
八雲祭 4月3日
小川村神明宮のお祭り。この日はよもぎで草まんじゅうを作ったり、お赤飯や手打ちうどんを食べた。
花まつり 4月8日
お釈迦さまの誕生日を祝う日。豊作を祈って、よもぎで草まんじゅうを作ったり、うどんを打ったりする。
代参講と帰り日待ち
村々では、代参人(代表者)を決め、御岳山、三峯山、榛名山、秋葉山などにお参りして、年ごとにお札をいただくならわしがあった。
代参人はくじ引きなどで選ばれ、その年の豊作や家内安全をお願いして来る。旅の費用はみんなでお金を出し合った。
代参人が帰って来るとお日待ちがひらかれ、集まった村人たちにお札が分けられる。当番の家で、うどんやお煮しめを食べたり、お酒を飲んだり、旅のみやげ話を聞いたりして、にぎやかにすごす。
端午の節句 5月5日
かしわもちを作り、うどんを打ってお祝いする。
端午の節句がおわると春蚕のはきたて、お茶つみと農家はとても忙しくなるのだ。
春蚕 5月上旬~6月上旬
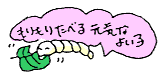 蚕
蚕のはきたて(
卵からかえったばかりの
蚕を
棚にうつす)にとりかかる。この1ヵ
月間はほんとにほんとに
忙しい。
食べ
盛りの
蚕さんたちに
夜中もエサの
桑をやらなければならない。その
中でも
脱皮の
時(
新しい
外皮を
作る
間)は、「とまる」といって
桑を
食べなくなるので、このおりにはうどんを
打ってひとときのお
休みができた。
春蚕のあがり 6月5日~10日ごろ
このころさなぎになった蚕を仲買人に卸す。大仕事をおえてほっとひと息。
うどんを打って食べ、次は麦刈りだ!
麦刈り 6月中旬~下旬
最初に
大麦、つづいて
小麦を
刈る。
刈りとった
麦は
乾燥させて
脱穀する。
千歯こきなどで
穂をこいで
粒をおとし、
天気の
良い
日に
庭一面に
敷いたムシロにそれを
広げて
干し、くるり
棒で
打つ。これを「
棒打ち」(ボウチ)と
言って、くるり
棒で
調子をとりながら、「
棒打ちうた」を
歌い、
何人もそろって
麦をうった。
昭和のはじめごろまではこれが
主な
脱穀方法だった。
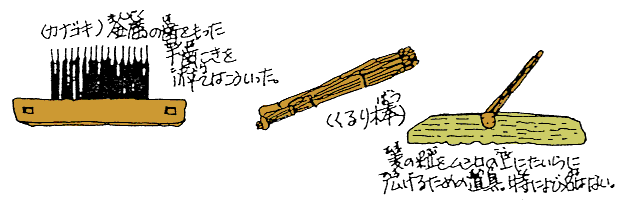
天王さま 7月15日
野中新田のお祭り。忙しい時期だけれどこの日1日はゆっくり休み、楽しくうどん、まんじゅうを作って食べる。
総合あがり 7月28日
農家の骨休めの日。この日を目標に、一生懸命夏の作物の手入れをすませて、1日ゆっくりする。うどん、まんじゅうを作って食べる。
お盆
8月1日だったり、8月15日だったり、村によって時期がちがう。
この時期、菩提寺(先祖のお墓のある寺)へ盆供(ボンコと発音)を持っていく。お盆のあいさつということでうどん粉とか、野菜とか、お金などを持って行った。
お盆の入りのよく日は、朝はまんじゅう、昼はうどんを食べる。
夏のあそび日 7月15日、8月1日、7日、15日、9月1日
むかし、これらの日は「夏のあそび日」といって、朝はまんじゅう、昼はうどんを食べて1日ゆっくりするしきたりだった。
5月下旬~9月は蚕と畑仕事で一番忙しかったので夏のこの時期、疲れ休めの日をこしらえていたのではないか、と考えられる。
麦まき 10月下旬~11月上旬
陸稲を刈り入れ、さつまいもの収穫をすませた畑に麦まきをする。
麦ふみ
年内のあたたかな
日を
選んで、
昼間1~2
回麦ふみをする。
 土
土の
中が
凍っているときにふむと
麦がいたむんだそうだ。
大晦日 12月31日
歳の市でお正月をむかえるための品々を買いそろえ、27、28日にはおもちつき。
そして大晦日にはうどんを打って、「年越しうどん」で新しい年を迎える。
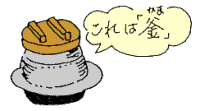 主にご飯をたくのに使ったが、手打ちうどんをゆであげる時にも使った。
主にご飯をたくのに使ったが、手打ちうどんをゆであげる時にも使った。
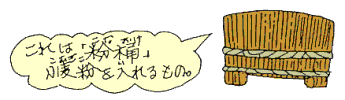 戦前は鉄釜だったけれど、戦後はアルミ合金に変わってしまったそうな。薪を使ってお釜でたいたご飯はとってもとってもおいしいというよ。
戦前は鉄釜だったけれど、戦後はアルミ合金に変わってしまったそうな。薪を使ってお釜でたいたご飯はとってもとってもおいしいというよ。
自分で手打ちうどんをつくってみようかな~と思う人へ
 中央図書館郷土資料室
中央図書館郷土資料室にはいっている『
男のうどん
学』(
加藤有次・
著)。
武蔵野手打ちうどん
保存普及会会報『
饂飩 創刊号』を
借りよう。くわしい
作り
方が
写真入りでのっているよ!
うどんづくりに挑戦する!

道具と材料
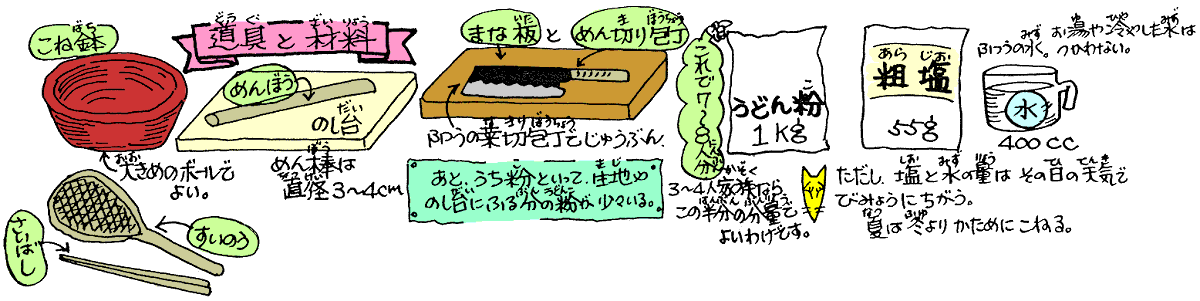
1.こねこねする
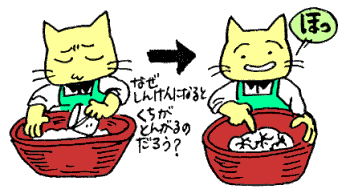 塩水
塩水を
作る。こね
鉢にうどん
粉をいれる。そこに
少しずつ
塩水を
入れながら、
円をかくようにこねる。
水かげんをみつつ、ていねいにこねる。
そのうち、まるくひとかたまりになる。
表面はでこぼこやひびのはいった
状態だ。
2.ふみふみする
大きめのビニール2
枚の
間にまるめた
生地をいれ、かか
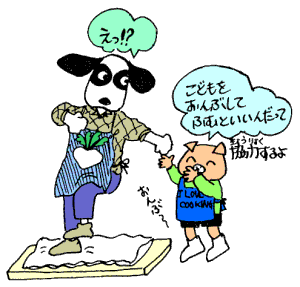
とを
中心にまわりながらふむ。
おせんべいのようになったら、またまるめてはふんでひらたくする。
何度もする。
3.もういちど、こね鉢にいれてまるめる。
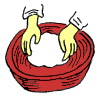
4.ねかせる
まとまった
生地をビニ
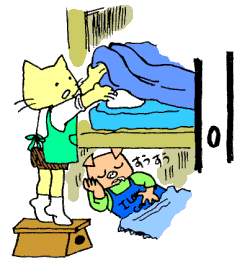
ールでつつみ、ふとんの
間などにいれて30
分~1
時間ねかせる。(
夏は30~40
分。
冬は1~2
時間)こうすると
水分が
粉にゆきわたる。
5.ねかせた生地は耳たぶのやわらかさ。

6.もういちどふみふみ
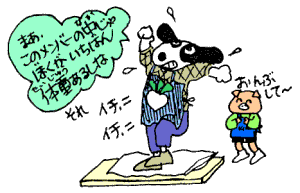 直径
直径50センチぐらいまでのばしてのし
台へ。
7.のばす
直径50センチ
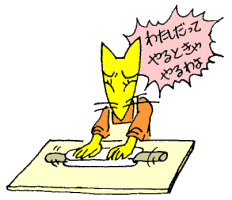
ぐらいにのばした
生地をのし
台へ。この
時、
生地は
裏側を
上にする。めん
棒でのばして、
表面がひびわれなくきれいになったらうち
粉をふる。
めん
棒に
生地をまきつけ、
前におしながら
両はしに
広げるように
強くこする。
8.とんとんする
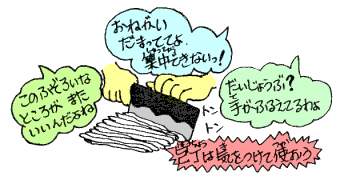
4ミリぐらいの
厚さになった
生地にじゅうぶんうち
粉をして8~10センチはばのびょうぶだたみにする。それを4~5ミリのはばに
切ってゆく。
9.ゆでる
大きいおな

べで
湯をわかし、そこに
塩をひとつかみ。さらに
生うどんをほぐしながらいれよう。ふっとうしてめんがういてきたらさし
水をする。これを
何回かくり返す。
10~15
分ぐらいゆでて、1
本とってみよう。めんの
切り
口がすきとおっていればゆであがりだ。
すいのうで
湯からあげて、
水をはったボールにあける。さらに
水を
流しながらよく、めんをもみ
洗い。ぬめりがとれたらザルに
盛ろう。
つゆと糧(かて)をつくろう
【
材料】
水2リットル、だしこんぶ20センチ、けずりぶし40~50グラム、みりん
大さじ2~3、しょうゆ150~180ミリリットル、
油あげ2まい、
生しいたけ4
枚

こんぶとかつおのダシ
汁に
切ったあぶらあげと
生しいたけを
入れ、しょうゆとみりんで
味をととのえる。
季節の
野菜をそえてだす。これは「
糧」といわれる。おこのみの
糧と“やくみ”(
長ねぎとか)をそえて、さあ、いただこう。
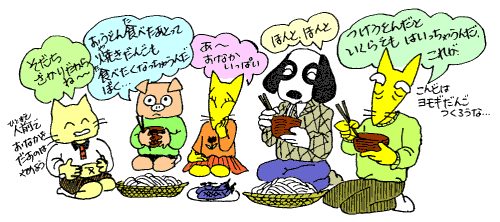
参考にした本
「男のうどん学」
「郷土こだいら」
武蔵野手打ちうどん保存普及会会報「饂飩」
「郷土の暮らしを探る民具展」
「市報こだいら」
「小平町誌」
「ちょっと昔」
「小平郷土研究会 会報2号」
「小平の民具 小平市収蔵民具資料目録」などなど
小平市に関すること
多摩に関すること
江戸・東京に関すること
玉川上水・小金井桜に関すること
その他
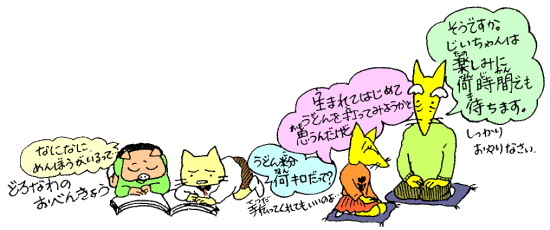
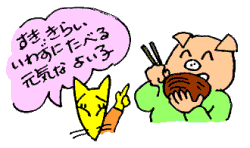
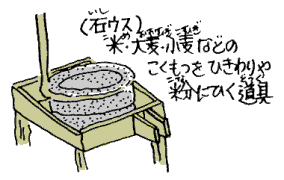
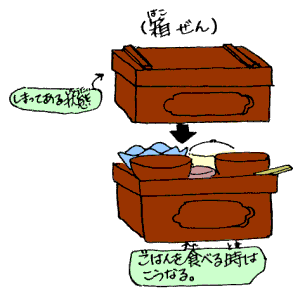

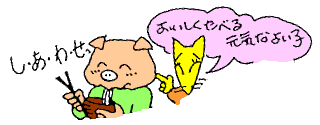
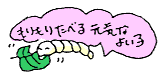
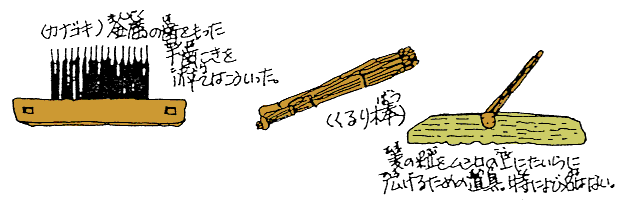

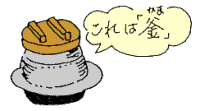
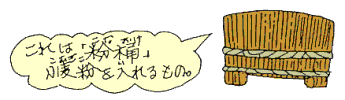

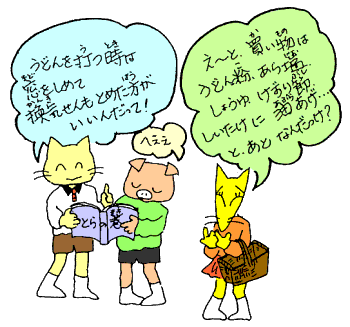

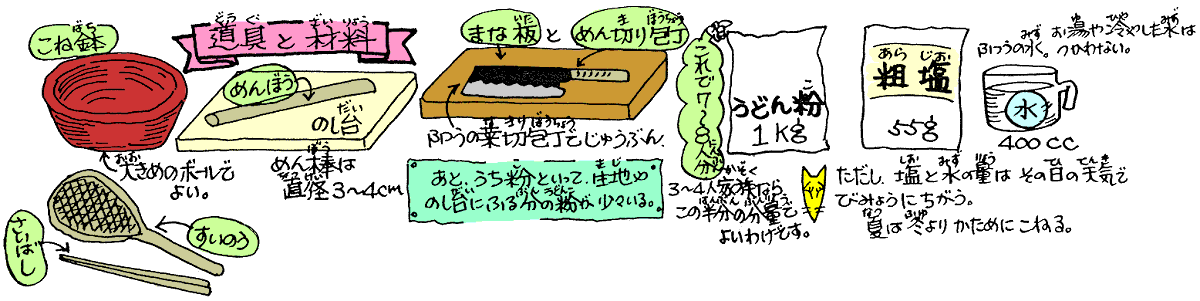
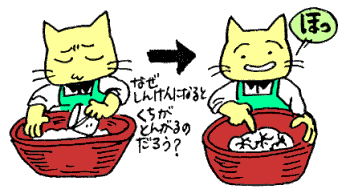
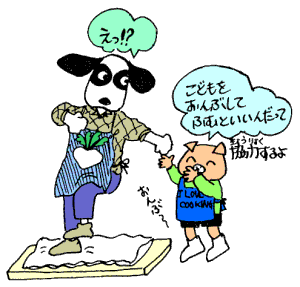 とを
とを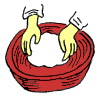
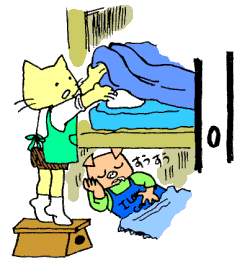 ールでつつみ、ふとんの
ールでつつみ、ふとんの
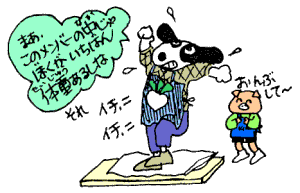
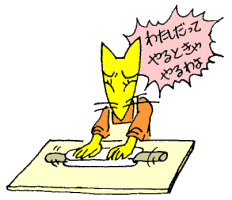 ぐらいにのばした
ぐらいにのばした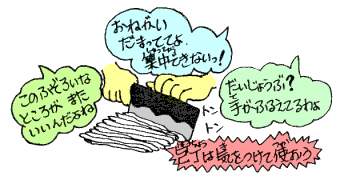 4ミリぐらいの
4ミリぐらいの べで
べで