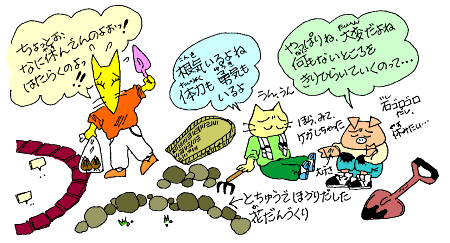武蔵野の新田のあらまし
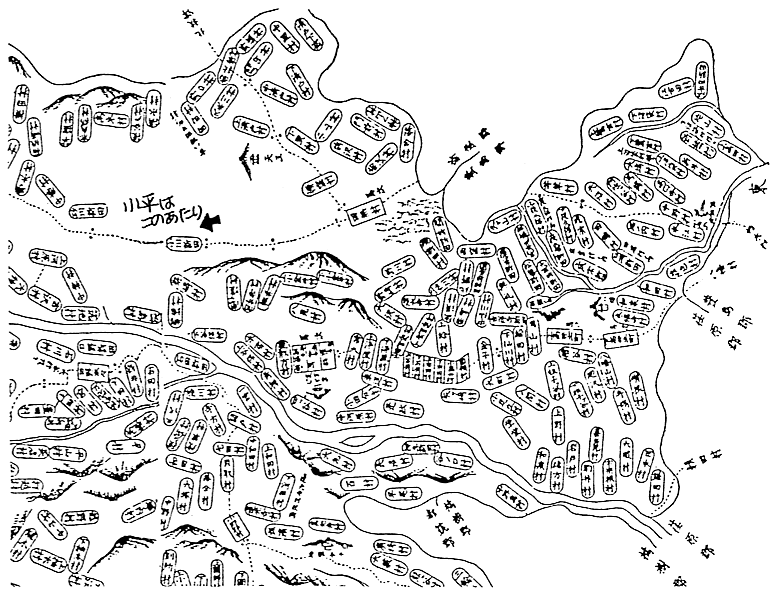
「新編武蔵風土記稿」より
≪元禄年間 多摩郡之図≫
(注意)普通の地図と、逆さまです。
武蔵野の新田のあらまし
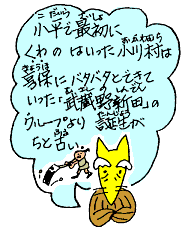 江戸時代
江戸時代の
初め、
武蔵国の
江戸川・
荒川・
多摩川の
下流には
水田が
開かれていった。それがすすむと、
今度は
武蔵野台地に
畑作地帯が
開かれるようになった。
中でも
享保7
年 (1722年)7
月、
江戸日本橋にたてられた
新田開発をすすめる
高札をきっかけにはじまり、
元文年間 (1736~1741年)に
検地を
受けたものを「
武蔵野新田」と
呼ぶ。
新田に
移ってくるのは
若夫婦に
子ども
1人くらいの
小さな
家族がほとんどで、
初めの
頃は
苦しいことも
多かったが、
川崎平右衛門という
人の
働きで、
新田のくらしもしだいに
落ち
着いていった。
武蔵野台地の
土は
関東ローム
層と
言って、
火山灰でできた
赤土で、
耕作には
向かない。けれど
農民は
灰やヌカを
与え、
赤土を
豊かな
黒土にかえ、
明和年間 (1764~1772年)ころより、
麦・アワ・ヒエがよくできるようになった。やがてまわりの
古くからの
村もしのぐようになり、
西多摩や
江戸の
町とも
品物の
流れがさかんになっていった。
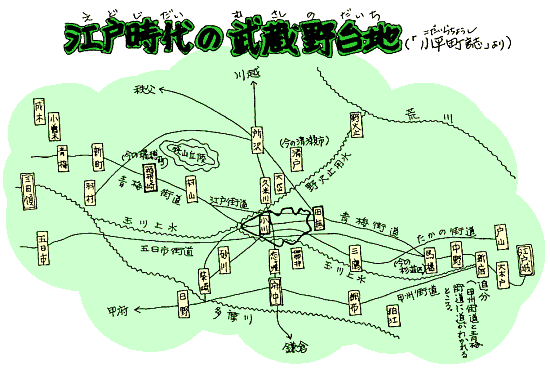
新田開発年表

新田開発年表
| 年 |
できごと |
| 1590(天正18年) |
8月1日 徳川家康、江戸入り。 |
| 1603(慶長8年) |
2月12日 家康、征夷大将軍となり、江戸幕府をひらく。
3月 江戸下町の建設はじまる。 |
| 1606(慶長11年) |
11月 武蔵国多摩郡三田領北小曽木村・上成木村より、江戸城普請のための石灰を運び始める。 |
| 1609(慶長14年) |
この年、砂川新田の開発はじまる。 |
| 1611(慶長16年) |
この年、新町の新田開発はじまる。 |
| 1654(承応3年) |
6月20日 玉川上水完成。 |
| 1655(承応4年) |
3月 野火止用水完成。 |
| 1656(明暦2年) |
この年、小川九郎兵衛、石灰御伝馬継を条件に、小川村の開発を願い出る。 |
| 1721(享保6年) |
11月 貫井村、鈴木利左衛門、新田開発を願い出るが許されず。 |
| 1722(享保7年) |
7月 江戸日本橋に新田開発をすすめる高札が立つ。
8月19日 鈴木利左衛門、再び新田開発を願い出る。
9月 小川村名主、市郎兵衛とその子孫市、神明宮の神主宮崎主馬が新田開発を願い出る。
10月8日 上谷保村農民、矢沢藤八、円成院住職大堅ら、新田開発を願い出る。 |
| 1724(享保9年) |
5月 小川新田、大沼田新田、鈴木新田、野中新田にいっせいに許可がおりて、開発がはじまる。 |
| 1726(享保11年) |
6月 野中新田の名まえが決まる。初代名主は源右衛門(あとで与右衛門と名をかえる)。組頭は善左衛門・長右衛門。
この年、廻り田村、野中新田から土地を買う。 |
| 1732(享保17年) |
10月 野中新田は、北野中・通野中・南野中にわかれ、与右衛門組・善左衛門組・六左衛門組になる。
この時、享保11年より野中新田の一部になっていた鈴木新田も独立。 |
| 1734(享保19年) |
この年、鈴木新田、玉川上水より水を引き、長久保に水田を作る。 |
| 1736(元文元年) |
12月 小川新田・鈴木新田・野中新田・大沼田新田・廻り田新田の検地、おこなわれる。 |
| 1738(元文3年) |
この年、武蔵野新田大凶作。 |
| 1739(元文4年) |
8月 川崎平右衛門、南北武蔵野新田世話役となる。
9月 川崎平右衛門、前の年の凶作の影響を調べる。 |
| 1741(元文6年) |
この年、川崎平右衛門、大沼田新田に井戸を2つ掘る。
大沼田新田に水田作られる。 |
| 1765(明和2年) |
この年、小川村名主弥次郎、小川分水に水車をしかける。 |
| 1772(明和9年) |
この年、大沼田新田名主、弥十郎、伝兵衛、大沼田分水に水車をしかける。 |
| 1775(安永4年) |
この年、小川新田、宮崎釆女、屋敷に水車をしかける。 |
| 1778(安永7年) |
この年、鈴木新田の善兵衛、水車をしかける。 |
| 1799(寛政11年) |
この年、榎戸新田妙法寺に、武蔵野新田82か村の農民が、川崎平右衛門の謝恩塔を建てる。 |
武蔵野新田の立て役者たち…
徳川吉宗
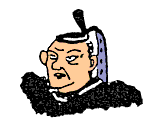 貞享元年
貞享元年(1684)
生まれ。
宝永2
年(1705)、
紀州藩主となり、
自分の
藩の
財政をよくするため、
倹約をすすめたり、いろいろな
工夫をした。
享保元年(1716)4
月、7
代将軍家継亡きあと、
老中たちにすいせんされ、
江戸幕府8
代将軍となる。
吉宗時代の
政治を「
享保の
改革」とよぶ。
享保2
年(1717)に
大岡忠相を
江戸町奉行にもちいた。
享保6
年(1721)には
目安箱の
制度を
作って、
将軍へ
直接訴えができるようにした。
その
後も、
能力のある
人をどんどん
抜てきして、
享保の
改革をすすめるため
働かせた。
享保の
改革は
財政をたてなおすのが
一番の
目的だったから
新田開発や
年貢を
決める
方法のみなおしなどもおこなった。
大岡忠相
延宝5
年(1677)、
三河時代からの
徳川氏の
家臣の
家に
生まれる。
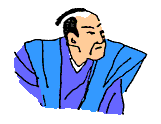 江戸町奉行
江戸町奉行となったのは、
享保2
年(1717)2
月3日、41
才のとき。
同時に、
越前守になった。それから60
才になるまで20
年間、この
役を
務めた。
吉宗時代ばかりか、
次の
将軍家重の
時代にも75
才で
亡くなるまで、
幕府で
一番重要な
仕事をまかされていた。このことは
大岡忠相が、
仕事のできる、
人がらのしっかりした
役人だったことをしめしている。
町奉行時代、
大岡忠相は、
江戸の
人々のくらしを
良くするため、
努力した。まず、
大きな
商人たちに
反対されながらも、
安くて
豊富な
品物が
江戸にはいるようにした。
それから、
火事の
多い
江戸の
町を
守るため、
町火消「いろは47
組」を
作って
消防の
仕事をまかせた。
火事の
時、
逃げる
場所も
作った。そのほか、
貧しい
人たちを
救うため
小石川養生所という
施設もつくった。
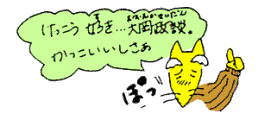
「
大岡政談」という
越前守の
名さばきは、ほとんど
作った
話なのだそうだ。でも、
江戸の
人たちの
願いがこめられ、できあがっていったんだろうね。
川崎平右衛門
元文3
年(1737)、
武蔵野新田は
大凶作にみまわれた。わずか2
年前の
元文元年に
検地をうけ、
年貢のかけられる
土地として、
1本立ちしたばかりなのに…。
畑は
砂ばくとなり、
作物は
何ひとつとれない。そのころ
武蔵野新田78か
村の
農家は1320
軒。なんとかくらしを
続けてゆけそうなのは、そのうちわずか35
軒だった。
土地を
捨てて
逃げる
者、
五日市街道をくだり
江戸まで
働きにゆく
者、さまざまだった。
農民がいなくなれば、せっかく
開いた
新田がむだになる。
幕府はこれをくい
止めるため、
武蔵野の
事情にくわしく、
仕事もできる
川崎平右衛門を
協力者としてもちいた。
平右衛門は
元禄7
年(1694)
生まれ。
押立村(
今の
府中市)の
名主で、
前にも
自分の
財産を
投げうって、
困っている
人を
救ったことがある。
農業にも
熱心な
人だった。
川崎家の
先祖は、もとは
後北条氏の
家臣だったという。
小川九郎兵衛の
家と
同じだねっ!
平右衛門は
小金井村の
勘左衛門、
鈴木新田の
利左衛門に
手伝わせ、
農家一
軒一
軒の
被害を
調べた。
逃げてしまった
農民たちを
呼びもどした。そして、みんなのくらしが
落ちつくように
土木工事をおこない、
農業の
手のあいた
農民をやとい
入れ、
賃金を
払った。また、
幕府のお
金で
新田に
井戸を
掘った。
新田の
作物も、
土地に
合ったものを
探し、
工夫した。
紫草(
染料)、はと
麦、からみ
大根を
作るよう、すすめた。
屋敷の
防風林にと、
杉・ひのき・
松・
栗を
植えることもすすめ、おかげで
武蔵野は、
将軍に
献上する
栗の
産地にもなった。
次のききんに
備えて
穀物を
貯えることもした。
貯えがたまるとときどき
売って、お
金をふやし、
最終的に
新田のみんなに
分けた。こうして、
武蔵野新田はつぶれずにすんだのだ。
関野新田(
今の
小金井市)から
小川新田(
今の
小平市)まで、
玉川上水べりに
桜の
苗を
植えたのも、
平右衛門の
仕事だ。「
新田のにぎわいのため
植えた」というねらいどおり、
小金井桜は
名所となった。
元文3
年から4
年の
武蔵野新田での
働きを
江戸町奉行、
大岡越前守忠相に
認められ、
元文4
年(1739)、
南北武蔵野新田世話役となった。さらに
寛保2
年(1742)61
才のとき
代官となり、
寛延2
年(1749)まで
武蔵野を
支配した。その
後も74
才で
亡くなるまで、
美濃国(
今の
岐阜県)の
輪中地帯の
水害を
防いだり、
農民のくらしを
守るために
働いた。
その
死後、
文化年間(1804~1818)に
榎戸新田の
妙法寺(
今の
国分寺市)に
武蔵野新田82か
村の
農民が
平右衛門の
人がらやおこないをたたえ、
報恩塔を
建てた。
中藤新田(
今の
武蔵村山市)の
観音寺と
関野新田(
今の
小金井市)の
真蔵院には
供養塔がある。
文化7
年(1810)3
月21
日、
小平市の
海岸寺に
建てられた「
小金井桜樹碑」には、
平右衛門が
吉野や、あちこちの
桜の
苗をあつめ、この
地に
植えたときざまれている。

新田開発
享保の改革
享保元年(1716)、徳川吉宗が8代将軍になると、幕府をたてなおすため、さまざまな改革がおこなわれた。
倹約令(ぜいたくをしてはいけない、という命令)が出され年貢の収入を増やすことが考えられた。新田開発もそのひとつとしておこなわれたものだ。
新田開発前の小平
慶長8年(1603)、家康が江戸に幕府を開くと、五日市街道と青梅街道は、江戸城を手直しするため、青梅の成木・小曽木から石灰や薪・炭を運ぶ大切な道になった。
街道は馬の往き来でにぎわったが、田無から箱根が崎(今の瑞穂町)の間、およそ20キロメートルは人の住まない荒野で、いちばんの難所だったのだ。この荒野にはなかつぎの宿が必要だった。
武蔵野の新田開発のはじまり
武蔵野の新田の多くは、享保の改革のころできたものだ。その中では小川村は古い方の新田だ。けれど、小川村より前にも、開発をめざした村があった。新町村(今の青梅市)と砂川村(今の立川市)だ。このふたつの新田は開発にとても時間がかかり、苦労もしている。
江戸時代の初めには、武蔵野の村では、農民が新しい土地に移るのは簡単ではなかったし、武蔵野台地は井戸を掘っても、なかなか水がでてこない性質の土地だったから。
江戸入りした家康は、飲み水のための水道として神田上水を作った。江戸が天下の中心になるとたちまち人口はふくれあがり、水は足りなくなってしまった。そこで承応3年(1654)、玉川上水ができたのだ。
多摩川の水が羽村の取り入れ口から武蔵野台地を流れはじめ、この荒野にも人が住める条件が整った。
新田開発って?
江戸時代におこなわれた
耕地の
開たくのこと。
大がかりな
土木工事は
戦国時代の
末ごろからおこなわれたが、
江戸時代にはいると、
大きな
川に
沿って
広い
土地が
開かれるようになった。
初めのころは
田んぼが、
田んぼに
向く
土地を
開発しつくすと、
中ごろからは
畑が
開かれていった。
享保の
改革のひとつとして、
享保7
年(1722)に
新田開発をすすめる
高札が
江戸日本橋に
立つと、いっそう
盛んになった。
耕地が
広がるということは
年貢をとる
土地が
広がるということだし、それまで
自分の
土地が
持てなかった
農民にとってはチャンスだったんだ。
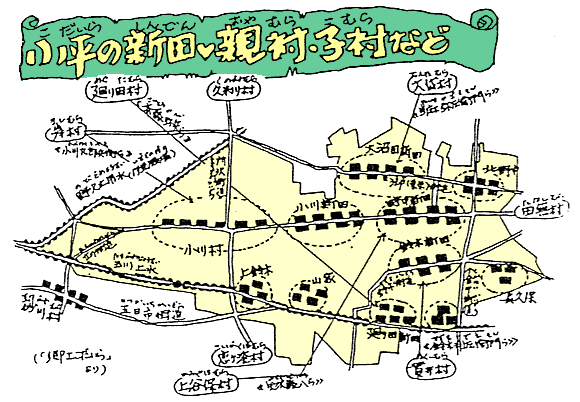
小川九郎兵衛と小川村の開たく
小川村の開たく者、九郎兵衛の生まれた家は、岸村(今の武蔵村山市)の郷士だった。郷士というのは、その土地にいついて、農業をしながら武士のあつかいをうける人のこと。
小川家は、もとをたどると武蔵七党の一つ、西党の出。のち、後北条氏に仕えるようになったが、天正18年(1590)、後北条氏が滅ぶと、岸村に住みついたのだ。
承応3年(1654)に玉川上水、よく承応4年に野火止用水ができあがると、武蔵野台地でいちばん難しい水の問題が解決できそうだ!と小川九郎兵衛は新田開発を決意した。
九郎兵衛の孫、九市が代官所に出した記録にはこう書かれている。
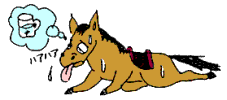 小川村の場所は、東西は田無から箱根が崎へ、南北は府中から所沢へ、2本の道の交差する大事な場所なのに全くのあれ野だ。人や馬は、暑さ寒さや悪い天気のおり、飲み水もなく、往き倒れて死ぬことも多かった。九郎兵衛はこのことを知っていて、ここに新田を開きたいと明暦2年(1656)、代官に願い出た。中つぎの宿にもなれば、往き来する人や馬もずいぶん助かる。
小川村の場所は、東西は田無から箱根が崎へ、南北は府中から所沢へ、2本の道の交差する大事な場所なのに全くのあれ野だ。人や馬は、暑さ寒さや悪い天気のおり、飲み水もなく、往き倒れて死ぬことも多かった。九郎兵衛はこのことを知っていて、ここに新田を開きたいと明暦2年(1656)、代官に願い出た。中つぎの宿にもなれば、往き来する人や馬もずいぶん助かる。
西は玉川上水と野火止用水の分水口から、田無村まで開発するように、と許しがでたが、このあたり、土地が肥えていないから、初めは開たくにくわわる農民も少なかったらしい。
九郎兵衛は自分の財産をかけて、農民を住みつかせ、開発願いの時の約束どおり、石灰伝馬とまわりの七か村への伝馬をうけ負って、よく明暦3年(1657)から、きちんと仕事をつとめた。
そのごほうびとして、九郎兵衛は屋敷地を年貢のかからぬ土地にしてもらった。
新田開発の方法
1.土豪開発新田
土豪とは、もと戦国大名の家臣で土地に居ついた者のこと。江戸時代の初めに多い開発のかたち。
土豪などの
有力者が
自分の
財産を
使い、
下働きの
者を
動かして
村を
開く。
村ができるとそこの
名主になる。
小川村はこのかたち。
2.村請負新田
村の人みんなで決めたこと、というかたちで新田開発の願いを出し、新しく開いた土地は、仕事にたずさわった人たちに分けられる。村は新田を責任を持って開発し、これを「親村」という。
(注意)(カッコ)の
中は
親村
小川新田(
小川村)、
大沼田新田(
大岱村)、
鈴木新田(
貫井村)、
廻り
田新田(
廻り
田村)はここにはいる。
3.町人請負新田
お金を持っている町人が開発を請け負い、働き手を集めておこなう。土地を開くと、農民を住まわせ、小作人にする。(小作人というのは、土地を借りて農業をする人)開発人は地主になるわけ。
このタイプの
新田は、
町人が
金持ちになってきて、
社会的にも
力を
持ちはじめた
元禄時代ごろからあらわれる。
4.百姓寄合新田
ちょっと見は町人請負新田に似ているけれど、性格がちがう!
有力な
農民や
町人が
1人~
数人で
開発願いを
出し、さらに
仲間を
集め、おこなう。
開いた
土地は
出したお
金の
額によって
分ける。
江戸時代の
中ごろからあらわれたかたち。
野中新田はこれだ。
入村請書
小川村に移って来る農民は、証人をたて、新田の開発人、小川九郎兵衛につぎのような証文(証拠の文書)を入れた。

- この者は身元がたしかです。法律にそむいたり、悪いことをした時は証人が責任を負います。
- この者が開たくに出ることはどこからも文句はでない。もし文句がでたら、証人がどこまでも申しひらきします。
- 屋敷地を分けてもらったからには、いつであろうとあなた(九郎兵衛のこと)の思うとおりに家を作り、ひっこしをさせます。
- 御伝馬継の新田だから、開たくに出る者は馬を持って、幕府の仕事や、その他の役をつとめます。
- この者は禁止されているキリスト教の信者ではありません。
証人になるのはたいてい本百姓。
本百姓というのは、自分の田畑を持ち、年貢を納める力を持った農民のことだ。
地割
武蔵野の
新田は、その
多くがきちんとした
地割(
土地の
区切り
方)をしている。
小川村も
屋敷地・
耕地が
青梅街道に
直角に
短ざくの
形に
区切られていた。
屋敷のうら
側には
玉川上水から
引いてきた
上水道が
通っている。
飲み
水から
洗たくまでこの
水を
使う。しかし、
大切な
水だから
川で
直接洗たくはしなかったんだ。
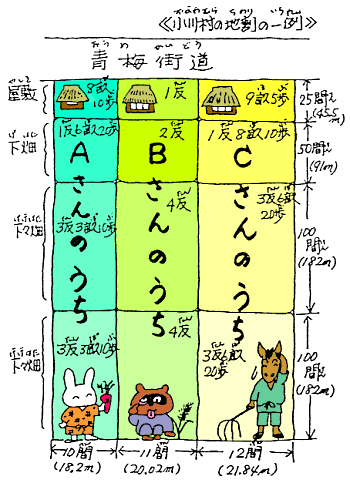 長
長さの
単位
1
間 =およそ1.82メートル
広さの
単位
1
歩=1
坪と
同じ。およそ3.3平方メートル、つまり
畳2
枚分の
広さ。
1
畝=30
歩 およそ99平方メートル
1
反=300
歩 およそ992平方メートル
このころ、
毎年作物を
植える
畑は、
作物の
種類には
関係なく、よく
収穫ができる
肥えた
土地かどうかによって「上畑」「中畑」「下畑」「下々畑」「山畑」というふうに
分けられていた。
小平の新田
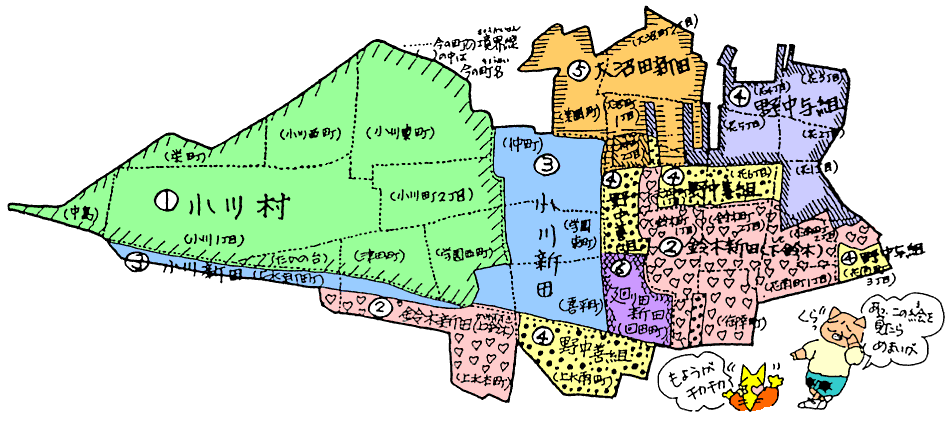
1.小川村
(小川町1・2丁目、小川西町、小川東町、栄町、たかの台、津田町、中島町のあたり。それと、学園西町の一部分。)
岸村(今の武蔵村山市)の小川九郎兵衛が開発。小平で最初に開発された場所だ。けれど荒野のまん中で土地は肥えていないから、開たくをしようという農民は少ない。九郎兵衛は自分の財産をそそいで、ここに人を住みつかせようと努めた。
また、水を手に入れることも、ひとつの問題だ。宝永元年(1704)、その時の名主、政右衛門が代官に出した手紙に事情がしのばれる。
「この地は原野で飲み水がなく、井戸を掘ったが、27~29メートル掘っても水が出ないので、開発に行きづまってしまいました。代官様に申し上げたら、玉川上水の水を分けてくださり、おかげで開発ができました。」
2.鈴木新田
(上水本町のほとんどと上水新町ちょっぴり=上鈴木という
鈴木町1・2丁目、御幸町、花小金井南町1~3丁目あたり、天神町1丁目の一部分=下鈴木という)
貫井村(今の小金井市)の名主、鈴木利左衛門重広が開発願いを出す。資金は上総国万石村(今の千葉県君津市)の商人、野中屋善左衛門が出した。善左衛門が野中新田の開発にかかわる2年前、享保6年(1721)のことだ。鈴木新田の開発の願い人の中に、野中新田開発の願い人のひとり、元右衛門の名がはいっている。鈴木新田と野中新田は関わりが深いみたい。
利左衛門は開発にとりかかった矢先の享保10年(1725)6月に病死。その後は、息子の利左衛門春昌が継いだ。享保9年から11年までの3年間、1年に4石8斗5升の米を納める約束を利左衛門春昌は守りきれなかった。
そのため、享保11年6月11日に、代官所はこの新田の責任者を利左衛門春昌から、善左衛門と元右衛門に替えてしまった。鈴木新田は野中新田の一部になってしまったかっこうだけれど、享保17年(1732)野中新田の村分けの時、利左衛門は再び名主となり、鈴木新田は独立。
ここには少しばかり水田もあった。長久保(今の花小金井南3丁目あたり)の低い湿地に享保19年(1734)玉川上水から水を引いてつくったのだ。
3.小川新田
(仲町、学園東町、喜平町、上水新町のあたり。それと学園西町、上水本町の一部分。)
小川村では早くから、東の地続きを開発したいと思っていた。享保7年(1722)9月、小川村名主、市郎兵衛とその子、弥市、神明宮の神主、宮崎主馬が「一本榎」のところまで開発を願い出て、享保9年(1724)5月に許された。
この地続きの開発地は「小川新田」と名づけられ、それまでの小川新田は「小川村」と呼ぶことにした。
最初は小川村が小川新田と呼ばれていたんだね。
4.野中新田
(
善左衛門組 上水南町…ここを
堀野中という、
花小金井6
丁目全部と
鈴木町1
丁目、
天神町1・2
丁目、
御幸町のそれぞれ
一部分などがはいる。)
(
与右衛門組 花小金井1~5
丁目、
花小金井南町3
丁目のあたりと
天神町2
丁目、
大沼町1
丁目の
一部分)
六左衛門組と
榎戸新田
国分寺市の
北町、
並木町、
新町、
高木町、
戸倉、
東戸倉、
富士本、
日吉町、
光町のあたりで、おたがいこんなふうに
入りくんでいた。
 上谷保村
上谷保村(
今の
国立市)の
農民、
矢沢藤八と
円成院住職大堅が
開発を
計画。
野中屋善左衛門に
資金を
出すよう
頼んで、そのかわり、「
矢沢新田」と
名づける
予定を「
野中新田」にかえた。
この
新田は
面積が
広すぎて、まとまりも
悪く、
年貢を
集めるにも
不便だった。そこで、
享保17
年(1732)10
月、
北野中、
通野中、
南野中の3
組に
分けられ、
名主もそれぞれ
与右衛門、
善左衛門、
六左衛門がなった。
この
新田のおもしろいところは、
名主が3
人とも
農民ではなく、
江戸の
町人であるところ。
開発のはじめ、
仲間であった
藤八や
元右衛門ら、
上谷保村の
農民の
半分は、
享保11
年(1926)までには、
土地を
手放してしりぞいてしまっている。
南野中の
六左衛門組は、
今は
国分寺市にはいっている。
同じく、
国分寺市の
榎戸新田も、
享保10
年(1725)に、
初め
南野中新田の
農民として
名を
連らねている
角左衛門という
人が
開いたもの。
だから、
野中新田の
範囲って、
本当に
広かった!
5.大沼田新田
(大沼町1・2丁目、美園町のあたり。)
大岱村(今の東村山市)の名主、当麻弥左衛門が開発。大岱村は「大沼田」とも「大怒田」とも書いたので、新田の名も「大沼田新田」とつけられたという。
寛保元年(1741)、この新田に、川崎平右衛門は飲み水用などに2つの井戸を作り、生活に使う水をととのえてくれた。
また飲み水の残りを利用して、何か所かのくぼ地に1600坪くらいの水田もつくられた。
「おんた」と呼ばれていたのか「おおぬまた」と呼ばれていたのかちょっとわからない。今の読み方だと「おおぬまた」だけど親村のよみの「おんた」に「大沼田」という字をあてていたのかもしれないからね。
6.廻り田新田
(回田町あたり。それに鈴木町1丁目ちょっぴり)
この新田は廻り田村(今の東村山市)が草刈り場として野中新田から土地を買ったのがはじまり。だから、他の新田とでき方がちょっと違う。まわりがどんどん武蔵野新田として開発され、農業に欠かせない「たい肥」を作るための草を採る場所が少なくなってきたから、土地を確保したかったんだ。だから元文元年(1736)の検地のとき、農民は誰もここに住みついていなかった。川崎平右衛門は、「ここに住みついて、農業をするように」と厳しく申しつけ、宝暦5年(1755)くらいには、新田の村らしくなったらしい。
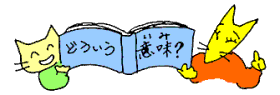 ちょっと説明
ちょっと説明
御伝馬継
伝馬は、宿駅の間を往復して荷物などを運ぶ馬のこと。
伝馬の制度は古代からある。家康がこの制度をしいたのは慶長6年(1601)。東海道がはじまりだった。街道に宿場をつくり、宿ごとに馬を置き、もっぱら幕府の用事に使った。
中山道、甲州街道とほかの街道もつぎつぎと伝馬の施設がつくられていった。幕府のご用となれば、昼も夜もなく、隣りの宿まで馬を走らせなければならない。実際にこの仕事を負担する人たちは大変だったろう。
小川村も江戸に石灰を運ぶための宿でもあったから、農民たちは、開たくのかたわら馬の世話をしたり、交代で石灰を運んだりしていたのだ。
高札
法律や
命令をみんなに
知らせるための
立て
札のこと。
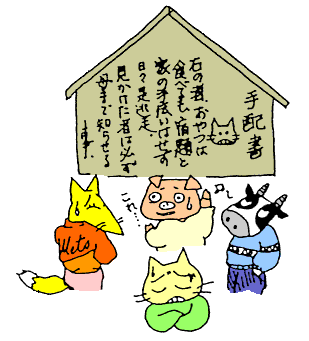
これも
古代からあったらしいけど、
江戸幕府はこの
方法をよく
使った。
名主の
家の
前などの
目立つ
場所にたてられていた。
検地
この言葉は戦国時代から使われている。領主が、自分の領地がどのくらあるか知るためにする調査のことだ。
農民の耕す田畑や、屋敷地の面積をはかり、この広さならどれくらい収穫があるはずかを計算する。
全国、ほぼ同じ基準でおこなった秀吉の太閤検地は有名。江戸幕府もはじめ、このやり方をまねた。
これによって年貢か決まるのだから、農民にとっては大事なのだ。
代官
もともとは
主君のかわりに

ある
役や
務めをおこなう
人をこう
呼んだ。
江戸時代には
代官の
制度がきちんと
整えられて、
幕府や
藩が
直接支配する
土地を
管理する
地方役人の
呼び
名になった。
年貢をあつめたり、
裁判所のような
役目をしたりした。
参考にした本
小平の「古文書目録」いろいろ
「小平事始め年表索引(稿)」
「小平町誌」
「郷土こだいら」
「角川地名大辞典」
「平凡社大百科事典」
「府中市史上編」
「玉川上水の碑」
「多摩の歴史3」
「武蔵野の集落」ほか…
小平市に関すること
多摩に関すること
江戸・東京に関すること
玉川上水・小金井桜に関すること
その他
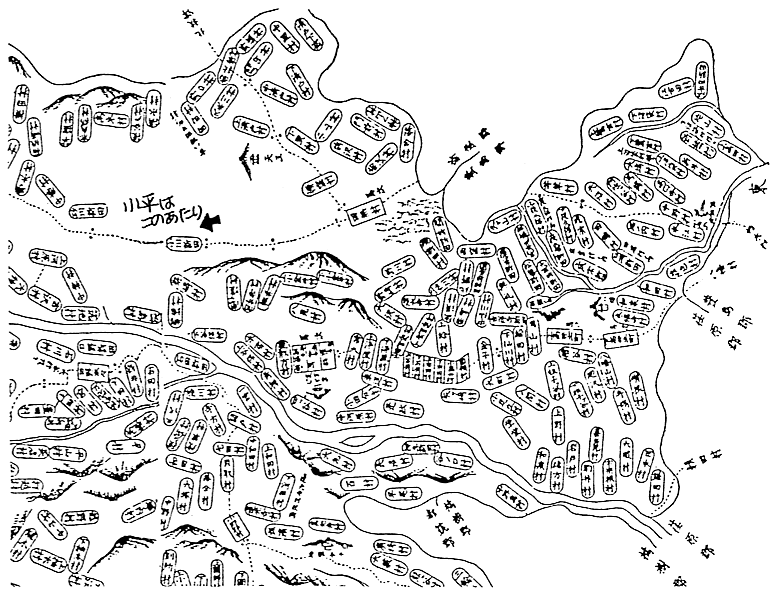
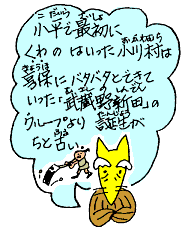
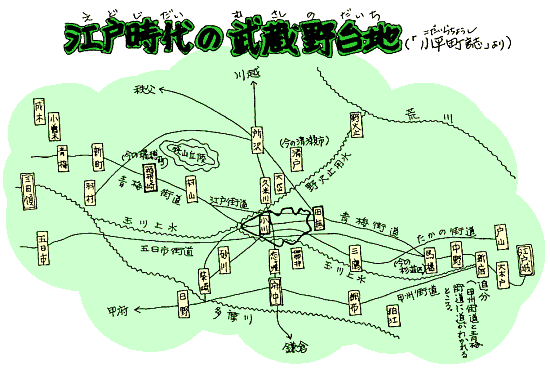

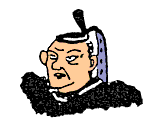
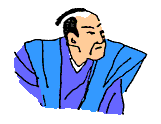
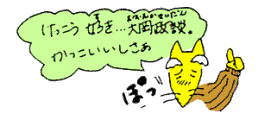 「
「
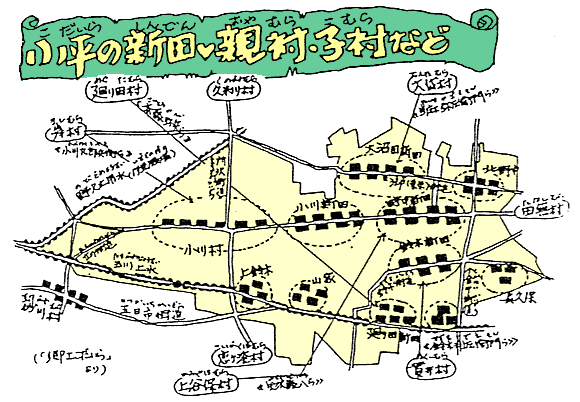
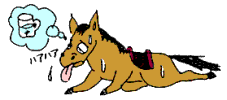

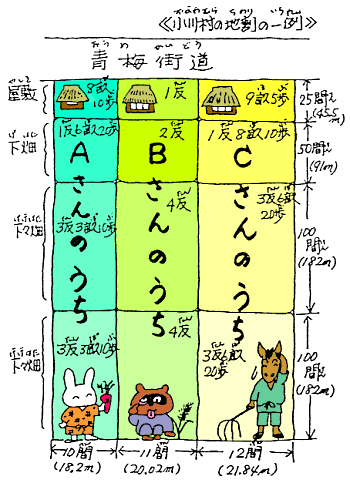
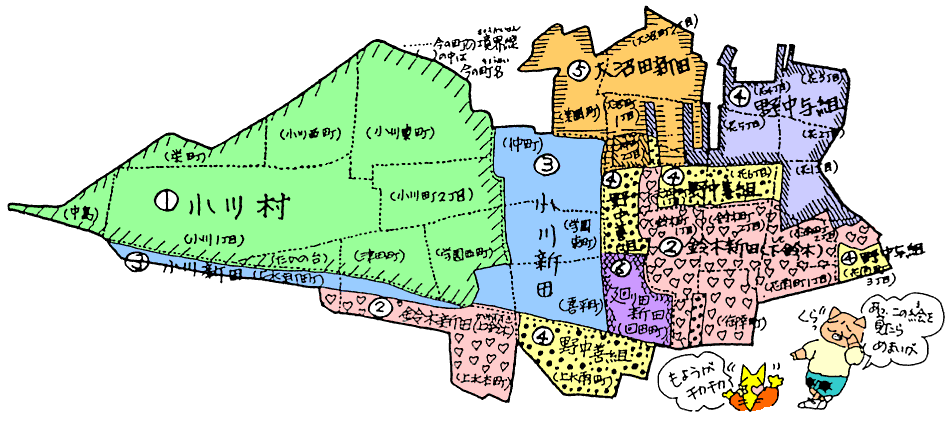


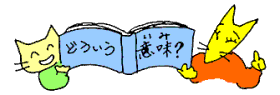 ちょっと説明
ちょっと説明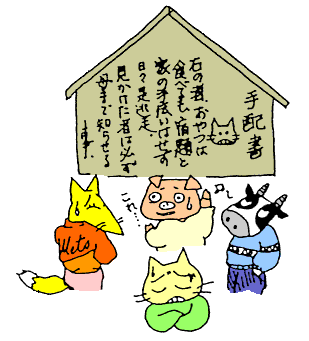
 ある
ある ある
ある