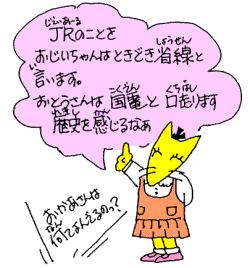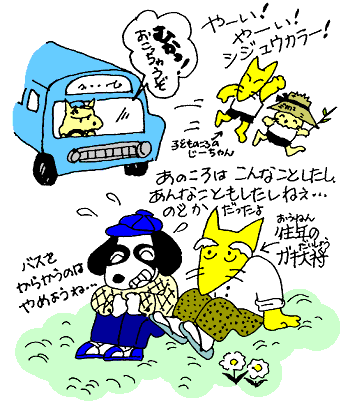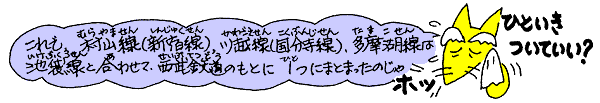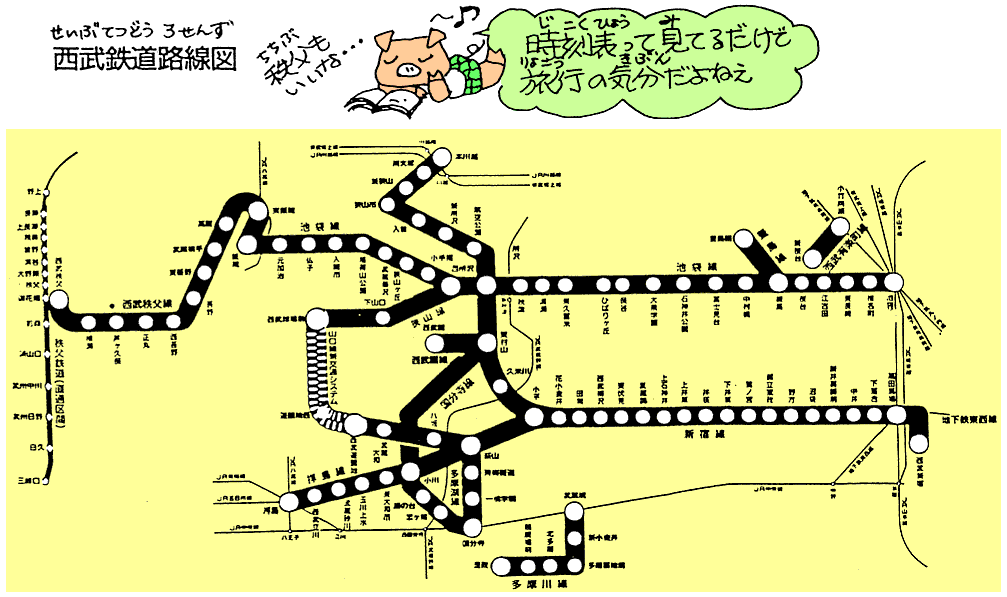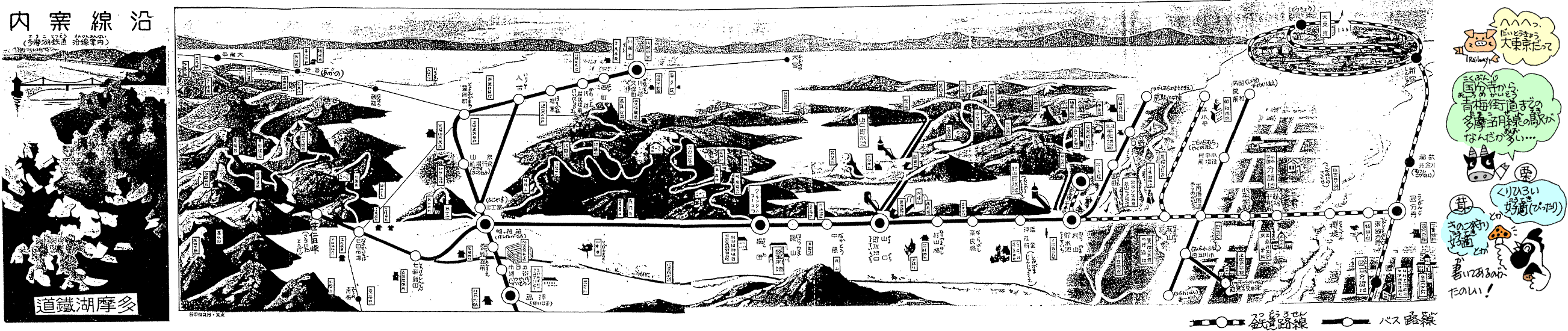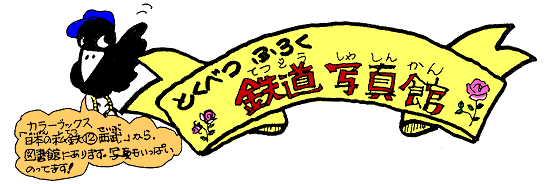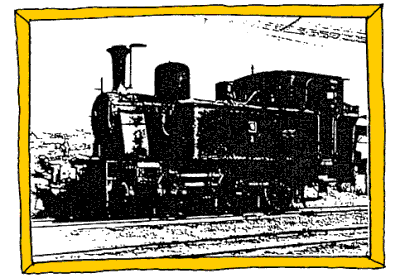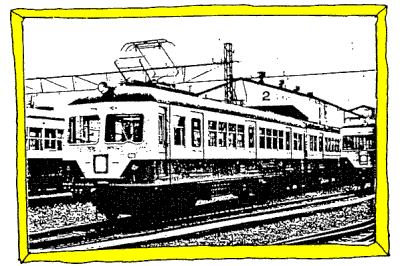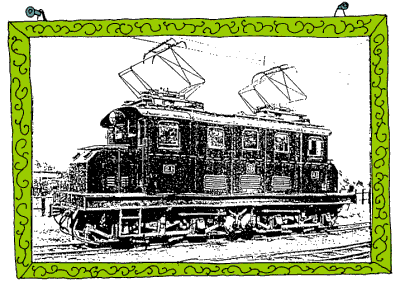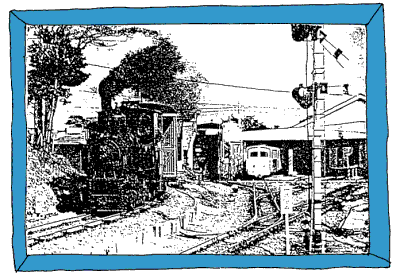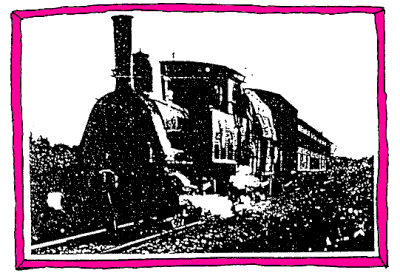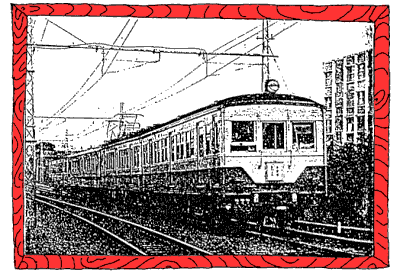小平の鉄道の歴史
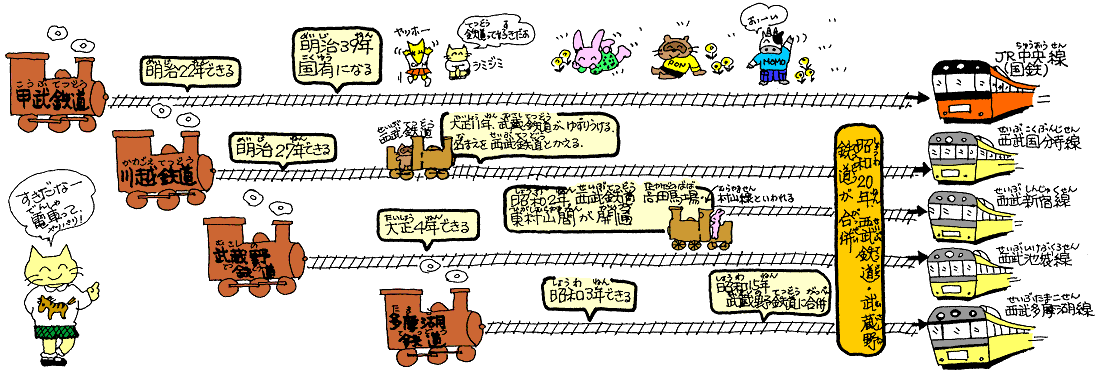
西武鉄道とか、JR中央線とか、みんながふだん乗っている電車たちにも、それぞれ歴史があるんだよ。
何だか楽しい、はじまりはじまりの頃の話…
中央線のたんじょう(甲武鉄道)
明治16
年、
東京から
羽村を
通って
青梅まで、
馬車鉄道をつくろうという
計画がもちあがりました。
青梅地方の
石灰石を
運ぶためです。
明治17
年にその
許可を
願い
出ましたが、そのころ
馬車鉄道にかわり、
汽車鉄道の
計画があちこちでおこりだしました。そこで、
明治19
年、
汽車鉄道として、もう
1度願いを
出し、
明治22
年に
許しがでました。
明治22
年3
月には
立川~
新宿間の
線路が
完成し、
汽車が
走りはじめました。その
時、
甲武線で
使われた
蒸気機関車はイギリス
製で、
時速は40キロメートルぐらい。はじめは
単線(
1本しか
線路がない!)で、
新宿と
立川の
間には「
中野」「
荻窪」「
境」「
国分寺」の4つの
駅しかありませんでした。
そして
明治39
年、
鉄道国有法により、
甲武鉄道は
国鉄(
今の
JR)にひきつがれました。

西武国分寺線のたんじょう(川越鉄道)
明治25年8月、川越鉄道会社はつくられました。所沢・狭山の地元の有力者と甲武鉄道の資本家(事業に必要なお金を出す人)たちが設立したのです。そして「川越」「入間」「所沢」「国分寺」の間に鉄道を敷くことを計画しました。
明治27年12月、まず国分寺~東村山間7.8キロメートルのきょりを汽車が走りはじめ、よく年には川越まで全線が通じました。小平には小川駅がおかれました。
これが西武鉄道では一番古い路線です。
そのころは蒸気機関車に客車(人がのる)1両、貨車(荷物がのる)10数両ついて、1日に6往復ほどしたとか。
川越は絹織物や綿織物の集まる場所でしたし、所沢も鎌倉街道の宿場で、交通の「かなめ」(大事なところ)でしたし、絹織物の市場町でもありました。
川越鉄道はこうした産物を東京に運ぶためにつくられたのでしょう。
川越鉄道はその仕事を甲武鉄道にまかせていたのですが、明治39年、甲武鉄道が国有になったので、自分でおこなうようになりました。その後何回か合併(会社どうしが手を組んで1つになること)をくりかえし、大正11年6月1日、帝国電灯という会社に合併されました。帝国電灯は鉄道部門を独立させて、武蔵鉄道という鉄道会社をつくりました。そして、その年の8月15日は武蔵鉄道を西武鉄道という名まえにあらためたのです。
JR武蔵野線
昭和48年4月1日たんじょう! この中では新しい。
小平を通っているJRはこれ! 青梅街道沿いに新小平という駅があります。府中本町から浦和(埼玉県)を通って、西船橋(千葉県)までぐるっとまわる、すぐれもの。
西武池袋線のたんじょう(武蔵野鉄道)
大正4年、武蔵野鉄道が池袋~飯能間43.8キロメートルに鉄道を敷いたのがはじまりです。最初のころは、この路線も蒸気機関車が走っていましたが、その後、どの鉄道会社より早く電車運転を始めました。
昭和2年には豊島(今の豊島園)まで開通し、昭和4年には西所沢~村山公園(今の西武球場前)も開通しました。(今の豊島線、狭山線とよばれる路線です。)
昭和2年、村山線をおこした西武鉄道とはライバル同士だったのですが(よい競争相手だったのだ!)、昭和20年にこの2つの会社は合併し、この路線は西武池袋線となったのです。
 これが「馬車鉄道」。馬車は線路の上を走って、お客や荷物をはこんだ。明治15年(1882年)、東京で走りだし、20年くらいつづいていたらしい。
これが「馬車鉄道」。馬車は線路の上を走って、お客や荷物をはこんだ。明治15年(1882年)、東京で走りだし、20年くらいつづいていたらしい。
都史紀要33「東京馬車鉄道」より
JRの歴史
明治39
年(1906
年)3
月31
日 “
鉄道国有法”
公布(
公布とは、みんなに
発表されること)
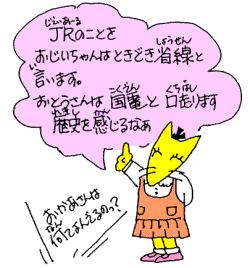 甲武
甲武・
総武など17
社の
私鉄が
買いとられ、1908
年、
鉄道院の
管かつとなる。
だから!このころは、
今の
中央線、
山手線などは、
院電とよばれていたのだ。
大正9
年5
月 鉄道院が
鉄道省という
名まえにかわる。
院電は
省線電車、つまり
省電とよばれるようになった。
昭和24
年6
月1日“
鉄道国有法”
施行(
施行とはその
法律がはたらきだすこと)
鉄道省は
日本国有鉄道とよばれる
公共企業体(というのは
政府などがお
金を
出して
経営する
企業のこと)となる。
省電が
国電とよばれるようになったのはこのころから。
(「
平凡社大百科事典」
参考)
そして、昭和63年(1987)4月1日、JRとして生まれかわった!
西武多摩湖線のたんじょう(多摩湖鉄道)
この
路線は
箱根土地会社がつくったものです。そのころ
建設中だった
村山貯水池がいずれたくさんの
観光客をよぶだろうというみこみと、
小平・
国立・
大泉を
中心にすすめられていた
学園都市計画で、
交通の
便をよくしなければならなかったからです。
箱根土地会社は「
多摩湖鉄道」という
名の
鉄道会社をつくり、
昭和3
年4
月、
国分寺~
萩山間を
開通させたのをはじまりに、
昭和11
年12
月には
村山貯水池下まで
線路をのばして
全線開通。さらに
今の
終点駅「
西武遊園地」のところまで
線路はのびました。この「
西武遊園地」
駅も
昭和54
年3
月24
日までは「
多摩湖駅」という
名まえだったのです。
はじめの
頃は、この
路線、
国産第1
号のガソリンカーが
1日1
時間おきに10
往復。
昭和5
年からは
電車になりました。が、ドアは
手で
動かす
方式で、
速度も
人が
走るのと
同じくらいだったとか。
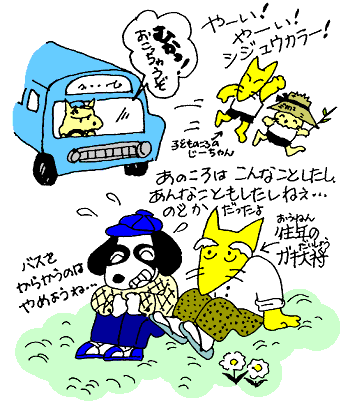 昭和
昭和15
年3
月、
多摩湖鉄道は
武蔵野鉄道(
今の
西武池袋線)に
合併。さらに
昭和20
年9
月22
日には
西武鉄道との
合併により、
西武農業鉄道株式会社となり、
昭和21
年にはふたたび
西武鉄道株式会社と
名まえをかえて、
今日にいたっています。
むかし、多摩湖線は「42人のり」とよばれていたよ。これは、“始終2人のり”=つまり、いつも運転手と車しょうさん2人しかのっていないという意味なんだ。
ついでに、同じころ国分寺から喜平橋を通って立川まで走っていたバスは「シジュウカラ」というあだ名だった。鳥のシジュウカラと「始終空っぽ」(お客がいなくて…)をかけてある。
おもしろいだろー?
西武新宿線のたんじょう(西武鉄道村山線)
大正11
年、
武蔵鉄道会社は
西武鉄道株式会社と
名まえをかえました。
大正12
年には
関東大震災があって、それ
以後、
東京の
人たちは
次々と
郊外に
引っ
越してきました。あわせて
交通の
手段も
必要になり、その
中で、
昭和2
年、
西武鉄道が
村山線を
敷きました。まず、
高田馬場~
東村山間が
開通。
小平にも
小平駅と
花小金井駅がおかれました。
昭和5
年には
東村山~
村山貯水池前(
今の「
西武園」
駅)までの
西武園線が
開通しました。
その
後、
西武鉄道は、
武蔵野鉄道に
合併されました。それより
前、
昭和15
年に、
武蔵野鉄道は
多摩湖鉄道を
合併していましたから、
昭和20
年のこの
合併で、
西武鉄道、
武蔵野鉄道、
多摩湖鉄道が
一つになったわけです。その
時「
西武農業鉄道株式会社」とかえられた
名まえは、よく年
昭和21
年にふたたび「
西武鉄道株式会社」という
名になりました。
西武新宿~
高田馬場が
開通したのは
昭和27
年のこと。
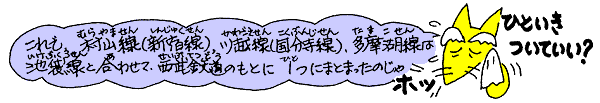
学園の町
大正12年の関東大震災をさかいに東京の人たちの間で郊外に住むことが大はやりとなりました。箱根土地会社は、ドイツの学園都市にならって、東京の郊外にも学園都市をつくる計画をたてました。そこで選ばれたのが、小平村、谷保村(今の国立市)、大泉村(今の練馬区大泉)の3ヵ所です。
小平には明治大学が10万坪(たたみが20万枚敷ける広さ!!)の土地を買って神田から引っ越してくることに……。ところが時代は第1次大戦のまっただ中で分譲地は思うように売れない! 明治大学も資金があつまらず、引っ越しをあきらめてしまいました。こまってしまった箱根土地会社は東京商科大学(今の一橋大学)にはたらきかけました。石神井にあった商科大学の予科がその土地と交かんという条件で昭和8年9月に引っ越してきました。
これが一橋大学の小平分校で、学校ができると周辺の分譲地もしだいに売れていったということです。
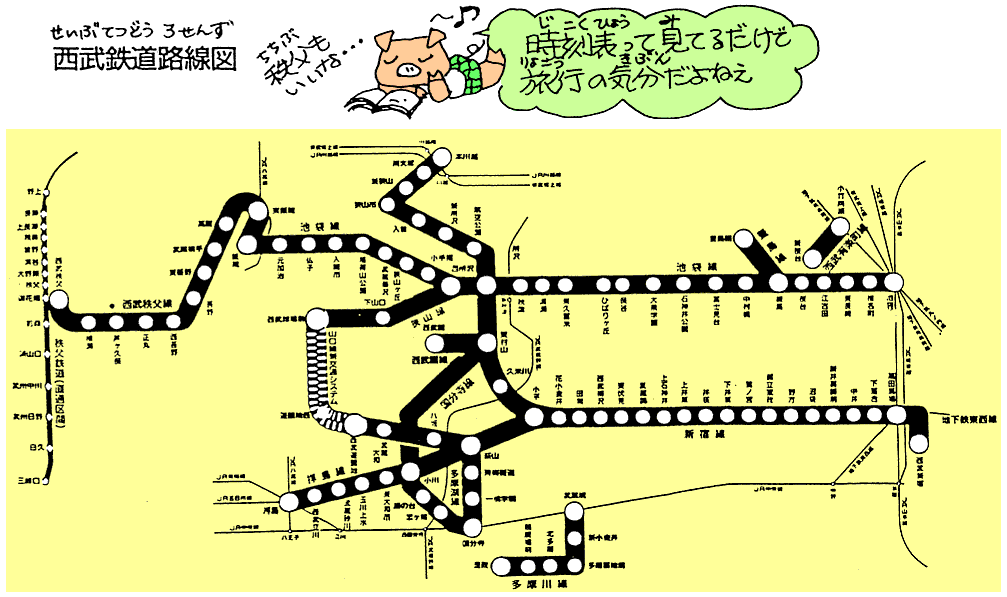
多摩湖鉄道「沿線案内」
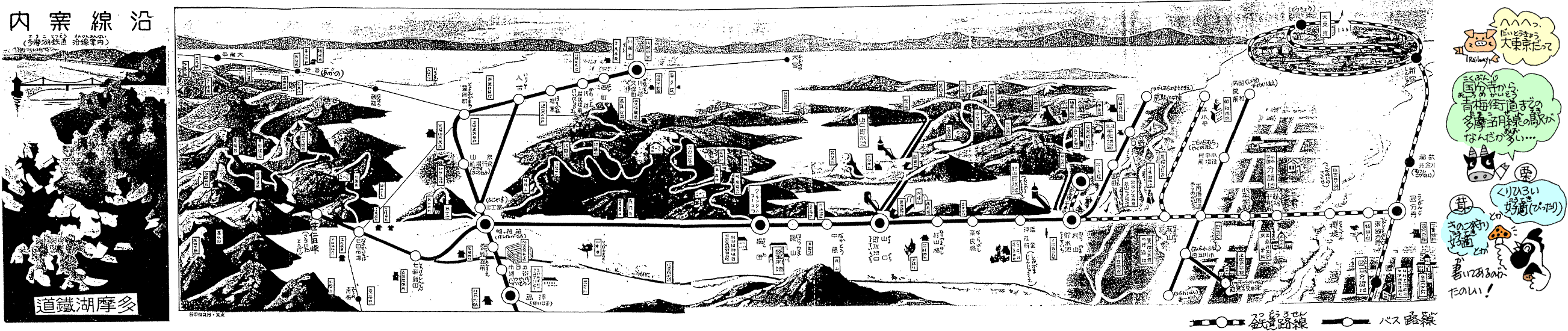
たぶん昭和5年~10年の間に作られたのでは…と思われる多摩湖鉄道の「沿線案内」
いろいろ今とちがっててオモシロイのだ!!

福生のあたりでキツネを飼っている場所があったらしい…。
個人の経営で300頭ものキツネがいたんだって。キツネ牧場みたいなものだったのかなあ。
鉄道写真館
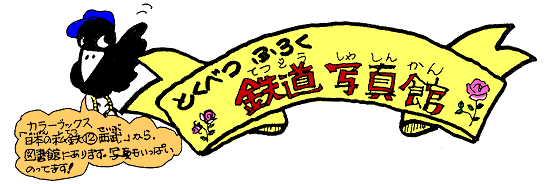
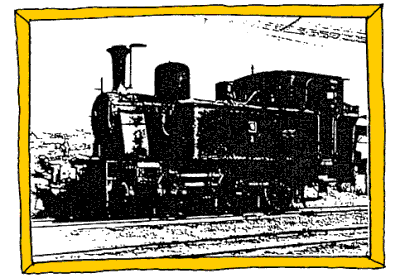
昭和の初め、武蔵野鉄道のヘンシェル2号機<池袋>

武蔵野鉄道と合併後(昭和15年以後)の多摩湖線モハ15形<萩山>
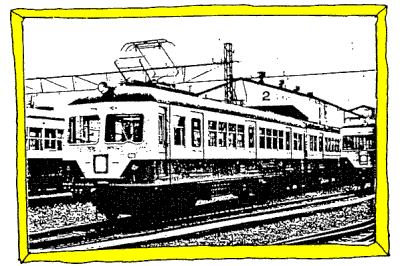
昭和29年誕生の351系。多摩湖線ではこの電車が平成2年まで走っていた。<保谷車両管理所>
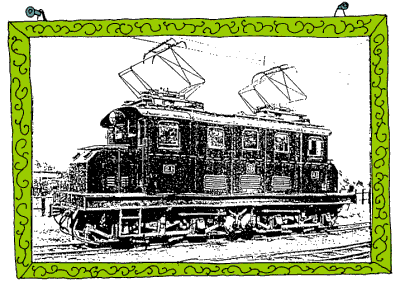
武蔵野鉄道の国産電車デキカ20形という電車<保谷>
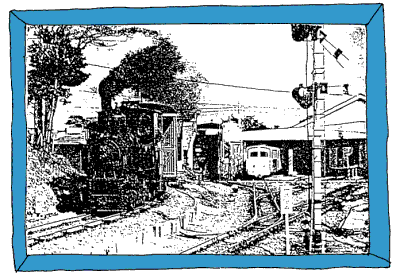
第2次世界大戦後に新しくできた路線、山口線。昭和48年、SLブームにのって蒸気機関車を走らせる<西武遊園地>
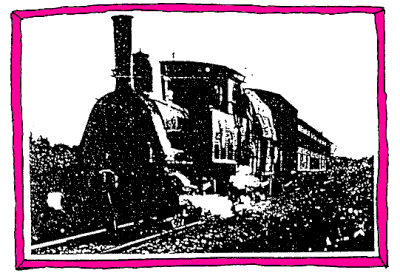
昭和の初め、川越鉄道を走る機関車<小川~国分寺>
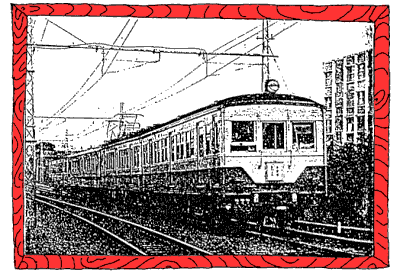
クハ1311形を先頭に行く多摩湖・玉川上水行電車。<鷺ノ宮~下井草>
参考にした本
「西武新宿線歴史散歩」
「西武池袋線歴史散歩」
「中央線歴史散歩」
「角川日本地名大辞典」
「市報小平縮刷版」
「小平町誌」「郷土こだいら」
みんなきょうどしりょうしつの本!
小平市に関すること
多摩に関すること
江戸・東京に関すること
玉川上水・小金井桜に関すること
その他
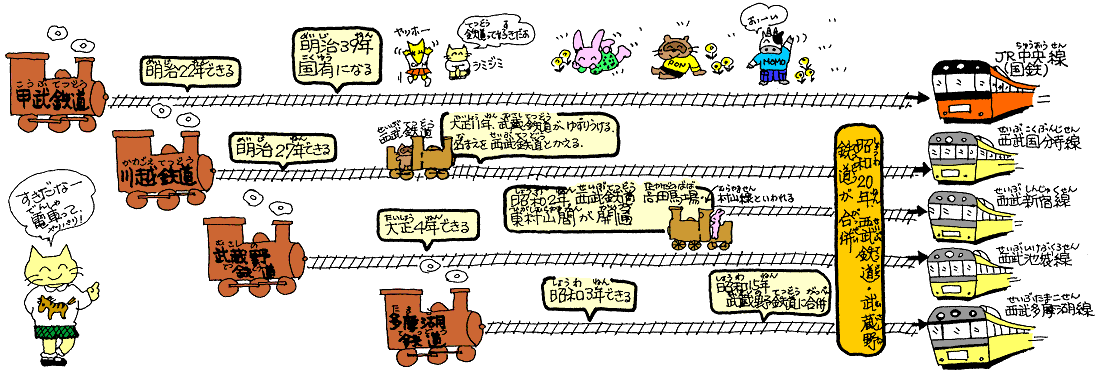

 これが「
これが「