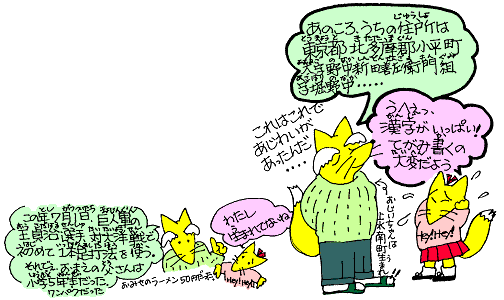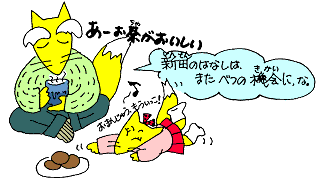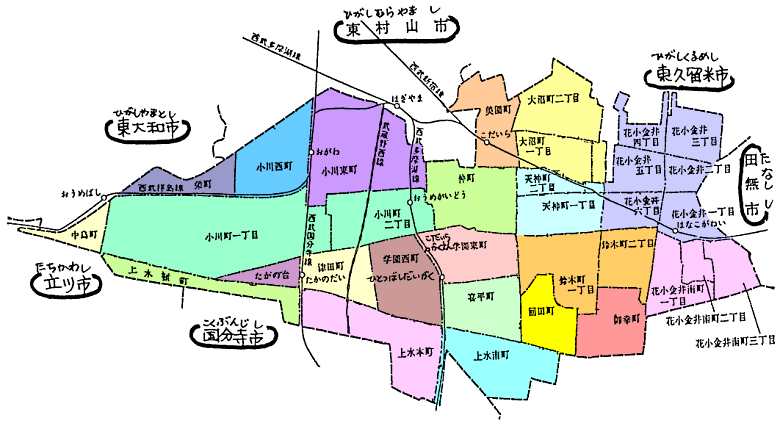小平町のころ(昭和37年9月30日まで)
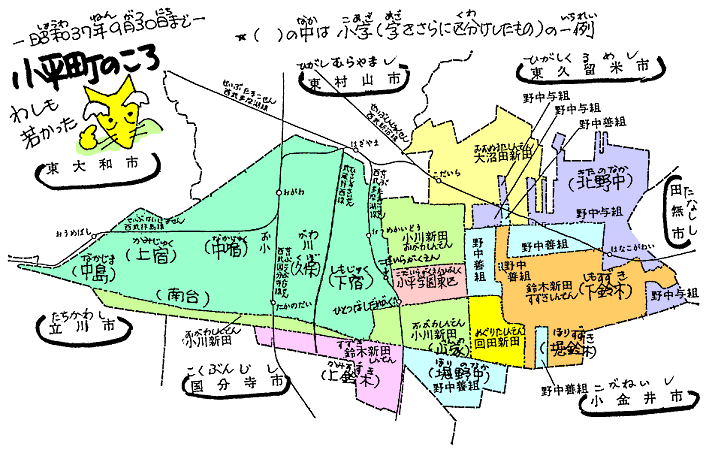
ご注意!
- 野中与組→野中新田与右衛門組のこと
- 野中善組→野中新田善左衛門組のこと
 新田の用水であり、みんなののみ水でもあった玉川上水を昔は「お堀」とよんで、大切にしたんだ。だから上水ぞいの地域は「ほりばた」とか「堀ナントカ」とよばれるところが多い。
新田の用水であり、みんなののみ水でもあった玉川上水を昔は「お堀」とよんで、大切にしたんだ。だから上水ぞいの地域は「ほりばた」とか「堀ナントカ」とよばれるところが多い。
 このころ、小平は、小川、小川新田、野中新田善左衛門組、野中新田与右衛門組、鈴木新田、回田新田、小平学園東区の8つの字(今の町のようなもの)にわかれていた。そのうちの4つの字は飛び地があり、(同じ名前の字が、あっちにもこっちにもわかれてあること)わかりにくかった。また、字がふくざつに入り組んでいるところもあった。これは小平の開たくの歴史のあとでもあるんだけどね。
このころ、小平は、小川、小川新田、野中新田善左衛門組、野中新田与右衛門組、鈴木新田、回田新田、小平学園東区の8つの字(今の町のようなもの)にわかれていた。そのうちの4つの字は飛び地があり、(同じ名前の字が、あっちにもこっちにもわかれてあること)わかりにくかった。また、字がふくざつに入り組んでいるところもあった。これは小平の開たくの歴史のあとでもあるんだけどね。
そして昭和37年10月1日、小平市の誕生とともに町名はかわった!
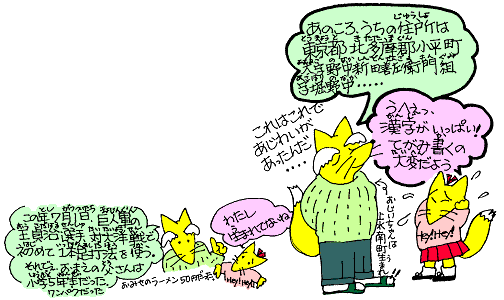
きわめつけ!
小平はなぜ、小平という名前になったか?!
明治22
年、
小川村、
小川新田、
大沼田新田、
野中新田与右衛門組、
野中新田善左衛門組、
鈴木新田、
廻り
田新田を
合わせて、ひとつの
村が
誕生した。
村のなまえは、
各新田から
代表者がでて
話し
合った。
それで、このあたりが
平らな
地形であることと、いちばん
早く
開たくされたのが
小川九郎兵衛由来の
小川村であることから「小」と「平」を
組み
合わせて「
小平」と
名付けた。
昭和19
年には、
村から
町に、
昭和37
年には
市になった。
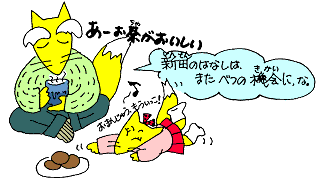
そして昭和37年10月1日! 町名はこうなった!
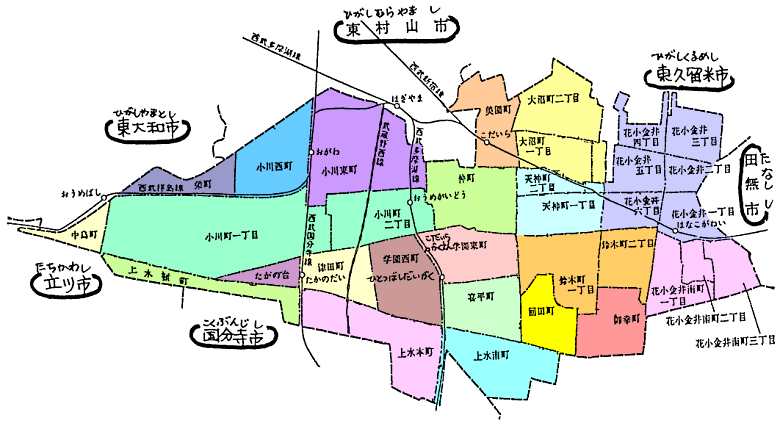
中島町
小川村の西部、玉川上水と野火止用水、それに小川分水にかこまれたこの地域は、中島とよばれていた。(むかしは海にうかんでいなくとも、水にかこまれていれば、その土地は「島」とよばれた。)そしてさらにその西部の西中島とよばれていたところが、今の中島町だ。
栄町
開たくの頃、この町のあたりは雑木林。住む人はほとんどなかったそうな。
小川村の農民はこの林の落ち葉や草をかり取って肥料にしたとか。
繁栄を願って栄町と名をつけた。
小川町
青梅街道沿いに東西に広がる町。
「小平開拓の祖」と言われる小川九郎兵衛が明暦3年 (1657年)から 開発した小川村の中心。
青梅街道は、青梅の石灰を江戸に運ぶ道として開かれたが、九郎兵衛が開発をはじめるまではこのあたり、人家はなく、一面の原っぱだったらしい。
たかの台
西武国分寺線たかの台駅前一帯の三角形をした町。この町の名は駅名から。このあたりは「小川村字鷹野街道外」の西側。小川村は尾張徳川家の“たか場”の中にあり、“おたかの道”があったのだ。
津田町
ここに津田塾大学があるところから、津田町と名がついた。昭和6年麹町(今の新宿区四谷)から、ひっこしてきた津田塾の最初の仕事は防風林づくりだった。つまり、その頃、まわりに住宅は少なく、砂あらしがすごかったのだ!
学園西町・学園東町
西武多摩湖線小平学園駅の西側と東側の地域なので。
この多摩湖線、大正14年開通。関東大震災直後で、近郊は住宅ブームだったこともあり、西町周辺の200万平方メートルを箱根土地会社が買収、分譲した。
東町は商店が多い。
多摩湖線の駅が今とはすこしちがうでしょう、ねっ!
小川西町・小川東町
西武国分寺線小川駅の西側と東側の地域なので。
仲町
小平のほぼ中央にあるし、また、「みんな仲よし」という気持ちもこめてこういう名になった。ほんとだよ。
美園町
広い、広い小平霊園のある町。霊園は小平、東村山、東久留米にまたがる。「美しい田園都市」を願ってつけられた。
大沼町
ここは、それまで大沼田新田とよばれていたから。むかしは「おおぬた」とか「おんた」ともよばれた。
天神町
このあたり、天神窪とよばれる場所があって、それにちなむ。
喜平町
昭和40年3月にできた小平団地によっていっぺんに人口が増えた。
「喜平」は堀野中の組頭(注釈)。この人の家のそばの橋が「喜平橋」とよばれ、さらに町の名はこの橋からついたのだ。
(注釈)組頭 村方三役のひとつで、名主や庄屋の仕事を手伝う。
村方三役とは「名主」「組頭」「百姓代」をいう。
回田町
ここらへん、回田新田とよばれていたので。
御幸町
明治16年4月、明治天皇が小金井橋でお花見をなさった。
この町の名はその行幸にちなんでついた。小金井橋の西、玉川上水北のつつみには「行幸松の碑」がある。
(注意)行幸というのは「天皇のおでまし」のことだよ。御幸もおなじ。
上水新町
上水本町
上水南町
玉川上水の南に沿った3つの町。
町の名はむろん、その玉川上水にちなんでいる。
上水南町(かつての野中新田善左衛門組)は開発のはじめ「喜平新田」とよばれていた。
鈴木町
鈴木街道、鈴木ばやし、鈴木小学校――鈴木の名は、このあたりを開発した鈴木利左衛門にちなむ。
享保9年 (1724年)、 利左衛門重広が、この地の開発を許され、その死後は息子の利左衛門春昌が仕事をひきついだ。
また、この町には石神井川の源があった。
花小金井、花小金井南町
西武新宿線の花小金井駅の名からとった。花小金井南というのは、駅の南にあるから。
この駅は小金井桜を花見にいく人の最寄駅だった。それで「花小金井」という名がついている。うつくしい~!
参考にした本
こだいら町報 縮刷版
小平市報 縮刷版
「東京の地名を歩く」日本名書出版
「小平町誌」「郷土こだいら」
きょうどしりょうしつにあるよ!
小平市に関すること
多摩に関すること
江戸・東京に関すること
玉川上水・小金井桜に関すること
その他
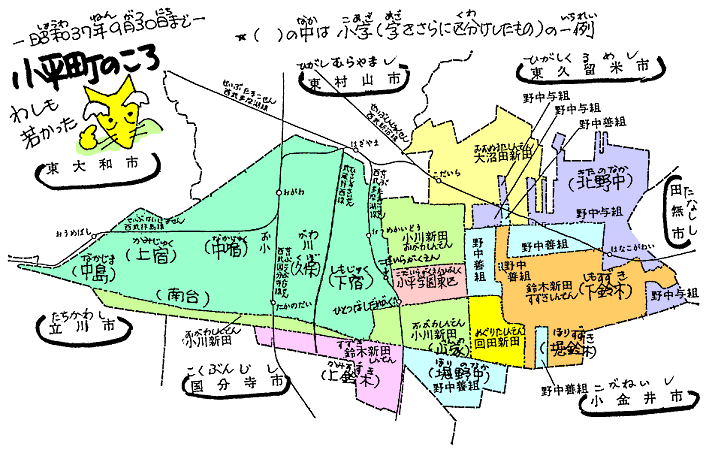

 このころ、
このころ、