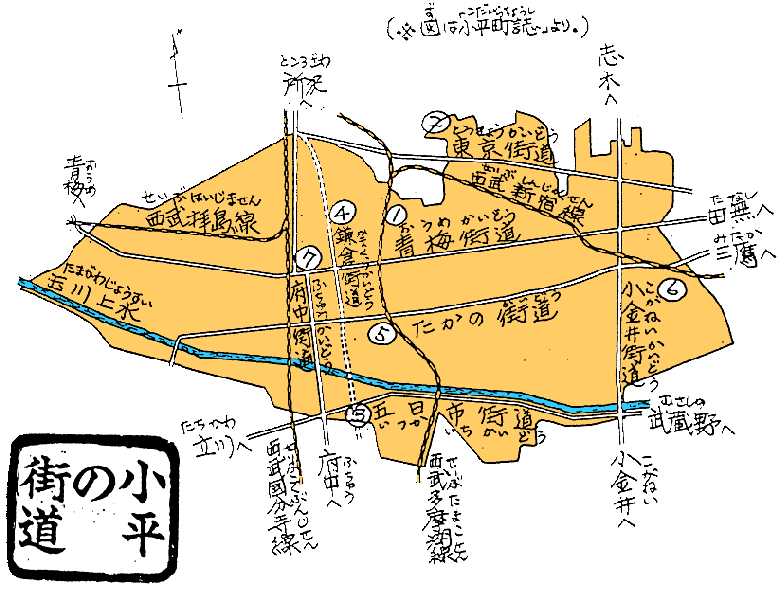| 年号 |
西暦 |
できごと |
| やく1万 ~3万年前 |
昭和49年(1974年)に鈴木町でこのころの遺跡を発見。 |
| やく1200から1300 年前 |
昭和45年(1970年)8小の校庭の東がわからむかしの住居あとや土器、石器がみつかった。 |
| 天正18年 |
1590年 |
徳川家康、江戸城にはいる。 |
| 慶長初めごろ |
青梅街道、五日市街道が通じる。 |
| 慶長8年 |
1603年 |
家康、江戸ばくふを開く。 |
| 承応3年 |
1654年 |
玉川上水できる。 |
| 明暦元年 |
1655年 |
野火止用水できる。 |
| 明暦2年 |
1656年 |
小川九郎兵衛、小川(小川町1、2丁目・小川東町・小川西町・栄町・たかの台)のかいこんを願いでる。 |
| 明暦3年 |
1657年 |
小川寺、小川にたてられる。 |
| 万治元年 |
1658年 |
日枝神社、小川にたてられる。 |
| 寛文元年 |
1661年 |
神明宮、小川にうつってくる。 |
| 宝永元年 |
1704年 |
熊野宮、一本榎の下に祭られる。 |
| 享保9年 |
1724年 |
小川新田(仲町・学園東町・学園西町)、大沼田新田(大沼町・美園町)、鈴木新田(鈴木町・御幸町・上水本町)、野中新田(花小金井・天神町・上水南町 )のかいこんがはじまった。
武蔵野神社、野中新田にたてられる。 |
| 享保11年 |
1726年 |
稲荷神社、鈴木新田にたてられる。
廻り田新田(回田町)のかいこんがはじまった。
宝寿院、鈴木新田に引寺される。 |
| 元文4年 |
1739年 |
平安院、小川新田にたてられる。 |
| 天明3年 |
1783年 |
浅間山大ふん火。小平にも火山灰おちる。
大ききんで農民苦しむ。(天明 3から7年) |
| 嘉永6年 |
1853年 |
ペリーが浦賀に来航。 |
| 安政5年 |
1858年 |
江戸にコレラ流行。 |
| 安政6年 |
1859年 |
安政の大獄おこる。 |
| 文久2年 |
1862年 |
小川にコレラ流行。 |
| 文久3年 |
1863年 |
近藤勇、土方歳三ら新選組をつくる。 |
| 慶応3年 |
1867年 |
大政奉還。 |
| 明治元年 |
1868年 |
「江戸」が「東京」とあらたまる。
小川・小川新田・廻り田新田がにらやま県(今の神奈川県)に、残りの新田は品川県(今の東京都)にはいる。 |
| 明治5年 |
1872年 |
今の小平の全地域が神奈川県にはいる。
学制(学校のきまり)ができる。 |
| 明治22年 |
1889年 |
大日本帝国憲法できる。
小平村たん生。 |
| 明治26年 |
1893年 |
小平村、東京都にはいる。 |
| 明治27年 |
1894年 |
川越線(国分寺~久米川)が通って、小川駅ができる。
日清戦争おこる。 |
| 明治37年 |
1904年 |
日露戦争おこる。 |
| 大正5年 |
1916年 |
小平村に電話がひかれる。 |
| 大正6年 |
1917年 |
小平村に電灯がつく。 |
| 大正7年 |
1918年 |
小川村開拓碑、神明宮境内にたてられる。 |
| 大正12年 |
1923年 |
関東大震災。 |
| 昭和2年 |
1927年 |
西武電車(高田馬場~東村山)が開通。 |
| 昭和3年 |
1928年 |
多摩湖線、開通。 |
| 昭和4年 |
1929年 |
昭和病院できる。 |
| 昭和6年 |
1931年 |
津田塾大学、小平にうつってくる。
満州事変おこる。 |
| 昭和8年 |
1933年 |
一橋大学、小平にうつってくる。
日本、国際連盟を脱退。 |
| 昭和14年 |
1939年 |
第2次世界大戦、はじまる。 |
| 昭和18年 |
1943年 |
「東京府」が「東京都」となる。 |
| 昭和19年 |
1944年 |
「小平村」が「小平町」となる。 |
| 昭和20年 |
1945年 |
東京大空襲(3月11日)
広島に原爆投下(8月6日)
長崎に原爆投下(8月9日)
終戦(8月15日) |
| 昭和21年 |
1946年 |
東京都薬用植物栽培所が小川(中島町)にできる。
日本国憲法ができる。 |
| 昭和23年 |
1948年 |
小平霊園ができる。 |
| 昭和26年 |
1951年 |
療養所緑風荘が小川にできる。 |
| 昭和27年 |
1952年 |
テレビ放送開始。 |
| 昭和29年 |
1954年 |
都立小金井公園ができる。 |
| 昭和33年 |
1958年 |
日立製作所武蔵工場(上水本町)ができる。 |
| 昭和34年 |
1959年 |
ブリヂストンタイヤ東京工場(小川東町)ができる。
『小平町誌』が完成する。
小平町章が制定。 |
| 昭和37年 |
1962年 |
「小平町」が「小平市」となる。 |
| 昭和41年 |
1966年 |
都立小平保健所、小川町2丁目にできる。
小平村山大和衛生組合ごみ焼却場、中島町にできる。 |
| 昭和44年 |
1969年 |
小平警察署が小川町2丁目にできる。 |
| 昭和47年 |
1972年 |
市立福祉会館が学園東町にできる。
市民憲章が制定される。 |
| 昭和50年 |
1975年 |
仲町図書館ができる。 |
| 昭和54年 |
1979年 |
花小金井図書館ができる。 |
| 昭和55年 |
1980年 |
小川西町図書館ができる。 |
| 昭和56年 |
1981年 |
喜平図書館ができる。 |
| 昭和57年 |
1982年 |
中央公園(野球場、競技場、テニスコート)ができる。
上宿図書館ができる。
玉川上水遊歩道が新東京百景にえらばれる。 |
| 昭和59年 |
1984年 |
平櫛田中館、学園西町1丁目にできる。 |
| 昭和60年 |
1985年 |
東部公園が、花小金井6丁目にできる。
中央図書館ができる。 |
| 昭和62年 |
1987年 |
津田図書館ができる。 |
| 平成元年 |
1989年 |
「こだいら秀景25」がきまる。 |
| 平成4年 |
1992年 |
市制施行30周年になる。
市の鳥をコゲラにする。 |
| 平成5年 |
1993年 |
小平ふるさと村開園となる。
市民文化会館(ルネこだいら)が開館となる。 |
| 平成6年 |
1994年 |
平櫛田中館(現平櫛田中彫刻美術館展示館が開館となる。 |
| 平成7年 |
1995年 |
ふれあい下水道館が開館する。 |
| 平成13年 |
2001年 |
大沼図書館がができる。 |
| 平成14年 |
2002年 |
FC東京練習場、小平グランドへ移転する。 |
| 平成15年 |
2003年 |
小川西グラウウンドの利用をはじめる。 |
| 平成16年 |
2004年 |
コミュニティバスの試運転をはじめる。
小平元気村おがわ東を開設する。
小平グリーンロード、「美しい日本の歩きたくなる道500選」に入選する。 |
| 平成18年 |
2006年 |
第1回灯りまつりをはじめる。
花小金井図書館が移転する。 |
| 平成20年 |
2008年 |
小平町と姉妹都市提携30周年となる。 |
| 平成21年 |
2009年 |
日本一大きな丸ポストが完成する。 |
| 平成24年 |
2012年 |
市制施行50周年になる。 |