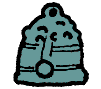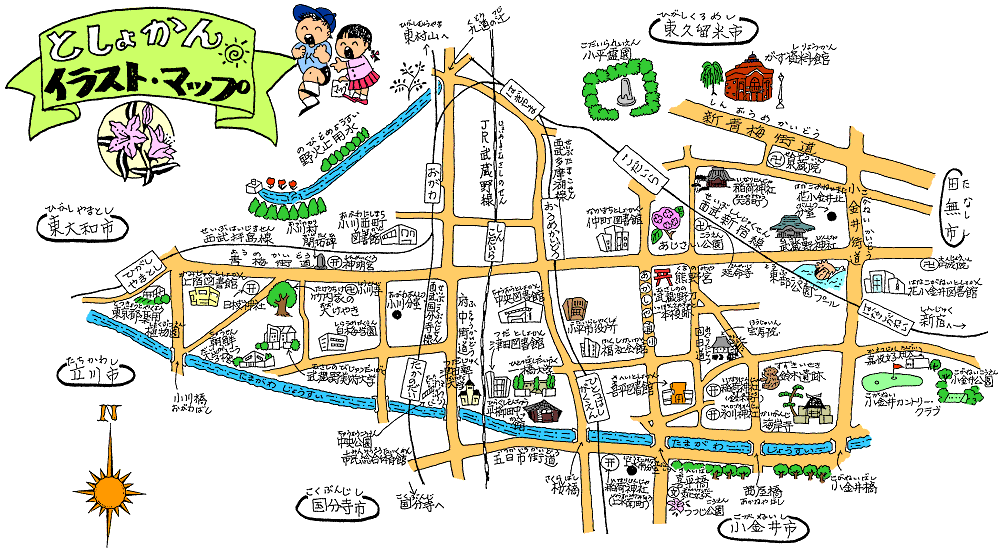見学 に 行 ってみようかな!・ 小平市 指定 文化財

九道 の 辻
旧 鎌倉 街道 のほぼまん 中 で江戸道・引股道・清戸道・奥州街道・大山街道・鎌倉街道の9 本 の 道 がここでわかれていたところから「 九道 の 辻 」といわれています。
むかし、ここに1 本 のサクラの 老木 ( 年 とった 木 )があって「 迷 いの 桜 」「 九道 の 桜 」といわれていました。 大正 時代 に 枯 れてしまいましたが、 昭和 55 年 10 月 、 交番 のうらになえ 木 が 植 えられました。
平櫛 田中 彫刻 美術 館
昭和 45 年 から 亡 くなる 昭和 54 年 まで、ここは 田中 のすまいでした。
開館 は 昭和 59 年 10 月 。
館内 にはたくさんの 作品 が 展示 してあります。
開館 時間 10時から16時
休館日 (お休みの日) 毎週 火 よう 日 年末 年始 (12月27日から1月5日)
がす 資料館
大沼町 2-590
ガスの 歴史 を 展示 している 東京 ガスの 資料館 。
開館 時間 10時から17時( 入館 は16時まで)
休館日 毎週 月 よう 日 年末 年始 (12月25日から1月4日)
鈴木 遺跡
鈴木 町 1-450-1
昭和 49 年 6 月 、 現在 鈴木 小学校 がある 場所 で 発見 された 遺跡 です。
約 1 万 から3 万 年 前 の 旧 石器 時代 のもの。
鈴木 遺跡 資料館
鈴木 町 1-487-1
鈴木 遺跡 から 発 くつされた 遺物 を 保存 ・ 展示 しています。
開館 時間 10時から16時
開館 日 日 よう・ 水 よう・ 土 よう・ 祝日
休館日 月 よう・ 火 ・ 木 よう・ 金 よう 年末 年始 (12月27日から1月5日)
東京 都 薬用 植物園
中島 町 21‐1
昭和 20 年 9 月 に 建 てられました。
約 1,600 種類 の 薬用 植物 ( 薬 として 使 う 植物 )が 栽培 されています。
開園 時間 9時から16時
休園日 毎週 月 よう 日 年末 年始 (12月29から1月3日)
入場 無料
資料館 休館日 土 よう・ 日 よう・ 祝日
小平 霊園
昭和 23 年 5 月 開園 の 都立 霊園 。 面積 は65 万 3,000 平方 メートル。
作家 の 壷井 栄 、 詩人 の 野口 雨情 など、 有名人 が 眠 っています。 小平 駅北口 から 霊園 までの 参道 はさわやかなケヤキ 並木 。
小平市 指定 文化財
鈴木 ばやし
江戸 時代 の 弘化 4 年 (1847 年 )から、 鈴木 地区 に 伝 わる「はやし」。
この「はやし」にのって、シシ、おかめおどりなどを 舞 います。
旧 小平 小川 郵便 局舎
 明治
明治 41
年 (1908
年 )に
建 てられました。
このころの
郵便局 の
様子 を
知 ることができる
貴重 なたてものです。
小川寺 梵鐘
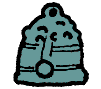 貞享
貞享 3
年 (1686
年 )につくられ、
小川寺 の
檀家 57
戸 により
寄進 (
寄付 のこと)されたものです。
このほか小平市の指定文化財は
延命 寺 庚申塔
八小 遺跡
小金井 桜 樹 碑
行幸松 と 行幸松 の 碑
當麻家 文書
小川 九郎兵衛 墓
小川村 開拓碑
竹内家 の 大 ケヤキ
海岸 寺 山門
武蔵野 乃 一本 榎 跡
旧 神山家 住宅主屋
旧 鈴木家 住宅穀櫃
旧 小川家 住宅玄関棟
いっぱいあるねっ!
きみのうちのちかくのお 寺 や 神社 !

平安院 仲町 676
元文 4
年 (1739
年 )
小川寺 6
代 の
省宗 碩要 禅師が
江戸 市ヶ谷 河田町 (
今 の
新宿区 )
月桂 寺 の
塔頭 (注釈1)にあった
寺号 (
寺 の
名前 )をうつして
建 てました。
熊野宮 仲町 361
神明宮 の
神主 、
宮崎 主馬 は、
名主 小川 九郎兵衛 とともに
小川 新田 を
開 きました。
この
時 、
武蔵国 多摩郡 岸村 (
今 の
武蔵村山市 )にあった
熊野宮 をうつして、
新田 の
鎮守 (注釈2)としたのです。
宝永 元 年 (1704
年 )、
榎 の
下 に
祭 りました。
武蔵野 乃 一本 榎 跡 仲町 362-1
初代 の 榎 は、たけが 群 をぬいて 高 く、 鎌倉 街道 を 行 き 来 する 旅人 のめじるしとして 親 しまれていたと 伝 えられています。
この 大木 は 寛保 年間 (1741~3 年 頃 ) 枯 れてしまい、その子木も 大正 13 年 の 台風 でたおれ、 現在 のは3 代目 の孫木で 樹令 ( 木 の 年令 )100 年 くらいと 思 われます。
日枝 神社 小川町 1-303
江戸 麹町 の
日枝 神社 の
分祠 (注釈3)として、
承応 3
年 (1654
年 )、
神主 、
山口 求馬 が
小川 九郎兵衛 と
協力 して、
今 の
場所 から100メートルほど
西 に、
日吉 山王社 として
祭 りました。その
後 、
台風 で
神殿 がこわれたので
宝暦 5
年 (1755
年 )
今 の
場所 に
建 てなおしたのです。
神明宮 小川町 1-2573
小川 九郎兵衛 が
小川村 を
開 たくするとき、
岸村 (
今 の
武蔵村山市 )にあった
産土神 (注釈4)を
移 してきて
造 られたものです。
寛文 元 年 (1661
年 )、
今 の
境内 から375メートルほど
北 の
野火 止 用水 ぎわに
建 てられ、その
後 、
天和 元 年 (1681
年 )に
今 の
場所 にうつりました。
小川寺 小川町 1-733
明暦 2 年 (1656 年 )、 小川 九郎兵衛 が 小川村 の 開 たくを 始 めるとともに、 江戸 市ヶ谷 河田町 ( 今 の 新宿区 )の 月桂 寺 住職 、 雪山 碩林 大禅師をむかえて 建 てたのがこの 寺 です。
「 小川 九郎兵衛 墓 」や「 小川寺 梵鐘 」などの 小平市 指定 の 有形 文化財 があります。
海岸 寺 御幸町 318
本明 宗全 禅師が
武蔵国 秩父郡 の
三 峯 山に
建 てた
寺 です。
鈴木 新田 に
入植 した
多 くの
農民 は、この
寺 を
菩提寺 (注釈5)としていましたが、
遠 くて
不便 だったので、
元文 元 年 (1736
年 )、
今 の
場所 に
引寺 されました。
本堂 は
昭和 32
年 につくりなおされたものですが、
山門 は
最初 の
頃 のものといわれ、「
鎌倉 式 」という
建築 様式 がとられています。
大仙寺 上水 南町 2-11-20
文禄 年間 に
正善院 日堂 上人を
開山 (注釈6)として、
台東区 寿 に
建 てられていた
寺 でしたが、
空襲 で
焼 けてしまい、
昭和 23
年 5
月 、
今 の
場所 にうつってきたものです。
江戸 時代 の
浮世 絵師 、
一勇斎 国芳 のお
墓 があります。
小川村開拓碑 神明宮境内
小川村を開いた小川九郎兵衛の10代目の孫、弥次郎が大正7年、小川村の開たく250年祭をおこなう時、村民と協力して、九郎兵衛の功績を後の世まで伝えるために建てたもの。
小川村開たくの由来がしるされています。
竹内家の大ケヤキ 小川町1-583
市内最大の木。高さは35メートル以上。幹の周囲は6.5メートルもあります。樹令(木の年令)は330年以上といわれています。
宝寿院 鈴木町1-129
鈴木新田を
開いた
鈴木利左衛門春昌が
多摩郡中宿(
今の
府中)
妙光院にあった
塔頭(注釈1)を
引寺してきたものです。
円成院 花小金井1-791
矢沢藤八とともに野中新田を開たくした大堅は宝永2年(1705年)、上谷保村(今の国立市)にひらいた円成院を享保12年(1727年)、野中新田に引寺をしたのでした。
武蔵野神社 花小金井5-461
円成院住職大堅と
矢沢藤八らは、
野中新田の
開発の
時、
開こん
地を12
等分して、その1つを
社地と
寺地にしました。そして
享保9
年(1724
年)
上谷保村(
今の
国立市)から“びしゃもん
天”をうつし、
村の
鎮守(注釈2)としました。
円成院が
管理していましたが、
明治維新のとき
分離独立して、
武蔵野神社という
社号になりました。
延命寺 天神町2-296
享保年間、
野中新田の
開発のため、
武蔵村山からうつり
住んだ
農民たちが
多摩郡中藤村(
今の
武蔵村山市)の龍華山
真福寺の
塔頭を
引寺して
菩提寺(注釈5)としたのがはじまりです。
稲荷神社
鈴木町1-500
享保9
年(1724
年)
鈴木新田の
名主、
鈴木利左衛門が
本村の
貫井村(
今の
小金井市貫井町)にあった
稲荷神社を
新田の
鎮守として
勧請。(注釈7)
本殿は
白ぬりの
土蔵づくりです。
上水本町2-6-14
上鈴木(
今の
上水本町)でも、
下鈴木(
今の
鈴木町1
丁目)と
同じように、
親村の
貫井村から
享保8
年(1723
年)
稲荷神社を
勧請(注釈7)しました。
上水南町1-2-15-5
野中新田善左衛門組にぞくしていた
堀端野中(
今の
上水南町)の
産土神として
元文 元 年 (1736
年)に
勧請(注釈7)されたと
伝えられます。
ちょっとむずかしい言葉のせつめい
(注釈1) 塔頭;本寺の
境内にある
小さい
寺のこと。
(注釈2) 鎮守;その
土地を
守る
神さま。
(注釈3) 分祠;
神さまを
分けてまつること。
(注釈4) 産土神;その
人が
生まれた
土地を
守る
神さま。
(注釈5) 菩提寺;
先祖代々のいはいをおさめる
寺のこと。
(注釈6) 開山;その
寺を
最初にひらいた
人のこと。
(注釈7) 勧請;
神さまの
霊をわけてまつること。
としょかん イラスト・マップ
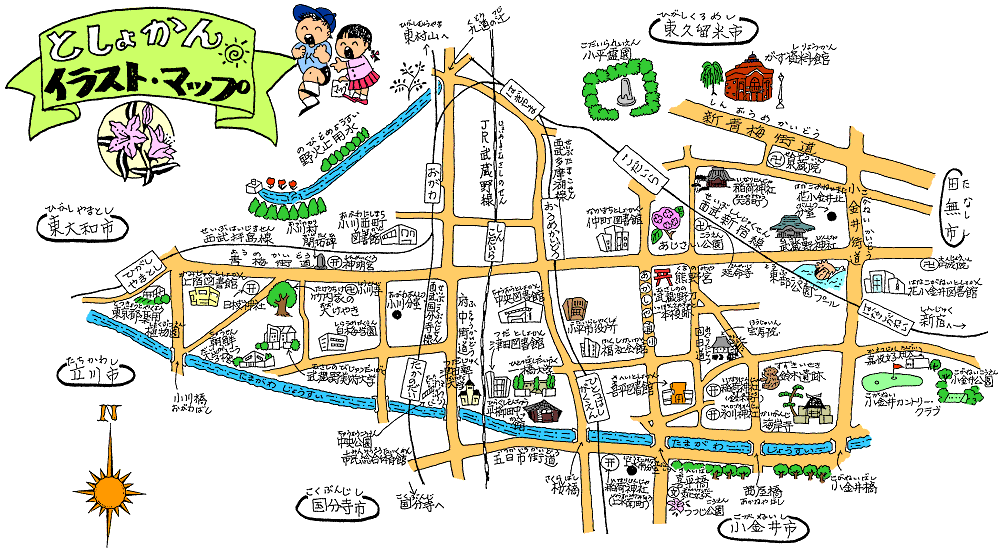
参考 にした 本 のしょうかい みんな 図書館 にある 本 です。
「 文化財 みて 歩 き」 「 郷土 こだいら」
「 文化財 みて 歩 き地図」 「 小平 町 誌 」
こだいらの 歴史 がわかる! 名所 ・ 旧跡 がわかる!
「 仏家 人名 辞書 」(おぼうさんの 名 まえの 辞典 )
「 広辞苑 」( 国語 辞典 )なども 参考 にしました。
小平市に関すること
多摩に関すること
江戸・東京に関すること
玉川上水・小金井桜に関すること
その他