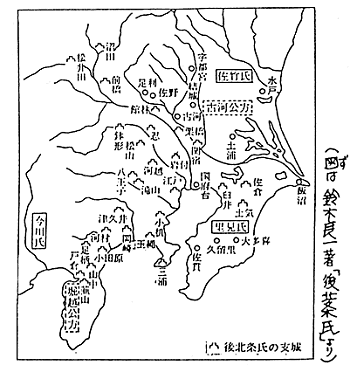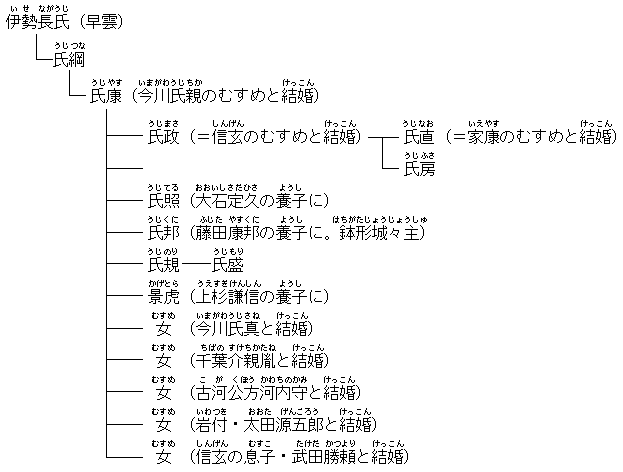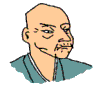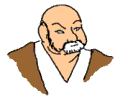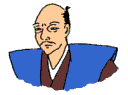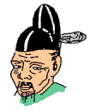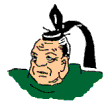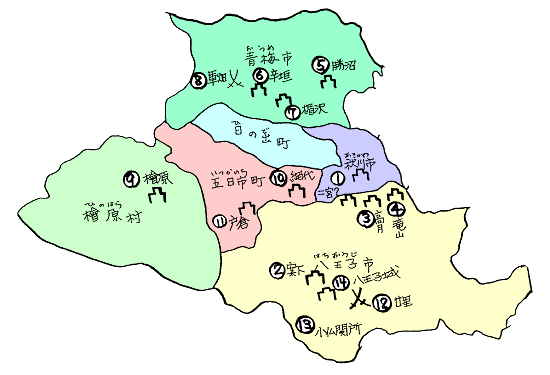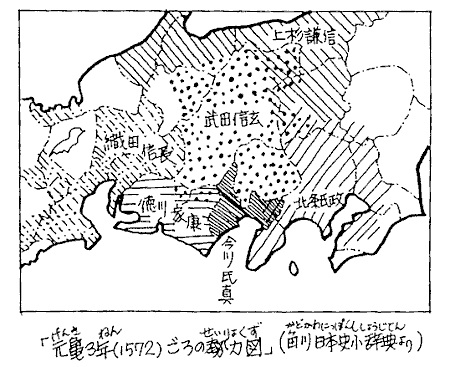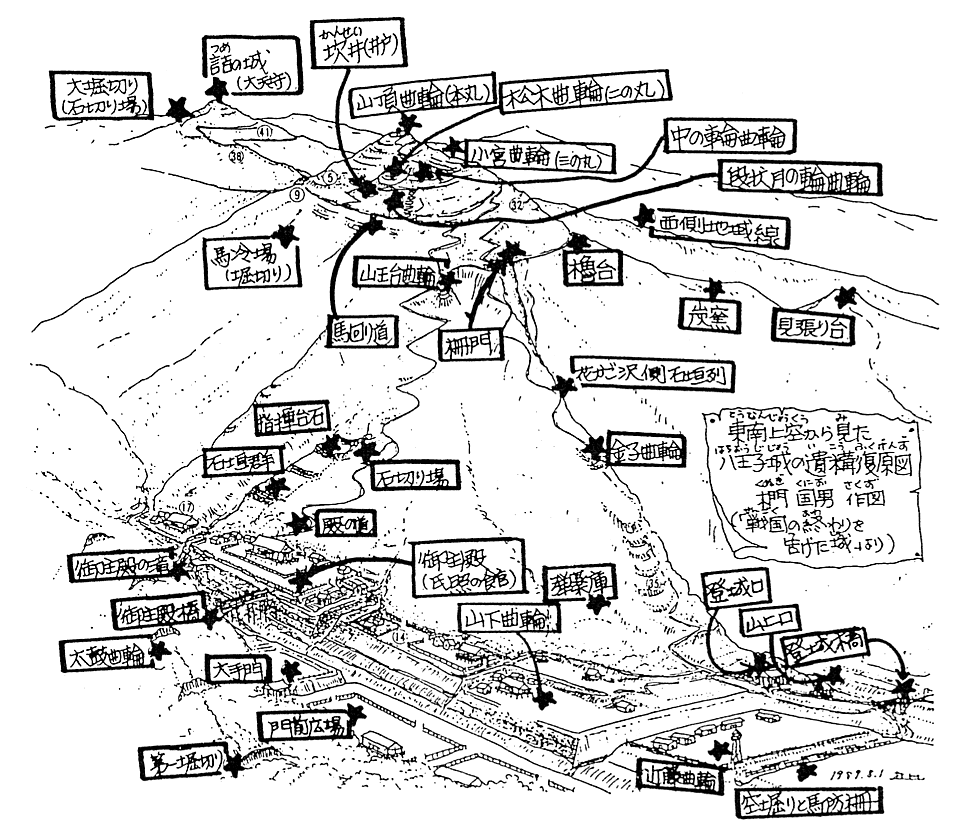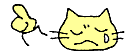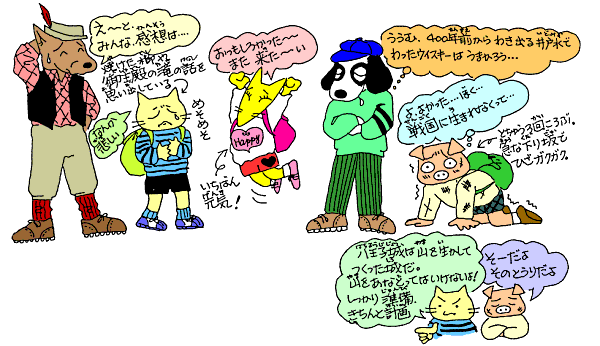戦国 時代 の 多摩
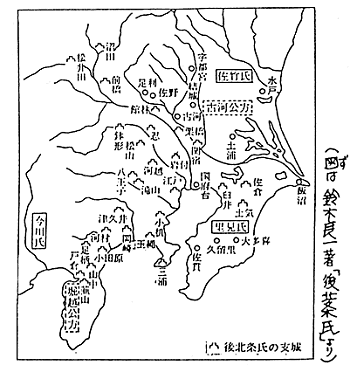 足利尊氏 のひらいた 室町 幕府 も、1467 年 の 応仁 の 乱 (注釈) 以降 おとろえた。
足利尊氏 のひらいた 室町 幕府 も、1467 年 の 応仁 の 乱 (注釈) 以降 おとろえた。
世 の 中 は 乱 れ、 守護 大名 にかわり、 新 しくおこってきた 戦国 大名 たちが 各地 で 領国 をつくる。
関東 の 北条早雲 、 遠江 ・ 駿河 の 今川氏 、 山城 の 油売 りから 身 をおこした 美濃 の 斎藤 道三 らはこの 下克上 時代 の 代表 選手 だ。
早雲 を 初代 として 伊豆 からおこり、 相模 の 領主 となった 後北条氏 が、 関東 の 支配 をめざし、 武蔵 に 進出 したのは 二代目 氏綱 のとき。 氏綱 は1524 年 、 扇谷上杉氏 の 江戸城 を 攻 めおとした。 城主 ・ 上杉朝興 を 武蔵 河越城 ( 埼玉県 川越市 )に 追放 。1537 年 には、その 河越城 も 攻 めおとしている。
三代目 氏康 のとき、 関東 管領 山内 上杉憲政 と 扇谷上杉 朝定 ( 朝興 の 子 )は、 後北条氏 を 倒 そうと 手 をむすんだ。1546 年 、 古河公方 ・ 足利晴氏 も 加 わって、 河越城 を 攻撃 。この 戦 いで 朝定 は 戦死 。 扇谷上杉氏 は 滅 んだ。 後北条氏 にとって、ふるくから 関東 に 勢力 を 持 つ 上杉氏 は、いずれ 倒 すべき 相手 だったのだ。
ところで 多摩郡 には、 大石氏 ・ 三田氏 の 二大 勢力 があった。 両氏 とも 関東 管領 ・ 上杉氏 の 重臣 で、 多摩 の 名族 だ。 氏康 は 二男 の 氏照 を 養子 として 大石氏 のもとに 送 りこみ、 姻戚 関係 ( 結婚 して 親 せきになること。 氏照 は 大石定久 の 娘 と 結婚 した。)を 結 んだ。1546 年 のことだ。
氏照 は 多摩郡 南部 の 大石氏 の 領土 をうけついだ。 一方 、 多摩 北部 から 高麗郡 に 力 を 持 つ 三田氏 は、いぜんとして 後北条氏 には 障がい物 だった。1563 年 ごろ、この 三田氏 を 滅 ぼして 氏照 の 八王子領 支配 も、 確 かなものとなったのだ。
(注釈) 応仁 の 乱 = 将軍家 や 有力 な 守護 大名 家 の 相続 争 いから 起 きた 戦乱 。
早雲 のおこした 北条氏 は 後北条氏 とか、 小田原北条氏 とかよばれている。
これは、 鎌倉 幕府 の 執権 だった 北条氏 と 区別 するためだ。
ちょっとひとこと!!
小川村 を 開拓 した 小川 九郎兵衛 の 先祖 、 小川 弥四郎 義勝 もこの 河越 の 合戦 の 時 に22 歳 で 戦死 したと伝えられている。
小川 家 の 先祖 は 武蔵 武士 として 活 やくしていたのだ!!
 戦国 時代 の 大名 は 仲 よくなったり 戦 ったり、また 仲 よくなったり、いそがしいのだ。
戦国 時代 の 大名 は 仲 よくなったり 戦 ったり、また 仲 よくなったり、いそがしいのだ。
結婚 だの、 養子 だのと 息子 や 娘 もいそがしい。
一族 の 命運 を 賭 けた 命 がけのおつき 合 いだしね。
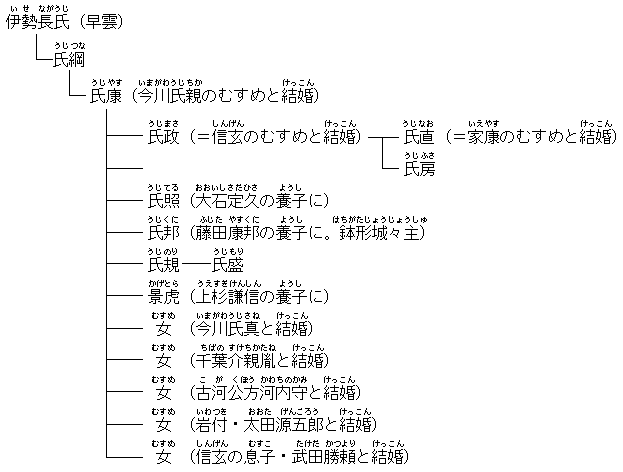
後北条氏 年表
後北条氏年表
| 年 |
月 |
できごと |
1476
( 文明 8)年 |
|
駿河 守護 、 今川 家 の 相続 争 いを、 早雲 、 太田 道灌 とともに 仲 直 りさせる。
この 時 、ふたりは45 歳 の 同 い 年 。 |
1491
( 延徳 3)年 |
|
この 年 早雲 、 伊豆 韮山 堀越 公方 、 足利家 のうちわもめに 乗 じて、 伊豆 に 攻 め 入 る。
足利 茶々丸 、 討 たれる。 |
1495
( 明応 4)年 |
9月 |
早雲 、 城主 大森藤頼 をやぶり、 小田原城 をとる。
« 関東 進出 の 第一歩 » |
1516
( 永正 13)年 |
7月 |
早雲 、 相模国 を 征服 する。 |
1519
( 永正 16)年 |
8月 |
早雲 、 伊豆国 韮山 城 で 没 する。 |
1524
( 大永 4)年 |
1月 |
氏綱 、 上杉朝興 をやぶり、 江戸城 を 攻 めとる。
朝興 は 河越 ( 埼玉県 川越市 )に 逃 げた。
« 武蔵国 進出 の 第一歩 » |
1537
( 天文 6)年 |
|
氏綱 、 今川 義元 と 戦 う。 河越城 を 攻 めおとす。
« 武蔵国 ほぼ 征服 » |
1540
( 天文 9)年 |
|
氏照 生 まれる。( 生年 、 他説 あり。) |
1541
( 天文 10)年 |
7月 |
氏綱 、 没 する。 |
1546
( 天文 15)年 |
4月 |
氏康 、 河越 で 扇谷上杉氏 を 滅 ぼす。« 河越 夜戦 »
この 年 、 氏照 、 大石氏 の 養子 となる。 |
1552
( 天文 21)年 |
1月 |
関東 管領 上杉憲政 、 氏康 に 追 われ、 上野国 より 越後国 へ、 長尾 景虎 ( 上杉謙信 )を 頼 って 行 く。 |
1561
( 永禄 4)年 |
2月 |
氏照 、 滝山城 にはいる。 |
| 3月 |
氏康 ・ 氏政 父子 、 長尾 景虎 の 小田原城 攻撃 をしりぞける。 |
1563
( 永禄 6)年 |
|
この 頃 、 三田氏 滅 ぶ。 |
1569
( 永禄 12)年 |
10月 |
武田信玄 、 小田原 にせまり、 滝山城 も 攻撃 をうける。
氏照 軍 、 廿里 などで 死 にものぐるいの 戦 いをくりひろげ、 落城 をまぬがれる。« 滝山 合戦 » |
1573
( 天正 元)年 |
4月 |
武田信玄 、 没 する。 |
| 7月 |
室町 幕府 滅 びる。 |
1578
( 天正 6)年 |
3月 |
上杉謙信 、 没 する。 |
1580
( 天正 8)年 |
3月 |
氏照 軍 、 武田勝頼 ( 信玄 の 子 )と 武蔵国 各地 で 対戦 する。 |
| 同月 |
氏照 、 安土 に 使者 を 出 し、 信長 と 近付 きになろうとする。 武田勝頼 ・ 上杉 景勝 らに 対抗 するためだ。 |
1582
( 天正 10)年 |
3月 |
信長 軍 、 武田勝頼 を 滅 ぼす。 |
| 6月 |
明智光秀 の 襲撃 をうけ、 信長 自殺 。« 本能寺 の 変 »
羽柴 秀吉 ( 豊臣 秀吉 )、 明智光秀 をやぶる。 |
1585
( 天正 13)年 |
3月 |
後北条氏 、 小田原城 ・ 韮山 城 の 普請 をする。
(普請=たてたり、 直 したりすること) |
| 7月 |
秀吉 、 関白 となる。 |
1586
( 天正 14)年 |
12月 |
秀吉 、 太政 大臣 となり、 豊臣 の 姓 をうける。 |
1587
( 天正 15)年 |
1月 |
後北条氏 、 小田原城 普請 。 |
| 5月 |
秀吉 、 九州 を 平定 。 |
| 9月 |
氏直 、 鉄砲 鋳造 にとりかかる。 |
1588
( 天正 16)年 |
1月 |
氏照 、 各地 に 八王子 守備 の 命令 を 出 す。
兵糧 確保 、 人質 として 妻子 を 八王子城 に 入 れることなどを 命 ず。« 戦争 準備 » |
| 4月 |
秀吉 、 大名 たちに 関白 ( 秀吉 )への 忠誠 を 誓 わせる。 後北条氏 は 出仕 せず。 |
1589
( 天正 17)年 |
11月 |
秀吉 、 諸 大名 に 北条 討伐 の 準備 をさせる。 |
1590
( 天正 18)年 |
4月 |
4日 秀吉 、 小田原城 をかこむ。
27日 江戸城 、 開城 。(開城= 城 をひらいて 降参 すること) |
| 5月 |
20日 岩付 城 、 開城 。 |
| 6月 |
14日 鉢形城 、 開城 。
23日 八王子城 、 攻撃 をうけ、その 日 のうちに 落城 。 |
| 7月 |
5日 氏直 、 秀吉 に 降伏 。
6日 秀吉 、 小田原城 を 手 に 入 れる。
11日 秀吉 、 氏政 ・ 氏照 を 切腹 させる。 氏直 は 高野山 に 流 される。
13日 秀吉 、 家康 に 関八州 を 与 える。 |
| 8月 |
1日 家康 、 江戸城 にはいる。 |
戦国 の 登場 人物
戦国 大名 ののぞみは…。 京 にのぼって、 天下 を 統一 すること。
そのためには、 合戦 に 勝 つばかりではなく、 手 をむすびあったり、はかりごとをしたり、 大変 なのだった。
北条 早雲 (1432~1519年)
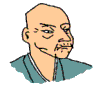 伊勢 新九郎 長氏
伊勢 新九郎 長氏 。
入道 してからは
早雲 庵宗瑞 と
名 のった。「
北条 」を
名 のるようになったのは、
二代目 氏綱 から。
早雲 の
出身 ははっきりしていない。
家 がらや
血 すじを
気 にする
人 ではなかったらしい。
妹 が
駿河 の
守護 ・
今川 義忠 の
妻 であった
縁 で、
今川氏 に
身 をよせた。
同 い
年 の
太田 道灌 は55
歳 で
謀 り
殺 されてしまったが、
早雲 が
関東 で
活躍 したのは、60
歳 を
越 えてから。うーん、
大器 晩成 !
連歌師 ・
宗長 は、
早雲 を「
針 ほどのものも
蔵 につむほどの
蓄 え
方 をしながら、
合戦 の
費用 には、
貴重 な
玉 でさえ
砕 いて
使 う
人 」だと
言 っている。
戦乱 の
世 を88
歳 まで
生 きぬいたのは、とにかくすごい。
古河公方と堀越公方
足利 成氏 とその 子孫 をいう。
成氏 は、1449 年 、 鎌倉 公方 になったが、1454 年 、 関東 管領 ・ 上杉 憲忠 を 殺 し、 室町 幕府 と 対立 。
1455 年 、 下総 古河城 に 移 り、 足利 政知 の 堀越 公方 に 対抗 して 古河公方 と 名 のった。
反抗 して 古河 にいってしまった 成氏 を 討 つため、 幕府 は1457 年 、 足利 政知 ( 義政 の 弟 )をむかわせた。が、 政知 には 力 がなくて、 鎌倉 にははいれず、 伊豆 韮山 の 堀越 にとどまり、 堀越 公方 を 名 のって 古河公方 に 対抗 。
その 死後 は、子の 茶々丸 がついだが、1491 年 、 早雲 に 滅 ぼされた。
古河公方 と 堀越 公方 は 対立 する。 山内 と 扇谷上杉 も 対立 する…。
で、 関東 は 戦乱 のまっさかり!
上杉氏
足利尊氏 ・ 直義 兄弟 の 母 が 上杉氏 出身 だったことから、 足利 氏 に 重 く 用 いられた。 山内 ・ 宅間 ・ 犬懸 ・ 扇谷 ・ 越後 の 各家 に 分 かれたが、 中 でも 山内 上杉 は 関東 管領 の 職 ( 鎌倉 公方 の 仕事 を 助 ける 役 )を 独占 。 上野 ・ 伊豆 ・ 武蔵 ・ 相模 など 関東 に 勢力 を 持 っていた。
15 世紀 後半 に、 古河公方 ・ 足利 成氏 との 対立 や、 山内 ・ 扇谷 両 上杉 家 の 対立 で 力 がおとろえた。
山内 上杉憲政 は、1546 年 、 河越 夜戦 で 北条 氏康 にやぶれ、 越後 の 長尾 景虎 (のちの 上杉謙信 )に 上杉 姓 と 関東 管領 の 職 をゆずってしまった。
武田 信玄 (1521~1573年)
領国 甲斐 をかためて、1555 年 には、 信濃 ( 長野 )の 一帯 を 攻 めとった。そのため、 上杉謙信 と 対立 することになった。
中 でも1561 年 の 川中島 の 戦 いは 有名 。
1570 年 には 駿河 も 合 わせ、 中部 地方 に 広大 な 領国 をつくり、 織田 信長 とも 対立 。1572 年 には 遠江 ( 静岡県 ) 三方ヶ原 で 信長 ・ 家康 連合 軍 をうち 破 り、 勢 いにのった。が、 京 へのぼる 夢 をはたさぬうちに 病死 。その 後 10 年 たらずのうちに、 息子 勝頼 は 信長 ・ 家康 連合 軍 にやぶれ、 武田 氏 は 滅 んだ。
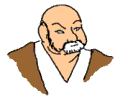 信玄 の 旗 じるしは「風林火山(ふうりんかざん)」
信玄 の 旗 じるしは「風林火山(ふうりんかざん)」
“はやきこと 風 のごとく、しずなかること林のごとし、 侵掠 すること 火 のごとく、動かざること 山 のごとし”
これが信玄の戦い方だった。
上杉 謙信 (1530~78年)
はじめ
長尾 景虎 、のち
政虎 、
輝虎 と
名 まえをかえた。
入道 して
謙信 と
名 のった。
越後 で
勢力 を
持 ち、
北条 氏康 に
追 われた
上杉憲政 、
武田信玄 に
攻 められた
村上 氏 ・
高梨 氏 らに
頼 りにされた。
謙信 は
氏康 ・
信玄 に
対抗 し、
信濃 ・
関東 によく
兵 を
出 している。

毘沙門天 のねっしんな 信者 だった 謙信 の 旗 じるしは「 毘 」の 字 をそめぬいたもの。
謙信は 生涯 結婚 せず、 質素 なくらしをしたとか。
織田 信長 (1534~1582年)
尾張 (
愛知県 )の
生 まれ。
1560
年 、
京 へのぼろうとした
駿河 の
今川 義元 を
桶狭間 にやぶり、
実力 を
認 められはじめる。
1562
年 、
三河 の
徳川 家康 と
同盟 。
尾張国 を
統一 。
1571
年 、
将軍 ・
足利 義昭 を
追放 して、
室町 幕府 をほろぼす。
1580
年 、
畿内 近国 (
京 の
近郊 )の
支配 権 をにぎる。
武田 氏 もほろぼし、
全国 統一 に「あと
一歩 」のところで、
家臣 ・
明智光秀 の
反逆 にあい、1582
年 本能寺 で
自殺 。
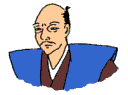
「 人間 五十 年 、 下天 のうちをくらぶれば 夢 まぼろしのごとくなり。ひとたび 生 をえて 滅 せぬ者のあるべきか」
桶狭間への出陣前に信長が舞ったという「 敦盛 」だ。
豊臣 秀吉 (1536~1598年)
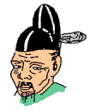 尾張
尾張 の
生 まれ。はじめ
木下 藤吉郎 。
信長 の
家臣 となって、
羽柴 の
姓 を
名 のる。
本能寺 の
変 でたおれた
信長 のあとをついで
1585
年 には
四国 の
長宗我部 氏
1587
年 には
九州 の
島津 氏
1590
年 には
関東 の
後北条氏 と
各地 の
実力者 たちを
次々 とたいらげ、
天下 をとった。
豊臣 の
姓 は、1585
年 、
関白 となった
時 、
朝廷 より
許 されたもの。
機転 のきく 秀吉 は、 短気 な 信長 にも 気 に 入 られた。
徳川 家康 (1542~1616年)
三河 岡崎 城主 、
松平 氏 の
長男 として
生 まれる。
松平 氏 は
実力者 、
今川氏 ・
織田 氏 に
両側 からはさまれた
弱 い
大名 だった。
家康 は、6
歳 から
織田 信秀 (
信長 の
父 )、
次 に
今川 義元 の
人質 としてすごした。
ひとり
立 ちができたのは、1560
年 、
桶狭間 の
戦 いで
義元 が
戦死 してからだ。
1562
年 、
信長 と
手 をむすび、
三河 を
平定 。
1590
年 、
秀吉 に
従 って
後北条氏 を
攻 め、
関八州 (武蔵・相模・安房・上総・下総・常陸・上野・下野)を
与 えられ、
江戸 を
居城 にした。
のち、ここで
徳川 幕府 をひらく。
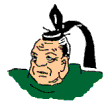
大名 らの 宝 じまんで、「 宝 は 自分 のために 水火 をとわぬ五百 人 の 三河 武士 」といったとか。 苦労人 らしいね。
戦国 の 城
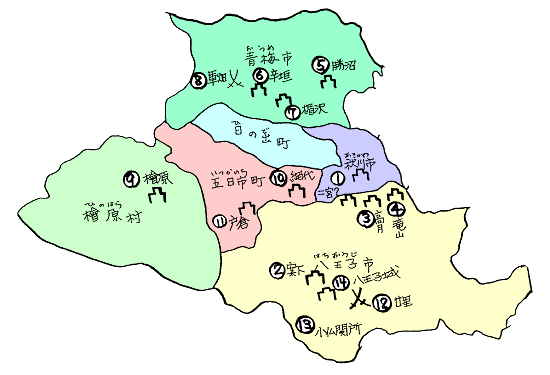
- 二宮城 (あきる 野市 二宮 小川 ?)← 別 の 場所 にあった、という 説 も…
信濃国 佐久郡 大石郷 より 武蔵 に 来 た 大石氏 の 居城 。 大石氏 は 木曽 義仲 の 子孫 を 名 のっていた。
この 城 は 貞和 年間 (1345 年 ころ) 大石 信重 が 築 いたといわれる。
- 案下城 ( 八王子市 下恩方 )
元中 年間 (1384 年 ころ)、 大石 信重 は、 二宮城 からここへ 移 った。
寺 の 名 から、 浄福寺城 。 山号 から 千手山城 。 地名 から 案下城 といろいろな 呼 び 名 を 持 っている。
- 高月城 ( 八王子市 丹木町 )
大石 顕重 が 築 き、1458 年 ( 長禄 2) 案下城 より 移 った。
その 子 、 定重 は 大永 年間 (1521~28ころ) 滝山城 へ 移 った。
- 滝山城 ( 八王子市 丹木町 )
もとは 大石氏 の 城 だが、 定重 の 子 、 定久 のときに 養子 にむかえた 氏照 の 城 になる。
1552 年 ( 天文 12)、 上杉謙信 の 攻撃 をうけ、1569 年 ( 永禄 12)には、 氏照 軍 と 武田信玄 ・ 勝頼 軍 との 死闘 の 舞台 になった 城 だ。 滝山城 は 落城 寸前 までいったがからくも 助 かった。
- 勝沼城 ( 青梅市 師岡 )
平将門 の 子孫 を 名 のる 三田氏 の 城 だった。 三田氏 は「 杣 の 保 」と 呼 ばれた 多摩 川 上流 一帯 を 領土 にしていた。「 杣 の 保 」とは 山方 という 意味 。16 世紀 前半 の 三田 弾正 氏宗 、その 子 政定 の 頃 が 最 も 盛 んだった。
1563 年 、 後北条氏 にそむいた 三田氏 は 滅 ぼされた。
この 城 は、 後北条氏 の 家臣 、 師岡 山城守 将景 が 住 み、 甲斐 の 武田 氏 への 備 えとなった。
- 辛垣城 ( 青梅市 二俣尾 )
後北条氏 と 対立 して 圧力 を 受 けた 三田氏 は、 勝沼城 から、ここ 辛垣城 に 移 って 来 た。 滅 んだのは 城主 ・ 三田 綱秀 の 時 。
綱秀 は 埼玉県 の 岩槻 におちのびて 自殺 した。250 年間 、 杣 の 保 を 支配 してきたのだけれど。
- 楯沢城 ( 青梅市 日向 和田 楯沢 )
三田氏 が 勝沼城 にいた 時代 からの 出城 だった。 辛垣城 攻撃 の 時 、 一緒 に 滅 んだ。
- 軍畑 ( 青梅市 沢井 )
ここは 三田氏 と 後北条氏 の 合戦 場 となったところ。このあたりの 多摩 川 は 谷 が 浅 く、 川 を 渡 って 攻 め 入 りやすかったそうな。
滝山城 から 進 んだ 氏照 軍 と、ここを 守 らねばと 主力 を 集 めた 三田氏 の 間 で 大激戦 となった。
- 檜原城 ( 檜原村 本宿 )
平山 氏 が 築 き、のち、 後北条氏 の 支配 する 城 になる。 八王子 の 滝山城 や 五日市 の 戸倉城 などとともに、 甲斐 の 武田 氏 への 備 えの 城 。
武田 軍 が 攻 めて 来 た 時 、 狼煙 をあげ、 戸倉 → 網代 → 戸吹 → 高月 → 滝山 へと 連絡 ができる。(お 城 の 位置 を 指 でたどってごらん。)
- 網代城 (あきる野市
- 戸倉城 (あきる野市
- 里 合戦 場 ( 八王子市 廿里 町 )
1569 年 ( 永禄 12)、 滝山城 に 進軍 した 武田 軍 と、むかえる 氏照 軍 が 激突 した 古戦場 。
ここで 小仏峠 をこえて 来 た 武田 の 部将 、 小山田 信茂 と 氏照 の 重臣 、 横地 監物 ・ 中山 勘解由 らが 戦 った。
- 小仏 関所 ( 八王子市 裏高尾 )
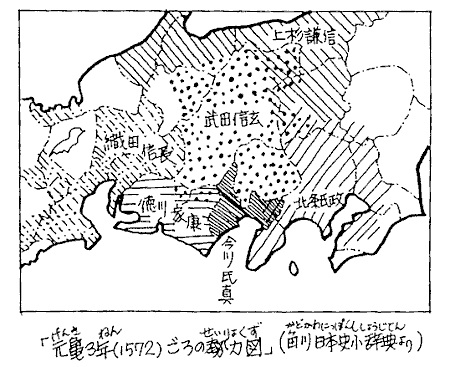 甲斐 ・ 相模 との 境 にある 小仏峠 のあたりは 後北条氏 にとって 重要 な 守 りの 場所 だった。
甲斐 ・ 相模 との 境 にある 小仏峠 のあたりは 後北条氏 にとって 重要 な 守 りの 場所 だった。
甲斐から 武田 氏 がはいりこめば、ここから 八王子城 に 狼煙 ですぐ 連絡 できた。
はじめは 小仏峠 の 頂上 にあったのを、 氏照 が1580 年 、 駒木野 にうつし、さらに 今 の 関所跡 のところにうつった。
- 八王子城 ( 八王子市 元八王子町 )
体験 ! 八王子城
八王子城 は 深沢山 ( 標高 540メートルの 自然 の 地形 に 手 を 加 え、いざという 時 はここにこもって 戦 えるようにつくられた 広大 な 城 だ。
「 曲輪 」とは、 土 るい、 石 るい、 掘 などで 区切 られた 場所 。 陣地 や 屋敷 を 置 くための 平 たい 場所 になっている。また、「 勢隠 し」という 軍隊 をかくしておく 場所 もつくられているし、「 掘 切 り」といって、 敵 がまっすぐ 進 めないよう 尾根 を 切 り 離 す 工夫 もしている。
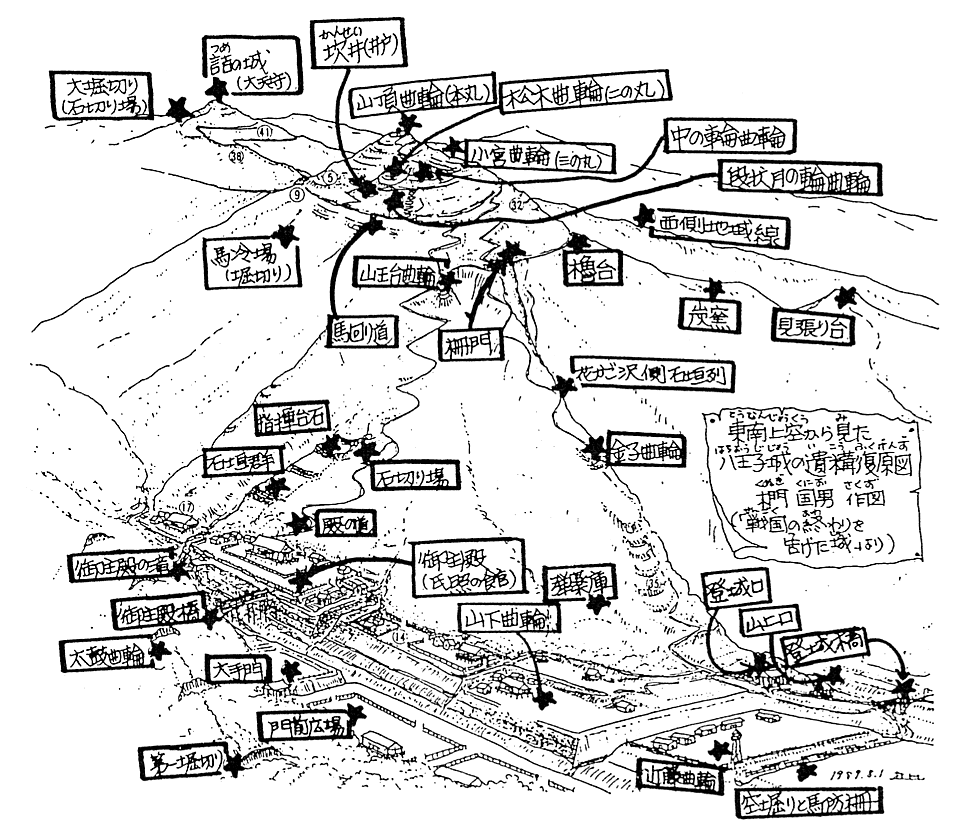
滝山城 から 八王子城 へ
後北条氏 の 勢力 におされた 大石定久 は 氏康 の 二男 、 氏照 を 滝山城 にむかえ、あとつぎにした。1546 年 のことだ。 氏照 はさらに 滝山城 から、 八王子城 へ 引 っ 越 すが、その 時期 ははっきりしていない。
- 元亀 から 天正 初 めごろ(1570~73)
- 天正 6 年 (1578) 前後
- 天正 10 年 (1582)よりあと。 落城 (1590) 近 くなど、いろいろな 説 がある。
引 っ 越 した 理由 も、 永禄 12 年 (1569) 甲斐 の 武田 氏 に 攻 められて、 落城 寸前 になった 滝山城 の 欠点 がわかったためとか 言 われる。しかし、 確 かなところはわからない。
八王子 はそのころから 栄 えていたし、 交通 の 要 でもあった。 軍事的 に 重要 な 場所 だったから、 氏照 は 早 くから、 城 を 八王子 に 移 そうと 思 っていたのではないか、という 説 もある。
小田原 戦争 前夜
織田 信長 の 意志 をついだ 豊臣 秀吉 は、 西日本 を 征服 した。さぁ、 次 は 東日本 の 番 だ! ところが、 関東 には 後北条氏 、 東北 には 伊達 氏 の 二大 勢力 がたちふさがっている。
天正 15 年 (1587)、 秀吉 は、 後北条氏 を 倒 すことを 決意 した。 天下 統一 のために。
天正 17 年 (1589)11 月 24 日 、 秀吉 はとうとう 話 し 合 いをうちきる 手紙 を 後北条氏 に 出 している。いよいよ 本格的 な 戦闘 準備 だ。
秀吉 の 動員 能力 ( 兵 を 動 かせる 力 )は58 州 、1,650 万石 で41 万 2,000 人 。
後北条氏 は 関八州 その 他 285 万石 で7 万 1,000 人 。 秀吉 はそのうち 約 15 万 人 を 小田原城 につぎこんだ。 八王子城 には1 万 5,000 人 あまりの 軍勢 が 攻 めこんだが、 守 る 城 側 はこれに 対 してわずか3,000 人 。
八王子城 落城
天正 18 年 (1590)4 月 より、 秀吉 軍 は 関東 にある 後北条氏 の 城 をつぎつぎとつぶしていった。 秀吉 は 上杉 景勝 ・ 前田 利家 の 部隊 に 八王子城 総 攻撃 を 命 じる。
八王子城 は、 横地 監物 ・ 中山 勘解由 ・ 狩野 一庵 ・ 近藤助実 ・ 金子家重 ら 重臣 が、 小田原 本城 につめた 城主 氏照 の 留守 をまもっていた。 氏照 の 領内 には 天正 16 年 (1588) 正月 には、すでに 出動 の「お 触 れ」がとんでいる。“15 歳 以上 70 歳 までの「 男 たるほどの 者 」はまかりいでよ。( 家臣 の) 妻子 は 人質 として 八王子城 にはいれ”という 内容 だった。 侍 だけでなく、 農民 ・ 職人 ・ 山伏 らもだ。
天正 18(1590) 年 、6 月 21 日 、 八王子城 代 ・ 横地 監物 あてに 降伏 をすすめる 手紙 が 送 られてきたが、 監物 らは「この 城 を 預 る 以上 は、 城 をたてに 討 ち 死 にする 覚悟 だ」と 申 し 出 をけった。
かくして6 月 23 日 午前 2 時 頃 より 八王子城 総 攻撃 は 開始 。その 日 、 午後 4 時 頃 まで、やく14 時間 の 戦闘 で、 八王子城 は 落 とされた。 重臣 たちは 次々 と 討 ち 死 に。 城 は 火 につつまれ、 女 の 人 や 子 どもたちは 自分 から 命 を 絶 っていった。
攻 める 方 も、 守 る 方 も、 大 きな 犠牲 をはらった 戦 いだった。
八王子城 落城 のしらせに、7 月 5 日 、 小田原城 もついに 無条件 降伏 。7 月 11 日 には、 氏照 も、 兄 、 氏政 とともに 切腹 。 家康 の 娘 と 結婚 していた 氏直 ( 氏政 の 子 )は 命 を 助 けられ、 高野山 に 追放 されたが 早死 だった。 秀吉 から 関八州 を 与 えられた 家康 は8 月 1日 に 江戸 入 り。のち、この 地 に 徳川 幕府 をひらく。
八王子城 の 出土品
おはじき(
遊 び
道具 か?)、
中国製 の
陶磁器 、
米 ・
麦 ・
粟 など
食品 が
焼 かれ
炭 のようになったもの。すずり、
茶 うすなどお
茶 の
道具 。
山頂 の
本丸 近 くでは、まだ
使 っていない
鉄砲 のたま、
焼 けた
櫛 (
女 の
人 がここまで
逃 げのびて
来 たのだろう。)なども
見 つかった。
他 にも
槍 ・
刀 ・かんざし・
鏡 などなど。
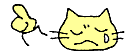 戦
戦 いの
道具 と
女 の
人 たちがふだんの
生活 で
使 っていたものがまざって
出 てくるのがよけい
悲 しい
気 がする。
御主殿 の 滝 のはなし
近藤助実 ・ 金子家重 らが 討 ちとられ、つづいて 狩野 一庵 も 討 ち 死 に。 御主殿 にいた 多 くの 女 の 人 や 子 どもたちは 追 いつめられ、 御主殿 の 滝 に 身 をなげた。 淵 はその 血 で 赤 く 染 まったという。
いつの 時代 も 戦争 というのはむごい…。

戦国 の 城 に、 舗装 されたはば 広 い 道 などない!
敵 がはいりこみにくいように 見渡 しが 悪 いように 工夫 してある。
また、せまい 道 を、わざとのぼったり、くだったりさせているんだ。

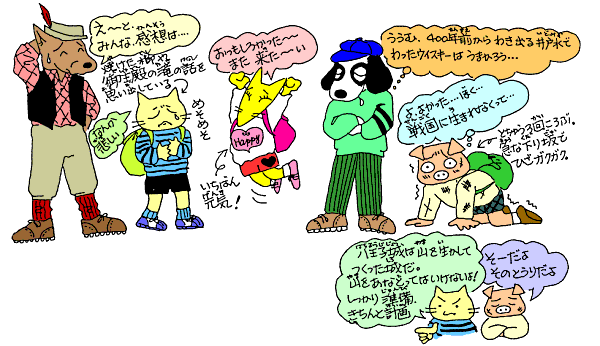
参考 にした 本
「 八王子城 -みる・きく・あるく-」
「 八王子市 史 」
「 八王子城 」(八王子市教育委員会)
「わが 町 の 歴史 八王子 」
「 多摩 の 古城址 」
「 多摩 丘陵 の 古城址 」
「 後北条氏 」
「 戦国 の 終 わりを 告 げた 城 」
「 武蔵野 の 城館址 」
「 多摩 のあゆみ」 第 40 号
「 角川 日本史 小辞典 」… 以上 2 階 参考室 ・ 郷土 資料室
「 学研 の 図 かん 日本 の 歴史 3」…1 階 児童 ・ 参考 図書 コーナー
「 中公文庫 日本 の 歴史 11. 戦国 大名 」
「 後北条氏 の 研究 」…1 階 大人 の 本 のコーナー
その他いろいろ…
小平市に関すること
多摩に関すること
江戸・東京に関すること
玉川上水・小金井桜に関すること
その他