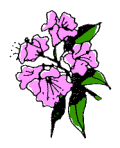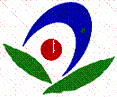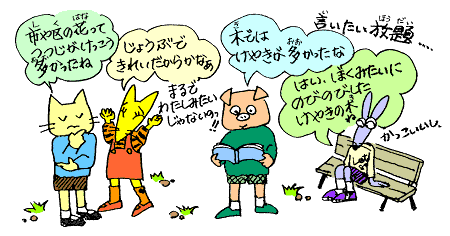東京都・小平市

<東京都のマーク> その由来
 明治
明治22(1889)
年12
月に
東京市議会で
決めた
市のマークをそのまま
東京都がうけついだ。
東京の
発展を
願って、
太陽を
中心に
6方に
光が
放たれているようすをあらわし、
日本の
中心としての
東京を
象徴している。
<東京都の木> いちょう
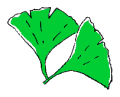 日本
日本と
中国の
一部だけに
現存する。
古代植物の
生き
残りといわれ、
公害にも、
火にも
強いのだ!
<東京都の花> ソメイヨシノ
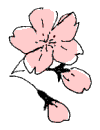 江戸
江戸の
末ごろから
昭和の
初めにかけて
染井村(
今の
豊島区)でヤマザクラを
品種改良して
育てられた。
咲いた
姿も、ちりぎわも
美しい。
<東京都の鳥> ゆりかもめ
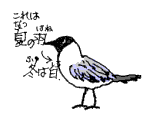
「みやこどり」とも
言う。からだは
白く、くちばしと
足が
朱色の
美しい
鳥。10
月下旬、シベリア、カムチャッカの
方から
飛んできて、よく
年4
月に
帰ってゆく
渡り
鳥。
≪小平のマーク≫ その由来
 昭和
昭和34(1959)
年11
月22
日制定のこのマーク。「
小平」の
字をデザインしたもので
安定感と
線の
太い
力強さがある。
左右にひろがるつばさは、
平和と
協調・
発展をあらわす。
≪市の木≫ けやき
市内の
東京街道・
青梅街道・
五日市街道などに
沿う
旧家の
屋敷森(
防風林)として
植えられてきたなじみぶかい
木。「けやき」とは

“けやけき
木”つまり、「めだつ
木」の
意味からついた
名前だとか。
空をめざす、のびやかな
姿だ。
≪市の花≫ つつじ
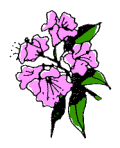 小平
小平では
大正のころから、
霧島つつじなどの
栽培がされてきた。つつじってあざやかさと、しんの
強さをあわせもっているよね。
≪市の鳥≫ こげら
 玉川上水付近
玉川上水付近で
見られるキツツキの
仲間。「ギィー」と
鳴く。
東京多摩地区
昭島市
 昭和
昭和29
年5
月制定。
黒い
部分は「昭」をあらわし、
内側、
白い
部分の4つの「マ」で「島」をあらわしている。
円は
団結を
意味する。
<木>もくせい
<花>つつじ
あきる 野市
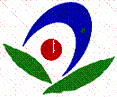 平成
平成8
年11
月制定。
あきる
野市の
頭文字「A」と
木の
葉をモチーフに、
人と
緑の
共生する
姿と
未来に
向けて
発展するあきる
野市を
象徴している。
<木>もくせい
<花>きく
<鳥>せきれい
稲城市
 昭和
昭和42
年10
月14
日制定。
稲城の「い」の
字をデザインしたもの。
市が
限りなく
発展する
姿をしめしている。
<木>いちょう
<花>
梨青梅市
 昭和
昭和26
年10
月1日制定。
青梅の「青」の
字を
飛ぶ
鳥のようにデザイン。
梅の
模様を
加えて、
市が
発展してゆくことをあらわす。
<木>
杉
<花>
梅
<鳥>うぐいす
清瀬市
 昭和
昭和36
年制定。
清瀬の「キ」の
字をまるくデザイン。
円は
団結と
平和を、
中央のたて
線は
発展を
意味する。
<木>けやき
<花>さざんか
<鳥>おなが
国立市
 昭和
昭和42
年9
月制定。
5
枚の
花びらの
梅の
花。
二重の
線の
外側は「国」のかまえを、
内側は「立」と
文教の「文」をしめしている。
<木>いちょう
<花>うめ
<
市の
色>みどり
小金井市
 昭和
昭和33
年10
月1日の
市政施行を
記念して
制定。
有名な
小金井桜の
市だから、マークにも
桜の
花びらをあしらっている。
小金井の「小」の
字のデザインでもあるんだ。
<木>けやき
<花>
桜国分寺市
 昭和
昭和33
年12
月5日
制定。
国分寺の「コク」を
円にデザインして、
仲良く
団結することをしめし、
中央に「分」の
字を
置いて、
市の
名をあらわす。
<木>けやき
<花>つつじ
狛江市
 昭和
昭和45
年10
月1日制定。
狛江の「こ」の
字をデザイン。
中央の
白い
部分は
多摩川の
流れ。マーク
全体で
発展する
姿をあらわす。
<木>いちょう
<花>つつじ
立川市
 昭和
昭和15
年12
月制定。
「立」と「川」の
字を
五角形にデザインした。
<木>けやき
<花>こぶし
多摩市
 昭和
昭和40
年1
月5日制定。
多摩の「多」の
字をハトがはばたき、
飛び
立つ
姿にたとえ、あらわす。まんなかの
線は
発展と
平和をしめしている。
<木>いちょう
<花>
山桜
<鳥>やまばと
調布市
 昭和
昭和30
年10
月1日制定。
調布の「ち」の
字をデザイン。
市民の
協力と
市の
発展をあらわす。
<木>くすのき
<花>さるすべり
西東京市
 平成
平成14
年1
月制定。
市民一人ひとりを
優しく
包み
込み、
市の
未来へ
突き
進む
先進性、
創造性を
躍動感いっぱいに
表現している。
<木>けやき、はなみずき
<花>つつじ、ひまわり、コスモス、すいせん
八王子市
 大正
大正6
年9
月1日の
市政施行をきっかけに、その
年の12
月22
日に
制定。
八王子の「八」と「王」の
字をデザインしたもの。
<木>いちょう
<花>ヤマユリ
<鳥>オオルリ
羽村市
 昭和
昭和31
年制定。
羽村の「羽」の
字をもとに、
羽村の
堰からふき
出す
水と
円にえがき、2
本の
虹で
伸びゆく
産業と
文化をあらわした。まるい
形は
市民の
団結をしめしている。
<木>いちょう
<花>
桜
<鳥>アオバズク
東久留米市
 昭和
昭和45
年10
月1日制定。
東久留米の「ひ」の
字をデザイン。
円から
外へ
飛びだそうとする
姿で、
市の
発展をあらわす。
<木>いちょう
<花>つつじ
<鳥>おなが
東村山市
 昭和
昭和39
年4
月1日制定。
東村山の「ヒ」と「ム」の
字をハトのかたちにデザイン。
市の
平和と
発展をあらわす。
<木>けやき
<花>つつじ
東大和市
 昭和
昭和38
年4
月1日制定。
東大和の「大」の
字でつばさをつくって、
大空にはばたく
様子を
描いている。また、
二重の
円は
人の「
和」を
意味している。
<木>けやき
<花>つつじ
日野市
 昭和
昭和38
年11
月3日制定。
日野の「日」の
字をまるくして、
炎のように
燃えさかり
発展してゆくさまをあらわす。
<木>かし
<花>きく
<鳥>かわせみ
府中市
 昭和
昭和29
年8
月7日制定。
府中の「ふ」と「中」の
字を
組み
合わせた。
中央の
線は、
多摩川の
流れでもある。
市民の
団結と
市の
発展をあらわす。
<木>けやき
<花>
梅
<鳥>ひばり
福生市
 昭和
昭和35
年制定。
福生の「ふ」の
字をデザイン。
市が
将来にむかってゆく
姿と
市民の
仲の
良い
姿とをあらわす。
<木>もくせい
<花>つつじ、さつき
町田市
 昭和
昭和33
年10
月1日制定。
町田の「マ」の
字を2つ
組み
合わせて、「田」のかたちをつくっている。
中央の
鳥は
平和と
発展を、
全体は
市民の
団結をあらわす。
<木>けやき
<花>サルビア
三鷹市
 昭和
昭和17
年8
月18
日制定。
三鷹がむかし、
府中領、
世田谷領、
野方領、三
領にまたがる
鷹場(
鷹を
使ってする
狩り
場)であったことから、3つの
輪の
中央に
飛ぶ
鷹の
姿を
描いた。
<木>いちょう
<花>ハナカイドウ
武蔵野市
 昭和
昭和3
年制定。
カタカナで「ムサシノ」の4
字を
組み
合わせ、デザインした。
円は
平和と
市の
発展をあらわす。
<木>けやき
<花>はなみずき
武蔵村山市
 昭和
昭和45
年11
月制定。
武蔵村山の「ム」の
字をハトの
姿にデザイン。
中央の
円は
市民の
仲の
良さをあらわして、
飛ぶ
様子は
市の
文化と
産業の
発展をしめしている。
<木>えのき
<花>
茶の
花奥多摩町
 昭和
昭和35
年4
月1日制定。
奥多摩の「奥」の
字をデザイン。
中の
白い
部分は
奥多摩湖をあらわす。
観光と
町の
団結・
協力で
発展していくという
意味。
<木>
杉
<花>みつばつつじ
<鳥>やまどり
日の出町
 昭和
昭和49
年2
月制定。
日の
出の「ヒ」の
字を
左右に
円形にデザイン。みんなの
円満と
明日の
発展をあらわす。
<木>もみ
<花>ふじ
<鳥>うぐいす
檜原村
 昭和
昭和54
年4
月1日制定。
檜原の「ひ」の
字をデザイン。
上の
三角の
部分は
飛び
立つ
鳥のつばさ、
下のまるい
部分はみんながひとつにまとまることをあらわす。
団結して
発展してゆく
姿だ。
<木>ひのき
<花>やまぶき
<鳥>うぐいす
瑞穂町
 昭和
昭和40
年4
月28
日制定。
瑞穂の「み」をデザイン。
円は
平和と
団結を
意味し、
全体は
飛ぶ
鳥をかたどって、
町の
発展をあらわす。
<木>
松、もくせい
<花>
茶の
花、つつじ
<鳥>ひばり
東京23区
足立区
 昭和
昭和33
年制定。
足立の「足」の
字をデザインした。
<木>いちょう、けやき、すずかけ
<花>
桜、チューリップ
荒川区
 昭和
昭和25
年5
月2日制定。
「
荒川」の「アラ」「川」をデザインしたもの。
円は
和をあらわす。
<木>
桜
<花>つつじ
板橋区
 昭和
昭和27
年4
月1日制定。
「イタバシ」の
字をデザイン。
中央の
円の
左が「イ」。
右が「タ」。
外に「ハ」を4つ
組み
合わせて「ハシ」。
<木>けやき
江戸川区
 昭和
昭和40
年8
月制定。
江戸川の「エ」の
字を
上向きに
飛ぶハトにデザイン。
発展と
平和をあらわす。
全体の
円は
区民の
協力と
和をしめしている。
<木>くすのき
<花>つつじ
大田区
 昭和
昭和27
年制定。
「
大森区」と「
蒲田区」が
昭和22
年に
合併してできた
大田区。マークも「大」と「田」の
字をデザインしてある。
<木>くすのき
<花>
梅葛飾区
 昭和
昭和26
年制定。
のびゆく
葛飾のシンボルとして、カタカナの「カ」と
漢字の「
力」の
両方の
意味をもつデザイン。さらに「カツ
シカク」なので
四角形になっている!
<木>しだれやなぎ
<花>ハナショウブ
北区
 昭和
昭和27
年7
月1日制定。
「北」の
字をデザインした
円形につばさをつけた。
力強くはばたく
北区の
未来をあらわす。
<木>
桜
<花>つつじ
江東区
 昭和
昭和26
年12
月21日
制定。
東京都の
一員としての
江東区をあらわす。
区内の
小・
中学生から
募集した
作品をもとにつくられた。
<木>クロマツ
<花>さざんか
品川区
 昭和
昭和27
年10
月制定。
品川の「品」の
字をデザイン。
友愛・
信義・
協力の3つを
中心に
前進してゆく
区をあらわす。
<木>しいのき、かえで
<花>さつき
<鳥>ゆりかもめ
渋谷区
 昭和
昭和31
年10
月1日制定。
渋谷の「渋」の
字をデザインしたもの。
<木>けやき
<花>ハナショウブ
新宿区
 昭和
昭和42
年3
月制定。
ひし
形はしっかりとして、
確かなようすをあらわす
形なんだって。そのひし
形をもとに、
新宿の「新」の
字を
一筆で
勢いよく
書いた。
区がますますしっかりと
発展してゆくことを
意味している。
<木>けやき
<花>つつじ
杉並区
 昭和
昭和27
年10
月1日制定。
杉並の「杉」の
字をデザインしたもの。
<木>さざんか、
杉、アケボノスギ
墨田区
 昭和
昭和32
年5
月15
日制定。
墨田の「ス」の
字を
組み
合わせて、
発展する
区の
姿をあらわす。
<木>
桜
<花>つつじ
世田谷区
 昭和
昭和31
年10
月制定。
外の
円は
区の
平和をあらわす。
中心の、
3方に
広がる「世」の
字は、
区の
発展とみんなの
協力を
意味している。
<木>けやき
<花>
鷺草
<鳥>おなが
台東区
 昭和
昭和26
年4
月18
日制定。
「台」と「東」の
字を
重ね
合わせてデザインしたもの。
中央の
白い
部分が「台」で、
黒い
部分が「東」だよ。
<木>
桜
<花>あさがお
中央区
 昭和
昭和23
年7
月31
日制定。
お
江戸の
日本橋・
京橋の
欄干擬宝珠(
橋の
柱の
頭につける
飾り)をデザイン。
中央の
小さな
円は
日本と
東京の
中心をあらわす。
<木>やなぎ
<花>つつじ
千代田区
 昭和
昭和25
年3
月26
日制定。
千代田の「千」の
字を
飛ぶ
鶴の
姿にかたどり、さらにこれを「よ」の
字に
似せ、
全体を「田」と
読んで、
千代田区をあらわす。
<木>
松
<花>
桜
<鳥>ハクチョウ
豊島区
 昭和
昭和57
年10
月1日制定。
でも、
制定される
以前から、
区の
行事の
時などに
使われてきたマークだ。
外側は
花びら12
枚の
菊。
内側は
亀の
甲羅の
中に「豊」の
字が
書かれている。
<木>ソメイヨシノ
<花>つつじ
中野区
 昭和
昭和15
年制定。
中野の「中」とひらがなの「の」の
字をデザインしたもの。
<木>しい
<花>つつじ
練馬区
 昭和
昭和28
年12
月制定。
平和で
健康な
明るい
町に
発展してゆこうという
願いをこめて、
練馬の「ネ」の
字と
馬のひづめの
形を
組み
合わせデザインした。
<木>こぶし
<花>つつじ
文京区
 昭和
昭和26
年3
月1日制定。
文京区の
姿をあらわすデザイン。
募集によって、
当時、
北多摩郡に
住んでいる
人の
作品が
選ばれた。
<木>いちょう
<花>つつじ
港区
 昭和
昭和24
年7
月30
日制定。
港区のもととなった
芝区・
麻布区・
赤坂区の3つが
一丸となったことをあらわし、
港の「み」の
字を
力強くデザインした。
<木>はなみずき
<花>ばら あじさい
目黒区
 大正
大正8
年ごろ、
目黒村役場にかかわりのある
人がつくったものだとか…。
目黒村の「目」の
字をデザインしたのだといわれている。
<木>しい
<花>はぎ
<鳥>しじゅうから
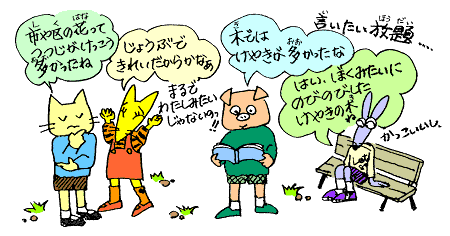
参考にした本
東京都の市区町村の、
「概要」、「便利帳」、「統計書」、「広報」など
市町村の役所の人たちにも親切にいろいろ教えてもらいました。
小平市に関すること
多摩に関すること
江戸・東京に関すること
玉川上水・小金井桜に関すること
その他
掲載日 令和7年8月1日


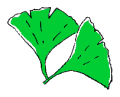
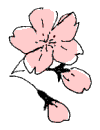
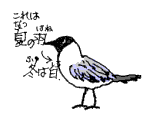 「みやこどり」とも
「みやこどり」とも
 “けやけき
“けやけき